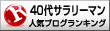短歌、俳句は、なぜ五と七の文字(音節)数でできているのか。
ある説によると、ちょうど四拍子になるからリズムがよいのだといいます。
例えばこの歌。
天の原ふりさけみれば春日なる 三笠の山に出でし月かも
この歌を口に出すとき、無意識に次のような読み方をしていないでしょうか。
|あま・のは・ら○・○○|ふり・さけ・みれ・ば○|かす・がな・る○・○○||みか・さの・やま・に○|いで・し○・つき・かも|
一つの音節を八分音符に喩えれば、ちょうど四分の四拍子にあてはまります。
○で表した休符の位置もころあいよく、リズムがとりやすいというわけです。
万葉や平安の時代の人が、このようにリズミカルに声に出したかは疑問です。
冷泉家に伝わる伝統的な詠み方、宮中で今も行われる歌会始の詠み方などを聞くと、必ずしも四拍子のリズムが意識されているとは思えません。
しかし一方で、なるほどそうかもしれない、と納得させられる説でもあります。
この説にのっとれば、一字(一音節)の字余りは、八分休符を一つつぶすのみで、四拍子を崩すことにはなりませんから、リズムの上ではあまり問題がないように思えます。
しかし、二音節の字余りになった瞬間に四拍子のリズムが崩れ、間の抜けた感じになってしまうことになります。
(それをあえてねらうなら、話しは別ですが…)
四拍子説にのっとれば、和歌や短歌の五と七による音の作り方は、一字の字余りを計算に入れた、柔軟な創作を可能にするシステムだといえるかもしれません。
http://blog.goo.ne.jp/syusakuhikaru/e/853b1a35b5951dbcc9f0a575a8d98322
ある説によると、ちょうど四拍子になるからリズムがよいのだといいます。
例えばこの歌。
天の原ふりさけみれば春日なる 三笠の山に出でし月かも
この歌を口に出すとき、無意識に次のような読み方をしていないでしょうか。
|あま・のは・ら○・○○|ふり・さけ・みれ・ば○|かす・がな・る○・○○||みか・さの・やま・に○|いで・し○・つき・かも|
一つの音節を八分音符に喩えれば、ちょうど四分の四拍子にあてはまります。
○で表した休符の位置もころあいよく、リズムがとりやすいというわけです。
万葉や平安の時代の人が、このようにリズミカルに声に出したかは疑問です。
冷泉家に伝わる伝統的な詠み方、宮中で今も行われる歌会始の詠み方などを聞くと、必ずしも四拍子のリズムが意識されているとは思えません。
しかし一方で、なるほどそうかもしれない、と納得させられる説でもあります。
この説にのっとれば、一字(一音節)の字余りは、八分休符を一つつぶすのみで、四拍子を崩すことにはなりませんから、リズムの上ではあまり問題がないように思えます。
しかし、二音節の字余りになった瞬間に四拍子のリズムが崩れ、間の抜けた感じになってしまうことになります。
(それをあえてねらうなら、話しは別ですが…)
四拍子説にのっとれば、和歌や短歌の五と七による音の作り方は、一字の字余りを計算に入れた、柔軟な創作を可能にするシステムだといえるかもしれません。
http://blog.goo.ne.jp/syusakuhikaru/e/853b1a35b5951dbcc9f0a575a8d98322