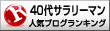新型コロナ感染拡大で、東京都民には身動きの取りにくい夏となりました。
遠出をするわけにもいかず、都内のホテルでささやかに夏休みを楽しむことにしました。
そんなある日の昼食での話です。
ホテル内のイタリアンレストランで、妻と二人でランチを楽しんでいました。
お腹が空いていた私は日替わりのランチコースを、妻は単品でパスタを頼みました。
コースですから、前菜、メイン、デザートと順番に運ばれてきます。
メインだけが選べるようになっていて、前菜とデザートはフィックスです。
妻はとっくにパスタを食べ終わり、私もメインまで終わり、皿も下げられ、談笑していたところに私のデザートが運ばれてきました。

ムースとチョコレートケーキのコンビネーションで、小ぶりな皿で見た目もおいしそう。
ウェイターの方が、その皿を私の前に置きながら、こう言いました。
「こちらでよろしいでしょうか」
私は、その問いがなにを聞きたかったのか、一瞬分からず戸惑いました。
というのも、目の前に置かれたデザートを見ながら聞いたその言葉が「このデザートで間違いないでしょうか」という風に聞こえたのです。
もともとコースの決められたデザートですから、その内容が間違っていないか聞かれてもよく分かりません。
次の瞬間、私はその問いの真意を理解しました。
「お二人のうち、貴方がデザート付きランチコースで間違いないでしょうか」
すでに皿が下げられた後で、二人のうち一人だけがデザート付きだったので、ウェイターさんからしてみると、どちらに置いてよいか迷ったのでしょう。
きっとたくさん食べるのは男性に違いない、という予測の下に、私の前に置きつつも念のため「こちらでよろしいでしょうか」と聞いたというわけです。
「こちら」という指示代名詞の幅広い可能性が、逆に曖昧さとなって表れた、日常の一幕でした。
遠出をするわけにもいかず、都内のホテルでささやかに夏休みを楽しむことにしました。
そんなある日の昼食での話です。
ホテル内のイタリアンレストランで、妻と二人でランチを楽しんでいました。
お腹が空いていた私は日替わりのランチコースを、妻は単品でパスタを頼みました。
コースですから、前菜、メイン、デザートと順番に運ばれてきます。
メインだけが選べるようになっていて、前菜とデザートはフィックスです。
妻はとっくにパスタを食べ終わり、私もメインまで終わり、皿も下げられ、談笑していたところに私のデザートが運ばれてきました。

ムースとチョコレートケーキのコンビネーションで、小ぶりな皿で見た目もおいしそう。
ウェイターの方が、その皿を私の前に置きながら、こう言いました。
「こちらでよろしいでしょうか」
私は、その問いがなにを聞きたかったのか、一瞬分からず戸惑いました。
というのも、目の前に置かれたデザートを見ながら聞いたその言葉が「このデザートで間違いないでしょうか」という風に聞こえたのです。
もともとコースの決められたデザートですから、その内容が間違っていないか聞かれてもよく分かりません。
次の瞬間、私はその問いの真意を理解しました。
「お二人のうち、貴方がデザート付きランチコースで間違いないでしょうか」
すでに皿が下げられた後で、二人のうち一人だけがデザート付きだったので、ウェイターさんからしてみると、どちらに置いてよいか迷ったのでしょう。
きっとたくさん食べるのは男性に違いない、という予測の下に、私の前に置きつつも念のため「こちらでよろしいでしょうか」と聞いたというわけです。
「こちら」という指示代名詞の幅広い可能性が、逆に曖昧さとなって表れた、日常の一幕でした。