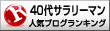「プロフェッショナル」で登場した同時通訳の長井鞠子さんのエピソードで、印象に残ったのは福島での仕事のことでした。
ある重要な国際会議で、浪江町長が福島の現状を世界に伝えるために、プレゼンをすることになった。その同時通訳を頼まれたのです。
プレゼンのキーコンセプトの一つが「ふるさと再生」という言葉でした。
この「ふるさと」をどう訳すか。そこに焦点が当てられていました。
辞書をひくと、「ふるさと」は通常home town、birth placeあるいは単純にhomeなどと訳されます。
どんな言葉でもそうですが、文意によって訳し方は幾通りもあります。
長井さんは、帰りたくても帰れず避難生活を余儀なくされている浪江の人たちの心情を察した時に、「ふるさと」という言葉をどんな英語に置き換えるかは重要なポイントだと考えました。
単にhome town だと、彼らの強い思いが伝わり切らないのではないか、と。
Ancestor home
Namie homes
幾つかの可能性が出てきますが、いずれもしっくりこないようです。
どの英語を使えば、「ふるさと」という言葉に込められた切実な思いをもっとも伝えることができるのか。
結局、本番で長井さんが選んだ表現は、beautiful Namie town as our home というものでした。
「ふるさと」を直接訳さずに、むしろ「浪江」という固有名詞を強調した表現にすることで、彼らにとって故郷が唯一無二の存在であることを表した。
あえて言えばそういうことでしょうか、名訳だと思います。
翻訳の中でも、歴史的・文化的背景を色濃く持った言葉は、英語など他の国の言葉に訳すのは難しいことが多いものです。
「ふるさと」もその一つと言えるでしょう。
日本語の「ふるさと」という言葉は、home townという言葉とは少し違う精神が表れている気がします。
「里(さと)」という言葉の語源は、諸説ありますが、奈良時代の律令制には、郡の下に「里(り・さと)」という単位があり、小さな村落の単位から出てきた言葉と言われます。
一説には、里という文字が「田」と「土」から成り、田畑を耕し、土着の信仰の拠り所とな場所を指すとも言われます。
単に「自分の生まれた場所」というだけではないニュアンスを含んでいます。
また、歴史的・地理的な背景も、日本語の「ふるさと」に影響を与えていると考えられます。
もともと日本は山がちな国で、かつ四方を海に囲まれた島国です。
多くの村落が山と山に、あるいは山と海に挟まれた小さな谷や平地に作られました。
多くの村と村は、山や海で仕切られていて、「ここが私の村」という範囲が目で見て把握しやすい景色になっていました。
また律令時代以来、稲作を中心とする農耕を基盤としてきた国ですから、民の移動が起こりにくい歴史でもありました。
多くの人が、先祖代々の土地に住み、田畑を耕し、村の神社に豊作を祈願し、暮らしてきました。
江戸時代には、自由な行き来が禁じられ、より民と土地の結びつきが強くなります。
さらに、この時代に各地で特産品を作ることが奨励され、各町村に自慢の品ができるようになります。
このことがより自分の町へのロイヤリティーとアイデンティティを育むことになったのでしょう。
かくして、日本人にとって「ふるさと」とは、単に自分が生まれた場所や自宅のある場所を指すだけでなく、長年の歴史と暮らしと信仰とが混然一体となって生み出された、唯一無二の特別な場所を指す言葉となったのです。
明治以降、都市化が進み、郷を離れる人が増えると、より「ふるさと」の持つ意味合いがさらに強まった気がします。
石川啄木や宮沢賢治などの文学に触れると、ふるさとへの想いが強く感じられますし、近年では「心のふるさと」といった、より「ふるさと」の精神性を強調した表現もよく見られます。
「ふるさと」は、英語のhomeとよく対比されますが、homeが「故郷」と同時に「家そのもの」を指す言葉であることが象徴するように、英語圏では故郷≒homeは自分の家や家族がある場所という意識が強いのでしょう。
その辺りに、異なる歴史をたどって来た国と国の言葉を置き換えることの難しさを感じます。
Namieという固有名詞を軸にして、my homeではなくour homeと表した長井さんの訳には、そうした日本の歴史や文化が持つ独特の価値観がうまく表現されていると思いました。
ある重要な国際会議で、浪江町長が福島の現状を世界に伝えるために、プレゼンをすることになった。その同時通訳を頼まれたのです。
プレゼンのキーコンセプトの一つが「ふるさと再生」という言葉でした。
この「ふるさと」をどう訳すか。そこに焦点が当てられていました。
辞書をひくと、「ふるさと」は通常home town、birth placeあるいは単純にhomeなどと訳されます。
どんな言葉でもそうですが、文意によって訳し方は幾通りもあります。
長井さんは、帰りたくても帰れず避難生活を余儀なくされている浪江の人たちの心情を察した時に、「ふるさと」という言葉をどんな英語に置き換えるかは重要なポイントだと考えました。
単にhome town だと、彼らの強い思いが伝わり切らないのではないか、と。
Ancestor home
Namie homes
幾つかの可能性が出てきますが、いずれもしっくりこないようです。
どの英語を使えば、「ふるさと」という言葉に込められた切実な思いをもっとも伝えることができるのか。
結局、本番で長井さんが選んだ表現は、beautiful Namie town as our home というものでした。
「ふるさと」を直接訳さずに、むしろ「浪江」という固有名詞を強調した表現にすることで、彼らにとって故郷が唯一無二の存在であることを表した。
あえて言えばそういうことでしょうか、名訳だと思います。
翻訳の中でも、歴史的・文化的背景を色濃く持った言葉は、英語など他の国の言葉に訳すのは難しいことが多いものです。
「ふるさと」もその一つと言えるでしょう。
日本語の「ふるさと」という言葉は、home townという言葉とは少し違う精神が表れている気がします。
「里(さと)」という言葉の語源は、諸説ありますが、奈良時代の律令制には、郡の下に「里(り・さと)」という単位があり、小さな村落の単位から出てきた言葉と言われます。
一説には、里という文字が「田」と「土」から成り、田畑を耕し、土着の信仰の拠り所とな場所を指すとも言われます。
単に「自分の生まれた場所」というだけではないニュアンスを含んでいます。
また、歴史的・地理的な背景も、日本語の「ふるさと」に影響を与えていると考えられます。
もともと日本は山がちな国で、かつ四方を海に囲まれた島国です。
多くの村落が山と山に、あるいは山と海に挟まれた小さな谷や平地に作られました。
多くの村と村は、山や海で仕切られていて、「ここが私の村」という範囲が目で見て把握しやすい景色になっていました。
また律令時代以来、稲作を中心とする農耕を基盤としてきた国ですから、民の移動が起こりにくい歴史でもありました。
多くの人が、先祖代々の土地に住み、田畑を耕し、村の神社に豊作を祈願し、暮らしてきました。
江戸時代には、自由な行き来が禁じられ、より民と土地の結びつきが強くなります。
さらに、この時代に各地で特産品を作ることが奨励され、各町村に自慢の品ができるようになります。
このことがより自分の町へのロイヤリティーとアイデンティティを育むことになったのでしょう。
かくして、日本人にとって「ふるさと」とは、単に自分が生まれた場所や自宅のある場所を指すだけでなく、長年の歴史と暮らしと信仰とが混然一体となって生み出された、唯一無二の特別な場所を指す言葉となったのです。
明治以降、都市化が進み、郷を離れる人が増えると、より「ふるさと」の持つ意味合いがさらに強まった気がします。
石川啄木や宮沢賢治などの文学に触れると、ふるさとへの想いが強く感じられますし、近年では「心のふるさと」といった、より「ふるさと」の精神性を強調した表現もよく見られます。
「ふるさと」は、英語のhomeとよく対比されますが、homeが「故郷」と同時に「家そのもの」を指す言葉であることが象徴するように、英語圏では故郷≒homeは自分の家や家族がある場所という意識が強いのでしょう。
その辺りに、異なる歴史をたどって来た国と国の言葉を置き換えることの難しさを感じます。
Namieという固有名詞を軸にして、my homeではなくour homeと表した長井さんの訳には、そうした日本の歴史や文化が持つ独特の価値観がうまく表現されていると思いました。