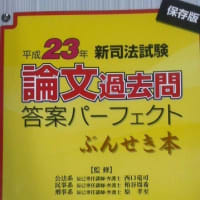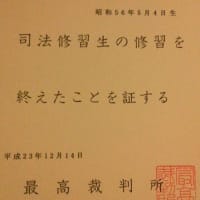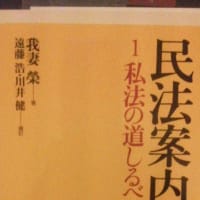平成22年・民事の答案です。作成日は,試験終了直後(出題趣旨等発表前)で,修正は加えていません(微修正があったほうがいい個所がありますが…)。講座で使用したものは基本的にブログで公開すべきではないと考えていますが,これは無料講座で使用されたものであること,講座から既に1年4か月が経過していることから,受験生の皆さんに参考になればと思い,ここに掲載しておきます。参考程度にお読みください。
[第1問]
第1 設問1
1.不足額支払責任(会社法52条1項)
(1)Aについて
Aは甲社の発起人であり設立時取締役であるので、現物出資財産の価額が、定款に記載された価額に「著しく不足する」場合は、甲社に対して不足額の支払責任を負う(会社法52条1項)。本件現物出資において、定款に記載された価額は5億円であるが、実際の価額は1億円にすぎず、これは「著しく不足する」場合であると言える。
そして、Aは本件現物出資をした者であるから、免責は認められず、無過失責任を負う(会社法52条2項かっこ書き)。
よって、Aは、4億円の不足額支払責任を負う。
(2)Bについて
Bも甲社の発起人であり設立時取締役である。しかしながら、BはAと異なり、現物出資をした者ではないので、会社法52条2項1号もしくは2号の免責事由に該当すれば免責される。本件では、検査役の調査(会社法33条2項)は行われていないので1号には該当しえず、2号の該当性が検討事項となる。
2号によれば、Bは「その職務を行うについて注意を怠らなかった」場合に免責される。本件でBは、本件不動産の評価額を5億円とする不動産鑑定士の鑑定評価を得、また、定款に記載された5億円の価額が相当であることについて公認会計士の証明を受けている(会社法33条10項3号)。これは、法令上、検査役の調査を不要とする適切な行為である。また、Bは設立時取締役に選任された後、遅滞なく上記不動産鑑定士の評価、公認会計士の証明が相当であること、設立時発行株式に係る出資の履行が完了していることを調査している(会社法93条1項2号、3号)。これも法令に則った適切な行為である。さらに、本件現物出資財産の価額が著しく不足した原因は土壌汚染によるものであるが、これは外形上明らかな瑕疵ではなく、専門家たる不動産鑑定士と公認会計士も認識しなかったのであるから、Bがこれに気付かなかったことをもって、「注意」を怠ったと評価することはできない。
よって、Bは会社法52条2項2号により免責され、責任を負わない。
2.損害賠償責任(会社法53条1項)
(1)Aについて
本件現物出資財産の価額が著しく不足していることにより、甲社には差額である4億円の損害が生じている。Aは、土壌汚染を知っていたのであるから、「任務を怠った」といえ、4億円の損害を賠償する責任がある。
(2)Bについて
他方、Bについては、「任務を怠った」とはいえない。1.(2)で述べたことに加え、Aが土壌汚染を認識していたとしても、土壌汚染は稀なことであり、その有無につき確認するまでの任務はないと考えられるからである。
よって、Bは責任を負わない。
第2 設問2
1.①払込みの効力と発行された株式の効力
(1)払込みの効力
本件募集株式発行は、形式上、丙社から1億円の払込みがあるが、このうち9000万円の部分については、払込みがされた翌日に甲社の口座から引き出され、丙社に返還されている。まず、このいわゆる見せ金と呼ばれる仮装払込みがなされた場合の効力であるが、その仮装された部分につき無効と考えるべきである(一部無効)。なぜなら、仮装払込みを有効と扱うことは資本充実原則を蔑ろにするものであり、他方で、現実に出資され資本に組み込まれた部分は資本充実原則の要請をみたすからである。したがって、本件では、1000万円の部分が有効な払込みであることはまず確定できる。問題は、9000万円の部分であるため、以下にそれを論ずる。
資本充実原則からすれば、払込みの効力の有無は、出資された財産が現実的に資本として意味をなすものであったかどうか、が基準とされるべきである。具体的には、①当該払込金とされた財産が返還・返済に充てられるまでの期間、②当該払込金とされた財産の運用の有無、③当該払込金とされた財産の返還・返済が募集株式発行会社に与える影響、を考慮して決せられるべきである。本件では、①問題の9000万円は翌日に甲社から丙社に返還され、丁銀行に返済されている。また、②この9000万円の運用の事実は全くない。さらに、③本件9000万円は甲社の資本金である3億5000万円(資料②)のかなりの部分を占めるもので、かつ、予定されていた店舗改装の可否に影響を与えるものであるから、甲社に与える影響は大きい。以上のことからすると、本件9000万円の部分は現実的に資本としての意味をなしたものとは評価できない。
よって、1000万円の部分については有効な払込みがあったが、9000万円の部分については、払込みとしての効力は認めらないと考える。
(2)発行された株式の効力
上述の通り、9000万円の部分についての払込みは無効であるが、本件では既に1億円の払込金額に相当する1000株の株式は、外形上、有効に成立している。
そこでまず問題になるのが、9000万円分に相当する900株を無効にできるか、つまり、株式の効力を一部無効にすることができるか、という点である。この点、新株発行無効の訴え(会社法828条1項2号)の認容判決が対世効を有する(会社法838条)ことから、一部無効は認められないようにも思える。しかし、この点は会社法828条1項2号に規定された訴えによらず、個別的に株主たる地位の不存在確認訴訟を提起することができるのだから、決定的な理由にならない。むしろ、募集株式の引受人が出資の履行をしない場合は失権する(会社法208条5項)と定めていることからすれば、法は部分的に株式の効力を失わしめることを認容していると考えられる。そうだとすれば、発行された株式の一部無効も認められると考える。
では、いかなる場合に無効になるか。この点、株式の無効事由は明定されていないので、解釈による必要がある。本来、発行に至る過程で重大な瑕疵があれば当該株式が成立する根拠はなく、無効となると考えるのが筋である。しかし、それでは株式の流通が阻害される。そこで、取引安全の見地から、既に発行された株式は原則として有効に扱われるが、取引安全を害さず、かつ、株式を無効とすべき特段の事情のある場合のみ例外的に無効になると解するべきである。本件では、株式は当初の引受人である丙社のもとにとどまっており、これを無効としても取引安全を害することはない。そして、本件の株式発行にかかる瑕疵は出資の実体を欠く仮装払込みであり、株式の効力を否定すべき必要性は大きい。
したがって、900株の部分につき、株式は無効であると考える。
2.②甲社に対しての責任
(1)甲社の損害について
A、B及び丙社が甲社に対して負う責任を論ずる前提として、本件募集株式発行によって甲社にいかなる損害が生じたかをまず検討する。
この点、損害は上述の9000万円であるように思えるが、これはあくまで出資であり、甲社の財産が既存されたわけではないので、損害と観念することはできない。甲社の損害は、本件募集株式発行が原因となり、破綻したことである。A、Bについてはこれを念頭に責任を論ずる。
(2)Aの責任
Aは、甲社の取締役であるから、会社法423条1項の責任を負うかが問題となる。
まず、「任務を怠った」か否かが問題となるが、Aは本件募集株式発行につき、見せ金による仮装払込みの主導的役割を果たした者であり、これは明らかに忠実義務(会社法355条)に反する行為である。そして、現実的に払込みがなかったことにより甲社は店舗改装ができなかった。そのため、引き続き大手ディスカウントストアに対抗できず、結果として甲社は倒産に至っているので、Aの行為と倒産による損害は因果関係も認められる。
したがって、Aは甲社の倒産により生じた損害を賠償する責任を負う。
(3)Bの責任
Bも甲社の取締役であるため、会社法423条1項の責任を負うかが問題となる。
この点、BはAと異なり、本件仮装払込みには関与していない。しかし、Bは取締役会の構成員として、取締役の職務執行を監督せねばならない(会社法362条2項1号)。にもかかわらず、BはAに本件募集株式発行の手続を実質的に一任しており、何ら監督をしていない。これは「任務を怠った」ものといえる。
したがって、Bも甲社の倒産により生じた損害を賠償する責任を負う。
(4)丙社の責任
丙社は、本件募集株式発行に際し、形式的には1億円の払込みをしているが、実質的に払込金として捻出したのは1000万円にとどまる。そうすると、1000万円の払込みで、その10倍である1億円の払込みに相当する1000株を引き受けたことになる。これは、「著しく不公正な払込み金額で募集株式を引き受けた」(会社法212条1項1号)ものと言える。かつ、本件仮装払込みは、丙社の代表取締役DがAの指示を受けて行ったものであり、「取締役と通じて」(会社法212条1項1号)なしたものといえる。したがって、丙社は公正な価額との差額である9000万円を支払う責任を負う。
なお、1.(2)で900株分は無効であるとしたが、株式の効力は訴訟を通じてはじめて判断されるものであり、これが丙社の負う上記差額の支払義務の結論を左右することはない。
3.③乙銀行に対しての責任
(1)Aの責任(会社法429条2項)
Aは、甲社の貸借対照表(資料①)を作成している。資産の部において、実質的には1000万円しか払込みのなかった本件募集株式発行の払込みにかかわる1億円を含む1億2000万円を現金資産として記載し、また、土壌汚染により本来は1億円の価値しかない建物及び土地を5億円と記載している。すなわち、「虚偽の記載」(会社法429条2項1号ロ)をしている。そして、これを乙銀行に示している。乙銀行はこれを信頼して甲社に1億円を融資したものの、甲社の破綻により回収不能となり、損害を被っている。
よって、Aは乙銀行に対して、1億円の損害賠償責任を負う。
(2)Bの責任(会社法429条1項)
BはAと異なり貸借対照表の記載者ではないので、責任の根拠としては、会社法429条1項が考えられる。まず、429条1項の法的性質が前提として検討されるべきであるが、第三者救済の見地から、これは特別の法定責任であると考え、「悪意又は重大な過失」(会社法429条1項)は、会社に対する任務違反について、を意味すると解する。
本件で「悪意又は重大な過失」が認められるか。まず、本件募集株式発行の手続きをAに一任していた点は、2.(3)に述べた通りである。これに加え、乙銀行からの融資はあくまでも店舗改装のためになされたはずなのに、甲社では実際に行われなかった。業績回復を狙った店舗改装であれば速やかに行われるべきところ、Bはこれについて確認や何らの指摘もしていない。これは、取締役としてあるまじき行為であり、忠実義務違反行為であると評価できる。
よって、Bは会社に対する任務を怠ったといえ、これに起因して生じた乙銀行の1億円の損害を賠償する責任を負う。
[第2問]
第1 設問1
1.金額に限度のない代理権を授与したとの主張
(1)有権代理の要件
Fが、表題の通りの主張をするためには有権代理(民法99条)の構成が考えられる。この場合、Fが主張立証すべきは、①FC間で本件消費貸借契約が締結されたこと、②前記①がAにとって商行為(商法504条)であること、③前記①に先立ってAからCに代理権が授与されたこと、である。
(2)事実①について
ア.「Cには交渉の経過を話してあり、それをCが理解しているから」の部分
これは、③の要件と関連して問題になる。つまり、CにはAの意向を全て話してあり、あくまでも意思決定権はAのみにあると解釈することのできる言葉である。Cには意思決定権限がなく、Aの手足として、使者として行動することを意味する。これは、③代理権授与の事実の間接反証としての意味を有すると考える。
イ.「後はCとの間でよろしく進めてほしい」の部分
これも、③の要件と関連して問題になる。ただし、この部分は上述のアと異なり、交渉はCとの間で進めること、つまり、交渉に際してはCの意思に委ねることを意味している。「よろしく進めて」ということからには、Cが柔軟に対応することを予定しており、金額についてもCに委ねた、ということを意味する。よって、この部分は金額を含めて、Cに③代理権を授与した事実を示す間接事実と考える。
(3)事実②について
事実②は、FがCに代理権があることを信じたか否かを示す事実であるが、有権代理構成では相手方の主観は問題とされないため、この事実は特段の意味を有するものではない。
2.1500万円の限度の代理権を授与したとの主張
(1)表見代理(民法110条)の要件
Fが、表題の通りの主張をするためには権限外の行為の表見代理(民法110条)の構成が考えられる。この場合、Fが主張立証すべきは、①FC間で本件消費貸借契約が締結されたこと、②前記①がAにとって商行為(商法504条)、③FがCに2000万円の借入れ権限があると信じたこと、④前記③と信じるにつき正当理由があったこと、⑤前記①に先立ってAからCに基本代理権(1500万円の借入れ権限)が授与されたこと、である。
(2)事実①について
ア.「Cには交渉の経過を話してあり、それをCが理解しているから」の部分
これは、③との関連で問題となる。つまり、FとAの従前の交渉では本件消費貸借契約の金額は1500万円とされていたのであり、AがCにこの経緯を話していたのだとすれば、与えられた代理権は1500万円であった、ということを意味する。要するに、この部分は、③FがCに2000万円の借入れ権限があると信じたこと、の評価障害事実となる。
イ.「後はCとの間でよろしく進めてほしい」の部分
これも、③との関連で問題となる。「よろしく進めてほしい」というからには、従前の内容をさらに詰める交渉をする権限をCに与えていると解釈することができる。とすると、金額は2000万円に変更し、Cがその新たな申し込みをする権限を与えられていたと考えうる。よって、この部分は、③FがCに2000万円の借入れ権限があると信じたこと、の評価根拠事実となる。
(3)事実②について
ア.「Aの携帯電話に電話をして融資額の変更を確認しようとした」部分
これは、④との関連で問題となる。つまり、Cが2000万円の借入れ権限を有していたかの確認としようとしたのであるから、④前記③と信じるにつき正当理由があったことを基礎づける評価根拠事実となる。
イ.「Aの電話がつながらなかったこと」の部分
これも、④との関連で問題となる。つまり、Aに直接確認することなく、Cに2000万円の借入れ権限があると信じることは軽率であって、④前記③と信じるにつき正当理由があったことの評価障害事実となる。Fは、Aに確認がとれないために自宅に電話をしてDに確認をしているが、本件融資額が2000万円であることからすれば、本人に直接確認をとるべきであり、それはさほど困難なことではない。よって、この部分は上記の通り、評価障害事実となる。
第2 設問2
1.小問(1)
(1)想定されるEの反論
ア.まず、Eとしては、丙建物を取り壊したとしても、依然として甲土地と乙土地は存在しているのであって、これらの残存価値が被担保債権額を上回るものであればFは満足を受けることができ、それゆえ損害は生じない、と反論することが考えられる。
イ.また、抵当権侵害に関する損害は、抵当権を実行してはじめて明らかになるものであって、実行前は損害を観念することはできない、と反論することが考えられる。
(2)検討
ア.まず、(1)アの点について検討する。
抵当権とは、目的物の価値把握権である。ここでいう価値とは、担保目的としての価値である。したがって、将来において満足を受けられないおそれがある場合は、抵当権を侵害された、すなわち、損害を観念することができる。
したがって、本件においても、残存価値のみでは将来において満足を受けられないおそれがある場合に、丙建物の取り壊しによって減少した担保価値を損害と捉えることができる。
イ.次に、(1)イの点について検討する。
アで述べた通り、将来の満足を妨げるおそれがあれば、抵当権者の価値把握権は侵害されているといえる。したがって、抵当権実行前であっても、残存価値のみでは将来において満足を受けられないおそれがある場合に、丙建物の取り壊しによって減少した担保価値を損害と捉えることができる。
ウ.なお、このように検討してきたことから、【事実】14に記す訴えに係る訴訟において留意すべき事項とは、甲土地と乙土地の残存価値が、Fの被担保債権をカバーしうるものであるか、ということになる。
2.小問(2)
(1)Eの反論の当否
ア.反論の根拠
Eの反論は、Fは抵当権設定登記を具備していないために、丙建物につき先に所有権移転登記を具備したEに対して、その抵当権を対抗できないというものである。すなわち、EとFは丙建物をめぐって相争う関係にあるから対抗関係にあり、民法177条の趣旨からして、Fは抵当権者であることを第三者であるEに主張することはできない、とするものである。
イ.Eの反論の当否
この点、所有権と抵当権は併存しうる関係にあるから、EとFは丙建物を相争う関係にはなく、そのため対抗関係にはならないようにも考えられる。しかしながら、所有権とは完全な物権であり、抵当権は目的物の価値把握権であることからすると、所有権は抵当権を飽食する関係にある物権であるといえ、その限度で両者は相争う関係にあると考えられる。そのため、やはり相争う関係と言えるのであり、Eの反論は妥当である。
(2)Fの再反論
Fとしては、仮にEとFが対抗関係にあるとしても、Eはいわゆる背信的悪意者であるため、なおFは抵当権者であることをEに主張することができる、との再反論が考えられる。つまり、「第三者」(民法177条)とは、当事者及び包括承継人以外の者であり、登記の欠けつを主張する正当な利益を有する者を意味するところ、単純悪意者はこれに含まれるが、背信的悪意者はこれに含まれないと考えるべきである。
本件でEは、AがFから金銭を借り入れた事実や、乙土地及び丙建物に抵当権設定契約がされたものの、登記がなされていないことを十分に認識している。そのうえで、丙建物が取り壊されれば自己の住居を建築することができると、私益を追及して丙建物の所有権移転登記を経ている。このようなEがFの抵当権の喪失を主張することは均衡を欠き、Fの抵当権設定登記の欠けつを主張する正当な利益は存在しないというべきである。
したがって、Fはこのような再反論をすべきであり、それは認められる。
第3 設問3
1.当事者について
本件訴訟行為の効力がEに及ぶかを検討する前提として、EとGのどちらが訴訟当事者であったか、その結論からGのした訴訟行為の効力はどうなるかを論ずる。
訴訟手続には明確性が要求されるから、訴訟当事者は、訴状の記載を合理的に解釈して決するべきである。本件では、訴状に記載された被告はEであり、また、Eこそまさに丙建物を破壊した者であるから、被告はEであることは明らかである。
したがって、原則として、訴訟当事者でないGのした訴訟行為は無効である。
2.本件におけるGの行為の効力について
上記のように解すると、Fにとっては酷な結果となる。つまり、知らぬ間に自己の氏名を使われる通常の氏名冒用訴訟と異なり、本件ではそもそもEが本件訴訟をGに一任したのであり、Gの行為が原則として無効となるや、Eは追認を拒否しているのである。Eの行為は訴訟上の信義に反するものであり、また、訴訟経済の要請からもGの行為の効果をEに及ぼすべき必要性は肯定される。ただし、無制限にそれを肯定した場合には、弁護士強制主義の原則(民事訴訟法54条1項)に反することになる。そこで、個別具体的な場面において、①相手方の利益を保護すべき必要が認められる場合であり、②弁護士強制主義原則の趣旨に反しない特段の事情がある場合に限り、当事者以外の行為の効果を肯定できる、と考えるべきである。
本件について考察する。まず、①本件ではFには全く帰責性がなく、また、第3回口頭弁論期日まで誠実に訴訟を追行してきた。にもかかわらず、Gの行為が無効となるとその間の訴訟活動が水泡に帰す。したがって、相手方であるFの利益を保護する必要がある。しかしながら、②仮に本件でGの行為の効果を肯定してしまうと、弁護士強制主義の原則をほとんど空文化させてしまいかねない。すなわち、他人に訴訟を行わせ、それが発覚してから弁護士に訴訟委任すれば従前の訴訟行為の効果が失われない、というのであれば、非弁活動を誘発することにもなりかねない。業務執行組合員のように本来的な当事者と関係を有する者ならばいざしらず、本件のような単なる同居人に訴訟を担当することを認めることは、弁護士強制主義の趣旨に反すること甚だしい。
したがって、本件においては、Gのした訴訟行為の効力はEには及ばないと考えるべきである。
第4 設問4
1.小問(1)
(1)法律構成①について
ア.長所について
まず、法律構成①によれば、訴訟物は元本債務全体であるので、確定判決の遮断効により、1500万円の部分については蒸し返しの恐れがないことが長所となる。
また、審判対象は元本債務の全体と構成し、1500万円の部分は原告自らが請求の範囲を画したものととらえることは、原告の意思を尊重し、それに忠実な審理をするという点も長所となる。
イ.短所について
まず、元本債務全体が審判対象であるところ、1500万円の部分も審判の対象となることになるが、この部分については当事者双方が争っていないため、確認の利益が肯定できるか、という疑問が生ずる点が短所といえる。
また、元本債務全体が訴訟物であるならば、1500万円の部分についても主文で判断すべきことになるところ、これが明確には判決主文に表現されないということは短所となりうる。
(2)法律構成②について
ア.長所について
1500万円の部分につき、請求の放棄があったと構成すれば、その部分につき「確定判決と同一の効力」(民事訴訟法267条)が与えられることになり、紛争の蒸し返しができなくなる点が長所として挙げられる。
イ.短所について
1500万円の部分について確認の利益が認められるかどうかの疑問が生ずる点は、(1)イで述べた点と同じである。
また、法律構成②は、1500万円の部分を原告の請求の放棄と捉えるが、これは原告の意思を拡張して解釈しているのではないか、原告の意思を蔑ろにする構成で はないか、という点が短所となる。
加えて、請求の放棄と構成するのであれば、本来は「調書」に記載しなくては確定判決と同一の効力が生じない(民事訴訟法267条)はずである。法律構成②のように構成した場合には、何をもって「調書」の記載があったとするのかが疑問である。仮に「調書」が不存在であれば確定判決と同一の効果は与えられず、紛争の蒸し返しを黙認することになりかねない。さらには、請求の放棄は「期日」でしなくてはいけないところ(民事訴訟法266条1項)、原告が明確に放棄の意思表示をしていないにもかかわらず、放棄があったと認めることができるのか、という点も短所となりうる。要するに、技巧的すぎる構成である。
2.小問(2)
(1)処分権主義(民事訴訟法246条)との関係
Fに対して、AがFに500万円を支払うことを条件として、抵当権設定登記抹消登記手続をすることを命ずる判決を下すことができるか。まず問題となるのは、これはAが明示的に求めている判決ではないので、処分権主義違反とならないか、ということである。いかに判断していくべきか。
この点、処分権主義の趣旨は、①原告の意思の尊重、②不意打ち防止、にある。とすると、原告の合理的意思からしてそのような判決をも許容するといえ、その判決を出すことが不意打ちとならない場合か否かを考慮して決すべきでさる。
本件では、元本が500万円残っているとして全部棄却されることは、原告Aが最も望まないことである。原告はあくまで抵当権設定登記の抹消を求めているのだから、全部棄却判決よりも、500万円の支払いをしても抵当権設定抹消登記手続をせよとの判決を求めると考えられる。また、元本債務が残存していればそれは返済がされるべきであり、そうした判決を出されることは原告Aにとって不意打ちとはいえない。また、被告は、元本債務が残存していれば返還を受ける地位にあり、完済された時には抵当権設定登記を抹消すべき地位にあるのだから、被告Fにとっても不意打ちとはいえない。
よって、本件において裁判所は、AがFに500万円を支払うことを条件として抵当権設定登記抹消登記手続をすることを命ずる判決を出すことができる。
(2)将来判決との関係
上記の通り、処分権主義との抵触はないとしても、抵当権設定登記抹消登記手続はAが500万円の返済をしてからのことであり、これは将来の給付を求める判決(民事訴訟法135条)である。将来の給付を求める判決は、「あらかじめその請求をする必要がある場合」に認められる。本件では、それが認められるか。
本件では、仮にAの債務が完済された場合に、Fは抵当権設定登記の抹消につき争っていると考える事情は見当たらない。Aとしても、現在において急ぎ抵当権設定登記抹消登記手続をせよとの判決を得ておく必要性は小さく、Aが債務を完済した場合に改めて同手続を求めても何ら障害はないと考えられる。むしろ、自己の債務を完済した後に抵当権設定登記抹消登記手続を求めるのが筋である。また、同時履行の抗弁が容れられた場合に出される引換給付と異なり、本件のような抵当権設定登記抹消登記手続請求権は訴訟物に付着するものではない。
そうだとすると、本件では「あらかじめその請求をする必要がある場合」とはいえない。
(3)結論
よって、本件において裁判所は、AがFに500万円を支払うことを条件として抵当権設定登記抹消登記手続をすることを命ずる判決を出すことはできない。
第5 設問5
1.AとEの父子関係
CとEの支払義務を考察する前提として、AとEの父子関係が肯定できるか、つまり、本件でAがしようとした認知が有効かをまず述べる。この点、認知は父子関係を発生させる対外的効果を有するものであるから、認知があったか否かは明確に線引きがなされなくてはいけない。したがって、認知は要式行為であって、届出によって効力が生ずる。民法781条1項もその趣旨である。
本件では、認知届を提出するだけの段階であり、また、Aの意思も明確であるが、認知届けはいまだ提出されていない。したがって、上述の点からして、このような段階においてもなお、認知の効果は肯定できない。
したがって、本件ではAとEに父子関係は生じていない。
2.支払義務の有無
(1)Cについて
CはAの子であり、相続人である。相続人は、「相続開始の時」から、被相続人の財産に属した「一切の権利義務を承継」する(民法896条)。Hは、Aの生前、Aに600万円を貸し付けているのであるから、「相続開始の時」に被相続人であるAは同債務を負っていた。そして、相続の対象は「一切の権利義務」であるから、同債務も相続の対象となる。
よって、Cは相続によりHに対する債務を承継したので、支払義務を負う。
(2)Eについて
先に述べた通り、EはAの子ではないので、相続人にはならない。とすると、Eが本件債務の支払義務を負うか否かが問題となるが、「私が死亡した時は、私の遺産はCを2、Eを1とする割合で分けること」とする自筆証書遺言は包括遺贈というべきであるところ、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を負う(民法990条)ので、EもCと同様に支払義務を負うことになる。
3.いくらの支払義務を負うか
本件では、Aの財産の3分の1はCに包括遺贈されており、金銭債務は相続に際して当然に分割されるので、CとEは、2:1の割合でHに対して負う債務を承継する。
よって、Cは400万円、Eは200万円を、Hに対して支払う義務を負う。
[第1問]
第1 設問1
1.不足額支払責任(会社法52条1項)
(1)Aについて
Aは甲社の発起人であり設立時取締役であるので、現物出資財産の価額が、定款に記載された価額に「著しく不足する」場合は、甲社に対して不足額の支払責任を負う(会社法52条1項)。本件現物出資において、定款に記載された価額は5億円であるが、実際の価額は1億円にすぎず、これは「著しく不足する」場合であると言える。
そして、Aは本件現物出資をした者であるから、免責は認められず、無過失責任を負う(会社法52条2項かっこ書き)。
よって、Aは、4億円の不足額支払責任を負う。
(2)Bについて
Bも甲社の発起人であり設立時取締役である。しかしながら、BはAと異なり、現物出資をした者ではないので、会社法52条2項1号もしくは2号の免責事由に該当すれば免責される。本件では、検査役の調査(会社法33条2項)は行われていないので1号には該当しえず、2号の該当性が検討事項となる。
2号によれば、Bは「その職務を行うについて注意を怠らなかった」場合に免責される。本件でBは、本件不動産の評価額を5億円とする不動産鑑定士の鑑定評価を得、また、定款に記載された5億円の価額が相当であることについて公認会計士の証明を受けている(会社法33条10項3号)。これは、法令上、検査役の調査を不要とする適切な行為である。また、Bは設立時取締役に選任された後、遅滞なく上記不動産鑑定士の評価、公認会計士の証明が相当であること、設立時発行株式に係る出資の履行が完了していることを調査している(会社法93条1項2号、3号)。これも法令に則った適切な行為である。さらに、本件現物出資財産の価額が著しく不足した原因は土壌汚染によるものであるが、これは外形上明らかな瑕疵ではなく、専門家たる不動産鑑定士と公認会計士も認識しなかったのであるから、Bがこれに気付かなかったことをもって、「注意」を怠ったと評価することはできない。
よって、Bは会社法52条2項2号により免責され、責任を負わない。
2.損害賠償責任(会社法53条1項)
(1)Aについて
本件現物出資財産の価額が著しく不足していることにより、甲社には差額である4億円の損害が生じている。Aは、土壌汚染を知っていたのであるから、「任務を怠った」といえ、4億円の損害を賠償する責任がある。
(2)Bについて
他方、Bについては、「任務を怠った」とはいえない。1.(2)で述べたことに加え、Aが土壌汚染を認識していたとしても、土壌汚染は稀なことであり、その有無につき確認するまでの任務はないと考えられるからである。
よって、Bは責任を負わない。
第2 設問2
1.①払込みの効力と発行された株式の効力
(1)払込みの効力
本件募集株式発行は、形式上、丙社から1億円の払込みがあるが、このうち9000万円の部分については、払込みがされた翌日に甲社の口座から引き出され、丙社に返還されている。まず、このいわゆる見せ金と呼ばれる仮装払込みがなされた場合の効力であるが、その仮装された部分につき無効と考えるべきである(一部無効)。なぜなら、仮装払込みを有効と扱うことは資本充実原則を蔑ろにするものであり、他方で、現実に出資され資本に組み込まれた部分は資本充実原則の要請をみたすからである。したがって、本件では、1000万円の部分が有効な払込みであることはまず確定できる。問題は、9000万円の部分であるため、以下にそれを論ずる。
資本充実原則からすれば、払込みの効力の有無は、出資された財産が現実的に資本として意味をなすものであったかどうか、が基準とされるべきである。具体的には、①当該払込金とされた財産が返還・返済に充てられるまでの期間、②当該払込金とされた財産の運用の有無、③当該払込金とされた財産の返還・返済が募集株式発行会社に与える影響、を考慮して決せられるべきである。本件では、①問題の9000万円は翌日に甲社から丙社に返還され、丁銀行に返済されている。また、②この9000万円の運用の事実は全くない。さらに、③本件9000万円は甲社の資本金である3億5000万円(資料②)のかなりの部分を占めるもので、かつ、予定されていた店舗改装の可否に影響を与えるものであるから、甲社に与える影響は大きい。以上のことからすると、本件9000万円の部分は現実的に資本としての意味をなしたものとは評価できない。
よって、1000万円の部分については有効な払込みがあったが、9000万円の部分については、払込みとしての効力は認めらないと考える。
(2)発行された株式の効力
上述の通り、9000万円の部分についての払込みは無効であるが、本件では既に1億円の払込金額に相当する1000株の株式は、外形上、有効に成立している。
そこでまず問題になるのが、9000万円分に相当する900株を無効にできるか、つまり、株式の効力を一部無効にすることができるか、という点である。この点、新株発行無効の訴え(会社法828条1項2号)の認容判決が対世効を有する(会社法838条)ことから、一部無効は認められないようにも思える。しかし、この点は会社法828条1項2号に規定された訴えによらず、個別的に株主たる地位の不存在確認訴訟を提起することができるのだから、決定的な理由にならない。むしろ、募集株式の引受人が出資の履行をしない場合は失権する(会社法208条5項)と定めていることからすれば、法は部分的に株式の効力を失わしめることを認容していると考えられる。そうだとすれば、発行された株式の一部無効も認められると考える。
では、いかなる場合に無効になるか。この点、株式の無効事由は明定されていないので、解釈による必要がある。本来、発行に至る過程で重大な瑕疵があれば当該株式が成立する根拠はなく、無効となると考えるのが筋である。しかし、それでは株式の流通が阻害される。そこで、取引安全の見地から、既に発行された株式は原則として有効に扱われるが、取引安全を害さず、かつ、株式を無効とすべき特段の事情のある場合のみ例外的に無効になると解するべきである。本件では、株式は当初の引受人である丙社のもとにとどまっており、これを無効としても取引安全を害することはない。そして、本件の株式発行にかかる瑕疵は出資の実体を欠く仮装払込みであり、株式の効力を否定すべき必要性は大きい。
したがって、900株の部分につき、株式は無効であると考える。
2.②甲社に対しての責任
(1)甲社の損害について
A、B及び丙社が甲社に対して負う責任を論ずる前提として、本件募集株式発行によって甲社にいかなる損害が生じたかをまず検討する。
この点、損害は上述の9000万円であるように思えるが、これはあくまで出資であり、甲社の財産が既存されたわけではないので、損害と観念することはできない。甲社の損害は、本件募集株式発行が原因となり、破綻したことである。A、Bについてはこれを念頭に責任を論ずる。
(2)Aの責任
Aは、甲社の取締役であるから、会社法423条1項の責任を負うかが問題となる。
まず、「任務を怠った」か否かが問題となるが、Aは本件募集株式発行につき、見せ金による仮装払込みの主導的役割を果たした者であり、これは明らかに忠実義務(会社法355条)に反する行為である。そして、現実的に払込みがなかったことにより甲社は店舗改装ができなかった。そのため、引き続き大手ディスカウントストアに対抗できず、結果として甲社は倒産に至っているので、Aの行為と倒産による損害は因果関係も認められる。
したがって、Aは甲社の倒産により生じた損害を賠償する責任を負う。
(3)Bの責任
Bも甲社の取締役であるため、会社法423条1項の責任を負うかが問題となる。
この点、BはAと異なり、本件仮装払込みには関与していない。しかし、Bは取締役会の構成員として、取締役の職務執行を監督せねばならない(会社法362条2項1号)。にもかかわらず、BはAに本件募集株式発行の手続を実質的に一任しており、何ら監督をしていない。これは「任務を怠った」ものといえる。
したがって、Bも甲社の倒産により生じた損害を賠償する責任を負う。
(4)丙社の責任
丙社は、本件募集株式発行に際し、形式的には1億円の払込みをしているが、実質的に払込金として捻出したのは1000万円にとどまる。そうすると、1000万円の払込みで、その10倍である1億円の払込みに相当する1000株を引き受けたことになる。これは、「著しく不公正な払込み金額で募集株式を引き受けた」(会社法212条1項1号)ものと言える。かつ、本件仮装払込みは、丙社の代表取締役DがAの指示を受けて行ったものであり、「取締役と通じて」(会社法212条1項1号)なしたものといえる。したがって、丙社は公正な価額との差額である9000万円を支払う責任を負う。
なお、1.(2)で900株分は無効であるとしたが、株式の効力は訴訟を通じてはじめて判断されるものであり、これが丙社の負う上記差額の支払義務の結論を左右することはない。
3.③乙銀行に対しての責任
(1)Aの責任(会社法429条2項)
Aは、甲社の貸借対照表(資料①)を作成している。資産の部において、実質的には1000万円しか払込みのなかった本件募集株式発行の払込みにかかわる1億円を含む1億2000万円を現金資産として記載し、また、土壌汚染により本来は1億円の価値しかない建物及び土地を5億円と記載している。すなわち、「虚偽の記載」(会社法429条2項1号ロ)をしている。そして、これを乙銀行に示している。乙銀行はこれを信頼して甲社に1億円を融資したものの、甲社の破綻により回収不能となり、損害を被っている。
よって、Aは乙銀行に対して、1億円の損害賠償責任を負う。
(2)Bの責任(会社法429条1項)
BはAと異なり貸借対照表の記載者ではないので、責任の根拠としては、会社法429条1項が考えられる。まず、429条1項の法的性質が前提として検討されるべきであるが、第三者救済の見地から、これは特別の法定責任であると考え、「悪意又は重大な過失」(会社法429条1項)は、会社に対する任務違反について、を意味すると解する。
本件で「悪意又は重大な過失」が認められるか。まず、本件募集株式発行の手続きをAに一任していた点は、2.(3)に述べた通りである。これに加え、乙銀行からの融資はあくまでも店舗改装のためになされたはずなのに、甲社では実際に行われなかった。業績回復を狙った店舗改装であれば速やかに行われるべきところ、Bはこれについて確認や何らの指摘もしていない。これは、取締役としてあるまじき行為であり、忠実義務違反行為であると評価できる。
よって、Bは会社に対する任務を怠ったといえ、これに起因して生じた乙銀行の1億円の損害を賠償する責任を負う。
[第2問]
第1 設問1
1.金額に限度のない代理権を授与したとの主張
(1)有権代理の要件
Fが、表題の通りの主張をするためには有権代理(民法99条)の構成が考えられる。この場合、Fが主張立証すべきは、①FC間で本件消費貸借契約が締結されたこと、②前記①がAにとって商行為(商法504条)であること、③前記①に先立ってAからCに代理権が授与されたこと、である。
(2)事実①について
ア.「Cには交渉の経過を話してあり、それをCが理解しているから」の部分
これは、③の要件と関連して問題になる。つまり、CにはAの意向を全て話してあり、あくまでも意思決定権はAのみにあると解釈することのできる言葉である。Cには意思決定権限がなく、Aの手足として、使者として行動することを意味する。これは、③代理権授与の事実の間接反証としての意味を有すると考える。
イ.「後はCとの間でよろしく進めてほしい」の部分
これも、③の要件と関連して問題になる。ただし、この部分は上述のアと異なり、交渉はCとの間で進めること、つまり、交渉に際してはCの意思に委ねることを意味している。「よろしく進めて」ということからには、Cが柔軟に対応することを予定しており、金額についてもCに委ねた、ということを意味する。よって、この部分は金額を含めて、Cに③代理権を授与した事実を示す間接事実と考える。
(3)事実②について
事実②は、FがCに代理権があることを信じたか否かを示す事実であるが、有権代理構成では相手方の主観は問題とされないため、この事実は特段の意味を有するものではない。
2.1500万円の限度の代理権を授与したとの主張
(1)表見代理(民法110条)の要件
Fが、表題の通りの主張をするためには権限外の行為の表見代理(民法110条)の構成が考えられる。この場合、Fが主張立証すべきは、①FC間で本件消費貸借契約が締結されたこと、②前記①がAにとって商行為(商法504条)、③FがCに2000万円の借入れ権限があると信じたこと、④前記③と信じるにつき正当理由があったこと、⑤前記①に先立ってAからCに基本代理権(1500万円の借入れ権限)が授与されたこと、である。
(2)事実①について
ア.「Cには交渉の経過を話してあり、それをCが理解しているから」の部分
これは、③との関連で問題となる。つまり、FとAの従前の交渉では本件消費貸借契約の金額は1500万円とされていたのであり、AがCにこの経緯を話していたのだとすれば、与えられた代理権は1500万円であった、ということを意味する。要するに、この部分は、③FがCに2000万円の借入れ権限があると信じたこと、の評価障害事実となる。
イ.「後はCとの間でよろしく進めてほしい」の部分
これも、③との関連で問題となる。「よろしく進めてほしい」というからには、従前の内容をさらに詰める交渉をする権限をCに与えていると解釈することができる。とすると、金額は2000万円に変更し、Cがその新たな申し込みをする権限を与えられていたと考えうる。よって、この部分は、③FがCに2000万円の借入れ権限があると信じたこと、の評価根拠事実となる。
(3)事実②について
ア.「Aの携帯電話に電話をして融資額の変更を確認しようとした」部分
これは、④との関連で問題となる。つまり、Cが2000万円の借入れ権限を有していたかの確認としようとしたのであるから、④前記③と信じるにつき正当理由があったことを基礎づける評価根拠事実となる。
イ.「Aの電話がつながらなかったこと」の部分
これも、④との関連で問題となる。つまり、Aに直接確認することなく、Cに2000万円の借入れ権限があると信じることは軽率であって、④前記③と信じるにつき正当理由があったことの評価障害事実となる。Fは、Aに確認がとれないために自宅に電話をしてDに確認をしているが、本件融資額が2000万円であることからすれば、本人に直接確認をとるべきであり、それはさほど困難なことではない。よって、この部分は上記の通り、評価障害事実となる。
第2 設問2
1.小問(1)
(1)想定されるEの反論
ア.まず、Eとしては、丙建物を取り壊したとしても、依然として甲土地と乙土地は存在しているのであって、これらの残存価値が被担保債権額を上回るものであればFは満足を受けることができ、それゆえ損害は生じない、と反論することが考えられる。
イ.また、抵当権侵害に関する損害は、抵当権を実行してはじめて明らかになるものであって、実行前は損害を観念することはできない、と反論することが考えられる。
(2)検討
ア.まず、(1)アの点について検討する。
抵当権とは、目的物の価値把握権である。ここでいう価値とは、担保目的としての価値である。したがって、将来において満足を受けられないおそれがある場合は、抵当権を侵害された、すなわち、損害を観念することができる。
したがって、本件においても、残存価値のみでは将来において満足を受けられないおそれがある場合に、丙建物の取り壊しによって減少した担保価値を損害と捉えることができる。
イ.次に、(1)イの点について検討する。
アで述べた通り、将来の満足を妨げるおそれがあれば、抵当権者の価値把握権は侵害されているといえる。したがって、抵当権実行前であっても、残存価値のみでは将来において満足を受けられないおそれがある場合に、丙建物の取り壊しによって減少した担保価値を損害と捉えることができる。
ウ.なお、このように検討してきたことから、【事実】14に記す訴えに係る訴訟において留意すべき事項とは、甲土地と乙土地の残存価値が、Fの被担保債権をカバーしうるものであるか、ということになる。
2.小問(2)
(1)Eの反論の当否
ア.反論の根拠
Eの反論は、Fは抵当権設定登記を具備していないために、丙建物につき先に所有権移転登記を具備したEに対して、その抵当権を対抗できないというものである。すなわち、EとFは丙建物をめぐって相争う関係にあるから対抗関係にあり、民法177条の趣旨からして、Fは抵当権者であることを第三者であるEに主張することはできない、とするものである。
イ.Eの反論の当否
この点、所有権と抵当権は併存しうる関係にあるから、EとFは丙建物を相争う関係にはなく、そのため対抗関係にはならないようにも考えられる。しかしながら、所有権とは完全な物権であり、抵当権は目的物の価値把握権であることからすると、所有権は抵当権を飽食する関係にある物権であるといえ、その限度で両者は相争う関係にあると考えられる。そのため、やはり相争う関係と言えるのであり、Eの反論は妥当である。
(2)Fの再反論
Fとしては、仮にEとFが対抗関係にあるとしても、Eはいわゆる背信的悪意者であるため、なおFは抵当権者であることをEに主張することができる、との再反論が考えられる。つまり、「第三者」(民法177条)とは、当事者及び包括承継人以外の者であり、登記の欠けつを主張する正当な利益を有する者を意味するところ、単純悪意者はこれに含まれるが、背信的悪意者はこれに含まれないと考えるべきである。
本件でEは、AがFから金銭を借り入れた事実や、乙土地及び丙建物に抵当権設定契約がされたものの、登記がなされていないことを十分に認識している。そのうえで、丙建物が取り壊されれば自己の住居を建築することができると、私益を追及して丙建物の所有権移転登記を経ている。このようなEがFの抵当権の喪失を主張することは均衡を欠き、Fの抵当権設定登記の欠けつを主張する正当な利益は存在しないというべきである。
したがって、Fはこのような再反論をすべきであり、それは認められる。
第3 設問3
1.当事者について
本件訴訟行為の効力がEに及ぶかを検討する前提として、EとGのどちらが訴訟当事者であったか、その結論からGのした訴訟行為の効力はどうなるかを論ずる。
訴訟手続には明確性が要求されるから、訴訟当事者は、訴状の記載を合理的に解釈して決するべきである。本件では、訴状に記載された被告はEであり、また、Eこそまさに丙建物を破壊した者であるから、被告はEであることは明らかである。
したがって、原則として、訴訟当事者でないGのした訴訟行為は無効である。
2.本件におけるGの行為の効力について
上記のように解すると、Fにとっては酷な結果となる。つまり、知らぬ間に自己の氏名を使われる通常の氏名冒用訴訟と異なり、本件ではそもそもEが本件訴訟をGに一任したのであり、Gの行為が原則として無効となるや、Eは追認を拒否しているのである。Eの行為は訴訟上の信義に反するものであり、また、訴訟経済の要請からもGの行為の効果をEに及ぼすべき必要性は肯定される。ただし、無制限にそれを肯定した場合には、弁護士強制主義の原則(民事訴訟法54条1項)に反することになる。そこで、個別具体的な場面において、①相手方の利益を保護すべき必要が認められる場合であり、②弁護士強制主義原則の趣旨に反しない特段の事情がある場合に限り、当事者以外の行為の効果を肯定できる、と考えるべきである。
本件について考察する。まず、①本件ではFには全く帰責性がなく、また、第3回口頭弁論期日まで誠実に訴訟を追行してきた。にもかかわらず、Gの行為が無効となるとその間の訴訟活動が水泡に帰す。したがって、相手方であるFの利益を保護する必要がある。しかしながら、②仮に本件でGの行為の効果を肯定してしまうと、弁護士強制主義の原則をほとんど空文化させてしまいかねない。すなわち、他人に訴訟を行わせ、それが発覚してから弁護士に訴訟委任すれば従前の訴訟行為の効果が失われない、というのであれば、非弁活動を誘発することにもなりかねない。業務執行組合員のように本来的な当事者と関係を有する者ならばいざしらず、本件のような単なる同居人に訴訟を担当することを認めることは、弁護士強制主義の趣旨に反すること甚だしい。
したがって、本件においては、Gのした訴訟行為の効力はEには及ばないと考えるべきである。
第4 設問4
1.小問(1)
(1)法律構成①について
ア.長所について
まず、法律構成①によれば、訴訟物は元本債務全体であるので、確定判決の遮断効により、1500万円の部分については蒸し返しの恐れがないことが長所となる。
また、審判対象は元本債務の全体と構成し、1500万円の部分は原告自らが請求の範囲を画したものととらえることは、原告の意思を尊重し、それに忠実な審理をするという点も長所となる。
イ.短所について
まず、元本債務全体が審判対象であるところ、1500万円の部分も審判の対象となることになるが、この部分については当事者双方が争っていないため、確認の利益が肯定できるか、という疑問が生ずる点が短所といえる。
また、元本債務全体が訴訟物であるならば、1500万円の部分についても主文で判断すべきことになるところ、これが明確には判決主文に表現されないということは短所となりうる。
(2)法律構成②について
ア.長所について
1500万円の部分につき、請求の放棄があったと構成すれば、その部分につき「確定判決と同一の効力」(民事訴訟法267条)が与えられることになり、紛争の蒸し返しができなくなる点が長所として挙げられる。
イ.短所について
1500万円の部分について確認の利益が認められるかどうかの疑問が生ずる点は、(1)イで述べた点と同じである。
また、法律構成②は、1500万円の部分を原告の請求の放棄と捉えるが、これは原告の意思を拡張して解釈しているのではないか、原告の意思を蔑ろにする構成で はないか、という点が短所となる。
加えて、請求の放棄と構成するのであれば、本来は「調書」に記載しなくては確定判決と同一の効力が生じない(民事訴訟法267条)はずである。法律構成②のように構成した場合には、何をもって「調書」の記載があったとするのかが疑問である。仮に「調書」が不存在であれば確定判決と同一の効果は与えられず、紛争の蒸し返しを黙認することになりかねない。さらには、請求の放棄は「期日」でしなくてはいけないところ(民事訴訟法266条1項)、原告が明確に放棄の意思表示をしていないにもかかわらず、放棄があったと認めることができるのか、という点も短所となりうる。要するに、技巧的すぎる構成である。
2.小問(2)
(1)処分権主義(民事訴訟法246条)との関係
Fに対して、AがFに500万円を支払うことを条件として、抵当権設定登記抹消登記手続をすることを命ずる判決を下すことができるか。まず問題となるのは、これはAが明示的に求めている判決ではないので、処分権主義違反とならないか、ということである。いかに判断していくべきか。
この点、処分権主義の趣旨は、①原告の意思の尊重、②不意打ち防止、にある。とすると、原告の合理的意思からしてそのような判決をも許容するといえ、その判決を出すことが不意打ちとならない場合か否かを考慮して決すべきでさる。
本件では、元本が500万円残っているとして全部棄却されることは、原告Aが最も望まないことである。原告はあくまで抵当権設定登記の抹消を求めているのだから、全部棄却判決よりも、500万円の支払いをしても抵当権設定抹消登記手続をせよとの判決を求めると考えられる。また、元本債務が残存していればそれは返済がされるべきであり、そうした判決を出されることは原告Aにとって不意打ちとはいえない。また、被告は、元本債務が残存していれば返還を受ける地位にあり、完済された時には抵当権設定登記を抹消すべき地位にあるのだから、被告Fにとっても不意打ちとはいえない。
よって、本件において裁判所は、AがFに500万円を支払うことを条件として抵当権設定登記抹消登記手続をすることを命ずる判決を出すことができる。
(2)将来判決との関係
上記の通り、処分権主義との抵触はないとしても、抵当権設定登記抹消登記手続はAが500万円の返済をしてからのことであり、これは将来の給付を求める判決(民事訴訟法135条)である。将来の給付を求める判決は、「あらかじめその請求をする必要がある場合」に認められる。本件では、それが認められるか。
本件では、仮にAの債務が完済された場合に、Fは抵当権設定登記の抹消につき争っていると考える事情は見当たらない。Aとしても、現在において急ぎ抵当権設定登記抹消登記手続をせよとの判決を得ておく必要性は小さく、Aが債務を完済した場合に改めて同手続を求めても何ら障害はないと考えられる。むしろ、自己の債務を完済した後に抵当権設定登記抹消登記手続を求めるのが筋である。また、同時履行の抗弁が容れられた場合に出される引換給付と異なり、本件のような抵当権設定登記抹消登記手続請求権は訴訟物に付着するものではない。
そうだとすると、本件では「あらかじめその請求をする必要がある場合」とはいえない。
(3)結論
よって、本件において裁判所は、AがFに500万円を支払うことを条件として抵当権設定登記抹消登記手続をすることを命ずる判決を出すことはできない。
第5 設問5
1.AとEの父子関係
CとEの支払義務を考察する前提として、AとEの父子関係が肯定できるか、つまり、本件でAがしようとした認知が有効かをまず述べる。この点、認知は父子関係を発生させる対外的効果を有するものであるから、認知があったか否かは明確に線引きがなされなくてはいけない。したがって、認知は要式行為であって、届出によって効力が生ずる。民法781条1項もその趣旨である。
本件では、認知届を提出するだけの段階であり、また、Aの意思も明確であるが、認知届けはいまだ提出されていない。したがって、上述の点からして、このような段階においてもなお、認知の効果は肯定できない。
したがって、本件ではAとEに父子関係は生じていない。
2.支払義務の有無
(1)Cについて
CはAの子であり、相続人である。相続人は、「相続開始の時」から、被相続人の財産に属した「一切の権利義務を承継」する(民法896条)。Hは、Aの生前、Aに600万円を貸し付けているのであるから、「相続開始の時」に被相続人であるAは同債務を負っていた。そして、相続の対象は「一切の権利義務」であるから、同債務も相続の対象となる。
よって、Cは相続によりHに対する債務を承継したので、支払義務を負う。
(2)Eについて
先に述べた通り、EはAの子ではないので、相続人にはならない。とすると、Eが本件債務の支払義務を負うか否かが問題となるが、「私が死亡した時は、私の遺産はCを2、Eを1とする割合で分けること」とする自筆証書遺言は包括遺贈というべきであるところ、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を負う(民法990条)ので、EもCと同様に支払義務を負うことになる。
3.いくらの支払義務を負うか
本件では、Aの財産の3分の1はCに包括遺贈されており、金銭債務は相続に際して当然に分割されるので、CとEは、2:1の割合でHに対して負う債務を承継する。
よって、Cは400万円、Eは200万円を、Hに対して支払う義務を負う。