さて,前回記事の回答です。短答肢の考え方,勉強の仕方を示していきます。「問題」「関連条文」「正解&解説」を示して,その後に「考え方」として,今日の本題にあたる部分を書きます。
=問題=
「Xは,Yに対して,平成18年1月1日と平成22年1月1日に,それぞれ100万円を貸し付けた。いずれも,弁済期・利息・保証の約定などはない。Yが,平成23年1月1日に,Xに対して,50万円を弁済した場合,それは平成18年1月1日の貸金債務に充当される。なお,X・Yいずれもどちらの債務に充当するか指定していないものとする。」
=関連条文=
(弁済の充当の指定)
第四百八十八条 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
3 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。
(法定充当)
第四百八十九条 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
=正解&解説=
正解:○
期限の定めのない債務は,つねに「弁済期が到来したもの」と解し,その間においては先に成立したものを「弁済期が先に到来したもの」とする(大判T.6.10.20,我妻・有泉「コンメンタール民法<補訂版>868頁」)。
=考え方=
解説を書けばこうなります。内田先生の本あたりにも書かれていないことなので,知識として知っている方はあまり多くないでしょう。合格者でもここまで押さえている人は少ないと思います。
ただ,合格者の多くは結論としてたどり着けるはず。私だったら,頭の中で次のように考えて,「○」の結論を出すと思います。
まず,同一当事者といえど,2回の貸付があれば,これは別個の金銭消費貸借契約が成立し,別個の債権が成立している(1個の契約で2回に分けて貸し付けた場合とは違う)。とうすると,平成18年の債務に充当されるか,平成22年の債務に充当されるか,という問題が生ずる。
充当の指定はしていないので,488の問題ではない。とすると,489の問題。そうであるなら,期限の定めなき債務について,弁済期をいつにとるのかで結論がだいぶ変わってくることになる。ここから考えなくては。
412Ⅲからすると,履行の請求をした時に弁済期が到来したことになるのか?いや,違う,412は付遅滞の時期を定めたもので,弁済期について規定したものではない。だから,履行の請求を弁済期の基準とするのは,ちょっとおかしい。現実的に考えても,債権者の履行の請求が,どの債権につき,いつあったかで結論が変わるとなると,あまりにも煩雑になってしまう。
それよりは,591Ⅰを参考にすべきでないか。消費貸借で貸主は(いつでも)相当の期間を定めて返還請求できるのだから,基本的に,期限の定めない金銭消費貸借契約は,契約成立のから弁済期にあるというべきで,ただそれでは契約の目的を達しえないので,591Ⅰは「相当の期間」という縛りを設けたのだ。
時効の時の話を参考にしても,そうであるはずだ。時効の場面では,期限の定めのない債権は,債権者はいつでも請求できるから,原則として債権成立の時から時効は進行する。
要するに,民法は,期限の定めがない債権は,契約の時から弁済期にあると考えているのだ(直ちに弁済期を迎えると考えているのだ)。だから,本件では,それぞれ平成18年,平成22年にすでに弁済期にあるのだ。
したがって,本件では,489①の場面ではない。②か③の場面だが,そうすると,②にいう,「債務者のために弁済の利益が多いもの」の場面かどうかが問題になる。
平成18年,平成22年,の時期の違いによって,債務者の利益に何か関係ある事由はあるか?強いて言えば,時効か?債務者からすると,後から時効になる平成22年に充当してもらった方が利益といえば利益。しかし,完成前の時効なんて,法的利益と言えるはずがない。事実上の利益にすぎない。
したがって,本件は,③の「債務者のために弁済の利益が相等しいとき」の場面だ。そうすると,弁済期が先に来るものから充当されることになるので,本件では平成18年の方から充当されることになる。だから,正解は「○」だ。
=以上=
頭の中で考えるであろうことを,ぐだぐだと文章にするとこんな感じになります(これはあまりにもぐだぐだ書き過ぎですが…)。
解説を読んで結論だけ押さえる勉強は,「点」の集積。ちょっと応用的な問題を出されると対応できず,それゆえもちろん試験で点は伸びない(さらに言えば,やはり実務家の資格を与える能力に欠く)。短答で6割(210点)の壁を超えられない方は,その多くがここらに問題があると思います。
そうではなく,短答の肢からこう「考え」ながら答えが導けるように勉強していくこと,常に基本原理・原則から思考を展開していくことは,「線」の勉強であり,これが「骨太な
」「理解」を伴う勉強です。=考え方=の部分には難しいことは書いていないです。誰でも知っていることを積み上げただけです。それで答えを導く。
論文ももちろん同じ。かつて記事にしましたが,難しい・何が問われているかわからないといわれた,平成21年・民訴もこういうイメージ。
確実な論理を積み上げる。これさえできれば合格です。短答であれば,「何度やっても8割くらい」の水準に到達します。論文であれば,「大枠をはずさない」「何が聞かれてもしっかり答えられる」「(時には)書くのが楽しい」という水準に到達します。目指すべきはここです。
今年の問題を見るに,安直な方法(判旨・結論だけの暗記,論証パターンの暗記など)では受からせない,そういう試験委員のメッセージが伝わってきます。軌道修正をするなら今です。参考にしていただければ幸いです。
=問題=
「Xは,Yに対して,平成18年1月1日と平成22年1月1日に,それぞれ100万円を貸し付けた。いずれも,弁済期・利息・保証の約定などはない。Yが,平成23年1月1日に,Xに対して,50万円を弁済した場合,それは平成18年1月1日の貸金債務に充当される。なお,X・Yいずれもどちらの債務に充当するか指定していないものとする。」
=関連条文=
(弁済の充当の指定)
第四百八十八条 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
3 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。
(法定充当)
第四百八十九条 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
=正解&解説=
正解:○
期限の定めのない債務は,つねに「弁済期が到来したもの」と解し,その間においては先に成立したものを「弁済期が先に到来したもの」とする(大判T.6.10.20,我妻・有泉「コンメンタール民法<補訂版>868頁」)。
=考え方=
解説を書けばこうなります。内田先生の本あたりにも書かれていないことなので,知識として知っている方はあまり多くないでしょう。合格者でもここまで押さえている人は少ないと思います。
ただ,合格者の多くは結論としてたどり着けるはず。私だったら,頭の中で次のように考えて,「○」の結論を出すと思います。
まず,同一当事者といえど,2回の貸付があれば,これは別個の金銭消費貸借契約が成立し,別個の債権が成立している(1個の契約で2回に分けて貸し付けた場合とは違う)。とうすると,平成18年の債務に充当されるか,平成22年の債務に充当されるか,という問題が生ずる。
充当の指定はしていないので,488の問題ではない。とすると,489の問題。そうであるなら,期限の定めなき債務について,弁済期をいつにとるのかで結論がだいぶ変わってくることになる。ここから考えなくては。
412Ⅲからすると,履行の請求をした時に弁済期が到来したことになるのか?いや,違う,412は付遅滞の時期を定めたもので,弁済期について規定したものではない。だから,履行の請求を弁済期の基準とするのは,ちょっとおかしい。現実的に考えても,債権者の履行の請求が,どの債権につき,いつあったかで結論が変わるとなると,あまりにも煩雑になってしまう。
それよりは,591Ⅰを参考にすべきでないか。消費貸借で貸主は(いつでも)相当の期間を定めて返還請求できるのだから,基本的に,期限の定めない金銭消費貸借契約は,契約成立のから弁済期にあるというべきで,ただそれでは契約の目的を達しえないので,591Ⅰは「相当の期間」という縛りを設けたのだ。
時効の時の話を参考にしても,そうであるはずだ。時効の場面では,期限の定めのない債権は,債権者はいつでも請求できるから,原則として債権成立の時から時効は進行する。
要するに,民法は,期限の定めがない債権は,契約の時から弁済期にあると考えているのだ(直ちに弁済期を迎えると考えているのだ)。だから,本件では,それぞれ平成18年,平成22年にすでに弁済期にあるのだ。
したがって,本件では,489①の場面ではない。②か③の場面だが,そうすると,②にいう,「債務者のために弁済の利益が多いもの」の場面かどうかが問題になる。
平成18年,平成22年,の時期の違いによって,債務者の利益に何か関係ある事由はあるか?強いて言えば,時効か?債務者からすると,後から時効になる平成22年に充当してもらった方が利益といえば利益。しかし,完成前の時効なんて,法的利益と言えるはずがない。事実上の利益にすぎない。
したがって,本件は,③の「債務者のために弁済の利益が相等しいとき」の場面だ。そうすると,弁済期が先に来るものから充当されることになるので,本件では平成18年の方から充当されることになる。だから,正解は「○」だ。
=以上=
頭の中で考えるであろうことを,ぐだぐだと文章にするとこんな感じになります(これはあまりにもぐだぐだ書き過ぎですが…)。
解説を読んで結論だけ押さえる勉強は,「点」の集積。ちょっと応用的な問題を出されると対応できず,それゆえもちろん試験で点は伸びない(さらに言えば,やはり実務家の資格を与える能力に欠く)。短答で6割(210点)の壁を超えられない方は,その多くがここらに問題があると思います。
そうではなく,短答の肢からこう「考え」ながら答えが導けるように勉強していくこと,常に基本原理・原則から思考を展開していくことは,「線」の勉強であり,これが「骨太な
」「理解」を伴う勉強です。=考え方=の部分には難しいことは書いていないです。誰でも知っていることを積み上げただけです。それで答えを導く。
論文ももちろん同じ。かつて記事にしましたが,難しい・何が問われているかわからないといわれた,平成21年・民訴もこういうイメージ。
確実な論理を積み上げる。これさえできれば合格です。短答であれば,「何度やっても8割くらい」の水準に到達します。論文であれば,「大枠をはずさない」「何が聞かれてもしっかり答えられる」「(時には)書くのが楽しい」という水準に到達します。目指すべきはここです。
今年の問題を見るに,安直な方法(判旨・結論だけの暗記,論証パターンの暗記など)では受からせない,そういう試験委員のメッセージが伝わってきます。軌道修正をするなら今です。参考にしていただければ幸いです。











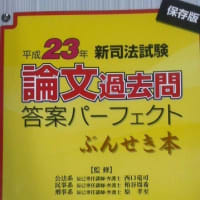
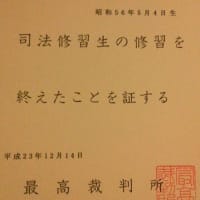
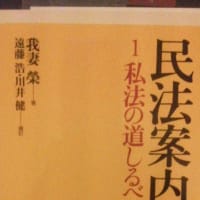






今頃言っていては笑われますが、先生の解答への考え方をみて目がさめました
私が短答問題を解くとき、先生のように筋道立てて考えていませんでした
私には家族もあり来年は絶対合格せねばなりません
先生のスタ短特訓講座を受講したいと思いますが、DVDは今でも購入できるのでしょうか?
今は藁にもすがりたい思いです
ご教示願います
…結論の確認・暗記に走りがちになってしまう気持ちはわかります。私も最初はそうでした。しかしながら,「その先」が合格水準であり,実務法曹として求められる水準なんですよね。法律に「使われる」のではなく,法律を「使いこなせる」ようになると,合格はほぼ確実といっていいと思います。「使いこなす」とは,条文から出発して,思考が展開できるようになることです(そして,それが多くの場合に判例の結論と一致する)。
ご家族のためにも,来年こそ,見事に合格を果たしてください。勉強法の質問等,こちらまでご遠慮なくどうぞ。
はるひろパパと申します。今後も宜しくお願いいたします。
親切なお返事、ありがとうございました。
過去問、脚別本などを繰り返しましたが、答えを覚える勉強に陥ってました
過去問は正しい法的思考を身に付けるツールなんですね。
もう一度自分で過去問にあたってみます。