発表直後のこの時期,リベンジを期す受験生から多くの相談を受けます。その際,私は,「これからどういうことをやろうとしているのか?」と問います。すると,返ってくる答えの中で多いものとして,「基礎知識が足りない(固まっていない)と思うので,もう一度基本書を読もうと思います。」というものがあります。
この答えの是非については難しいですが(本当に基礎知識の欠如で不合格だったのか,当該受験生にとって基本書を読むことが最善の補強であるのか,アウトプットを重ねた方が合格に近づくのではないか),仮に,基本書を読むことが当該受験生にとって必要である場合,私は,以下のようにアドバイスします。
基本書を読む際に,多くの受験生は頭から漫然と読み進めてしまいます。最初はきっちり読むのですが,次第に読み方が荒っぽくなって,結果,「最初の方はよく頭に入っているのだけども,後に進むにつれて目で追っていただけできちんと頭に入っていない。」ということになってしまいます。ですから,一通り勉強したことのある受験生であれば,「まずは目次に,自分の理解度(得意度)をランク付けしていきましょう。民法で言えば,意思表示はA(よくわかっている)が,時効はC(よくわかっていない)とか。その上で,試験での出題頻度が高く,かつ,自分の理解度の低い単元から基本書を読んでいくようにしましょう。」と。
こういうふうに基本書を読んでいくことで,限られた時間の中で効果的にインプットをしていくことができます。私は,受験生の時に,こんなふうにしていました。基本書は漫然と読むものではなく,単元ごと能動的に読むべきものです。











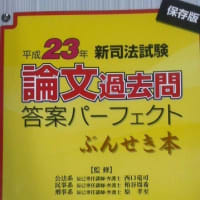
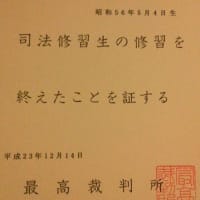
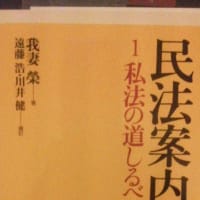






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます