お紺は相も変わらず読売のねたを拾うべく、江戸府中をあちこち出庭っていた。ねたの仕入れ先は、各町内にある番太郎。大体が自身番の前にある木戸番の店である。駄菓子・蝋燭・糊・箒・草鞋などの荒物や夏には金魚、冬には焼き芋なども売っていたので、商番屋とも呼ばれていた。
自身番に出向いた方が話は早そうなものだが、詰めている大家や差配は口が堅いばかりか、岡っ引きは何かと読売を目の敵にしているのだ。その点、番太郎は目の前の自身番での出来事を見知っており、町木戸が閉まってからの見廻りが役目なので、口は滑らかである。
「おじさん、焼き芋でも貰おうかね」。
歩き疲れた身体に芋の甘さが有難い。顔見知りの番太郎では、店先で焼き芋を食べお茶を貰う事も出来る。
「おじさん。このところ、急に冷え込んできたねえ。夜回りも大変だ」。
「ああ、そうだな。年のせいかすっかり寒さも身に染みらあ」。
「あら嫌だ。おじさんは未だ未だ若いですよ」。
「世辞を言っても出涸らしの茶しかねえよ」。
そんなやり取りも板に付いたものだ。
「ねえ、おじさん」。
「ほれ、きなすった」。
「ほれ、きなすったって、あたしは未だ何も言っちゃいませんよ」。
芋よりも目当てはそっちだろうと、言う木戸番のおやじは、店先に叩きを掛けながら軽口を叩く。
「てえした事もねえが、この先の松の湯、知ってんだろう。あすこで板の間稼ぎがあったくれえなもんさ」。
「松の湯ったら、伝蔵親分の湯屋じゃないか」。
伝蔵は深川冬木町界隈を縄張りとする岡っ引きである。岡っ引きに給金は年四両。これだけでは到底生計(たつき)の足しにもならず、副業を持つのが常であり、伝蔵も湯屋を営んでいた。
「ああ、そうだ。随分ととんちきな板の間稼ぎも居たもんさ」。
「なら直ぐにお縄かい」。
(何だ詰まらない)。
直ぐさまそんな思いは不謹慎であると己を戒める。人様の不幸を飯のたねにしているおの稼業が時として嫌になる事もあった。巾着切りに掛け金を盗まれ命を絶ったお店者、勾引しに合った大店の娘、心中者。数え切れない涙を瓦版に刷ってきている。そして今も、そんな不幸を探し歩いているのだ。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。
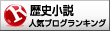
 にほんブログ村
にほんブログ村

自身番に出向いた方が話は早そうなものだが、詰めている大家や差配は口が堅いばかりか、岡っ引きは何かと読売を目の敵にしているのだ。その点、番太郎は目の前の自身番での出来事を見知っており、町木戸が閉まってからの見廻りが役目なので、口は滑らかである。
「おじさん、焼き芋でも貰おうかね」。
歩き疲れた身体に芋の甘さが有難い。顔見知りの番太郎では、店先で焼き芋を食べお茶を貰う事も出来る。
「おじさん。このところ、急に冷え込んできたねえ。夜回りも大変だ」。
「ああ、そうだな。年のせいかすっかり寒さも身に染みらあ」。
「あら嫌だ。おじさんは未だ未だ若いですよ」。
「世辞を言っても出涸らしの茶しかねえよ」。
そんなやり取りも板に付いたものだ。
「ねえ、おじさん」。
「ほれ、きなすった」。
「ほれ、きなすったって、あたしは未だ何も言っちゃいませんよ」。
芋よりも目当てはそっちだろうと、言う木戸番のおやじは、店先に叩きを掛けながら軽口を叩く。
「てえした事もねえが、この先の松の湯、知ってんだろう。あすこで板の間稼ぎがあったくれえなもんさ」。
「松の湯ったら、伝蔵親分の湯屋じゃないか」。
伝蔵は深川冬木町界隈を縄張りとする岡っ引きである。岡っ引きに給金は年四両。これだけでは到底生計(たつき)の足しにもならず、副業を持つのが常であり、伝蔵も湯屋を営んでいた。
「ああ、そうだ。随分ととんちきな板の間稼ぎも居たもんさ」。
「なら直ぐにお縄かい」。
(何だ詰まらない)。
直ぐさまそんな思いは不謹慎であると己を戒める。人様の不幸を飯のたねにしているおの稼業が時として嫌になる事もあった。巾着切りに掛け金を盗まれ命を絶ったお店者、勾引しに合った大店の娘、心中者。数え切れない涙を瓦版に刷ってきている。そして今も、そんな不幸を探し歩いているのだ。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。










