宝永5(1708)年の大火以降、中京区六角通りに移転されてから、六角獄舎または六角獄、六角牢などと呼ばれるようになった三条新地牢屋敷は、宝永4(1707)年に、医師・山脇東洋による日本初の遺体解剖が行われた事でも知られている。
その敷地は、堀を巡らした周囲、東西69m、南北53mで総面積3,660㎡である。内部は一般牢(本牢)のほかに揚り屋、キリシタン牢、女牢などに分かれていた。
その六角獄舎で、あってはならない前代未聞の悲劇が起きたのは、元治元(1864)年7月20日。「八月十八日の政変」による火災の余波を受けての集団処刑であった。
会津・薩摩藩によるクーデターにより、長州軍と御所を守る諸藩との激しい攻防戦が始まり、市中に火の手が上がるや、あっと言う間に町を飲み込んでいったのだ。そして、19日、衰えを見せぬ火勢は六角獄舎にも迫り、20日になっても火の手が消える事はなかった。
「生野の変」に敗れて投獄されていた尊王攘夷派の指導者・平野国臣(福岡藩士)始め、新撰組に捕らえられた古高俊太郎(近江国)ら志士たちが収容されていた。
火の手が獄舎に迫るや、人の破獄を恐れた西町奉行・滝川播磨守具挙の命により、平野国臣、古高俊太郎らの処刑が下される。「生野の変」の関係者から順に引き出され、斬刑は3時間にも及ぶものであり、この間に33名もの命が失われたのである。
有罪か無罪の判決が下される前の斬首は、もはや殺人と言っても良いだろう。判決前であれば無罪の者もいた筈である。何より、火災の場合は解き放ちが原則ではなかったのか。
この滝川播磨守具挙という人物、余程肝っ玉が小さいとみるか、幕府に反抗する者たちであり、危険分子と受け止めての決断と受け止めるか。いずれにしても、奉行としての判断力や人命の尊さを認知していなかったのは事実。
しかし、外交関連の関連の役職を歴任し、外国奉行・神奈川奉行を経ての京都西町奉行就任である。優秀な人物だったのだろう。なにせ、33名もの命を奪っておきながら、同年には大目付にまで昇進しているのだ。幕府も特に処罰を与えぬどころか、出世させているのだから、何とも…。唯一、京都所司代の会津藩主・松平容保は叱咤したと伝えられる。
余談だが、小栗忠順とは学問の同門であり、隣家同士の幼馴染みであった。鳥羽伏見の戦いに敗走後は、御役御免、寄合へと降格、登城禁止の上に、逼塞の処分を受け、後に改めて永蟄居に処されるなど、散々な憂き目をみながらも、江戸開城後も蟄居していた屋敷が、小栗忠順の屋敷の隣家であった為に、新政府軍の馬場拡張野為に接収され、立退きを命じられたというから、これも六角獄舎の祟りとでも言おうか。
六角獄舎にて斬首された志士たちの遺骸は、藁筵に巻き、西二条刑場の椋の木の下に埋められた後、竹林寺へ合葬される。 〈第一部終了〉
次回からは、「その後(のち)の新撰組」。新時代に生き残った元新撰組隊士は、どう生き抜いたのか。
幕末を駆け抜けた新撰組。だが鳥羽伏見の敗走後は、脱走者も後を絶たず、転戦しながらその形を変えていった。
会津で、米沢で、仙台で、そして函館へと転戦し、函館戦争の終結を持って新撰組は消滅する。
そして時は、明治。剣豪だった彼らが、新時代をどのように生き抜いていったのだろうか。
ここでは、明治以の新撰組元隊士たちの生き様を追ってみたいと思う。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。
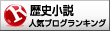
 にほんブログ村
にほんブログ村

その敷地は、堀を巡らした周囲、東西69m、南北53mで総面積3,660㎡である。内部は一般牢(本牢)のほかに揚り屋、キリシタン牢、女牢などに分かれていた。
その六角獄舎で、あってはならない前代未聞の悲劇が起きたのは、元治元(1864)年7月20日。「八月十八日の政変」による火災の余波を受けての集団処刑であった。
会津・薩摩藩によるクーデターにより、長州軍と御所を守る諸藩との激しい攻防戦が始まり、市中に火の手が上がるや、あっと言う間に町を飲み込んでいったのだ。そして、19日、衰えを見せぬ火勢は六角獄舎にも迫り、20日になっても火の手が消える事はなかった。
「生野の変」に敗れて投獄されていた尊王攘夷派の指導者・平野国臣(福岡藩士)始め、新撰組に捕らえられた古高俊太郎(近江国)ら志士たちが収容されていた。
火の手が獄舎に迫るや、人の破獄を恐れた西町奉行・滝川播磨守具挙の命により、平野国臣、古高俊太郎らの処刑が下される。「生野の変」の関係者から順に引き出され、斬刑は3時間にも及ぶものであり、この間に33名もの命が失われたのである。
有罪か無罪の判決が下される前の斬首は、もはや殺人と言っても良いだろう。判決前であれば無罪の者もいた筈である。何より、火災の場合は解き放ちが原則ではなかったのか。
この滝川播磨守具挙という人物、余程肝っ玉が小さいとみるか、幕府に反抗する者たちであり、危険分子と受け止めての決断と受け止めるか。いずれにしても、奉行としての判断力や人命の尊さを認知していなかったのは事実。
しかし、外交関連の関連の役職を歴任し、外国奉行・神奈川奉行を経ての京都西町奉行就任である。優秀な人物だったのだろう。なにせ、33名もの命を奪っておきながら、同年には大目付にまで昇進しているのだ。幕府も特に処罰を与えぬどころか、出世させているのだから、何とも…。唯一、京都所司代の会津藩主・松平容保は叱咤したと伝えられる。
余談だが、小栗忠順とは学問の同門であり、隣家同士の幼馴染みであった。鳥羽伏見の戦いに敗走後は、御役御免、寄合へと降格、登城禁止の上に、逼塞の処分を受け、後に改めて永蟄居に処されるなど、散々な憂き目をみながらも、江戸開城後も蟄居していた屋敷が、小栗忠順の屋敷の隣家であった為に、新政府軍の馬場拡張野為に接収され、立退きを命じられたというから、これも六角獄舎の祟りとでも言おうか。
六角獄舎にて斬首された志士たちの遺骸は、藁筵に巻き、西二条刑場の椋の木の下に埋められた後、竹林寺へ合葬される。 〈第一部終了〉
次回からは、「その後(のち)の新撰組」。新時代に生き残った元新撰組隊士は、どう生き抜いたのか。
幕末を駆け抜けた新撰組。だが鳥羽伏見の敗走後は、脱走者も後を絶たず、転戦しながらその形を変えていった。
会津で、米沢で、仙台で、そして函館へと転戦し、函館戦争の終結を持って新撰組は消滅する。
そして時は、明治。剣豪だった彼らが、新時代をどのように生き抜いていったのだろうか。
ここでは、明治以の新撰組元隊士たちの生き様を追ってみたいと思う。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。










