人様の不幸ばかりを飯の種にしている訳ではないが、それが多いのも事実である。時には読売を拵えるのに胸を痛める事もある。
あの優しかった姉の静江を見る目が冷ややかになった。
「母上の差し金ですか。母上は、わたくしが疎ましいのです」。
初江は、目頭に涙をにじませながら、平三郎に詰め寄った。
「静江に家督を継がせたいのです」。
平三郎が幾ら説いても、初江は頑に聞き入れない。初江の産みの母は産褥の後に初江を残し世を去っていた。乳飲み子を抱えた平三郎は周囲の勧めも有って後添えを迎えたのである。そして静江が産まれたのだ。
「初江、そなたはそのように思うていたのか」。
「いいえ、今の今迄は母上を実の母と慕ってまいりました。ですが、跡取りであるわたくしを嫁に出し、実の娘と暮らしたいと思おておいでのご様子」。
「そうではない。これはわしの一存ぞ」。
「ならば、何故、初江に田所の家を継がせてはくれないのです」。
三十表二人扶持の同心よりも、格上の与力の家に入った方が幸せであると平三郎は信じている。その幸福を初江は掴めるのだ。それを頑なまでに拒む訳が分からなかった。
一方の初江にとっては、子どもの頃から己が継ぐ筈の家督を静江に奪われた気持ちでいた。やはり己よりも静江の方が可愛いのだ。そう頭から思い込んでいたのである。
「わたくしは承服し兼ねます」。
頑な初江に、ついに平三郎は本音を洩らす。
初江であれば、幾らでも良縁があるが、平三郎に御神酒徳利の静江は、家付きでもなければ嫁の口がないのだと。
それでも初江は承服はしない。
「父上は、静江を第一にお考えですか」。
そうではない、そうではないのだが、与力との縁組を喜びこそすれ、これ程迄嫌がるとは思ってもいなかった。
相手は見てくれこそぱっとしないが、人知にも優れ、ゆくゆくは筆頭与力との声も高い人物である。何より、初江を嫁にと懇願しているのだ。これ程の幸せがあろうかと、平三郎は膝を打って喜んだものであった。
「ええい、初江、見苦しいぞ。武家の娘が縁組に異を唱えるなどもってのほか」。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。
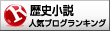
 にほんブログ村
にほんブログ村
あの優しかった姉の静江を見る目が冷ややかになった。
「母上の差し金ですか。母上は、わたくしが疎ましいのです」。
初江は、目頭に涙をにじませながら、平三郎に詰め寄った。
「静江に家督を継がせたいのです」。
平三郎が幾ら説いても、初江は頑に聞き入れない。初江の産みの母は産褥の後に初江を残し世を去っていた。乳飲み子を抱えた平三郎は周囲の勧めも有って後添えを迎えたのである。そして静江が産まれたのだ。
「初江、そなたはそのように思うていたのか」。
「いいえ、今の今迄は母上を実の母と慕ってまいりました。ですが、跡取りであるわたくしを嫁に出し、実の娘と暮らしたいと思おておいでのご様子」。
「そうではない。これはわしの一存ぞ」。
「ならば、何故、初江に田所の家を継がせてはくれないのです」。
三十表二人扶持の同心よりも、格上の与力の家に入った方が幸せであると平三郎は信じている。その幸福を初江は掴めるのだ。それを頑なまでに拒む訳が分からなかった。
一方の初江にとっては、子どもの頃から己が継ぐ筈の家督を静江に奪われた気持ちでいた。やはり己よりも静江の方が可愛いのだ。そう頭から思い込んでいたのである。
「わたくしは承服し兼ねます」。
頑な初江に、ついに平三郎は本音を洩らす。
初江であれば、幾らでも良縁があるが、平三郎に御神酒徳利の静江は、家付きでもなければ嫁の口がないのだと。
それでも初江は承服はしない。
「父上は、静江を第一にお考えですか」。
そうではない、そうではないのだが、与力との縁組を喜びこそすれ、これ程迄嫌がるとは思ってもいなかった。
相手は見てくれこそぱっとしないが、人知にも優れ、ゆくゆくは筆頭与力との声も高い人物である。何より、初江を嫁にと懇願しているのだ。これ程の幸せがあろうかと、平三郎は膝を打って喜んだものであった。
「ええい、初江、見苦しいぞ。武家の娘が縁組に異を唱えるなどもってのほか」。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。










