豊島町に住む江戸の禁裏大工棟梁・左甚五郎は、上野東照宮完成後、讃岐高松藩の客文頭領になるも同年すぐに死亡。享年五十八歳。
善兵衛はその後、郷里の近江国坂田郡宮川に戻ることなく、甚五郎の跡を引き継ぎ讃岐高松藩に従事。
明暦三年(1657)の明暦の大火で焼け落ちた際、万治三年(1660)の神田川御茶ノ水の拡幅工事で、江戸城の普請に参画するも、西の丸地下道の秘密計画保持のため命を狙われ、江戸幕府の若年寄・下総古河藩主・土井利隆の庇護の下、下総古河に逃れる。
その後、寛永十年(1633)より彦根藩領となった下野の国・佐野の天応寺増築に三代彦根藩主の井伊直澄の命で加わり、その地で生涯を閉じたと伝えられる。
近江国坂田郡宮川の大森家には、「最初に産まれた男児は近江国坂田郡宮川に戻し大森家を継がせること」を条件に善兵衛の継承放棄は許された。
大森善兵衛の名を伝える資料はほとんどないが、佐野の善兵衛として現存する記録は現存する。
万治三年(1660)、御家改易となった近江宮川藩では、多くの家臣が浪々の身となった。小納戸方の岡崎一馬のその後は、近江を去ったとしか伝えられていない。
同じく、御家改易で、婚家を出された千代姫は仏門に入る。そこには同じく髪を下ろした早苗の姿もあった。
日本橋呉服町に店を構える大店、太物問屋の恵美須屋の一人娘ひさは、回船問屋の二男を婿に向かえ、相変わらずの様子。
永富町の表長屋大工棟梁平造の娘・みつは、婿を取り、後に二男、三女に恵まれる。江戸は何度も火事に見舞われるが、いつでもいの一番に愛用の包丁を持ち出していた。
西横町の裏長屋。入れ替わり立ち代わり、住まう人は違えども、今日も威勢のいい声が聞こえている。
そして不忍池で不敵に泳ぎ回った龍は今なお、上野東照宮で、自由に動ける日を待っている。
お仕舞い。
長い間おつきあいくださいました皆さんありがとうございました。
文中登場する実在の人物は、なるべく年代や年齢を合わせましたが、話の流れ上、どうしても誤差が生じている部分もあります。ご了承ください。
次は幕末を舞台に構想をねっておりますので、準備が整いますまで、お待ちください。
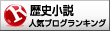
善兵衛はその後、郷里の近江国坂田郡宮川に戻ることなく、甚五郎の跡を引き継ぎ讃岐高松藩に従事。
明暦三年(1657)の明暦の大火で焼け落ちた際、万治三年(1660)の神田川御茶ノ水の拡幅工事で、江戸城の普請に参画するも、西の丸地下道の秘密計画保持のため命を狙われ、江戸幕府の若年寄・下総古河藩主・土井利隆の庇護の下、下総古河に逃れる。
その後、寛永十年(1633)より彦根藩領となった下野の国・佐野の天応寺増築に三代彦根藩主の井伊直澄の命で加わり、その地で生涯を閉じたと伝えられる。
近江国坂田郡宮川の大森家には、「最初に産まれた男児は近江国坂田郡宮川に戻し大森家を継がせること」を条件に善兵衛の継承放棄は許された。
大森善兵衛の名を伝える資料はほとんどないが、佐野の善兵衛として現存する記録は現存する。
万治三年(1660)、御家改易となった近江宮川藩では、多くの家臣が浪々の身となった。小納戸方の岡崎一馬のその後は、近江を去ったとしか伝えられていない。
同じく、御家改易で、婚家を出された千代姫は仏門に入る。そこには同じく髪を下ろした早苗の姿もあった。
日本橋呉服町に店を構える大店、太物問屋の恵美須屋の一人娘ひさは、回船問屋の二男を婿に向かえ、相変わらずの様子。
永富町の表長屋大工棟梁平造の娘・みつは、婿を取り、後に二男、三女に恵まれる。江戸は何度も火事に見舞われるが、いつでもいの一番に愛用の包丁を持ち出していた。
西横町の裏長屋。入れ替わり立ち代わり、住まう人は違えども、今日も威勢のいい声が聞こえている。
そして不忍池で不敵に泳ぎ回った龍は今なお、上野東照宮で、自由に動ける日を待っている。
お仕舞い。
長い間おつきあいくださいました皆さんありがとうございました。
文中登場する実在の人物は、なるべく年代や年齢を合わせましたが、話の流れ上、どうしても誤差が生じている部分もあります。ご了承ください。
次は幕末を舞台に構想をねっておりますので、準備が整いますまで、お待ちください。









