元禄十四年(1701)三月二十六日、吉良上野介義央は高家肝煎職のお役御免願いを提出した。表向きは飽くまでも高齢を理由にしてのことだが、十四日に江戸城松の廊下での浅野内匠頭長矩の刃傷。一方的な長矩の切腹そして赤穂藩御取り潰しの裁定に世論は、赤穂藩への道場へと動いていたのだった。
義央は斬り付けられた上、世紀の悪役となっていったのである。
「富子が申すように確かにお上の裁定は片手落ちやも知れぬ。なれば余も隠居でもするしかあるまい」。
義央は自身が隠居をすれば旧赤穂藩士たちの憤りも、世論も鎮まるだろうと安易に考えていた。
それでも妻の富子は、
「片や御切腹。それではお役御免などでことは済みますまい」。
そう洩らすのだが、義央が腹を斬らないとあればそれしか残された道もないのだ。
「殿、お願いがございます」。
富子は義央に申し出た。
「義周殿の養子縁組を解消し、上杉にお戻しくださいませ」。
「何を申すのじゃ。それではこの吉良の家はどうなるのじゃ」。
「高家肝煎りを返上なさいませ。世間で言われているような卑怯者の家を義周殿に継がせる訳にいきますまい」。
「この上野介のどこが卑怯だと申すのじゃ」。
義央の怒りはそうとうなもので、顔を真っ赤にさせ思わず立ち上がったその拳は小刻みに震えているほどであった。
養子入りしてた米沢上杉四代藩主・綱憲の二男であり、義央夫妻の実の孫に当たる吉良左兵衛義周は、初めて見る養父の怒りに驚きを隠せなかったが、それでも富子が言い過ぎであると、
「父上、落ち着いてください。わたしは、上杉に戻るつもりはございませぬ。物心つく前より吉良の家を継ぐ者としてお育ていただきました、父上、母上の恩に報いるべく当家を守っていきまする」。
「ん。義周、よくぞ申した」。
義央は安堵の表情を浮かべ、どうだと言わんばかりに富子に目を送った。
だが八月十九日、吉良家は本所への幕命を受けていた。このことに関しても富子は、
「お上とて、本所への屋敷換えなど、もはやあなた様を庇うことはありますまい」。
と頑である。
元は松平信望の屋敷である本所は、江戸城のお膝元である呉服橋内とは違い郊外の辺鄙なところである。
この転居による改築、建て回しの資金はまたも上杉家の負担となった。
「富子、そなたは上杉に戻られよ」。
こうして夫婦の間にできた溝は、事実上の離縁といった形にまで進んでしまったのである。
富子は静かに頭を垂れると、そのまま座を辞した。
「母上、お待ちくださいませ」。
義周は富子を追った。
「母上、お気を回し過ぎにございます。浅野様への御裁定はお上が決められたものにございます。当家に非はございませぬ」。
義周は富子を宥めるが、富子ははらはらと泣き、
「さりとて、それを受け入れられぬのが人の業じゃ。赤穂の者たちは殿を仇と思うておる」。
「母上の御懸念が事実でありますれば、尚更わたしは父上をお守りせねばなりませぬ」。
立派な若者へと成長した義周に富子は感服するが、万が一を考えなくもない。
先に義周付きとさせた中臈の藤波、侍女の浅尾局のほかに、自身に仕える中臈の高野、侍女の丹後局ほか小性など十数名に、旧赤穂藩士の動きを逐一報告すること、そしてその時が来れば義周を上杉屋敷に導くことを含め、義周の元に残し、白金の上杉下屋敷へと下がって行った。
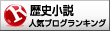

にほんブログ村

義央は斬り付けられた上、世紀の悪役となっていったのである。
「富子が申すように確かにお上の裁定は片手落ちやも知れぬ。なれば余も隠居でもするしかあるまい」。
義央は自身が隠居をすれば旧赤穂藩士たちの憤りも、世論も鎮まるだろうと安易に考えていた。
それでも妻の富子は、
「片や御切腹。それではお役御免などでことは済みますまい」。
そう洩らすのだが、義央が腹を斬らないとあればそれしか残された道もないのだ。
「殿、お願いがございます」。
富子は義央に申し出た。
「義周殿の養子縁組を解消し、上杉にお戻しくださいませ」。
「何を申すのじゃ。それではこの吉良の家はどうなるのじゃ」。
「高家肝煎りを返上なさいませ。世間で言われているような卑怯者の家を義周殿に継がせる訳にいきますまい」。
「この上野介のどこが卑怯だと申すのじゃ」。
義央の怒りはそうとうなもので、顔を真っ赤にさせ思わず立ち上がったその拳は小刻みに震えているほどであった。
養子入りしてた米沢上杉四代藩主・綱憲の二男であり、義央夫妻の実の孫に当たる吉良左兵衛義周は、初めて見る養父の怒りに驚きを隠せなかったが、それでも富子が言い過ぎであると、
「父上、落ち着いてください。わたしは、上杉に戻るつもりはございませぬ。物心つく前より吉良の家を継ぐ者としてお育ていただきました、父上、母上の恩に報いるべく当家を守っていきまする」。
「ん。義周、よくぞ申した」。
義央は安堵の表情を浮かべ、どうだと言わんばかりに富子に目を送った。
だが八月十九日、吉良家は本所への幕命を受けていた。このことに関しても富子は、
「お上とて、本所への屋敷換えなど、もはやあなた様を庇うことはありますまい」。
と頑である。
元は松平信望の屋敷である本所は、江戸城のお膝元である呉服橋内とは違い郊外の辺鄙なところである。
この転居による改築、建て回しの資金はまたも上杉家の負担となった。
「富子、そなたは上杉に戻られよ」。
こうして夫婦の間にできた溝は、事実上の離縁といった形にまで進んでしまったのである。
富子は静かに頭を垂れると、そのまま座を辞した。
「母上、お待ちくださいませ」。
義周は富子を追った。
「母上、お気を回し過ぎにございます。浅野様への御裁定はお上が決められたものにございます。当家に非はございませぬ」。
義周は富子を宥めるが、富子ははらはらと泣き、
「さりとて、それを受け入れられぬのが人の業じゃ。赤穂の者たちは殿を仇と思うておる」。
「母上の御懸念が事実でありますれば、尚更わたしは父上をお守りせねばなりませぬ」。
立派な若者へと成長した義周に富子は感服するが、万が一を考えなくもない。
先に義周付きとさせた中臈の藤波、侍女の浅尾局のほかに、自身に仕える中臈の高野、侍女の丹後局ほか小性など十数名に、旧赤穂藩士の動きを逐一報告すること、そしてその時が来れば義周を上杉屋敷に導くことを含め、義周の元に残し、白金の上杉下屋敷へと下がって行った。
にほんブログ村





















また時間を見つけて、遊びに来させて頂きますね!