まずは、「水波の如し」を読まれ、吉良左兵衛義周の配流先での諏訪(高島)藩での扱いに、まさかと思われた方も居たのではないだろうか。伝わる話では、月代や髭もあたれず、着替えも侭ならないため、垢染みた衣類で過ごさざるを得ないなど、悲痛な話が伝わっている。
だが、それなりに身分のある者に対しては、配流先でも礼を尽くすのが当たり前であり、火鉢は駄目だが炬燵は用意されていたり、諏訪は田舎故、口に合う物がないだろうと、江戸から菓子を取り寄せたりといった記述は、諏訪(高島)藩に残されている。
これは、御家再興がなった折りへの配慮とされ、江戸時代には一般的であった。ただし、左兵衛に関してはやはり厳しい面も否めず、自害を危惧して剃刀などの刃物から、庭の小石まで遠ざけられたとある。
よって、月代、髭をあたれなかったのは分からなくもないが、着替えひとつにしても江戸表に書面を通したりといった手続きは如何なるものなのだろう。一重に、諏訪(高島)藩主の気質を非難する作家もいるが、それは定かではない。
吉良家も享保17年(1732年)、上野介の実弟・東条義叔により復興している。ただし高家の格式は認められなかった。
因に、諏訪(高島)藩には徳川家康の六男・松平忠輝も蟄居させられている。
そして、日本中が涙して止まない、赤穂浅野家の悲劇。そして、それに伴う四十七士の討入りを知らない人はいないのではないだろうか。いや、いないどころか判官贔屓の日本人にとっては、白虎隊と双璧の大好きな歴史ロマンであろう。
四十七士に肩入したくなるのも致し方ないが、原点に返って柔軟に考えてみよう。そもそも浅野内匠頭長矩は、何故に切腹に陥ったのか。
そう、殿中での刃傷どころか抜刀は御法度の法を破った為である。そもそも、江戸城のみならず各大名家の屋敷内への大刀の持ち込み自体が禁じられているのだ。
浅野内匠頭の刃傷のあった元禄14(1701)年3月14日より時代をさかのぼれば、二件の江戸城内刃傷事件が記録されている。
ひとつは、寛永5(1628)年8月10日、旗本・豊島明重が遠江国横須賀藩初代藩主であり老中の井上正就を殺傷し、駆け寄った青木忠精に背後から組み止められたものの、それを振り払うかのようにして脇差を取り出し、忠精もろともその場で自らの腹を貫いて死亡。嫡子・吉継は切腹。御家断絶。
二つ目は、貞享元(1684)年8月28日には、美濃青野藩主で若年寄の稲葉正休が上野安中藩主で大老の堀田正俊を殺傷し、正休はその場にて老中・大久保忠朝、阿部正武、戸田忠昌らに滅多斬りにされ死亡。稲葉家は改易処分となった。
平成の素町人である自分でも知りうる史実を、大石内蔵助良雄ともあろう者が知らない筈もなく、吉良家襲撃に当たっては、単なる主君の仇討ちだけではなくほかに子細があっての事ではないだろうか。飽くまでも私的な考えであるが、仇討ちで名を挙げることにより、御家再興を願ったのではないかと思って止まないのだ。
そうでなければ、大名家の家老ともあろう者が、夜襲などといった暴挙に出るだろうか。事を大きくして世に知ら示す。それが目的だったのではないか。
いずれにしても、迷惑千万なのは吉良家である。唐突に夜襲をかけられ、多くの死傷者を出した挙げ句に改易。当主の吉良左兵衛義周に至っては、薙刀を手に果敢にも戦い、背と額に手傷を負いながらも、月目付のを老中・稲葉正通に子細を文に認め提出したにも関わらず、「親を見殺しにした」として、諏訪藩にお預けである。
加えて、左兵衛の実の親である出羽米沢藩の第四代藩主・上杉綱憲と嫡男・吉憲(左兵衛の異母兄)は謹慎処分(吉憲は後に五代藩主)。もう頭を捻るざるを得ない結末である。
幕末の会津藩の悲運も憤りを隠せないが、それにも増して無体な仕打ちに、全く関係のない平成のお気楽素町人も胸が詰まる思いだ。
多勢で夜襲をかける。これは士道に反していないのだろうか。仇討ちとは名乗りを上げ、一対一が基本ではないのかといった疑問がふと脳裏を過る。
因に、異論もあると思われるが、討入りに関わる説を少しばかり。
まず、浅野内匠頭は、元禄14年よりさかのぼること7年前にも勅使饗応役を務めており、この時の指南役も吉良上野介であった。よって、畳の表替えや装束に関する嫌がらせなどは、後の創作と思われる。
では、7年前は何事も起こらず、なぜこの度は…。これには些かの不幸も含まれ、指南役の吉良上野介は京に赴いており、その地で風を召して江戸へ戻るのが大幅に遅れたのだ。よって浅野内匠頭は、指南を仰がずに役目を進めるしかならなかった。
一方の吉良上野介にしてみれば、7年前と物価も大分上がっているため、浅野家の費用700両では納得出来ずに1400両を主張。ほかにも、細部に違いが生じていたために、それを指摘したtころが、浅野側は、けちを付けられたと受け止めたのではないだろうか。
また、武家屋敷において女中は、当主の妻女や娘付きしかおらず、所謂(いわゆる)時代劇のように表向きに矢羽根柄のお仕着せに立て矢結びの帯で顔を出すことはなく、吉良家も富子が上杉家下屋敷に移ると女中も上杉家から入った小姓も全て上杉家に引き揚げていた。時代劇では、討入り当夜に女中が逃げ回っているシーンを見掛けるが、当夜、吉良家に女性はいなかったのだ。
武家屋敷では、多くの家臣は屋敷内の門に繋がる長屋で寝起きをしていた。吉良家も同様で、赤穂浪士はまずこの長屋の戸口を板で打ち付け、中から出て来られなくしたため、屋敷内に詰めていた家臣しか戦えなかったとあるが、山吉新八郎は、長屋に退いていたにも関わらず、差料を手にいち早く飛び出したといった記述もあり、その後の戦いぶりは本文でも記述のとうり。
当日、赤穂浪士を迎え撃った吉良方は、上杉家から入った家臣がほとんどで、譜代の吉良家家臣は長屋に篭っていたという話も伝わっている。
家老の左右田孫兵衛重次に於いては、同じく家老の斎藤宮内と共に、長屋の壁を切り破り、向かいの傘屋に逃げたという不名誉な噂が立ったが、吉良家が断絶となった後も左兵衛に従い、配流先の諏訪藩高遠城へ供し、左兵衛が死去した後は帰参せずに三河国吉良へ、吉良家の菩提を弔いながら余生を過ごしたとされる。この事からも、彼の忠誠心は疑い用もなく、生き残ったがための、中傷と思われる。
次に吉良上野介について。時代劇では世紀の悪役、エロ爺として描かれることの多いが、実際には、彼は上杉十五万石から迎えた正室の富子を大切にし、二男四女を設けている。側室の記録は残されていない。
また、22歳にして従四位上に昇進。24回に及ぶ上洛は高家の中でも群を抜いており、さらに部屋住みの身でありながら使者職を行っていた。これは高家としての技倆が卓越していたことを示すにほかならない。
領地の吉良庄(愛知県西尾市吉良町)には、増水のたびに隣藩上流の広田川、須美川から流れ込む水により洪水が起こり水路もたびたび変わるという泥沼地帯があり、その度に田畑や住まいを流される領民のために私財を投じて築いた黄金堤も残されている。
因に、江戸城内での刃傷事件は十九件起きているが、下記は七大刃傷事件と呼ばれるものである。
寛永5 (1628)年8月10日 旗本・豊島明重が、遠江国横須賀藩藩主・老中・井上正就を殺傷し、自らも自害。豊島家は断絶
貞享元 (1684)年8月28日 美濃青野藩主・若年寄・稲葉正休が、上野安中藩主・大老・堀田正俊をを傷殺し、その場で斬り殺される。稲葉家は改易
元禄14 (1701)年3月14日 播州赤穂藩藩主・浅野長矩が、旗本・高家肝煎・吉良義央への刃傷に及び、即日切腹。浅野家は改易
享保10 (1725)年7月28日 信濃松本藩藩主・水野忠恒が、長門長府藩世子・毛利師就(後に長門長府藩主)へ刃傷に及び、水野家は改易
延享4 (1747)年8月15日 旗本・板倉勝該が、肥後国熊本藩主・細川宗孝を殺傷し、水野忠辰宅に召し預けられ切腹。浅野家は改易
天明4 (1784)年3月24日 旗本・佐野政言が、若年寄・田沼意知(田沼意次の嫡男)へ斬り付け、意知は八日後に死亡。佐野政言は切腹の処分を受け自害。佐野家は改易
文政6 (1823)年4月22日 旗本・松平外記による旗本・本多伊織ら五名を殺傷し自らも腹を斬り、更に咽喉を突き自害。相番の者は改易または小普請入り
この裁定によれば、浅野内匠頭の切腹(評定所に上げずに即日切腹は幕府の落ち度であり、大名に庭先で腹を斬らせるなどもってのほかだが)、改易はそう間違ったものではなかったのだ。
筆者は、この赤穂浪士による討入りと、後の戊辰戦争を、世紀の二大逆恨み(今風に言えば、逆切れ)事件と認識して止まない。
戊辰戦争に関しては、鳥羽伏見の戦いまではなんとか許容範囲だが、江戸城明け渡しで政権交代は済んだ筈。それからどれだけ尊い命が無駄に散ったと思っているのだ。薩摩、長州さんよ。
簡単に言えば、長州が勝手に御所に攻め入ったり、外国船に発砲したりして、これまた勝手に負けたにも関わらずに、会津憎しとは何事か。薩摩などは世紀の裏切り、腹黒ではないかといった私見である。
だいたいにおいて坂本龍馬が、商人ではなく維新の志士というなら、薩長同盟ではなく、会津と長州の仲立をしたのではないか? 「幕府を説得しようぜよ」とか言いながら。
以上、つれづれなるままの雑文であります。賛否あるとは思われますが(否の方が圧倒的多数でしょう)、飽くまでも個人的な私見として、読み流して頂ければ幸いです。こういった臍曲りもいるということで、筆を置きたいと思います。
臍曲りの私見
次回作まで、しばしお待ちください。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。
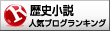
 にほんブログ村
にほんブログ村

だが、それなりに身分のある者に対しては、配流先でも礼を尽くすのが当たり前であり、火鉢は駄目だが炬燵は用意されていたり、諏訪は田舎故、口に合う物がないだろうと、江戸から菓子を取り寄せたりといった記述は、諏訪(高島)藩に残されている。
これは、御家再興がなった折りへの配慮とされ、江戸時代には一般的であった。ただし、左兵衛に関してはやはり厳しい面も否めず、自害を危惧して剃刀などの刃物から、庭の小石まで遠ざけられたとある。
よって、月代、髭をあたれなかったのは分からなくもないが、着替えひとつにしても江戸表に書面を通したりといった手続きは如何なるものなのだろう。一重に、諏訪(高島)藩主の気質を非難する作家もいるが、それは定かではない。
吉良家も享保17年(1732年)、上野介の実弟・東条義叔により復興している。ただし高家の格式は認められなかった。
因に、諏訪(高島)藩には徳川家康の六男・松平忠輝も蟄居させられている。
そして、日本中が涙して止まない、赤穂浅野家の悲劇。そして、それに伴う四十七士の討入りを知らない人はいないのではないだろうか。いや、いないどころか判官贔屓の日本人にとっては、白虎隊と双璧の大好きな歴史ロマンであろう。
四十七士に肩入したくなるのも致し方ないが、原点に返って柔軟に考えてみよう。そもそも浅野内匠頭長矩は、何故に切腹に陥ったのか。
そう、殿中での刃傷どころか抜刀は御法度の法を破った為である。そもそも、江戸城のみならず各大名家の屋敷内への大刀の持ち込み自体が禁じられているのだ。
浅野内匠頭の刃傷のあった元禄14(1701)年3月14日より時代をさかのぼれば、二件の江戸城内刃傷事件が記録されている。
ひとつは、寛永5(1628)年8月10日、旗本・豊島明重が遠江国横須賀藩初代藩主であり老中の井上正就を殺傷し、駆け寄った青木忠精に背後から組み止められたものの、それを振り払うかのようにして脇差を取り出し、忠精もろともその場で自らの腹を貫いて死亡。嫡子・吉継は切腹。御家断絶。
二つ目は、貞享元(1684)年8月28日には、美濃青野藩主で若年寄の稲葉正休が上野安中藩主で大老の堀田正俊を殺傷し、正休はその場にて老中・大久保忠朝、阿部正武、戸田忠昌らに滅多斬りにされ死亡。稲葉家は改易処分となった。
平成の素町人である自分でも知りうる史実を、大石内蔵助良雄ともあろう者が知らない筈もなく、吉良家襲撃に当たっては、単なる主君の仇討ちだけではなくほかに子細があっての事ではないだろうか。飽くまでも私的な考えであるが、仇討ちで名を挙げることにより、御家再興を願ったのではないかと思って止まないのだ。
そうでなければ、大名家の家老ともあろう者が、夜襲などといった暴挙に出るだろうか。事を大きくして世に知ら示す。それが目的だったのではないか。
いずれにしても、迷惑千万なのは吉良家である。唐突に夜襲をかけられ、多くの死傷者を出した挙げ句に改易。当主の吉良左兵衛義周に至っては、薙刀を手に果敢にも戦い、背と額に手傷を負いながらも、月目付のを老中・稲葉正通に子細を文に認め提出したにも関わらず、「親を見殺しにした」として、諏訪藩にお預けである。
加えて、左兵衛の実の親である出羽米沢藩の第四代藩主・上杉綱憲と嫡男・吉憲(左兵衛の異母兄)は謹慎処分(吉憲は後に五代藩主)。もう頭を捻るざるを得ない結末である。
幕末の会津藩の悲運も憤りを隠せないが、それにも増して無体な仕打ちに、全く関係のない平成のお気楽素町人も胸が詰まる思いだ。
多勢で夜襲をかける。これは士道に反していないのだろうか。仇討ちとは名乗りを上げ、一対一が基本ではないのかといった疑問がふと脳裏を過る。
因に、異論もあると思われるが、討入りに関わる説を少しばかり。
まず、浅野内匠頭は、元禄14年よりさかのぼること7年前にも勅使饗応役を務めており、この時の指南役も吉良上野介であった。よって、畳の表替えや装束に関する嫌がらせなどは、後の創作と思われる。
では、7年前は何事も起こらず、なぜこの度は…。これには些かの不幸も含まれ、指南役の吉良上野介は京に赴いており、その地で風を召して江戸へ戻るのが大幅に遅れたのだ。よって浅野内匠頭は、指南を仰がずに役目を進めるしかならなかった。
一方の吉良上野介にしてみれば、7年前と物価も大分上がっているため、浅野家の費用700両では納得出来ずに1400両を主張。ほかにも、細部に違いが生じていたために、それを指摘したtころが、浅野側は、けちを付けられたと受け止めたのではないだろうか。
また、武家屋敷において女中は、当主の妻女や娘付きしかおらず、所謂(いわゆる)時代劇のように表向きに矢羽根柄のお仕着せに立て矢結びの帯で顔を出すことはなく、吉良家も富子が上杉家下屋敷に移ると女中も上杉家から入った小姓も全て上杉家に引き揚げていた。時代劇では、討入り当夜に女中が逃げ回っているシーンを見掛けるが、当夜、吉良家に女性はいなかったのだ。
武家屋敷では、多くの家臣は屋敷内の門に繋がる長屋で寝起きをしていた。吉良家も同様で、赤穂浪士はまずこの長屋の戸口を板で打ち付け、中から出て来られなくしたため、屋敷内に詰めていた家臣しか戦えなかったとあるが、山吉新八郎は、長屋に退いていたにも関わらず、差料を手にいち早く飛び出したといった記述もあり、その後の戦いぶりは本文でも記述のとうり。
当日、赤穂浪士を迎え撃った吉良方は、上杉家から入った家臣がほとんどで、譜代の吉良家家臣は長屋に篭っていたという話も伝わっている。
家老の左右田孫兵衛重次に於いては、同じく家老の斎藤宮内と共に、長屋の壁を切り破り、向かいの傘屋に逃げたという不名誉な噂が立ったが、吉良家が断絶となった後も左兵衛に従い、配流先の諏訪藩高遠城へ供し、左兵衛が死去した後は帰参せずに三河国吉良へ、吉良家の菩提を弔いながら余生を過ごしたとされる。この事からも、彼の忠誠心は疑い用もなく、生き残ったがための、中傷と思われる。
次に吉良上野介について。時代劇では世紀の悪役、エロ爺として描かれることの多いが、実際には、彼は上杉十五万石から迎えた正室の富子を大切にし、二男四女を設けている。側室の記録は残されていない。
また、22歳にして従四位上に昇進。24回に及ぶ上洛は高家の中でも群を抜いており、さらに部屋住みの身でありながら使者職を行っていた。これは高家としての技倆が卓越していたことを示すにほかならない。
領地の吉良庄(愛知県西尾市吉良町)には、増水のたびに隣藩上流の広田川、須美川から流れ込む水により洪水が起こり水路もたびたび変わるという泥沼地帯があり、その度に田畑や住まいを流される領民のために私財を投じて築いた黄金堤も残されている。
因に、江戸城内での刃傷事件は十九件起きているが、下記は七大刃傷事件と呼ばれるものである。
寛永5 (1628)年8月10日 旗本・豊島明重が、遠江国横須賀藩藩主・老中・井上正就を殺傷し、自らも自害。豊島家は断絶
貞享元 (1684)年8月28日 美濃青野藩主・若年寄・稲葉正休が、上野安中藩主・大老・堀田正俊をを傷殺し、その場で斬り殺される。稲葉家は改易
元禄14 (1701)年3月14日 播州赤穂藩藩主・浅野長矩が、旗本・高家肝煎・吉良義央への刃傷に及び、即日切腹。浅野家は改易
享保10 (1725)年7月28日 信濃松本藩藩主・水野忠恒が、長門長府藩世子・毛利師就(後に長門長府藩主)へ刃傷に及び、水野家は改易
延享4 (1747)年8月15日 旗本・板倉勝該が、肥後国熊本藩主・細川宗孝を殺傷し、水野忠辰宅に召し預けられ切腹。浅野家は改易
天明4 (1784)年3月24日 旗本・佐野政言が、若年寄・田沼意知(田沼意次の嫡男)へ斬り付け、意知は八日後に死亡。佐野政言は切腹の処分を受け自害。佐野家は改易
文政6 (1823)年4月22日 旗本・松平外記による旗本・本多伊織ら五名を殺傷し自らも腹を斬り、更に咽喉を突き自害。相番の者は改易または小普請入り
この裁定によれば、浅野内匠頭の切腹(評定所に上げずに即日切腹は幕府の落ち度であり、大名に庭先で腹を斬らせるなどもってのほかだが)、改易はそう間違ったものではなかったのだ。
筆者は、この赤穂浪士による討入りと、後の戊辰戦争を、世紀の二大逆恨み(今風に言えば、逆切れ)事件と認識して止まない。
戊辰戦争に関しては、鳥羽伏見の戦いまではなんとか許容範囲だが、江戸城明け渡しで政権交代は済んだ筈。それからどれだけ尊い命が無駄に散ったと思っているのだ。薩摩、長州さんよ。
簡単に言えば、長州が勝手に御所に攻め入ったり、外国船に発砲したりして、これまた勝手に負けたにも関わらずに、会津憎しとは何事か。薩摩などは世紀の裏切り、腹黒ではないかといった私見である。
だいたいにおいて坂本龍馬が、商人ではなく維新の志士というなら、薩長同盟ではなく、会津と長州の仲立をしたのではないか? 「幕府を説得しようぜよ」とか言いながら。
以上、つれづれなるままの雑文であります。賛否あるとは思われますが(否の方が圧倒的多数でしょう)、飽くまでも個人的な私見として、読み流して頂ければ幸いです。こういった臍曲りもいるということで、筆を置きたいと思います。
臍曲りの私見
次回作まで、しばしお待ちください。
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。










