相馬主計(明治時代以降は主殿または肇)は、加入時期は不明だが、慶応3(1867)年12月の新撰組編成表に平隊士として名を連ねているので、その直前であろう。
同年10月、副長・土方歳三が江戸で隊士を募った際に応募し上洛した説が最も濃厚である。
新撰組としてはもはや晩年であり、衰退の一途を辿る中にあって、名も無き隊士として終わる筈であった。
そんな相馬主計が歴史の表舞台に顔を現すのは、同年4月、下総流山で局長・近藤勇が新政府軍に投降し、板橋の総督府に出頭した後である。
まずは相馬主計の略歴を振り返ろう。天保6(1835)年、常陸国笠間藩士・船橋平八郎の子として生まれる。笠間藩では、唯心一刀流剣術、示現流剣術が盛んであり、相馬もいずれかの流派であったと思われる。
慶応4(1868)年1月・鳥羽伏見の戦いにおいては、入隊間もなくにも関わらず、隊長附50名の組頭を任じられている事から、上記・剣術の腕前の程を知る事が出来るというものだ。
その頭角を現し始めたのが、甲州勝沼の戦いであり、ここで優れた軍事力を示し、副長・土方歳三の目に留る。
そして同戦いに敗走後に陣を敷いた房州流山にて、4月3日捕縛された局長・近藤助命の為、幕府の軍事総裁・勝海舟、陸軍軍事方・松濤権之丞、新撰組副長・土方歳三(幕臣・内藤隼人)の書状を携え、隊士・野村利三郎と共に板橋の東山道軍本営(総督府)を訪れた際に、初めてその名を見る事ができる。
だが
総督府では、近藤との面会も許されず、先に捕えられた局長付・野村利三郎(近藤に同道)と同じ牢に入れられ、斬首刑が決まっていたが、近藤が、「(斬首は)わたしひとりで良かろう」と、彼らの助命をし、近藤の処刑後、笠間藩に預けられ謹慎生活を送る。
近藤の処刑を強引に押し進めたのは、坂本龍馬暗殺を新撰組とする、土佐藩・谷干城とされているが、近藤はともかく、相馬や野村といった言わば新参の名も無き兵士の首を取ったところでどうなるのだと思うのだが…。
実際に、龍馬暗殺時に彼らは新撰組には入隊もしていない。
こういった新政府の勝ち驕った裁定が嫌でたまらないのだ。新政府軍の主力は下級武士。己の藩で虐げられた弱者の気持ちを分かっていた筈ではないか。
そもそも維新のきっかけは尊王だ。攘夷だではなかったのか。尊王は天皇政権にしようと実行したのは良いとして、外国人を実力行使で排斥しようという思想の下の攘夷の筈が、外国から武器は買うなど接近し、明治になれば西欧文化を取り入れまくり。
その辺りを薩長土に是非とも伺いたいものだ。〈続く〉
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。
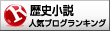
 にほんブログ村
にほんブログ村

同年10月、副長・土方歳三が江戸で隊士を募った際に応募し上洛した説が最も濃厚である。
新撰組としてはもはや晩年であり、衰退の一途を辿る中にあって、名も無き隊士として終わる筈であった。
そんな相馬主計が歴史の表舞台に顔を現すのは、同年4月、下総流山で局長・近藤勇が新政府軍に投降し、板橋の総督府に出頭した後である。
まずは相馬主計の略歴を振り返ろう。天保6(1835)年、常陸国笠間藩士・船橋平八郎の子として生まれる。笠間藩では、唯心一刀流剣術、示現流剣術が盛んであり、相馬もいずれかの流派であったと思われる。
慶応4(1868)年1月・鳥羽伏見の戦いにおいては、入隊間もなくにも関わらず、隊長附50名の組頭を任じられている事から、上記・剣術の腕前の程を知る事が出来るというものだ。
その頭角を現し始めたのが、甲州勝沼の戦いであり、ここで優れた軍事力を示し、副長・土方歳三の目に留る。
そして同戦いに敗走後に陣を敷いた房州流山にて、4月3日捕縛された局長・近藤助命の為、幕府の軍事総裁・勝海舟、陸軍軍事方・松濤権之丞、新撰組副長・土方歳三(幕臣・内藤隼人)の書状を携え、隊士・野村利三郎と共に板橋の東山道軍本営(総督府)を訪れた際に、初めてその名を見る事ができる。
だが
総督府では、近藤との面会も許されず、先に捕えられた局長付・野村利三郎(近藤に同道)と同じ牢に入れられ、斬首刑が決まっていたが、近藤が、「(斬首は)わたしひとりで良かろう」と、彼らの助命をし、近藤の処刑後、笠間藩に預けられ謹慎生活を送る。
近藤の処刑を強引に押し進めたのは、坂本龍馬暗殺を新撰組とする、土佐藩・谷干城とされているが、近藤はともかく、相馬や野村といった言わば新参の名も無き兵士の首を取ったところでどうなるのだと思うのだが…。
実際に、龍馬暗殺時に彼らは新撰組には入隊もしていない。
こういった新政府の勝ち驕った裁定が嫌でたまらないのだ。新政府軍の主力は下級武士。己の藩で虐げられた弱者の気持ちを分かっていた筈ではないか。
そもそも維新のきっかけは尊王だ。攘夷だではなかったのか。尊王は天皇政権にしようと実行したのは良いとして、外国人を実力行使で排斥しようという思想の下の攘夷の筈が、外国から武器は買うなど接近し、明治になれば西欧文化を取り入れまくり。
その辺りを薩長土に是非とも伺いたいものだ。〈続く〉
ランキングに参加しています。ご協力お願いします。










