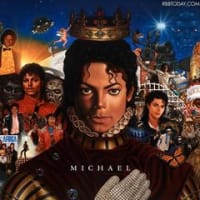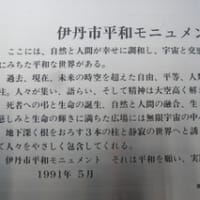物を遠くに投げようとするとき、人はだれでも斜め上がいいと知っている。真上では前へ進まないし、斜め下方向だとすぐ地上に落ちることが直感でわかるからだ。では、斜め上のどの角度が最適か?と問い直すと、はたと考え込んでしまう。考えてわからないなら実験して分析するのが人の常。実際やってみると、45度の角度が飛行距離が一番であることがわかる。でも、注意深く観測するともっと大切なことが見えてくる。それは、物体の飛行中の軌跡がすべて大きさは違えど同じ放物線を描いているという事実である。つまり、人の手を離れた瞬間に物体は我々の思いとは関係なく、なにかの法則に突き動かされて飛んでいくのではないか?この法則を探るのが物理学の力学という分野である。(いくつもの公式をただ覚え、それを問題に適用するのが物理ではない。公式は単純な法則から導きだされる結果にほかならない。結果だけを見て、本質を探求しないところに物理教育の問題がある。)
ケプラーたちによる天体の観測や惑星の運動に関する蓄積をもとに1686年ニュートンは物体の運動に関する3つの法則をうちたてる。
1.慣性の法則
物体は外から力が加わらなければ、いつまでも速さと向きを変えない。
2.運動の法則(運動方程式)
加速度は力の大きさに比例し、物体の質量に逆比例する。
3.作用・反作用の法則
ある物体に別の物体から力が作用すると同じ大きさで反対の向きの力が作用する。
彼がすごいのは、地上の雑多な物体の運動から惑星の運動まですべて、3つの法則から説明してしまったことである。運動方程式を記述し、それを解くことによって、物体の未来の軌跡を知ることが可能になった。人工衛星を宇宙に飛ばすのにも、運動方程式は不可欠なのである。
今日の我々の日常で起こる物理的現象は、ほぼ体系的にまとめられている。自然を操作可能にする科学の力を手に入れ、人類を神の支配から解放したのだ。(音は空気の振動なので運動の法則で説明がつく。われわれに身近な電気は、電磁気学という分野でマックスウェル方程式でまとめらているし、熱に対しては熱力学という分野で4つの法則で定式化されている。力学、電磁気学、熱力学をまとめて古典物理学と呼んでいる。)
法則というものは、新たな現象を理解するときに、うまく説明がつかなくなると、そこで法則としての命を終えるか修正が加えられ、さらに発展していく。物理学の歴史とはそのようなものなのである。
ギリシアの哲学者は、万物は何でできているかということに強く興味をもった。
デモクリトスは「物質をどんどん細かくしていったとき,これ以上分割できない」というものの存在をみとめ、アトムと名づけ、「原子論」を成立させた。しかし、近代科学の原子モデルに近いこの発想は1803年のドルトンに見直されるまでは約2000年も無視されていた。
しかし、20世紀初頭になってもまだ原子の存在は認められていない状況であったが、ついに1913年ジャン・ペランが実験により原子・分子の存在を実証した。原子の存在が明らかになると、次の問いが当然でてきます。原子はどのような構造になっているか?そしてその構造を支配する法則はあるのか?この問いはマクロからミクロな世界への物理学すなわち現代物理学へと発展していくことになります。

ラザフォードは実験を通して、上のような原子模型を提案します。原子核の周りを複数の電子がくるくる回転しているイメージです。
ニュートン力学は地上から宇宙までを説明できる万能な法則であったので、ミクロの世界でも適用されると期待しましたが、現象をうまく説明することができないという結果に終わりました。修正か新法則かが物理学にせまられたのです。修正の道を進んだのが現代物理学の父ニールス・ボーアです。

ニュートン力学を借用しながら、いくつかの仮定条件を入れて進めていくことで、水素原子(構造が単純)にはうまく説明がついたが、複雑な構造まで応用するには限界であった。ミクロな世界は我々の世界とは別の秩序で成り立っているということだ。そしてそれは、量子力学という新たな学問を切り開くことになった。これまでの古典物理学と違って、量子力学は哲学的な問いを含む不思議な学問である。
「物質は波でもあり、粒子でもある何か」だというのが出発点である。
シュレーディンガーは物質を波として捕らえ、波動力学を確立する。

逆にハイゼンベルグは物質を粒子として捕らえ、行列力学を確立する。

波でも粒子でもあるなら、波動力学と行列力学は物質を別の側面で説明するだけの違いだけであり、両者は一つの形式にまとめられるはずだと考えたのがディラックである。

ディラックの扱う記号(ケットベクトル)で成り立つ関係式は美しく、学生時代、彼に憧れて原書で著書「量子力学」を背伸びして読んだがまったくは歯が立たなかったことを記憶している。この本を読んで、別の定式化(経路積分)を思いついたのが、ファインマンです。

これで、ミクロの世界を記述する法則を人類は手にすることができた。高校の時に意味も無く覚えた化学式は量子力学を応用することにより生命を吹き返します。(非常に難しい学問ですが・・・)
ここで一つ疑問が残りませんか?だれもが知っているアインシュタイン博士は、何をした人なのか?と
ちなみにアインシュタインは、量子力学が形成される時代に生きた人で最後まで量子力学に懐疑的で、晩年は孤独でした。
「神はサイコロをふらない」

アインシュタインは物体が光の速度で運動した場合にどうなるかという不思議な問いを立てます。そして1905年に特殊相対論として発表します。
特殊相対論は次の2つを指導原理としています。
1.光速度不変の原理
真空中の光の速さは、光源の運動状態に影響されない一定値cである。
2.特殊相対性原理
お互いに等速度で運動しているすべての慣性系において、すべての基本的物理法則は、まったく同じ形で表される。それらの慣性系のなかから、なにか特別なものを選び出すことはできない。
ニュートン力学は修正を加えられることで相対論的運動方程式へと発展することになります。相対論的運動方程式がより普遍的な法則で、物体の速度が光の速度に比べ十分に遅い我々の世界の運動に対しては、近似式としてニュートンの運動方程式で説明がつくということになったのです。
物理と聞くと、耳を塞ぎたくなる人が多いと思いますが、歴史を通して見ていくと、世界を体系的に説明するという過去から連綿と続く人類の夢と希望が努力において実を結んだ貴重な学問分野といえるのです。どんな学問でもスポーツでもそうですが、できるようになるには基礎体力が必要です。物理では基礎体力にあたる数学は必須といえますが、その努力にみあうだけの驚きと喜びを最後には与えてくれることと思います。
ケプラーたちによる天体の観測や惑星の運動に関する蓄積をもとに1686年ニュートンは物体の運動に関する3つの法則をうちたてる。
1.慣性の法則
物体は外から力が加わらなければ、いつまでも速さと向きを変えない。
2.運動の法則(運動方程式)
加速度は力の大きさに比例し、物体の質量に逆比例する。
3.作用・反作用の法則
ある物体に別の物体から力が作用すると同じ大きさで反対の向きの力が作用する。
彼がすごいのは、地上の雑多な物体の運動から惑星の運動まですべて、3つの法則から説明してしまったことである。運動方程式を記述し、それを解くことによって、物体の未来の軌跡を知ることが可能になった。人工衛星を宇宙に飛ばすのにも、運動方程式は不可欠なのである。
今日の我々の日常で起こる物理的現象は、ほぼ体系的にまとめられている。自然を操作可能にする科学の力を手に入れ、人類を神の支配から解放したのだ。(音は空気の振動なので運動の法則で説明がつく。われわれに身近な電気は、電磁気学という分野でマックスウェル方程式でまとめらているし、熱に対しては熱力学という分野で4つの法則で定式化されている。力学、電磁気学、熱力学をまとめて古典物理学と呼んでいる。)
法則というものは、新たな現象を理解するときに、うまく説明がつかなくなると、そこで法則としての命を終えるか修正が加えられ、さらに発展していく。物理学の歴史とはそのようなものなのである。
ギリシアの哲学者は、万物は何でできているかということに強く興味をもった。
デモクリトスは「物質をどんどん細かくしていったとき,これ以上分割できない」というものの存在をみとめ、アトムと名づけ、「原子論」を成立させた。しかし、近代科学の原子モデルに近いこの発想は1803年のドルトンに見直されるまでは約2000年も無視されていた。
しかし、20世紀初頭になってもまだ原子の存在は認められていない状況であったが、ついに1913年ジャン・ペランが実験により原子・分子の存在を実証した。原子の存在が明らかになると、次の問いが当然でてきます。原子はどのような構造になっているか?そしてその構造を支配する法則はあるのか?この問いはマクロからミクロな世界への物理学すなわち現代物理学へと発展していくことになります。

ラザフォードは実験を通して、上のような原子模型を提案します。原子核の周りを複数の電子がくるくる回転しているイメージです。
ニュートン力学は地上から宇宙までを説明できる万能な法則であったので、ミクロの世界でも適用されると期待しましたが、現象をうまく説明することができないという結果に終わりました。修正か新法則かが物理学にせまられたのです。修正の道を進んだのが現代物理学の父ニールス・ボーアです。

ニュートン力学を借用しながら、いくつかの仮定条件を入れて進めていくことで、水素原子(構造が単純)にはうまく説明がついたが、複雑な構造まで応用するには限界であった。ミクロな世界は我々の世界とは別の秩序で成り立っているということだ。そしてそれは、量子力学という新たな学問を切り開くことになった。これまでの古典物理学と違って、量子力学は哲学的な問いを含む不思議な学問である。
「物質は波でもあり、粒子でもある何か」だというのが出発点である。
シュレーディンガーは物質を波として捕らえ、波動力学を確立する。

逆にハイゼンベルグは物質を粒子として捕らえ、行列力学を確立する。

波でも粒子でもあるなら、波動力学と行列力学は物質を別の側面で説明するだけの違いだけであり、両者は一つの形式にまとめられるはずだと考えたのがディラックである。

ディラックの扱う記号(ケットベクトル)で成り立つ関係式は美しく、学生時代、彼に憧れて原書で著書「量子力学」を背伸びして読んだがまったくは歯が立たなかったことを記憶している。この本を読んで、別の定式化(経路積分)を思いついたのが、ファインマンです。

これで、ミクロの世界を記述する法則を人類は手にすることができた。高校の時に意味も無く覚えた化学式は量子力学を応用することにより生命を吹き返します。(非常に難しい学問ですが・・・)
ここで一つ疑問が残りませんか?だれもが知っているアインシュタイン博士は、何をした人なのか?と
ちなみにアインシュタインは、量子力学が形成される時代に生きた人で最後まで量子力学に懐疑的で、晩年は孤独でした。
「神はサイコロをふらない」

アインシュタインは物体が光の速度で運動した場合にどうなるかという不思議な問いを立てます。そして1905年に特殊相対論として発表します。
特殊相対論は次の2つを指導原理としています。
1.光速度不変の原理
真空中の光の速さは、光源の運動状態に影響されない一定値cである。
2.特殊相対性原理
お互いに等速度で運動しているすべての慣性系において、すべての基本的物理法則は、まったく同じ形で表される。それらの慣性系のなかから、なにか特別なものを選び出すことはできない。
ニュートン力学は修正を加えられることで相対論的運動方程式へと発展することになります。相対論的運動方程式がより普遍的な法則で、物体の速度が光の速度に比べ十分に遅い我々の世界の運動に対しては、近似式としてニュートンの運動方程式で説明がつくということになったのです。
物理と聞くと、耳を塞ぎたくなる人が多いと思いますが、歴史を通して見ていくと、世界を体系的に説明するという過去から連綿と続く人類の夢と希望が努力において実を結んだ貴重な学問分野といえるのです。どんな学問でもスポーツでもそうですが、できるようになるには基礎体力が必要です。物理では基礎体力にあたる数学は必須といえますが、その努力にみあうだけの驚きと喜びを最後には与えてくれることと思います。