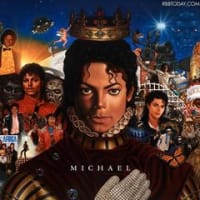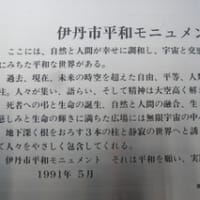家族を殺された遺族にとって加害者の償いとは、何であるかを問うドキュメンタリー番組を見た。
そこであきらかにされるのは、償いとは程遠い加害者の開き直りと加害者家族の信じられない無神経さによって翻弄される遺族の悲しい実態である。
遺族の会代表で、自身も妻を刺殺された80歳の弁護士は言う。
「だれでも、がんになったり、交通事故に遭うことは想像できても、自分が被害者の遺族になるなどとは思わないでしょう。・・・償いとは何ですか?償いという言葉は好きじゃない。人の命を奪った人間は、その命を蘇えさせられない限り償いとはいえない。もともと人を殺すような人間に償いを求めても無理だ。犯人を許すわけではないが、それが現実です。だから、裁判で決着を図った国が責任をもって遺族を保障すべきだと思う。」
確かにそうだ。被害者の遺族は刑事裁判において蚊帳の外に放り出され、加害者の反省の態度は裁判官へと向かい、その裁判官が判断を下す。それでは、正義からも悪からも見放された遺族の深い心の傷跡が残るだけになってしまう。
その傷を癒し、遺族の方々の怒りを静められるのは、加害者とその家族でしかない。法で守られた命であるのなら、誠意をつくすのが道理だと思う。刑期を終えたからそれで終わりではない。それは、社会が決めたルールとしてのけじめが済んだだけで、人間としての罪に対する罰が終わったわけではない。
ハンナ・アレントは書いている。
「誠実の反対は忘却であり、それこそが真の罪だ。人間は過ちを犯す。それと同時に自分が犯した過ちを悔い、それを決して忘れず、新たにはじめることができる。自らの罪を認めないもの、あるいは自らの罪に開き直って悔いることのないものは、赦されることはないであろう。」と。
被害を被った人間の手で、加害者を裁き得ないのが現実であるとしたら、被害者とその遺族を社会全体で救済できる仕組みを構築するのが急務だと思う。そして、なにより加害者とその家族が深く自省する過程で、被害者とその遺族の傷ついた心を少しでも和らげ、償いの道を歩んでくれたらと願う。
そこであきらかにされるのは、償いとは程遠い加害者の開き直りと加害者家族の信じられない無神経さによって翻弄される遺族の悲しい実態である。
遺族の会代表で、自身も妻を刺殺された80歳の弁護士は言う。
「だれでも、がんになったり、交通事故に遭うことは想像できても、自分が被害者の遺族になるなどとは思わないでしょう。・・・償いとは何ですか?償いという言葉は好きじゃない。人の命を奪った人間は、その命を蘇えさせられない限り償いとはいえない。もともと人を殺すような人間に償いを求めても無理だ。犯人を許すわけではないが、それが現実です。だから、裁判で決着を図った国が責任をもって遺族を保障すべきだと思う。」
確かにそうだ。被害者の遺族は刑事裁判において蚊帳の外に放り出され、加害者の反省の態度は裁判官へと向かい、その裁判官が判断を下す。それでは、正義からも悪からも見放された遺族の深い心の傷跡が残るだけになってしまう。
その傷を癒し、遺族の方々の怒りを静められるのは、加害者とその家族でしかない。法で守られた命であるのなら、誠意をつくすのが道理だと思う。刑期を終えたからそれで終わりではない。それは、社会が決めたルールとしてのけじめが済んだだけで、人間としての罪に対する罰が終わったわけではない。
ハンナ・アレントは書いている。
「誠実の反対は忘却であり、それこそが真の罪だ。人間は過ちを犯す。それと同時に自分が犯した過ちを悔い、それを決して忘れず、新たにはじめることができる。自らの罪を認めないもの、あるいは自らの罪に開き直って悔いることのないものは、赦されることはないであろう。」と。
被害を被った人間の手で、加害者を裁き得ないのが現実であるとしたら、被害者とその遺族を社会全体で救済できる仕組みを構築するのが急務だと思う。そして、なにより加害者とその家族が深く自省する過程で、被害者とその遺族の傷ついた心を少しでも和らげ、償いの道を歩んでくれたらと願う。