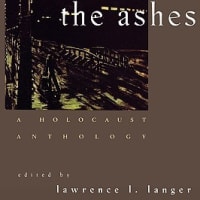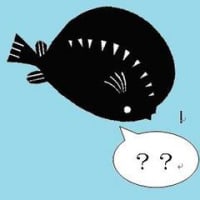所沢市文化振興事業団発行「Info Mart」1995年3.1 Vol.2掲載
文化のバトラーを訪ねて(2)
カザルスホール総合プロデューサー 萩元晴彦氏
サントリーホールを建てたのはウィスキーの会社だった。魂を吹き込んだのはプロデューサー萩原晴彦だった。
サントリーホールを世界的なオーケストラ専用ホールへと離陸させた萩元は「劇場支配人」の地位に居続けるには、あまりにプロデューサーでありすぎたのかも知れない。新しい自分自身に出会うことを面白がる本能が彼を次なる仕事に導いた。
カザルスホールを建てたのは、主婦の友という出版社だった。この建造物にもまた、魂と哲学が必要だった。萩元のところに総合プロデューサーになって欲しいという要請が来たことに、彼は人の意思を越えたものを感じた。
「サントリーホールのオープニングシリーズで僕はやめようと思ってたわけじゃないんです。途中からカザルスホールの相談を受け、これはやるべき仕事だと思った。神の見えざる手に導かれ、としか言いようがないのです。」
昭和22年、夏の甲子園大会で松本中学(旧制)の投手として活躍した萩元は、1977年から3年間、押しかけコーチとして毎週土曜日、東京から長野県松本市の母校野球部のグラウンドに出向いた。その時、主婦の友社『私の健康』の女性記者が松本まで萩元を取材に来た。彼女はたまたま社内の新ホール開発プロジェクトの一員だった。萩元と主婦の友社との出会いである。
かつて萩元は、1970年に開催された大阪万博博覧会の電電館のプロデューサーを務めたことがある。それに先立つモントリーオール万国博覧会のパンフレットに萩元は興味深い文章を見つけた。それは、いいパビリオンのための二つの必須条件だった。
一、何をやるかを決めてからパビリオンを建てなさい。
二、そのことを深く愛している人間をプロデューサーにして、彼に任せなさい。そして狂い死にするくらい彼に仕事をさせなさい。
萩元は言う。「一、について、残念ながら日本では、設計図ができてから、さて何をやるのかという企画委員会を召集しますね。僕もある地方都市の文化ホールの委員を頼まれたことがあり、その席で、まず建築をストップせよと主張して物議をかもしたことがあります。僕はこう思います。建築物のコンペの前に、まずソフトのコンペをやるべきです。そのプランをオープンにしてから建築のコンペをすべきだと思います。日本では順番が逆ですね。企画コンペそのものが建物のパブリシティになるはずなのです」
磯崎新の手により設計されたカザルスホール。萩元の頭にひらめいたのは「室内楽」だった。その時、彼にひらめいたのは「ことば」ではなく「旋律」だったかも知れない。
「日本にはもっと室内楽が必要だ、という小沢征爾さんの意見を常々聞いていましたから、自主公演を核にした室内楽専用ホールに、というコンセプトを僕はたてたのです」
《多目的ホール》全盛の当時、室内楽専用ホールをうたうことは無謀ではなかったか?アーチストを次々よべるのか?採算は合うのか?時には演歌や落語もいいんじゃないか?
しかし、萩元には室内楽に特別な思いがあった。演奏の上では命令・服従の関係でなく、自立した音楽家によるアンサンブルの芸術であること。思えばプロデューサー萩元晴彦の歩みそのものがそれに重なる。
TBSという巨大企業を離れ、テレビマンユニオンという組織を作った。株式会社にして創作集団の代表として、二律背反の組織運営に悪戦苦闘して来た。その萩元にとって室内楽は調和と創造の極み、天才たちのいとなみであった。よし、この場をアンサンブルの会堂にしよう。
その時、ホールは器ではなく、人格となった。
客席数511のカザルスホールが世界的な室内楽ホールの評判を得ながら、それを持続させる実務と収支の困難は想像に難くない。テレビマンユニオン主催公演など、「オーケストラがやって来た」のノウハウと、アーチスト・ネットワークがあって初めて乗り切れた部分もあっただろう。
「スポンサーがつけばいい、と簡単に言いますけどね、アーチストの契約って、3年先の分を行わなくちゃいけないんです。そんな先のことでスポンサーなどつくわけがないんです」
今から3年先にはカザルスホール開館10周年が待っている。そのための企画と交渉のことで萩元の頭脳は回転している。
「ゾウリ取りをしながら天下取りを考えている若き秀吉の心境です」と笑う。
プロデューサーは後継者の教育をどう考えているのだろう。
「チェロ奏者のヨー・ヨー・マに会いに行く時、一緒に行ったアシスタントに、僕が事故にあって一人で彼と交渉することになったら、君は彼に何と言うか、と質問したことがあります。そういう教育をしてゆかなければいけないのかな、と最近考えることがあります。アートマネジメントの学校はありますが、現実の場面でどこまで役に立つものやら。実践的なセミナーが必要で、それから、1年ぐらい、いいホールに出向いて勉強することをしたらいいでしょうね」
サラリーマンではなくインディペンデントなプロデューサーは、自分の考えをオーナーとスタッフの両方に、明快に説明できなければならない。哲学を持つこと、哲学なしに始めると問題が起こる。哲学があっても問題が起きることがあるのだから――。
萩元晴彦はホールプロデューサーのモデルとして、イギリス、ウィグモア・ホールのウィリアム・ラインの名前をあげる。市の予算で運営される音楽ホールのマネジャーとして彼は、館内を案内する女性のマナーやポスターのデザインにも気を配る。そしてピアニスト内田光子によるモーツァルトのソナタ全曲演奏を「水曜日のミツコ」といった魅力的なタイトルで企画し実現させた。すべては音楽を愛するがゆえに。ラインもまた音楽の神に仕えるバトラー(執事)のこころを持って客をもてなす。
新約聖書の冒頭は、キリストにいたる予言者たちの系図が語られている。萩元は天才音楽家たちの系図に自分がつながっていることにひそかな自負を持っている。
カザルスホール開館公演によんだピアノのホルショフスキーの先生はレシェティツキー、その先生はチェルニー、その先生はベートーヴェン。萩元はこれを「黄金の鎖」と呼ぶ。ホルショフスキーに学んだ相澤吏江子はカザルスホールが世に送り出したピアニストだ。
萩元晴彦は、この黄金の鎖の端を握る人として、音楽の使徒の系図に加わる。これは世俗の利得を越えた、プロデューサーへの恩寵である。
(敬称略)
文化のバトラーを訪ねて(2)
カザルスホール総合プロデューサー 萩元晴彦氏
サントリーホールを建てたのはウィスキーの会社だった。魂を吹き込んだのはプロデューサー萩原晴彦だった。
サントリーホールを世界的なオーケストラ専用ホールへと離陸させた萩元は「劇場支配人」の地位に居続けるには、あまりにプロデューサーでありすぎたのかも知れない。新しい自分自身に出会うことを面白がる本能が彼を次なる仕事に導いた。
カザルスホールを建てたのは、主婦の友という出版社だった。この建造物にもまた、魂と哲学が必要だった。萩元のところに総合プロデューサーになって欲しいという要請が来たことに、彼は人の意思を越えたものを感じた。
「サントリーホールのオープニングシリーズで僕はやめようと思ってたわけじゃないんです。途中からカザルスホールの相談を受け、これはやるべき仕事だと思った。神の見えざる手に導かれ、としか言いようがないのです。」
昭和22年、夏の甲子園大会で松本中学(旧制)の投手として活躍した萩元は、1977年から3年間、押しかけコーチとして毎週土曜日、東京から長野県松本市の母校野球部のグラウンドに出向いた。その時、主婦の友社『私の健康』の女性記者が松本まで萩元を取材に来た。彼女はたまたま社内の新ホール開発プロジェクトの一員だった。萩元と主婦の友社との出会いである。
かつて萩元は、1970年に開催された大阪万博博覧会の電電館のプロデューサーを務めたことがある。それに先立つモントリーオール万国博覧会のパンフレットに萩元は興味深い文章を見つけた。それは、いいパビリオンのための二つの必須条件だった。
一、何をやるかを決めてからパビリオンを建てなさい。
二、そのことを深く愛している人間をプロデューサーにして、彼に任せなさい。そして狂い死にするくらい彼に仕事をさせなさい。
萩元は言う。「一、について、残念ながら日本では、設計図ができてから、さて何をやるのかという企画委員会を召集しますね。僕もある地方都市の文化ホールの委員を頼まれたことがあり、その席で、まず建築をストップせよと主張して物議をかもしたことがあります。僕はこう思います。建築物のコンペの前に、まずソフトのコンペをやるべきです。そのプランをオープンにしてから建築のコンペをすべきだと思います。日本では順番が逆ですね。企画コンペそのものが建物のパブリシティになるはずなのです」
磯崎新の手により設計されたカザルスホール。萩元の頭にひらめいたのは「室内楽」だった。その時、彼にひらめいたのは「ことば」ではなく「旋律」だったかも知れない。
「日本にはもっと室内楽が必要だ、という小沢征爾さんの意見を常々聞いていましたから、自主公演を核にした室内楽専用ホールに、というコンセプトを僕はたてたのです」
《多目的ホール》全盛の当時、室内楽専用ホールをうたうことは無謀ではなかったか?アーチストを次々よべるのか?採算は合うのか?時には演歌や落語もいいんじゃないか?
しかし、萩元には室内楽に特別な思いがあった。演奏の上では命令・服従の関係でなく、自立した音楽家によるアンサンブルの芸術であること。思えばプロデューサー萩元晴彦の歩みそのものがそれに重なる。
TBSという巨大企業を離れ、テレビマンユニオンという組織を作った。株式会社にして創作集団の代表として、二律背反の組織運営に悪戦苦闘して来た。その萩元にとって室内楽は調和と創造の極み、天才たちのいとなみであった。よし、この場をアンサンブルの会堂にしよう。
その時、ホールは器ではなく、人格となった。
客席数511のカザルスホールが世界的な室内楽ホールの評判を得ながら、それを持続させる実務と収支の困難は想像に難くない。テレビマンユニオン主催公演など、「オーケストラがやって来た」のノウハウと、アーチスト・ネットワークがあって初めて乗り切れた部分もあっただろう。
「スポンサーがつけばいい、と簡単に言いますけどね、アーチストの契約って、3年先の分を行わなくちゃいけないんです。そんな先のことでスポンサーなどつくわけがないんです」
今から3年先にはカザルスホール開館10周年が待っている。そのための企画と交渉のことで萩元の頭脳は回転している。
「ゾウリ取りをしながら天下取りを考えている若き秀吉の心境です」と笑う。
プロデューサーは後継者の教育をどう考えているのだろう。
「チェロ奏者のヨー・ヨー・マに会いに行く時、一緒に行ったアシスタントに、僕が事故にあって一人で彼と交渉することになったら、君は彼に何と言うか、と質問したことがあります。そういう教育をしてゆかなければいけないのかな、と最近考えることがあります。アートマネジメントの学校はありますが、現実の場面でどこまで役に立つものやら。実践的なセミナーが必要で、それから、1年ぐらい、いいホールに出向いて勉強することをしたらいいでしょうね」
サラリーマンではなくインディペンデントなプロデューサーは、自分の考えをオーナーとスタッフの両方に、明快に説明できなければならない。哲学を持つこと、哲学なしに始めると問題が起こる。哲学があっても問題が起きることがあるのだから――。
萩元晴彦はホールプロデューサーのモデルとして、イギリス、ウィグモア・ホールのウィリアム・ラインの名前をあげる。市の予算で運営される音楽ホールのマネジャーとして彼は、館内を案内する女性のマナーやポスターのデザインにも気を配る。そしてピアニスト内田光子によるモーツァルトのソナタ全曲演奏を「水曜日のミツコ」といった魅力的なタイトルで企画し実現させた。すべては音楽を愛するがゆえに。ラインもまた音楽の神に仕えるバトラー(執事)のこころを持って客をもてなす。
新約聖書の冒頭は、キリストにいたる予言者たちの系図が語られている。萩元は天才音楽家たちの系図に自分がつながっていることにひそかな自負を持っている。
カザルスホール開館公演によんだピアノのホルショフスキーの先生はレシェティツキー、その先生はチェルニー、その先生はベートーヴェン。萩元はこれを「黄金の鎖」と呼ぶ。ホルショフスキーに学んだ相澤吏江子はカザルスホールが世に送り出したピアニストだ。
萩元晴彦は、この黄金の鎖の端を握る人として、音楽の使徒の系図に加わる。これは世俗の利得を越えた、プロデューサーへの恩寵である。
(敬称略)