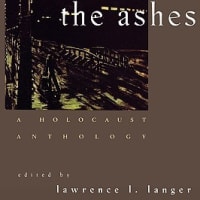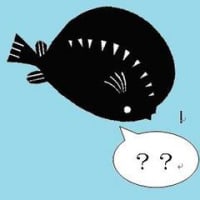風と、光と、ゆっくり流れる時間が、病いに捕らわれた私を解き放った
取材執筆 石井信平
病いとは、不思議な乗り物である。病人を苦悩に閉じ込めたまま停止することもあれば、思わぬ場所に連れて行き、めぐり合いを作る。脚本家・高木凛さんは、7年前の乳ガン手術後、心身の疲労を癒そうと沖縄に出掛けた。それは逃避行であり、ふるさとへの帰還のようでもあった。
「自分でも、心の中で何が起こったのかわからないのです。心療内科に行けばよかったのでしょうけど、自分が乳ガンであわただしく手術した後、立て続けに、舅、姑がガンになり、その対応に疲労困憊していました」。
それでも仕事人間の高木さんは、病気を吹っ切るためにも2時間ドラマの脚本執筆を引き受けた。資料を読み、プロットを作った。さあ書こうとして、まったく筆が進まない。空虚な感じを埋めるのが、ただ焦燥感だとしたら、人はその場にとどまっていられないだろう。思い立って出掛けた先が沖縄だった。
ひとり旅の長逗留が始まった。締め切りを真近にして東京の放送局に電話をした「すみません、書けないので今回は降ろしてください」。
作家にとって致命的ともいえる言葉である。ガン体験は高木さんから一時的に書く能力を奪った。しかし、決して無能力にしたのではない。大きな仕事から降りた時、彼女は何か巨大なものを「背負い投げ」のように投げ飛ばしたと言えないだろうか。健常者が作り出す掟や、生活のリズムや、早駆ける時間の移ろいに対して「不服従」を決めたのだ。
「何で沖縄か、とよく人に聞かれるのです。ふいに沖縄が私の前に現れた、衝動ですね。人と自然と神が、混在している、当たり前の姿がそこにありました。神といっても、人々が畏れの対象をもっているということです。そこから本来の人間の姿が見えてくるのです」
沖縄の光と風が全身を包んでくれた。テーゲー(大概)なゆとりで彼女を遇してくれた民宿の人々。久高島に古代から伝わる神事への畏怖と陶酔の体験。そして、ゆっくりと流れる時間。高木さんは、そこで文字通り「解き放」たれて時を過ごした。いったい彼女は、何にそんなに疲れきったのだろうか? 沖縄で「本来の人間の姿が見えてきた」というなら、それまで彼女がまみれた日本の医療は、何を見てくれていたのだろうか? 高木さん記憶がよみがえる。
半日以上も待たされた末の、三分間のあわただしい診療。ガン告知をされ、「すぐ手術です」と言われ、考えるいとまもない入院・手術の段取り。インフォームド・コンセントは患者が学習してくるのが当たり前、の風潮。丁寧な説明がないまま、切り取られる臓器。
「義母の胃癌手術のとき、膿盆に一杯に取った臓器を見せられたのはショックでした。高齢で小柄な義母から、こんなに取ってどうなるの、という思いでした。医療技術は間違いなく進歩しているのに、一つ進んでいないのが「死の教育」(デス・エデュケーション)ですね。イギリスやドイツにあって日本にないのが、人間が生きて死ぬことの根源的な教育です。何か基本的なところで社会が機能していないのは、それを学校も家庭もマスメデイアも怠っているからではないでしょうか」
生きること、食べること、サカナや獣の命を頂くことの大切さ。沖縄体験は高木さんを大いなる事業に促した。そこで食べた島野菜の奥深さと、ヤマトから画然と独立してある沖縄文化を伝えたいという思いが、沖縄懐石料理屋「潭亭」を東京、赤坂に開店させた。これもまた、病いという乗り物が彼女を拉致した先だった。
実は、今回インタビューを行なった場所は店にほど近い山王病院の病室だった。死の恐怖を味わった左胸のガン体験は、遥か7年前のこと。最近、胸の異常を感じ、レントゲン写真を撮った。何と、体内に前回の手術で残された金属クリップが発見された。他病院のこの失態にも、主治医の松井哲・外科部長は冷静に言った。「よくあることで、そんなに心配はいりません。それより、こっちですよ問題は」
乳ガンのプロは、彼女の右胸に新たに発症したガンを見逃さなかった。幸いなるかな、あの金属クリップが早期発見に導いたとも言える。彼女は他病院にセカンド・オピニオンを確かめた後、すべてを松井医師に託し、手術は一週間前に順調に終った。前回と同じく、乳房温存法だった。今後は、抗癌剤、ホルモン、放射線治療がプログラムされている。今回は取り乱さなかったのだろうか?
「ガンという病気はなかなか冷静にはなれないものです。でも一度、地雷を踏んだ身には大体が予測の範疇でした。入院に際しては、店のスタッフにも淡々と事実を話しました」
そう言い掛けた時、松井医師が病室に現れた。思いがけず、主治医と患者のやり取りを直接取材する結果になった。私は彼の権威ぶらないモノの言い方に強い印象を受けた。
「採血結果、感染症などのデータはまとめて、きょうの夕方にはお渡ししましょう。病理の結果は今週中に外来でお渡しします。リンパの結果は・・・熱海にいらっしゃるのですか。じゃ、電話でもいいですよ。今週中には、私の中で今後の方針を決めます」
リキんでいない、イバッていない。ああ、私もこういう医者なら命を預けたいと思う。彼が立ち去った後、高木さんが言った。
「松井先生の素晴らしいところは、ケレンのないところです。淡々と、冷静に、事実を語って下さることです。実に、聞く側にとって楽でした」
シロウトを楽にさせてくれるのが、本当のプロである。その実在モデルを目の前にした思いだった。次に病室のドアーを叩いて登場したのは、芸能プロダクション、音楽事務所、映画製作会社など「ブルーミング・グループ」を統括経営する牧山真智子さん。超多忙の中をお見舞いに駆けつけた。積る話の中で、牧山さんは印象的な一言を漏らした。「ガンになる人はいい人。いい人ばかりがガンになるのね」
お二人の長い付き合いの中で得た確信に、きょう初対面の私など立ち入れない。しかし私が知る身内や知人のガン患者を思い起こしても、これは真実に近いコメントではないか。
退院を目の前にした高木さんの負担にならないよう、牧山さんのお見舞いの花は箱の中にキッチリと入れられていた。蓋を取れば病室に花の香りが匂い、花たちが笑顔で笑っている。閉じれば自宅にすぐに持ち帰れる。ひとしきり歓談の時があり、短からず、長からず、絶妙なタイミングで牧山さんは病室を去った。彼女も8年前にガンの手術を受けているから、患者としては高木さんの先輩になる。後日、私はメールを出し、高木さんについて一言コメントを求めた。その返事に、こう書かれてあった。
「私は、あのように自分の考えに妥協することなく生きてこられた強さを、大変尊敬しています。損も一杯していらっしゃると思いますが、私はそのような生き方が好きです。今後は、もっともっと凛さんにしか書けない脚本を書いて欲しいです。このような方は少なくなってきましたから」
損得だけが蔓延する時代と国土に、高木さんは馴染まない。彼女はエッセーの中で、沖縄の人々のことを「足ることを知る民族」と書いている。私のインタビューに答える時、高木さんからは「ヤマトの人は」という言葉が自然に出てくる。沖縄とヤマトは全く違う歴史と文化圏を作ってきた。何と理不尽なことだろう、先の戦争で、沖縄はヤマトの尖兵として「本土決戦」唯一の戦場となり、沢山の死が強制された。その沖縄が、7年前に死ぬほどのストレスにあった高木さんを深々と抱きしめ、ヌチグスイ(命の薬)を口に含めてくれたのである。
「病気の苦痛というものがあり、それが沖縄との関わりや、店を作るまでに導いてくれたわけですね。死を考えたことが、むしろ有り難い結果につながったと思います。今度のガンの発症では、またそういうことが起こるとは思えないけれども、静かに色々なことが受け止められて、有り難い事です。今はただ、出来るだけのことを、出来るうちにやっておこうという心境です。この平穏は、どうしてでしょうと、自分でも思います」
確かな事実として彼女が驚いたことは、この7年間のガン医療技術の進歩である。乳ガンについて、ハルステット法か乳房温存法か、という議論は時代遅れになった。手術前検査も、麻酔技術も、その進歩を高木さんは身をもって体験した。
今回は死ということを考えましたか?
「それは考えました。いつもそれは自然なことで、定義すれば、死とは、その時がくるまで生きることです。目を閉じるまで、何かしていられれば幸せです。死を意識の外に置こうとしたのが前回でした。今は日常の草や木があるように、自然なこととして受け入れられそうです」
彼女の語りには、風が草や木をゆらすような「しじま」があった。それを教えたのは7年間という時間だろうか。一度「地雷」を踏んでしまった経験知だろうか。
沖縄で海の彼方に魂が帰るところを「ニライカナイ」という。病いという不思議な乗り物の窓から、高木さんは、自分が帰るところをハッキリと見たに違いない。
(終り)
取材執筆 石井信平
病いとは、不思議な乗り物である。病人を苦悩に閉じ込めたまま停止することもあれば、思わぬ場所に連れて行き、めぐり合いを作る。脚本家・高木凛さんは、7年前の乳ガン手術後、心身の疲労を癒そうと沖縄に出掛けた。それは逃避行であり、ふるさとへの帰還のようでもあった。
「自分でも、心の中で何が起こったのかわからないのです。心療内科に行けばよかったのでしょうけど、自分が乳ガンであわただしく手術した後、立て続けに、舅、姑がガンになり、その対応に疲労困憊していました」。
それでも仕事人間の高木さんは、病気を吹っ切るためにも2時間ドラマの脚本執筆を引き受けた。資料を読み、プロットを作った。さあ書こうとして、まったく筆が進まない。空虚な感じを埋めるのが、ただ焦燥感だとしたら、人はその場にとどまっていられないだろう。思い立って出掛けた先が沖縄だった。
ひとり旅の長逗留が始まった。締め切りを真近にして東京の放送局に電話をした「すみません、書けないので今回は降ろしてください」。
作家にとって致命的ともいえる言葉である。ガン体験は高木さんから一時的に書く能力を奪った。しかし、決して無能力にしたのではない。大きな仕事から降りた時、彼女は何か巨大なものを「背負い投げ」のように投げ飛ばしたと言えないだろうか。健常者が作り出す掟や、生活のリズムや、早駆ける時間の移ろいに対して「不服従」を決めたのだ。
「何で沖縄か、とよく人に聞かれるのです。ふいに沖縄が私の前に現れた、衝動ですね。人と自然と神が、混在している、当たり前の姿がそこにありました。神といっても、人々が畏れの対象をもっているということです。そこから本来の人間の姿が見えてくるのです」
沖縄の光と風が全身を包んでくれた。テーゲー(大概)なゆとりで彼女を遇してくれた民宿の人々。久高島に古代から伝わる神事への畏怖と陶酔の体験。そして、ゆっくりと流れる時間。高木さんは、そこで文字通り「解き放」たれて時を過ごした。いったい彼女は、何にそんなに疲れきったのだろうか? 沖縄で「本来の人間の姿が見えてきた」というなら、それまで彼女がまみれた日本の医療は、何を見てくれていたのだろうか? 高木さん記憶がよみがえる。
半日以上も待たされた末の、三分間のあわただしい診療。ガン告知をされ、「すぐ手術です」と言われ、考えるいとまもない入院・手術の段取り。インフォームド・コンセントは患者が学習してくるのが当たり前、の風潮。丁寧な説明がないまま、切り取られる臓器。
「義母の胃癌手術のとき、膿盆に一杯に取った臓器を見せられたのはショックでした。高齢で小柄な義母から、こんなに取ってどうなるの、という思いでした。医療技術は間違いなく進歩しているのに、一つ進んでいないのが「死の教育」(デス・エデュケーション)ですね。イギリスやドイツにあって日本にないのが、人間が生きて死ぬことの根源的な教育です。何か基本的なところで社会が機能していないのは、それを学校も家庭もマスメデイアも怠っているからではないでしょうか」
生きること、食べること、サカナや獣の命を頂くことの大切さ。沖縄体験は高木さんを大いなる事業に促した。そこで食べた島野菜の奥深さと、ヤマトから画然と独立してある沖縄文化を伝えたいという思いが、沖縄懐石料理屋「潭亭」を東京、赤坂に開店させた。これもまた、病いという乗り物が彼女を拉致した先だった。
実は、今回インタビューを行なった場所は店にほど近い山王病院の病室だった。死の恐怖を味わった左胸のガン体験は、遥か7年前のこと。最近、胸の異常を感じ、レントゲン写真を撮った。何と、体内に前回の手術で残された金属クリップが発見された。他病院のこの失態にも、主治医の松井哲・外科部長は冷静に言った。「よくあることで、そんなに心配はいりません。それより、こっちですよ問題は」
乳ガンのプロは、彼女の右胸に新たに発症したガンを見逃さなかった。幸いなるかな、あの金属クリップが早期発見に導いたとも言える。彼女は他病院にセカンド・オピニオンを確かめた後、すべてを松井医師に託し、手術は一週間前に順調に終った。前回と同じく、乳房温存法だった。今後は、抗癌剤、ホルモン、放射線治療がプログラムされている。今回は取り乱さなかったのだろうか?
「ガンという病気はなかなか冷静にはなれないものです。でも一度、地雷を踏んだ身には大体が予測の範疇でした。入院に際しては、店のスタッフにも淡々と事実を話しました」
そう言い掛けた時、松井医師が病室に現れた。思いがけず、主治医と患者のやり取りを直接取材する結果になった。私は彼の権威ぶらないモノの言い方に強い印象を受けた。
「採血結果、感染症などのデータはまとめて、きょうの夕方にはお渡ししましょう。病理の結果は今週中に外来でお渡しします。リンパの結果は・・・熱海にいらっしゃるのですか。じゃ、電話でもいいですよ。今週中には、私の中で今後の方針を決めます」
リキんでいない、イバッていない。ああ、私もこういう医者なら命を預けたいと思う。彼が立ち去った後、高木さんが言った。
「松井先生の素晴らしいところは、ケレンのないところです。淡々と、冷静に、事実を語って下さることです。実に、聞く側にとって楽でした」
シロウトを楽にさせてくれるのが、本当のプロである。その実在モデルを目の前にした思いだった。次に病室のドアーを叩いて登場したのは、芸能プロダクション、音楽事務所、映画製作会社など「ブルーミング・グループ」を統括経営する牧山真智子さん。超多忙の中をお見舞いに駆けつけた。積る話の中で、牧山さんは印象的な一言を漏らした。「ガンになる人はいい人。いい人ばかりがガンになるのね」
お二人の長い付き合いの中で得た確信に、きょう初対面の私など立ち入れない。しかし私が知る身内や知人のガン患者を思い起こしても、これは真実に近いコメントではないか。
退院を目の前にした高木さんの負担にならないよう、牧山さんのお見舞いの花は箱の中にキッチリと入れられていた。蓋を取れば病室に花の香りが匂い、花たちが笑顔で笑っている。閉じれば自宅にすぐに持ち帰れる。ひとしきり歓談の時があり、短からず、長からず、絶妙なタイミングで牧山さんは病室を去った。彼女も8年前にガンの手術を受けているから、患者としては高木さんの先輩になる。後日、私はメールを出し、高木さんについて一言コメントを求めた。その返事に、こう書かれてあった。
「私は、あのように自分の考えに妥協することなく生きてこられた強さを、大変尊敬しています。損も一杯していらっしゃると思いますが、私はそのような生き方が好きです。今後は、もっともっと凛さんにしか書けない脚本を書いて欲しいです。このような方は少なくなってきましたから」
損得だけが蔓延する時代と国土に、高木さんは馴染まない。彼女はエッセーの中で、沖縄の人々のことを「足ることを知る民族」と書いている。私のインタビューに答える時、高木さんからは「ヤマトの人は」という言葉が自然に出てくる。沖縄とヤマトは全く違う歴史と文化圏を作ってきた。何と理不尽なことだろう、先の戦争で、沖縄はヤマトの尖兵として「本土決戦」唯一の戦場となり、沢山の死が強制された。その沖縄が、7年前に死ぬほどのストレスにあった高木さんを深々と抱きしめ、ヌチグスイ(命の薬)を口に含めてくれたのである。
「病気の苦痛というものがあり、それが沖縄との関わりや、店を作るまでに導いてくれたわけですね。死を考えたことが、むしろ有り難い結果につながったと思います。今度のガンの発症では、またそういうことが起こるとは思えないけれども、静かに色々なことが受け止められて、有り難い事です。今はただ、出来るだけのことを、出来るうちにやっておこうという心境です。この平穏は、どうしてでしょうと、自分でも思います」
確かな事実として彼女が驚いたことは、この7年間のガン医療技術の進歩である。乳ガンについて、ハルステット法か乳房温存法か、という議論は時代遅れになった。手術前検査も、麻酔技術も、その進歩を高木さんは身をもって体験した。
今回は死ということを考えましたか?
「それは考えました。いつもそれは自然なことで、定義すれば、死とは、その時がくるまで生きることです。目を閉じるまで、何かしていられれば幸せです。死を意識の外に置こうとしたのが前回でした。今は日常の草や木があるように、自然なこととして受け入れられそうです」
彼女の語りには、風が草や木をゆらすような「しじま」があった。それを教えたのは7年間という時間だろうか。一度「地雷」を踏んでしまった経験知だろうか。
沖縄で海の彼方に魂が帰るところを「ニライカナイ」という。病いという不思議な乗り物の窓から、高木さんは、自分が帰るところをハッキリと見たに違いない。
(終り)