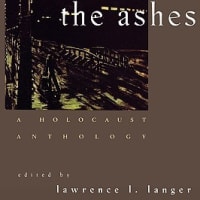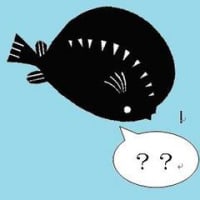所沢市文化振興事業団発行「Info Mart」1995年 Vol.1掲載
文化のバトラーを訪ねて(1)
カザルスホール総合プロデューサー 萩元晴彦氏
カザルスホール総合プロデューサー、萩元晴彦は「プロデューサーになるには試験も免許もいりません。印刷屋に行って名刺を作ればなれますよ」と言って笑った。
世にプロデューサーを名乗る人は多い。企画を立てる人も多い。しかし、企画を実現させ、アーチストと聴衆の両方を満足させるプロデューサーは少ない。萩元は数少ないプロデューサーの中でも先駆的な歩みをしてきた。
TBS社員時代とテレビマンユニオン創設を通して数多くの話題作、問題作を放送番組として世に送り出した。その中には王将戦のドキュメントもあれば、日本初の3時間ドラマもあった。いずれも放送界の常識を破る試みだった。また「オーケストラがやってきた」という番組が音楽界に与えた影響もはかり知れないものがあった。
その萩元に、サントリーホール出発の時、総合プロデューサーの話が来た。企業名を冠した音楽ホールも珍しいが、プロデューサーを迎えることも話題となった。
「ぼくはその話が来た時、二つのことを考えました。一つは、何をするのか、何のためにこの仕事をするのか。自分で考えなくちゃならないな、と思いました。プロデューサーという仕事は日本ではあいまいで、概念規定がありませんからね。もう一つは、引き受けるに当たっては小沢征爾さんに相談しよう、ということでした」
最初、小沢は賛成しなかった。このホールにどれだけフィロソフィーがあるのか疑わしく、何より、企業名を冠したところに宣伝意図が見えすいていたからである。ある日、小沢はサントリーホールの社長、佐治敬三に聞いた。
「佐治さん、あなたが死んだら、サントリーホールはどうなるの?」
この質問が、佐治にプロデューサーの必要を一層痛感させたと考えていいだろう。
萩元は言う。
「世界中のホールを知り尽くしている小沢さんにして初めてできる率直な質問です。小沢さんはこの質問を通してホールの哲学を問うたのです。ウィスキーが売れに売れていた当時でも、大音楽ホール建設は企業としては重大決意であり、佐治さんがいなければできないことでした」
サントリーホール総合プロデューサーに正式就任した萩元は、1985年5月15日、佐治の前で次のようなプレゼンテーションを行った。
「初めに音楽ありき。音楽こそがホールの主人(あるじ)である。そこに美しい音楽がみたされなければならない。クラシック音楽専用のホールとして理想的な音響空間を有し、再現と創造の場として機能する。自主公演を企画、制作し、オープニングシリーズは音楽でいえば主題の提示部であり、通年企画は展開部である。
ホールは音楽家にとって楽器である。そこで練習し公演するオーケストラを持つことを将来の課題とする。私企業のホールとして一切の官僚的規制を設けない。質の高いサービスも聴衆にも献身するスタッフを揃える。ここは商品開発の場であり、商品は不朽のロングセラー『クラシック音楽』であり、新しい発想によるマーケティング展開によって音楽人口の拡大を図る。以上を実現するために、私たち全員が音楽という主人(あるじ)の僕
である」
ホールはスタートした。「小沢征爾とベルリンフィル」「内田光子とイギリス室内オーケストラ」といった一級の企画がオープニングシリーズを飾り、サントリーホールを一流のホールとして世界に知らせた。それも前述のマニフェストが血となり肉としてスタッフ全員に分かち合われたからであろう。
準備段階の頃を萩元はこんな風に回想し苦笑する。
「初めは、プロデューサーといえども時間給で、出勤簿に線を引かされたものです」
雇う方も、雇われる方も試行錯誤だった。
「ぼくなんか、ずい分なまいきと思われたかも知れません。準備やアーチストとの交渉のための海外出張はぜんぶファーストクラスを主張しました。ホールを設計した建築家の先生がファーストクラスなら、プロデューサーも同格じゃなきゃおかしい、という考えです。あとから来る人のために使命感もありました。どうも日本では建築家の方がエライということになっていますね」
これは企画や方向性より先に建物の設計が決まってしまう風潮への警告である。同時にファーストクラスの感動に観客を誘うプロデューサーの自負も込められている。
建造物には惜しみなく金が使われ、アーチストにもそれなりに支払われる。けれどもその二つをつなぐ知恵や志に費用が考えられていない。総じて「ソフト」と呼ばれる部分へのプライオリティ(優先順位)の低さは日本をユニークな文化国家にしている。しかしそのことを嘆いても何もはじまらないだろう。プロデューサーに戦略がないことを暴露するだけだから。
萩元は連絡を続けている『婦人公論』の「プロデューサーは何をするか」の中で、《説得すること》こそプロデューサーの重要な仕事だとあげている。
「プロデューサーは命令しない。技術を練磨して説得する。説得力は企画に対する確信と情熱から生まれる。まず企画。最後は魅力ある人間になること」(同誌、'94年11月号)
プロデューサーは文化のバトラー(執事)である。彼は芸術の神につかえる。企画も説得力も日常の実務も、すべて芸術への愛に裏打ちされている。そこではプロとアマの差もない。
「愛情を持たないプロより、知識経験に欠けても、音楽に愛情を持ったアマチュアが一生懸命に仕事をすること、それが大事なのです。例えば、松本ハーモニーホールの館長さんは市の農政部長だった人ですよ」
ソバやジャガイモの収穫を思案する人が、音楽に心をくだくということは自然なことだ。そこには宮沢賢治が描いたユートピアのイメージがわいてくる。現実はもちろんユートピアに遠い。だからこそ、時代は夢と現実をつなぐプロデューサーを必要としていた。童話「シンデレラ」に登場するおばあさんは、カボチャを美しい馬車に変える魔術を持っていた。私は「プロデューサー」という言葉からこのおばあさんを連想する。
変哲のない空間も、プロデューサーの夢や企画力によって、人が集い、楽しみ、感動する場所に変えてしまう。プロデューサーは現実をおとぎ話に変える術を持っていると言うべきだろう。
サントリーホール総合プロデューサーの席が温まる間もなく、萩元のところに新しいホールの仕事が舞い込んだ。日本で初めての室内楽専用ホールとなった「カザルスホール」。シンデレラのおばあさんは「魔術」を使ったが、萩元は何を持って新しい仕事場に乗り込んだのか。その話は次回にゆずりたい。
(敬称略)
文化のバトラーを訪ねて(1)
カザルスホール総合プロデューサー 萩元晴彦氏
カザルスホール総合プロデューサー、萩元晴彦は「プロデューサーになるには試験も免許もいりません。印刷屋に行って名刺を作ればなれますよ」と言って笑った。
世にプロデューサーを名乗る人は多い。企画を立てる人も多い。しかし、企画を実現させ、アーチストと聴衆の両方を満足させるプロデューサーは少ない。萩元は数少ないプロデューサーの中でも先駆的な歩みをしてきた。
TBS社員時代とテレビマンユニオン創設を通して数多くの話題作、問題作を放送番組として世に送り出した。その中には王将戦のドキュメントもあれば、日本初の3時間ドラマもあった。いずれも放送界の常識を破る試みだった。また「オーケストラがやってきた」という番組が音楽界に与えた影響もはかり知れないものがあった。
その萩元に、サントリーホール出発の時、総合プロデューサーの話が来た。企業名を冠した音楽ホールも珍しいが、プロデューサーを迎えることも話題となった。
「ぼくはその話が来た時、二つのことを考えました。一つは、何をするのか、何のためにこの仕事をするのか。自分で考えなくちゃならないな、と思いました。プロデューサーという仕事は日本ではあいまいで、概念規定がありませんからね。もう一つは、引き受けるに当たっては小沢征爾さんに相談しよう、ということでした」
最初、小沢は賛成しなかった。このホールにどれだけフィロソフィーがあるのか疑わしく、何より、企業名を冠したところに宣伝意図が見えすいていたからである。ある日、小沢はサントリーホールの社長、佐治敬三に聞いた。
「佐治さん、あなたが死んだら、サントリーホールはどうなるの?」
この質問が、佐治にプロデューサーの必要を一層痛感させたと考えていいだろう。
萩元は言う。
「世界中のホールを知り尽くしている小沢さんにして初めてできる率直な質問です。小沢さんはこの質問を通してホールの哲学を問うたのです。ウィスキーが売れに売れていた当時でも、大音楽ホール建設は企業としては重大決意であり、佐治さんがいなければできないことでした」
サントリーホール総合プロデューサーに正式就任した萩元は、1985年5月15日、佐治の前で次のようなプレゼンテーションを行った。
「初めに音楽ありき。音楽こそがホールの主人(あるじ)である。そこに美しい音楽がみたされなければならない。クラシック音楽専用のホールとして理想的な音響空間を有し、再現と創造の場として機能する。自主公演を企画、制作し、オープニングシリーズは音楽でいえば主題の提示部であり、通年企画は展開部である。
ホールは音楽家にとって楽器である。そこで練習し公演するオーケストラを持つことを将来の課題とする。私企業のホールとして一切の官僚的規制を設けない。質の高いサービスも聴衆にも献身するスタッフを揃える。ここは商品開発の場であり、商品は不朽のロングセラー『クラシック音楽』であり、新しい発想によるマーケティング展開によって音楽人口の拡大を図る。以上を実現するために、私たち全員が音楽という主人(あるじ)の僕
である」
ホールはスタートした。「小沢征爾とベルリンフィル」「内田光子とイギリス室内オーケストラ」といった一級の企画がオープニングシリーズを飾り、サントリーホールを一流のホールとして世界に知らせた。それも前述のマニフェストが血となり肉としてスタッフ全員に分かち合われたからであろう。
準備段階の頃を萩元はこんな風に回想し苦笑する。
「初めは、プロデューサーといえども時間給で、出勤簿に線を引かされたものです」
雇う方も、雇われる方も試行錯誤だった。
「ぼくなんか、ずい分なまいきと思われたかも知れません。準備やアーチストとの交渉のための海外出張はぜんぶファーストクラスを主張しました。ホールを設計した建築家の先生がファーストクラスなら、プロデューサーも同格じゃなきゃおかしい、という考えです。あとから来る人のために使命感もありました。どうも日本では建築家の方がエライということになっていますね」
これは企画や方向性より先に建物の設計が決まってしまう風潮への警告である。同時にファーストクラスの感動に観客を誘うプロデューサーの自負も込められている。
建造物には惜しみなく金が使われ、アーチストにもそれなりに支払われる。けれどもその二つをつなぐ知恵や志に費用が考えられていない。総じて「ソフト」と呼ばれる部分へのプライオリティ(優先順位)の低さは日本をユニークな文化国家にしている。しかしそのことを嘆いても何もはじまらないだろう。プロデューサーに戦略がないことを暴露するだけだから。
萩元は連絡を続けている『婦人公論』の「プロデューサーは何をするか」の中で、《説得すること》こそプロデューサーの重要な仕事だとあげている。
「プロデューサーは命令しない。技術を練磨して説得する。説得力は企画に対する確信と情熱から生まれる。まず企画。最後は魅力ある人間になること」(同誌、'94年11月号)
プロデューサーは文化のバトラー(執事)である。彼は芸術の神につかえる。企画も説得力も日常の実務も、すべて芸術への愛に裏打ちされている。そこではプロとアマの差もない。
「愛情を持たないプロより、知識経験に欠けても、音楽に愛情を持ったアマチュアが一生懸命に仕事をすること、それが大事なのです。例えば、松本ハーモニーホールの館長さんは市の農政部長だった人ですよ」
ソバやジャガイモの収穫を思案する人が、音楽に心をくだくということは自然なことだ。そこには宮沢賢治が描いたユートピアのイメージがわいてくる。現実はもちろんユートピアに遠い。だからこそ、時代は夢と現実をつなぐプロデューサーを必要としていた。童話「シンデレラ」に登場するおばあさんは、カボチャを美しい馬車に変える魔術を持っていた。私は「プロデューサー」という言葉からこのおばあさんを連想する。
変哲のない空間も、プロデューサーの夢や企画力によって、人が集い、楽しみ、感動する場所に変えてしまう。プロデューサーは現実をおとぎ話に変える術を持っていると言うべきだろう。
サントリーホール総合プロデューサーの席が温まる間もなく、萩元のところに新しいホールの仕事が舞い込んだ。日本で初めての室内楽専用ホールとなった「カザルスホール」。シンデレラのおばあさんは「魔術」を使ったが、萩元は何を持って新しい仕事場に乗り込んだのか。その話は次回にゆずりたい。
(敬称略)