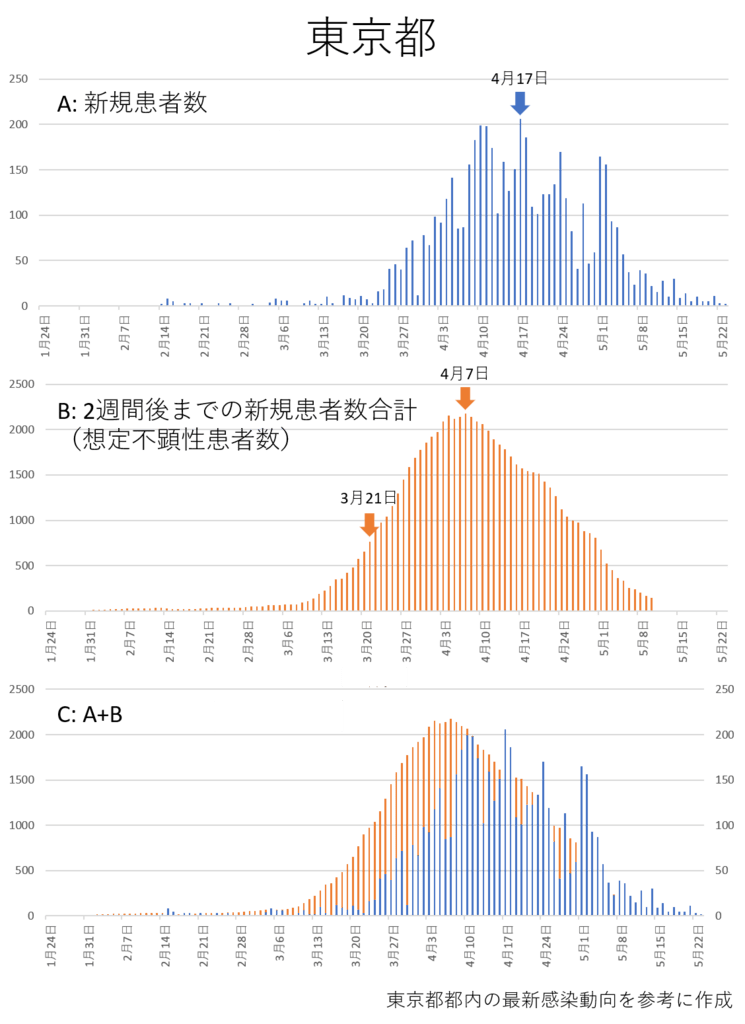新型コロナウイルス感染症の流行は病院機能にも大きな影響を与えましたが、外科医にとっては必要な手術を延期せざるを得なかった点は大きな問題でした。延期した理由としては、術前、あるいは術後にSARS-CoV-2の感染が明らかになった場合の転帰がわからないという点がありました。このような疑問に答えるような研究がLancet誌に掲載されました。
この論文は24か国の235病院で1月1日から3月31日までに手術を受けた患者で、術前7日~術後30日にSARS-CoV-2感染症の診断を受けた手術患者の予後を調べたものです。基本的に前向きに患者を登録していますが、すべての基準適格患者を同定できる場合は後ろ向きの組み入れも許可しています。Primary outcomeは術後30日以内の死亡(30-day mortality)、secondary outcomeとしては肺合併症、肺塞栓、7-day mortality、ICU入室、再手術、入院期間などを調べています。
(結果)対象患者は1128人で、男性が53.6%、年齢は50歳未満19.0%、50-69歳31.3%、70歳以上49.5%です。SARS-CoV-2の感染が術前に診断されたのは26.1%でした。緊急手術が74.0%、予定手術が24.8%でした。良性病変54.5%、癌14.6%、外傷20.1%で、Minor surgery22.3%、Major surgery74.6%でした。
Primary outcomeである30日以内死亡率は23.8%でした。
男性 vs 女性(28.4% vs 18.2% p<0.0001)
70歳以上vs70歳未満(33.7% vs 13.9% p<0.0001)
緊急手術vs予定手術(25.6% vs 18.9% p=0.023)
死亡に関与する因子としては、男性(OR 1.75)、70歳以上(2.30)、ASA grades 3–5(vs grades 1–2)2.35 、悪性疾患1.55 、緊急手術1.67 、major surgery1.52などが有意なものでした。
51.2%の患者に1つ以上の肺合併症がありました(肺炎40.4%、予期せぬ人工呼吸器使用21.3%、ARDS 14.4%)。肺合併症の存在は有意な30-day mortalityのリスク因子でした(38.0% vs 8.7%, p<0.0001)。特にARDS患者では162例中102例(63.0%)で死亡しました。肺塞栓は22例(2.0%)のみでした。
ちなみに整形外科手術(おそらく外傷が多いと思われますが)は299例で30-day mortalityは71.2%(!)、肺合併症率は55.7%でした。
この研究自体はone armの研究ですので、過去の術後合併症や死亡率と比較してみる必要があります。
①2019年の英国NELA報告では、術前の死亡リスクが高い患者で16.9%、予期せぬICU入院患者の16.8%、70歳以上のフレイル患者で23.4%の30-day mortality(NELA Project Team)。
②低所得国と中所得国を含む 58 カ国を対象とした研究では、緊急の正中開腹手術(midline laparotomy)を受けたハイリスクサブグループの 30 日死亡率は 14.9%であった(GlobalSurg Collaborative, Br J Surg 2016;103: 971–88.) 。
③2014-15年にヨーロッパ28カ国の211病院を対象としたPOPULAR多施設前向き観察研究では、肺合併症率は8%(Kirmeier et al., Lancet Respir Med. 2019; 7: 129-140)。
④ARDSは様々な合併症の中で最も死亡率が高いものでした(今回の死亡率63.0%)が、パンデミック前のAfrican Surgical Outcomes Studyの報告(0.05%)よりもはるかに高い頻度(20%)で発生していました。米国の7つのセンターで心臓以外の手術を受けた高リスクのASAグレード3の患者を対象とした別の研究では、0.2%がARDSを発症し、術後の肺合併症に関連した全体の死亡率は2.3%であったとされています(Fernandez-Bustamante A et al., JAMA Surg. 2017; 152: 157-166)。
以上の先行データと比較しても、今回の死亡率・合併症率がいかに高かったかがわかります。このように見てみると、やはり不急(不要の手術はないと思いますので)の手術は延期という判断は適切であったと思われます。
検査や放射線読影などは標準化しておらず、すべてのCOVID-19の患者を拾い切れていない可能性あり。ヨーロッパと北米が中心といったlimitationはありますが、本研究は SARS-CoV-2 感染症患者の手術後の死亡率を評価した最初の国際的研究であり、すべての外科専門分野にまたがる最初の研究である点で高く評価されるべきでしょう。
この論文は24か国の235病院で1月1日から3月31日までに手術を受けた患者で、術前7日~術後30日にSARS-CoV-2感染症の診断を受けた手術患者の予後を調べたものです。基本的に前向きに患者を登録していますが、すべての基準適格患者を同定できる場合は後ろ向きの組み入れも許可しています。Primary outcomeは術後30日以内の死亡(30-day mortality)、secondary outcomeとしては肺合併症、肺塞栓、7-day mortality、ICU入室、再手術、入院期間などを調べています。
(結果)対象患者は1128人で、男性が53.6%、年齢は50歳未満19.0%、50-69歳31.3%、70歳以上49.5%です。SARS-CoV-2の感染が術前に診断されたのは26.1%でした。緊急手術が74.0%、予定手術が24.8%でした。良性病変54.5%、癌14.6%、外傷20.1%で、Minor surgery22.3%、Major surgery74.6%でした。
Primary outcomeである30日以内死亡率は23.8%でした。
男性 vs 女性(28.4% vs 18.2% p<0.0001)
70歳以上vs70歳未満(33.7% vs 13.9% p<0.0001)
緊急手術vs予定手術(25.6% vs 18.9% p=0.023)
死亡に関与する因子としては、男性(OR 1.75)、70歳以上(2.30)、ASA grades 3–5(vs grades 1–2)2.35 、悪性疾患1.55 、緊急手術1.67 、major surgery1.52などが有意なものでした。
51.2%の患者に1つ以上の肺合併症がありました(肺炎40.4%、予期せぬ人工呼吸器使用21.3%、ARDS 14.4%)。肺合併症の存在は有意な30-day mortalityのリスク因子でした(38.0% vs 8.7%, p<0.0001)。特にARDS患者では162例中102例(63.0%)で死亡しました。肺塞栓は22例(2.0%)のみでした。
ちなみに整形外科手術(おそらく外傷が多いと思われますが)は299例で30-day mortalityは71.2%(!)、肺合併症率は55.7%でした。
この研究自体はone armの研究ですので、過去の術後合併症や死亡率と比較してみる必要があります。
①2019年の英国NELA報告では、術前の死亡リスクが高い患者で16.9%、予期せぬICU入院患者の16.8%、70歳以上のフレイル患者で23.4%の30-day mortality(NELA Project Team)。
②低所得国と中所得国を含む 58 カ国を対象とした研究では、緊急の正中開腹手術(midline laparotomy)を受けたハイリスクサブグループの 30 日死亡率は 14.9%であった(GlobalSurg Collaborative, Br J Surg 2016;103: 971–88.) 。
③2014-15年にヨーロッパ28カ国の211病院を対象としたPOPULAR多施設前向き観察研究では、肺合併症率は8%(Kirmeier et al., Lancet Respir Med. 2019; 7: 129-140)。
④ARDSは様々な合併症の中で最も死亡率が高いものでした(今回の死亡率63.0%)が、パンデミック前のAfrican Surgical Outcomes Studyの報告(0.05%)よりもはるかに高い頻度(20%)で発生していました。米国の7つのセンターで心臓以外の手術を受けた高リスクのASAグレード3の患者を対象とした別の研究では、0.2%がARDSを発症し、術後の肺合併症に関連した全体の死亡率は2.3%であったとされています(Fernandez-Bustamante A et al., JAMA Surg. 2017; 152: 157-166)。
以上の先行データと比較しても、今回の死亡率・合併症率がいかに高かったかがわかります。このように見てみると、やはり不急(不要の手術はないと思いますので)の手術は延期という判断は適切であったと思われます。
検査や放射線読影などは標準化しておらず、すべてのCOVID-19の患者を拾い切れていない可能性あり。ヨーロッパと北米が中心といったlimitationはありますが、本研究は SARS-CoV-2 感染症患者の手術後の死亡率を評価した最初の国際的研究であり、すべての外科専門分野にまたがる最初の研究である点で高く評価されるべきでしょう。
COVIDSurg Collaborative. Mortality and pulmonary complications in patients undergoing surgery with perioperative SARS-CoV-2 infection: an international cohort study. Lancet DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31182-X