心のケアと自立のための日記指導-17
(2)「会話」のある場面を日記の題材に
③行事のあった日の家でのことを書く
「ある日、ある時」の、短い間の出来事を、その時、したことや見たことだけでなくその時の会話をよく思い出して、時間の順序にしたがって書く。すなわち、一つの体験「~した。~した。」「~しました。~しまし。」「~したのだった。」「~したのでした。」と展開的過去形表現形体」の文章を書くときに、大事な会話を落とさずに書く力をつけるとともに、日常の会話に興味を持たせ、会話のもつ重要性を理解させることをここでのねらいとした。
劇が終わった時に「今日の劇、上手にできたね。家の人は何て言ってくれるかなあ。何て言ってくれたか、次の日に発表してもらうよ。家の人がこない人だって、きっと今日の劇のことを聞くと思うよ。
そのことを話してくれればいいんだよ」と言っておいた。
文化祭の日や、運動会、授業参観があった日などは、家で必ずそのことについて話し合う。会話がはずむに違いない。
そこに目をつけ、作文を書くから(日記に書くから)「よく聞いてこい。」とは言わないにしても、どんな会話をしたのか、耳と心をはたらかせるように言っておいて書くようにする。
そうして、その会話をよく思い出して、しっかりと文章化させることにより、時と場所、話の内容にあわせて、ありのままの文章を書くようにさせる。また、その時の人びとの会話にこめられているその人の考え、会話の意味などに気を配れる子どもに育てたいと考えた。
『家に帰って』 優子
家に帰りついてから
「ただいまあ。」
とお母さんに言った。そうしたらお母さんが、
「お帰り」
と言った。
わたしは、どうだったのかなあと思いながら、
「お母さん、文化祭、どうだった。」
と聞いた。そうしたら、お母さんが、
「よかったよ。」
と言ったので、わたしは、
「どこがよかったの。」
と聞いたら、
「そうねえ、みんなで話を考えて、先生がまとめたと聞いたけど、話のなかみが、教えられることがいっぱいでよかったね。それに、声もよくとおったし、先生も出られて、全体にまとまりがあったと思 うわ。」
わたしは、そうかなあと思っていました。そしたらお母さんがまた続けて、
「山がりっばにできていたけれど、だれが書いたの。」
と聞いたので、わたしは、
「だれが書いたのかは、わすれたけれど、グループで書いたんだよ。わたしは、草を作ったんだよ。」
と説明してあげた。さいごにお母さんは、
「田中先生の歌もじょうずだったわ。あんなにうまいとは知らなかったよ。」
と言っていた。わたしも、田中先生にならっていたけれど、歌がうまいとは、あまり思っていなかった。
(以下略)
「優子さんのお母さんは、こう言ってほめてくれたんだね。」と、ほめている部分を二度ほど読んで上げたら、他の子どもたちが、ぼくのお母さんは、こうだと、作品を読みはじめた。そうして、「会話もそのとおりうつすと長くなるなあ、よく聞いてなければ書けないなあ」という感想をもった子もいた。
● 今「会話」の入った文章を書くことの意味
・身のまわりのひとの見方や考え方を理解する。
その人の認識や思考の深さや広さに気づくことができる。
その人の見方、考え方をつかむことができる。
その人の感情や意志をつかむことができる。
・他人の気持ちをおしはかる力を育てる
・人の話を意識して聞いたり、集中して聞く力
会話が事件や出来事のきっかけとなっていたり、展開の重要な役割をはたしていたりすることに気づくようになる。
・会話のなかにあるその人の考えや願いを、自分の生活に生かす力
・事実にもとづいて考える力。
・会話のはいった生き生きとした文章を書く力。(注6)
(注6 詳しくは「会話を書く大切さを教える」『書ける子どもを育てる』田中定幸著・出版・1995年 P10 9~11 7を参照)
この③は以前書いた『つくる・つづる』(未発表)からの引用です。前後の内容と重複する部分がありますが、③として挿入しておくことにしました。













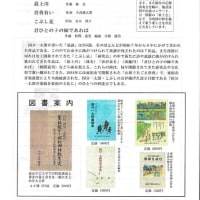


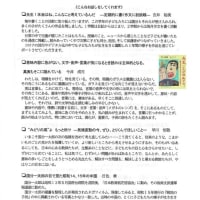
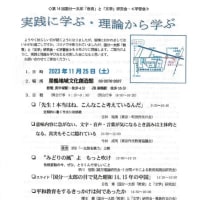

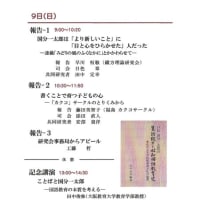
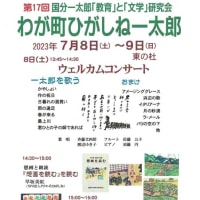





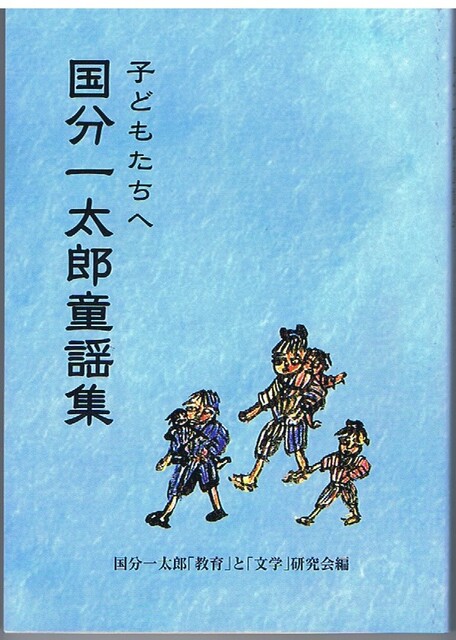

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます