閲覧有難う御座います。本日はその他の話です。

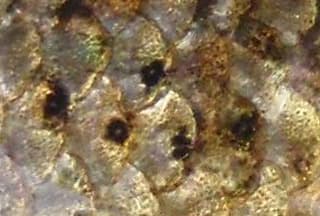

先日、この様なフナを採取しました。いわゆるゴマ鮒と呼ばれるものですね。
鰭や鱗の辺りに、黒い小さな斑点が多数見られます。
この症状は通称?『黒点病』と呼ばれるよく見る病気ですね。
よく見る割に詳しく知らないもので、今回少し調べて見ました。参考・引用文献
病名:
黒点病
症状:
魚類に寄生した吸虫類のまわりに、メラニン色素が集まり黒い斑点ができる
原因:
アユ、オイカワ、ウグイ等は横川吸虫及び宮田吸虫の寄生
フナ類は高橋吸虫の寄生
感染:
ほ乳類、鳥類の糞に含まれる卵を第1中間宿主のカワニナ類が摂取、そこから放出された幼生を第2中間宿主の魚類が摂取し感染、その後は寄生魚類を捕食した終宿主(ほ乳類、鳥類)の元へ。だから生で食べれば、人間にも寄生し得るとの事。
治療:
塩水浴、薬浴、気が付けば治ってる
私見:
①金魚のジプロストマムとの関係が分からない・・・、どちらも黒点病
②そう言えば、トウヨシノボリにも黒点が有ったけど何吸虫だろう?
③ごまタナゴは嫌われて、銀鱗タナゴは有り難がたがられるのは
『本是同根生 相煎何太急』と言ったところか?
④そう言えば、感染による害もよくわかりませんね
画像:
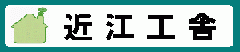

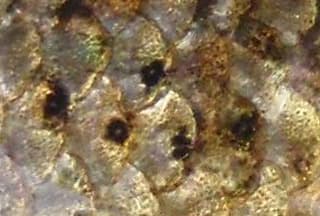

先日、この様なフナを採取しました。いわゆるゴマ鮒と呼ばれるものですね。
鰭や鱗の辺りに、黒い小さな斑点が多数見られます。
この症状は通称?『黒点病』と呼ばれるよく見る病気ですね。
よく見る割に詳しく知らないもので、今回少し調べて見ました。参考・引用文献
病名:
黒点病
症状:
魚類に寄生した吸虫類のまわりに、メラニン色素が集まり黒い斑点ができる
原因:
アユ、オイカワ、ウグイ等は横川吸虫及び宮田吸虫の寄生
フナ類は高橋吸虫の寄生
感染:
ほ乳類、鳥類の糞に含まれる卵を第1中間宿主のカワニナ類が摂取、そこから放出された幼生を第2中間宿主の魚類が摂取し感染、その後は寄生魚類を捕食した終宿主(ほ乳類、鳥類)の元へ。だから生で食べれば、人間にも寄生し得るとの事。
治療:
塩水浴、薬浴、気が付けば治ってる
私見:
①金魚のジプロストマムとの関係が分からない・・・、どちらも黒点病
②そう言えば、トウヨシノボリにも黒点が有ったけど何吸虫だろう?
③ごまタナゴは嫌われて、銀鱗タナゴは有り難がたがられるのは
『本是同根生 相煎何太急』と言ったところか?
④そう言えば、感染による害もよくわかりませんね
画像:

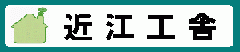



















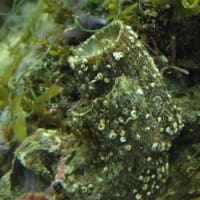
しまいます。。。
酷い時には全身がごまだらけで、それを中途半端な理解
で寄生虫だと思っているから余計ですね。。。
症状の進行によるのかもしれませんが、治療方法は割と
簡単なものでよかったです~。
ありがとうございました~。
最後の宿主のお尻から、また新しいサイクルが始まるんですね。
と、言う事は人間の体内にきた場合は、大概はトイレへ...ごく少数が、野へ~という事ですね。
川へ直接ブリブリは、あまりいないか...。
って言われて、詠んだらしい…。
真偽の程は知らんけど、嫌な奴やなぁ…。
黒点病は、見た目は悪いですが、生死に関するような重大な病気とは思ってません。
認識が甘いかな?
それよりも、発見したからって、寄生虫に自分の名前付けることに違和感なかったんだろうか?
そっちが解らん…。
この症状が見られる魚がいる川って
ほとんどが感染しているような気がするんですがね。
琵琶湖周辺のタナゴはゴマがあって当然だと。
確かにゴマがないヤリ・ボテの固体を見たことがないですね。
一体、琵琶湖周辺で何が起こっているのか???
ryuさん、そこら中で野○ソしてませんか?
の稚魚でして、この魚は何だろう?と思い持ち
帰って塩浴薬を常に入れて飼育してたらプラチ
ナカネヒラへと変身しました!
凄く嬉しかったのを覚えています。
しかしゴマが寄生虫が元になっているのは知っ
ていましたが高橋・・・ 横川・・・
そんなに種類かあったんですか・・・w
実は治療法、試した事が無いんですよ~
何時も気が付けば持って帰った
ゴマタナゴが直っていたりすますから。
ですから、詳しいことは
参考文献載せているサイトとかでね(笑)
基本的に川魚を生でワイルドに
食べると感染しちゃう感じですね~
だから将軍、野外で排出しちゃ駄目ね!
>七歩歩く間に詩を作らんと死刑だぞ!
お、詳しいですね~
結構この詩、上手いなーと思うんですよ~
父親の血でしょうかね?アレは凄い奴です。
>寄生虫に自分の名前付けること
懐畔さんは新種のドジョウを発見したら
カイハンドジョウと名付けて下さいませ!
一定のサイクルに組み込まれている
感染ルートそんな感じがしますね~
あとは、時期の問題もあるのかな?