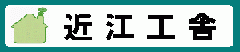本日は、餌のお話です。
何時ものお昼の10分ガサですが、現場からの移動中でカメラが無い・・・。取敢えず、結果だけを報告します。

本日の成果。ミナミヌマエビは2網くらいで大量です!生餌だけのつもりでしたが + α としてメダカが数匹捕れましたので、飼育用にお持ち帰り致します(餌にはしない)。ミナミヌマエビは大きな個体が繁殖用、小さな個体が動くものしか食べない魚の餌用になります。

ヤゴの仲間。サイズが小さければ食べますが、大きなサイズでは興味を示さないこともあります。ギンヤンマのヤゴ等は、ドンコくらいしか興味を示しませんでした。

ミズムシ。何時も思いますが、見た目とネーミングで差別されている生物・・・個人的に生餌としてはかなり評価が高く、ヨコエビよりも良いのでは?どちらも枯葉等の分解者なので水槽を掃除してくれます(捕食されなければ・・・)。

天然の赤虫。釣具店で市販されている個体より、サイズが小さい個体が採取できるのがうれしいです。魚も好んで食べますね。
メダカの撮影を忘れた・・・
※生餌は河川から病気を持ち込む恐れがあります。使用に際しては、十分に検討してから与えて下さい!
ただいま細々と活動中
近江フィールドワーク別館
よろしければこちらにもお越し下さい。
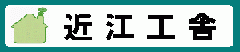
何時ものお昼の10分ガサですが、現場からの移動中でカメラが無い・・・。取敢えず、結果だけを報告します。

本日の成果。ミナミヌマエビは2網くらいで大量です!生餌だけのつもりでしたが + α としてメダカが数匹捕れましたので、飼育用にお持ち帰り致します(餌にはしない)。ミナミヌマエビは大きな個体が繁殖用、小さな個体が動くものしか食べない魚の餌用になります。

ヤゴの仲間。サイズが小さければ食べますが、大きなサイズでは興味を示さないこともあります。ギンヤンマのヤゴ等は、ドンコくらいしか興味を示しませんでした。

ミズムシ。何時も思いますが、見た目とネーミングで差別されている生物・・・個人的に生餌としてはかなり評価が高く、ヨコエビよりも良いのでは?どちらも枯葉等の分解者なので水槽を掃除してくれます(捕食されなければ・・・)。

天然の赤虫。釣具店で市販されている個体より、サイズが小さい個体が採取できるのがうれしいです。魚も好んで食べますね。
メダカの撮影を忘れた・・・
※生餌は河川から病気を持ち込む恐れがあります。使用に際しては、十分に検討してから与えて下さい!
ただいま細々と活動中
近江フィールドワーク別館
よろしければこちらにもお越し下さい。