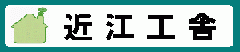今日の1本は銀杏(イチョウ)。草津の道路沿いの街路樹のイチョウに、果実ができていました。オレンジ色の果実には皺ができていて、もうすぐ落ちそうでした。落ちていたら、拾って帰ろうと思い道路を探しましたが、1つも見つからず。まだ熟しきっていないようなので写真だけ撮影しました。
<データ>
名前:
イチョウ(イチョウ科・イチョウ属)
分布:
日本のほぼ全土
体長:
種子は30cmくらい
棲息:
神社、お寺、公園、道路沿い
特徴:
中国原産の落葉高木で、扇形の葉は、秋になると黄色く色付いて落葉する。雌雄異株(枝が上に伸びるのが雄?枝が垂れているのが雌?)で、9月初め頃に精子を出して受精を行い果実を付ける。種子(これが銀杏)は、焼いて食される。果肉は悪臭がするため、拾って持ち歩くと危険!さらに、果肉の油脂は手が荒れ、食べるまでの作業も面倒です。銀杏は食べすぎや幼児が食べると体調を崩す恐れが有るようなので注意して下さい。
捕獲:
果実を拾い、果肉を腐らせて、種子を取り出し、天日干しして乾燥させたものをフライパンで炒る。
飼育:
害虫が付き難く、強い為育て易いようです。雌雄異株なので育てているのが雄株の場合結実しないので注意して下さい。また雌株の場合、近隣住宅の迷惑になるかもしれないので注意して下さい。

果実に皺ができて、もうすぐ落ちそうです。
※当ブログはリンクフリーです。相互リンクも募集中なので、御連絡下さい。
投票歓迎


よろしければこちらにもお越し下さい。
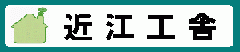
<データ>
名前:
イチョウ(イチョウ科・イチョウ属)
分布:
日本のほぼ全土
体長:
種子は30cmくらい
棲息:
神社、お寺、公園、道路沿い
特徴:
中国原産の落葉高木で、扇形の葉は、秋になると黄色く色付いて落葉する。雌雄異株(枝が上に伸びるのが雄?枝が垂れているのが雌?)で、9月初め頃に精子を出して受精を行い果実を付ける。種子(これが銀杏)は、焼いて食される。果肉は悪臭がするため、拾って持ち歩くと危険!さらに、果肉の油脂は手が荒れ、食べるまでの作業も面倒です。銀杏は食べすぎや幼児が食べると体調を崩す恐れが有るようなので注意して下さい。
捕獲:
果実を拾い、果肉を腐らせて、種子を取り出し、天日干しして乾燥させたものをフライパンで炒る。
飼育:
害虫が付き難く、強い為育て易いようです。雌雄異株なので育てているのが雄株の場合結実しないので注意して下さい。また雌株の場合、近隣住宅の迷惑になるかもしれないので注意して下さい。

果実に皺ができて、もうすぐ落ちそうです。
※当ブログはリンクフリーです。相互リンクも募集中なので、御連絡下さい。
投票歓迎

よろしければこちらにもお越し下さい。