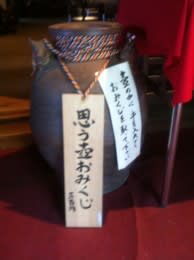過日の「幸せに生きるための心理学」の報告で、
「ネガティブさに向き合うことについてはまた書きます」と
書いたまま、ほったらかしてしまっていました。
ネガティブさに向き合うというのは、
まず、自分のネガティブさに気づく、認める、
ということから始まります。
でも、それで終わりではありません。
そこからどんな感情がわいてくるか。
悲しさや口惜しさ、憂鬱さなどが感じられるならば、
それをもたらしているものは何か?
・何に(どんな出来事に)対して?
・それは自分にとってどんな意味がある(あった)?
時には
・それは悲しむべきことだろうか?
も考えたりしながら、
結局自分は
・何を求めて?
・どうありたいのか?
・どうするか
を探っていく、ということです。
ネガティブな感情について
「どうしてこうなってしまったんだろう」という問いは、
本来、建設的な答えにつながるものなのですが、
多くの場合、その問いにちゃんと答える前に
「そういえばあんなこともあった」とか、
「またそうなったらどうしよう」など、
ネガティブな感情を増幅させるような思考を
反芻していってしまう。
この時、人は、ネガティブな感情に覆われ、それを感じているのだから
向き合っているように見えるのですが、
本当はちゃんと問いに答えていません。
そのような思考に対しては「反芻」ではなく「反論」を行い、
自分をネガティブスパイラルにもたらしている思考に対して
「ホントに?」「どうして?」ときちんと問うと、
その暗い淵から、自分の歩むべき道が
次第にほの白く見えてくる・・・
というのが、ネガティブさに向き合う、ということなのです。
こういうのはなかなか書くのが難しいですね。
事例を出さないと伝わらないだろうなと思いながら
事例を出さずに書いてしまいました・・・
伝わりましたでしょうか。
「ネガティブさに向き合うことについてはまた書きます」と
書いたまま、ほったらかしてしまっていました。
ネガティブさに向き合うというのは、
まず、自分のネガティブさに気づく、認める、
ということから始まります。
でも、それで終わりではありません。
そこからどんな感情がわいてくるか。
悲しさや口惜しさ、憂鬱さなどが感じられるならば、
それをもたらしているものは何か?
・何に(どんな出来事に)対して?
・それは自分にとってどんな意味がある(あった)?
時には
・それは悲しむべきことだろうか?
も考えたりしながら、
結局自分は
・何を求めて?
・どうありたいのか?
・どうするか
を探っていく、ということです。
ネガティブな感情について
「どうしてこうなってしまったんだろう」という問いは、
本来、建設的な答えにつながるものなのですが、
多くの場合、その問いにちゃんと答える前に
「そういえばあんなこともあった」とか、
「またそうなったらどうしよう」など、
ネガティブな感情を増幅させるような思考を
反芻していってしまう。
この時、人は、ネガティブな感情に覆われ、それを感じているのだから
向き合っているように見えるのですが、
本当はちゃんと問いに答えていません。
そのような思考に対しては「反芻」ではなく「反論」を行い、
自分をネガティブスパイラルにもたらしている思考に対して
「ホントに?」「どうして?」ときちんと問うと、
その暗い淵から、自分の歩むべき道が
次第にほの白く見えてくる・・・
というのが、ネガティブさに向き合う、ということなのです。
こういうのはなかなか書くのが難しいですね。
事例を出さないと伝わらないだろうなと思いながら
事例を出さずに書いてしまいました・・・
伝わりましたでしょうか。


















 なスポットがあるではありませんか。
なスポットがあるではありませんか。

 、そして、小雨ゼミになり
、そして、小雨ゼミになり


 )
)


 開いているという、珍しいものです。
開いているという、珍しいものです。