前回はこれ。
アタッチメント黎明編:カンガルーケアからレイドバックしてヴァン・デン・ベルクで力尽きる
では,未来編,字数やばいので早速ゴー
これにて,まあまずまず,現代的な論点をおさえることができるんじゃないでしょうか。言い回しも極めて気配りの効いたというか慎重というかしかし本質的でもあります。憎たらしくなる手際のよさ。
ちなみに数井先生の次回作は『アタッチメントと臨床領域』だそう。楽しみね。
しかし,「社会的ネットワーク」つうのは,なるほどという感じですね。結果としての,見かけ上,母と子に代表されて捉えられがちな,アタッチメントというひとつの現象というか。サッカーで点が取れないのはFWの問題だけじゃない,みたいな感じですかね。FWを責めてもしょうがねえ。
もうひとつ,現代的なトピックとしては「世代間伝達」でしょうかね。これはかなり臨床的な話と直結してくる気もし,AAIとかもありますしね。一方で,安易なAC論等に陥る危険性もありますが,ってこんなことpsy-pubにいわれるまでもないね。
なお学術的な最新動向については,Decoさんが「最近のアタッチメント~終わりゆくブーム~」にてみっちりやってくれてるので,上掲書とあわせ,そっちを見て頂くとして,日本の臨床的な動向を伺うと,こうなりますな乳幼児精神保健。
これはめっさ豪華な著者陣です。渡辺久子・橋本洋子先生の共編の元,トレヴァーセン,ホプキンスなどの外国勢に加え,本間博彰,小林隆児,清水將之,川畑友二,小倉清など各先生,すごいメンツを取り揃えました。
ちなみに渡辺久子先生は,慶応大学病院の小児科医で,かつタヴィストック・クリニックにも留学の経験があるという,まあ言ってみりゃ,現代小児医学と伝統的な力動精神医学が奇跡的に良いマッチングを見せているという,世界のDr. Watanabeでありますな。
こちらにも渡辺久子先生書かれてますね。いわゆるD.N.スターンのいうような線に沿った「乳幼児精神医学」を描き出しております。
特集自体は「母と子:周産期と乳幼児期への心理援助」で,どちらかというと,実務家というか現場の空気を重視したような感じで,名より実をとるといった感じですかね。すばらしいです。
また,
こういう柔らかげな本も書いちゃうという。いってみりゃ,ウィニコットが精神分析家にならずに小児科医のままでいた,みたいな感じで,小児科医を保ちつつ,優しげに語るわけですね。
また隔世の感があるのやらないのやら,わかりませんけど,かつてのエソロジーに変わって,今は脳科学ですよ,という方向も結構進んでます。
まなThe See,視覚つうのがポイントなのね。紹介したい本が山のようにあるのですが,それはまた別の機会にネ。しかし研究者は,今や光トポなんかを使って,それでも四苦八苦してるのでしょうね。こういう成果も取り入れて理論化する現代のボウルビィは誰なんでしょうか?
ま,それで,アタッチメント,といえば,黎明期においては,ミルクor毛布みたいなところもあったわけですが,
ミルクね,母乳ですよ,これめっちゃ肝要であるというのが,UNICEFとWHOの見解なわけでして,母乳じゃないとね,できないことがあるんですね。SIDSの防止とかね(それだけじゃないけど)。もちろん,母乳育児も諸条件が揃わなければならないのですが,揃うのならば,できるだけ,母乳育児が望ましいということなんですよ。
だからやっぱね,あれかこれかじゃなくてね,あれもこれも,ミルクも毛布もなんですよね,理想的には。理想的にいくかどうかは別としても,理想的にはね。
ちなみに,母乳育児となると,とあるConflict of Interest(さあ皆で考えよう)が発生してくるわけですが,そこら辺はこれを読んでおきますように。
ま,母乳なんですが,やっぱ母親にとっては負担が大きいわけですよ,いろんな意味で。したがって,そういう状況において,社会文化的なコンテクストを踏まえつつ,家族のシステミックな連動というかね,必要になってくるわけで,そうなると簡単に愛着なんていうけれど,実はまこと複雑な内容をもってるわけですな。しかも誰もアタッチメントを形成するために育児するわけではないんですよ。そういう意味では結果論なんですよね。
したがって,いわゆるね3歳児神話を安易にマンセーしたりあるいは即刻却下したり,つう短絡的な二元論で捉えきれない,多元宇宙のひとつの表現系として,アタッチメントという概念が浮かび上がってくるに過ぎないみたいな感じなのかなと個人的には思います(変な文章)。
で,ね,こんだけだったら,なにも「未来編」じゃないわけでして,なんで,そうしたかといいますと,赤ちゃんってね,どこで生まれるんでしたっけ? っていう話なんですよ。まあ例外はいろいろあるけれど,ごく一般的に考えるとね,産婦人科で生まれるわけですよね。
周産期医療の崩壊をくい止める会
もうとんでもないことになってしまってるのね。全体的に読んでみてほしいですが,手っ取り早くは,リンクのブログのところなんかを2,3みてみると,現場の実践者の方がたの悲痛な叫び声が上がってるわけでして,ぜひ読んで頂きたいと思います。
著者のインタビューはこちら
もうね,3歳児神話がどうしたこうしたなんて話じゃなくてね,子どもを生まんとする家族を根底で支える環境が危機に瀕してるわけでして,環境的にHoldingすることが困難ないし対価に大きく左右されるというね,おちおち安心して出産すらできやしない,そんな状況がね,もう近づいてるわけです。
世界最高峰の周産期の医療は,世界最低の医療費と劣悪な環境で踏ん張るマンパワーに支えられてるのであって,子育て支援だとか少子化対策だとか,もちろん大切ですけどね,あえて間違ってるとはいわないけれど,見落としが過ぎる,という気はします。
カンガルーケアが良いったって,それをサポートしてくれるのはいったい誰なんだでいう話なんですよ。アタッチメントどころかホスピタリズムの時代までレイドバックしうる危険性がありありなわけですよ。
こういう話,あんまり関係ないなあと思う人は,即刻,臨床家やめてください。むいてないどころか害悪です。全体的な状況を見るんです,それをすべし。
もう一度,
周産期医療の崩壊をくい止める会
…………
余力あれば,次回「復活・羽衣編」に続きます。
アタッチメント黎明編:カンガルーケアからレイドバックしてヴァン・デン・ベルクで力尽きる
では,未来編,字数やばいので早速ゴー
 | アタッチメント―生涯にわたる絆数井 みゆき 遠藤 利彦 ミネルヴァ書房 2005-04売り上げランキング : 49197Amazonで詳しく見る by G-Tools |
これにて,まあまずまず,現代的な論点をおさえることができるんじゃないでしょうか。言い回しも極めて気配りの効いたというか慎重というかしかし本質的でもあります。憎たらしくなる手際のよさ。
ちなみに数井先生の次回作は『アタッチメントと臨床領域』だそう。楽しみね。
しかし,「社会的ネットワーク」つうのは,なるほどという感じですね。結果としての,見かけ上,母と子に代表されて捉えられがちな,アタッチメントというひとつの現象というか。サッカーで点が取れないのはFWの問題だけじゃない,みたいな感じですかね。FWを責めてもしょうがねえ。
もうひとつ,現代的なトピックとしては「世代間伝達」でしょうかね。これはかなり臨床的な話と直結してくる気もし,AAIとかもありますしね。一方で,安易なAC論等に陥る危険性もありますが,ってこんなことpsy-pubにいわれるまでもないね。
なお学術的な最新動向については,Decoさんが「最近のアタッチメント~終わりゆくブーム~」にてみっちりやってくれてるので,上掲書とあわせ,そっちを見て頂くとして,日本の臨床的な動向を伺うと,こうなりますな乳幼児精神保健。
 | 乳幼児精神保健の新しい風―子どもと親の心を支える臨床の最前線渡辺 久子 橋本 洋子 ミネルヴァ書房 2001-12売り上げランキング : 137037Amazonで詳しく見る by G-Tools |
これはめっさ豪華な著者陣です。渡辺久子・橋本洋子先生の共編の元,トレヴァーセン,ホプキンスなどの外国勢に加え,本間博彰,小林隆児,清水將之,川畑友二,小倉清など各先生,すごいメンツを取り揃えました。
ちなみに渡辺久子先生は,慶応大学病院の小児科医で,かつタヴィストック・クリニックにも留学の経験があるという,まあ言ってみりゃ,現代小児医学と伝統的な力動精神医学が奇跡的に良いマッチングを見せているという,世界のDr. Watanabeでありますな。
| 臨床心理学(第6巻第6号) 母と子:周産期と乳幼児期への心理援助金剛出版 2006-11売り上げランキング : 49117Amazonで詳しく見る by G-Tools |
こちらにも渡辺久子先生書かれてますね。いわゆるD.N.スターンのいうような線に沿った「乳幼児精神医学」を描き出しております。
特集自体は「母と子:周産期と乳幼児期への心理援助」で,どちらかというと,実務家というか現場の空気を重視したような感じで,名より実をとるといった感じですかね。すばらしいです。
また,
 | 抱きしめてあげて―育てなおしの心育て渡辺 久子 太陽出版 2005-12売り上げランキング : 123237Amazonで詳しく見る by G-Tools |
こういう柔らかげな本も書いちゃうという。いってみりゃ,ウィニコットが精神分析家にならずに小児科医のままでいた,みたいな感じで,小児科医を保ちつつ,優しげに語るわけですね。
また隔世の感があるのやらないのやら,わかりませんけど,かつてのエソロジーに変わって,今は脳科学ですよ,という方向も結構進んでます。
 | まなざしの誕生―赤ちゃん学革命下條 信輔 新曜社 2006-06売り上げランキング : 211296Amazonで詳しく見る by G-Tools |
まなThe See,視覚つうのがポイントなのね。紹介したい本が山のようにあるのですが,それはまた別の機会にネ。しかし研究者は,今や光トポなんかを使って,それでも四苦八苦してるのでしょうね。こういう成果も取り入れて理論化する現代のボウルビィは誰なんでしょうか?
ま,それで,アタッチメント,といえば,黎明期においては,ミルクor毛布みたいなところもあったわけですが,
 | UNICEF/WHO母乳育児支援ガイドUNICEF WHO 橋本 武夫 医学書院 2003-09売り上げランキング : 71774Amazonで詳しく見る by G-Tools |
ミルクね,母乳ですよ,これめっちゃ肝要であるというのが,UNICEFとWHOの見解なわけでして,母乳じゃないとね,できないことがあるんですね。SIDSの防止とかね(それだけじゃないけど)。もちろん,母乳育児も諸条件が揃わなければならないのですが,揃うのならば,できるだけ,母乳育児が望ましいということなんですよ。
だからやっぱね,あれかこれかじゃなくてね,あれもこれも,ミルクも毛布もなんですよね,理想的には。理想的にいくかどうかは別としても,理想的にはね。
 | 母乳育児の文化と真実ナオミ ボームスラグ ダイア・L. ミッチェルズ Naomi Baumslag メディカ出版 1999-08売り上げランキング : 68659Amazonで詳しく見る by G-Tools |
ちなみに,母乳育児となると,とあるConflict of Interest(さあ皆で考えよう)が発生してくるわけですが,そこら辺はこれを読んでおきますように。
ま,母乳なんですが,やっぱ母親にとっては負担が大きいわけですよ,いろんな意味で。したがって,そういう状況において,社会文化的なコンテクストを踏まえつつ,家族のシステミックな連動というかね,必要になってくるわけで,そうなると簡単に愛着なんていうけれど,実はまこと複雑な内容をもってるわけですな。しかも誰もアタッチメントを形成するために育児するわけではないんですよ。そういう意味では結果論なんですよね。
したがって,いわゆるね3歳児神話を安易にマンセーしたりあるいは即刻却下したり,つう短絡的な二元論で捉えきれない,多元宇宙のひとつの表現系として,アタッチメントという概念が浮かび上がってくるに過ぎないみたいな感じなのかなと個人的には思います(変な文章)。
で,ね,こんだけだったら,なにも「未来編」じゃないわけでして,なんで,そうしたかといいますと,赤ちゃんってね,どこで生まれるんでしたっけ? っていう話なんですよ。まあ例外はいろいろあるけれど,ごく一般的に考えるとね,産婦人科で生まれるわけですよね。
周産期医療の崩壊をくい止める会
もうとんでもないことになってしまってるのね。全体的に読んでみてほしいですが,手っ取り早くは,リンクのブログのところなんかを2,3みてみると,現場の実践者の方がたの悲痛な叫び声が上がってるわけでして,ぜひ読んで頂きたいと思います。
 | 医療崩壊―「立ち去り型サボタージュ」とは何か小松 秀樹 朝日新聞社 2006-05売り上げランキング : 540Amazonで詳しく見る by G-Tools |
著者のインタビューはこちら
もうね,3歳児神話がどうしたこうしたなんて話じゃなくてね,子どもを生まんとする家族を根底で支える環境が危機に瀕してるわけでして,環境的にHoldingすることが困難ないし対価に大きく左右されるというね,おちおち安心して出産すらできやしない,そんな状況がね,もう近づいてるわけです。
世界最高峰の周産期の医療は,世界最低の医療費と劣悪な環境で踏ん張るマンパワーに支えられてるのであって,子育て支援だとか少子化対策だとか,もちろん大切ですけどね,あえて間違ってるとはいわないけれど,見落としが過ぎる,という気はします。
カンガルーケアが良いったって,それをサポートしてくれるのはいったい誰なんだでいう話なんですよ。アタッチメントどころかホスピタリズムの時代までレイドバックしうる危険性がありありなわけですよ。
こういう話,あんまり関係ないなあと思う人は,即刻,臨床家やめてください。むいてないどころか害悪です。全体的な状況を見るんです,それをすべし。
もう一度,
周産期医療の崩壊をくい止める会
…………
余力あれば,次回「復活・羽衣編」に続きます。












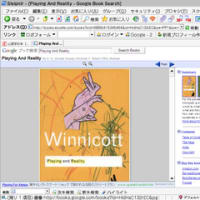


>多元宇宙のひとつの表現系として,アタッチメントという概念が浮かび上がってくるに過ぎない
この領域の一つの特徴はこれだけ広範な理論体系であるにも関わらず、しかも臨床を出自とするものであるにも関わらず、独自の心理療法を持たないというところだと思うのです。このことはつながりとはそれとして取り上げた途端に変質してしまう背景なのであって、表に現れて存在を主張するようなものではないことを表わしているように思うのです。その背景の前でいろいろな議論や技法の展開が繰り広げられているように思えるわけです。
それだけつながりは目に触れる機会が少ないということでもあり、「こと」が起きるまで軽視されることになるということでもあるのでしょう。周産期医療の崩壊というトピックはその「こと」が起きつつあるという1つの象徴であるように思います。
愛着理論や精神分析になじんでいると、物事の始まりは幼少期や生まれた時や生まれる前からすらすでに始まっていると強く思います。私たちの基盤は記憶に残らない、目に見えない「いつか」や「どこか」にあるように思うのですよ。それがいつの間にか重要な問題ではないように扱われるという、経済性や効率性や成果や証拠を求めることの1つの否定的帰結がこのような形で現れることを危惧するわけです(経済性や効率性や成果や証拠の全てを否定するものではありませんので。念為)。
コメントありがとうございます。ちょっと,ひと息にレスしてしまうのが,もったいないような感じがしてます。ちょっとよく考えたていきたいことですね。
>このことはつながりとはそれとして取り上げた途端に変質してしまう背景なのであって、表に現れて存在を主張するようなものではないことを表わしているように思うのです
ちょっと自信ないですが,それ自体を標的とすべきか結果としてそれに象徴されるものを扱うべきか,わからないのですが,でも言われてるほど確固とした枠組みをもてている概念ではないような気がします。すいません自分が何を言ってるかわかりません。
>周産期医療の崩壊というトピックはその「こと」が起きつつあるという1つの象徴であるように思います
私の駄文を一気に意味のあるものにしていただいてありがとうございますです(笑)。もっとしっかりとつなげられればよかったのですが,なにぶん,思い余って力足りず,でして。
>愛着理論や精神分析になじんでいると、物事の始まりは幼少期や生まれた時や生まれる前からすらすでに始まっていると強く思います
いろんな意味で「いま,ここ」重視のご時世ですので,愛着のような気の長い見方はフィットしないのかもしれないですね。フィットしない,で済む問題じゃないんですけどね。記憶しかりで,ショート・タームとロング・タームはセットであって然るべきと思います。
あとは,戯言ですけど,理想的な愛着が築きえた時代って,いったいそんな時代あったんでしょうかと,そんなことも思います。思うだけですけど。
>理想的な愛着が築きえた時代って,いったいそんな時代あったんでしょうか
というのは反語表現としてピッタリだなぁと思います。
また僕もよく分からずに言いますが,あの理論は,「愛着なんとか療法」を体系化するよりも,もっと基本的な,治療関係そのものとかラポートとか,そういう所で生きてくる理論だと思うのです。とは言いつつ,メンタライゼーション・ベースド・サイコセラピーなんてのもあるわけですが。
んで戯れ言としては,このご時世「なんとか療法」が脚光を浴び易いようなのですが,その基となる「治療関係」ってやつが忘れられちゃうと,それってどうかなぁ大丈夫なのかなぁと思います。
>理想的な愛着が築きえた時代って,いったいそんな時代あったんでしょうか
私も「こと」の話を書きながら思っていました。以前はそれほど子育てということが重視されていたと確かに言えるのだろうかと。愛着理論が生まれた段階で、すでにマターナル・デプリベーションと呼ばれるある種の状態が存在していたわけですから。ただ
>愛着の理想像なんてモノは,それこそ社会文化的コンテクストの中で「構成される」ものでしかないわけでして
と言ってしまうと、種を超えて偏在するという愛着の立脚点も失われるわけですよね。進化論的に適応的な、という。
そうした概念化がそもそも意味をなしていなかったとか、そうした概念化をなさなければならないほどの必要性が生じていたということ自体を一つの時代的要請と捉えることもできるのかもしれませんが。
あるいは「こと」は時代に合わせて形を変えて繰り返し現れるものなのだとも言えるのでしょうか。安全と脅威とはいつもせめぎ合っていて、それが社会の変化に伴って1つの具体的な形をとっていると。そしてそのことに危機感を覚える人々がいて回復がめざされると。
…もう少しまとめてみたいと思います。
>メンタライゼーション・ベースド・サイコセラピーなんてのもあるわけですが
あれは愛着関係による自己の組織化を物理的安全や生存の代わりに置いていますよね。その差異をまだ計りかねているところなのですが、いかがですか、Decoさま?
これももう少し考えてみたいところです。
朝から長文のコメントですみません。
アタッチメントと臨床の邂逅 ~レビュー書き散らし~
http://decoooooo.blog21.fc2.com/blog-entry-229.html
で,
>Decoさま
>もっと基本的な,治療関係そのものとかラポートとか,そういう所で生きてくる理論だと思うのです
なるほどなあと思いつつ,治療と治療関係,の関係が,教科書的な意味ではなく,気になるところですが,自己生産的に,力動っぽい治療にマッチするのだろうなと素人的には思います。
>nocteさま
>愛着理論が生まれた段階で、すでにマターナル・デプリベーションと呼ばれるある種の状態が存在していたわけですから
これ,絶対そうだろうなと思います。スピッツ(1945)ですもんね。
>あるいは「こと」は時代に合わせて形を変えて繰り返し現れるものなのだとも言えるのでしょうか。安全と脅威とはいつもせめぎ合っていて、それが社会の変化に伴って1つの具体的な形をとっていると。
なんかちょいベイトソンぽくもありますですね(ちょっと適当かも)。nature, nurtureも繰り返してますしね。揺れつ戻りつ,それでも着実に進歩してる,と思いたいですけどね。
>進化論的に適応的な
これは戯れ言なんですが,進化論的に適応的な「社会文化的コンテクスト」っつうのも,なんか誰かが発想してそうな気もするんですが,どうなんでしょう?(本当に戯れ言です)。