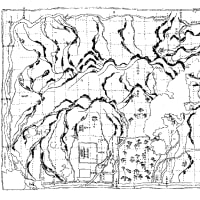お水取りを喩えて「火と水の行法」と呼びますがとても的を射た表現だと思います。それに加えるなら暗闇の堂の中、様々な音が飛び交い光と影が織り成す神秘的な体験とでもいいましょうか。
但し、本行の本義はあくまで十一面観音を奉賛し、あらゆる罪障を懺悔することなので二月堂内で行なわれる称名悔過などが中心のはずです。ただ堂内は人の出入りも制限され、特に女性は各局から格子越しにしか行を見る事が出来ないために派手で衆目を集めやすい行事が注目されるのでしょう。あ、でも女人禁制は伝統ですからどうする必要も無いと思います。
練行衆は現在は11人で構成される。和上・大導師・咒師・堂司の四職と、平衆と呼ばれる7人、総衆ノ一・南衆ノ一・北衆の二・南衆ノ二・中灯・処世界・権処世界。それ以外に行を補佐する堂童子・小綱・駆士の三役を筆頭として、更にその下に多くの童子や仲間が行を支え、そのまた縁の下で多くの二月堂講者が支えています。
練行衆は三月一日より始まる本行に先立って「別火」と称す精進潔斎を行ないます。試別火(ころべっか)から総別火(そうべっか)と潔斎の度合いを高めていくのですが、娑婆の穢れを祓い清める最も判りやすい方法がその名前の通り火を別けることです。更に火だけではなく水も娑婆のものと別ける事で身を清めていくのですが、その水はと言うと佐保川上流の蛭子川の水を汲み上げたものです。
精進潔斎の象徴でもある浄火は全て「一徳」の僧名を持つ堂童子の手によって熾されれます。試別火、総別火そして二月堂本行から一年間堂内で使用される常燈の元になる「一徳火」に至るまでの全てを三役の堂童子が熾すのです。
堂童子はかつて一徳などの僧名を与えられながら妻帯を許された半俗半僧の者達で各堂に存在したが、今は川上郷の稲垣家のみが存続している。稲垣家が、稲垣家が受け継いできた二月堂の堂童子が本行において重要な役割を果たしている事は、史実なのか伝説の類なのかわからないが、稲垣家と実忠和尚との深いかかわりに他ならない。本行を始めるに当たって実忠が南方補陀落浄土に十一面観音の請来を祈念し見事に果たしたその後、稲垣氏が小観音を難波津よりこの地のもたらしたとの伝承がそれです。
小観音は本行中の三月七日、小観音出御で須弥壇の裏(東方)より礼堂へ一端搬出され(もちろん御輿付きの扉の無い厨子に安置されており見る事はできない)、日付が変わった八日の深夜一時前に内陣をぐるりと一巡して須弥壇の正面西に安置する。これが「小観音後入」で下七日の本尊が大観音から小観音に移ったことになる。
七日の出御から初夜上堂までの間、小観音を警護するのが堂童子と手向山八幡宮の宮司の二人ですが、ここで唐突に八幡宮宮司が出てくる理由が、昔小観音が盗難にあったときにそれを取り戻したのが八幡宮宮司だからと云う、堂童子が警護の任に就いている理由は言うまでもありません。
小観音の移動はかつて修二月会がはじまると堂外の印蔵より二月堂へ小観音が迎え入れられていた儀式の名残だと言うのが主流の見解です。ただ、小観音が大観音以上に絶対視されるようになったのは何故なのかよく解らないところで、そもそも何故二尊を行の本尊とするのか?についても定かではありません。
十二日、日付が変わった午前二時に行なわれる「お水取り」は四職の咒師を中心に六人の水取衆それに堂童子と童子、庄駆士が別名蓮松明とも呼ばれる咒師松明を先頭に列を成して階段を降りる。興正社に参拝したあと若狭井のある閼伽井屋に実際入るのは咒師と堂童子と庄駆士の三人のみで、他の五人は外で警護をする。若狭井の実忠と遠敷名神の話は書くまでもありませんか、遅参した詫びに遠敷名神が若狭から水を送ったところ、黒白二羽の鵜が飛び立ったあと水が噴き出したという。
ちなみにこの水取衆の五人が持つ杖は練行衆の持物で「牛玉杖」と呼び、春日祭やおん祭りにも見られる「梅のズバエ」またはズワイと同じものですが、梅ではなく柳の木製で杖の端に牛玉札を挿すことからその名が付きます。(下の牛玉札とはどうも別物)
牛玉札(ごおうふだ)は三月八日、九日の牛玉日(ごおうび)に練行衆が刷る護符の一種です。下の写真の札が正式なもので少し高いですが二月堂で購入出来ます。ただ注意したいのは似たような廉価版が一緒に売られている事で、こちらは納所などで寺男等が刷ったものでしょう。病の時にはこのお札の墨の文字を切り取って水に溶かして飲むと効果があるといいます。と言うのも、正式な牛玉札は「牛黄」つまり生薬の牛の胆石が入った牛玉墨と御香水による墨汁で刷られているからです。廉価版は恐らくただの墨で刷られたものだと思います、違うかな?
何故、中世において起請文を燃した灰を一味神水として飲むのか理解しがたかったのですが、本来起請文の牛玉宝印は牛黄が含まれており、それを飲む事が始まりだったと考えると腑に落ちます。

二月堂牛玉札とその下は最も有名な熊野の烏文字の牛玉宝印
但し、本行の本義はあくまで十一面観音を奉賛し、あらゆる罪障を懺悔することなので二月堂内で行なわれる称名悔過などが中心のはずです。ただ堂内は人の出入りも制限され、特に女性は各局から格子越しにしか行を見る事が出来ないために派手で衆目を集めやすい行事が注目されるのでしょう。あ、でも女人禁制は伝統ですからどうする必要も無いと思います。
練行衆は現在は11人で構成される。和上・大導師・咒師・堂司の四職と、平衆と呼ばれる7人、総衆ノ一・南衆ノ一・北衆の二・南衆ノ二・中灯・処世界・権処世界。それ以外に行を補佐する堂童子・小綱・駆士の三役を筆頭として、更にその下に多くの童子や仲間が行を支え、そのまた縁の下で多くの二月堂講者が支えています。
練行衆は三月一日より始まる本行に先立って「別火」と称す精進潔斎を行ないます。試別火(ころべっか)から総別火(そうべっか)と潔斎の度合いを高めていくのですが、娑婆の穢れを祓い清める最も判りやすい方法がその名前の通り火を別けることです。更に火だけではなく水も娑婆のものと別ける事で身を清めていくのですが、その水はと言うと佐保川上流の蛭子川の水を汲み上げたものです。
精進潔斎の象徴でもある浄火は全て「一徳」の僧名を持つ堂童子の手によって熾されれます。試別火、総別火そして二月堂本行から一年間堂内で使用される常燈の元になる「一徳火」に至るまでの全てを三役の堂童子が熾すのです。
堂童子はかつて一徳などの僧名を与えられながら妻帯を許された半俗半僧の者達で各堂に存在したが、今は川上郷の稲垣家のみが存続している。稲垣家が、稲垣家が受け継いできた二月堂の堂童子が本行において重要な役割を果たしている事は、史実なのか伝説の類なのかわからないが、稲垣家と実忠和尚との深いかかわりに他ならない。本行を始めるに当たって実忠が南方補陀落浄土に十一面観音の請来を祈念し見事に果たしたその後、稲垣氏が小観音を難波津よりこの地のもたらしたとの伝承がそれです。
小観音は本行中の三月七日、小観音出御で須弥壇の裏(東方)より礼堂へ一端搬出され(もちろん御輿付きの扉の無い厨子に安置されており見る事はできない)、日付が変わった八日の深夜一時前に内陣をぐるりと一巡して須弥壇の正面西に安置する。これが「小観音後入」で下七日の本尊が大観音から小観音に移ったことになる。
七日の出御から初夜上堂までの間、小観音を警護するのが堂童子と手向山八幡宮の宮司の二人ですが、ここで唐突に八幡宮宮司が出てくる理由が、昔小観音が盗難にあったときにそれを取り戻したのが八幡宮宮司だからと云う、堂童子が警護の任に就いている理由は言うまでもありません。
小観音の移動はかつて修二月会がはじまると堂外の印蔵より二月堂へ小観音が迎え入れられていた儀式の名残だと言うのが主流の見解です。ただ、小観音が大観音以上に絶対視されるようになったのは何故なのかよく解らないところで、そもそも何故二尊を行の本尊とするのか?についても定かではありません。
十二日、日付が変わった午前二時に行なわれる「お水取り」は四職の咒師を中心に六人の水取衆それに堂童子と童子、庄駆士が別名蓮松明とも呼ばれる咒師松明を先頭に列を成して階段を降りる。興正社に参拝したあと若狭井のある閼伽井屋に実際入るのは咒師と堂童子と庄駆士の三人のみで、他の五人は外で警護をする。若狭井の実忠と遠敷名神の話は書くまでもありませんか、遅参した詫びに遠敷名神が若狭から水を送ったところ、黒白二羽の鵜が飛び立ったあと水が噴き出したという。
ちなみにこの水取衆の五人が持つ杖は練行衆の持物で「牛玉杖」と呼び、春日祭やおん祭りにも見られる「梅のズバエ」またはズワイと同じものですが、梅ではなく柳の木製で杖の端に牛玉札を挿すことからその名が付きます。(下の牛玉札とはどうも別物)
牛玉札(ごおうふだ)は三月八日、九日の牛玉日(ごおうび)に練行衆が刷る護符の一種です。下の写真の札が正式なもので少し高いですが二月堂で購入出来ます。ただ注意したいのは似たような廉価版が一緒に売られている事で、こちらは納所などで寺男等が刷ったものでしょう。病の時にはこのお札の墨の文字を切り取って水に溶かして飲むと効果があるといいます。と言うのも、正式な牛玉札は「牛黄」つまり生薬の牛の胆石が入った牛玉墨と御香水による墨汁で刷られているからです。廉価版は恐らくただの墨で刷られたものだと思います、違うかな?
何故、中世において起請文を燃した灰を一味神水として飲むのか理解しがたかったのですが、本来起請文の牛玉宝印は牛黄が含まれており、それを飲む事が始まりだったと考えると腑に落ちます。

二月堂牛玉札とその下は最も有名な熊野の烏文字の牛玉宝印