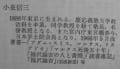読書論, 小泉信三, 岩波新書 F87(青版)47, 1950年
・明治生まれの著者による骨太な読書論。読書の方法について特に目新しい記述はありませんが、福沢諭吉、夏目漱石、森鴎外など、今となっては歴史上の人物についての身近な話題が多く、歴史の生き証人的な記述が所々に出てきます。章は『何を読むべきか』、『如何に読むべきか』、『読書と思索』、『書斎及び蔵書』と進みますが、最後は自らの半生を振り返る、回顧録のような雰囲気に。読書の技術的なことよりも、著者自身の留学体験を含む読書遍歴や、当時の世相を感じられる点で、興味深い内容です。
・このテーマでなら、私でも何がしかの文章が書けそうな気がしてきます。 『読書論 ~ぴかりんの場合』 近日公開!?
・「即ち大別すれば、共産主義者無政府主義者が三人(マルクス、エンゲルス、バクーニン)、社会主義劇作家が一人(ショー)、経済学者が二人(スミス、ウェッブ)、政治家が二人(グレイ、チャーチル)、教育家が一人(福沢)、文芸作家が三人(漱石、?外、露伴)ということになる。もちろん私の愛読作家がこれで尽きるというわけではないけれども、およそ私がどんなものを好んで読むかはこの小さい縮図にも示されているといえるであろう。」p.2
・「書籍を離れて読書を論じている閑に、先ず書籍に向かって突進せよということが差し当たり親切な忠告である。「ファウスト」の一句「始めに業(実行)ありき」がここでも大切であると思う。美術や音楽の鑑賞も同様であろう。」p.3
・「一般方針として私は心がけて古典的名著を読むことを勧めたい。」p.5
・「すぐ役に立つ人間はすぐ役に立たなくなるとは至言である。同様の意味において、すぐに役に立つ本はすぐ役に立たなくなる本であるといえる。」p.12
・「たしかに大著を読むことによって、人は別人となる。極言すれば、その顔も変ると言えるかも知れない。」p.18
・「一芸一能の士、或いは何かの事業を成し遂げた人の容貌には、何か凡庸でない気品と風格がおのずからにして備わるものであることは、多数の例証の吾々に示すところである。読書もまた然り。本を読んで物を考えた人と、全く読書しないものとは、明かに顔がちがう。」p.18
・「私の特に言いたいと思うのは、大抵の本はくり返して読めば解るもの、また意外によく解るものだと謂うにある。」p.24
・「少年が柱に印して身長を測り、自分で自分の成長を知るように、時を隔てて同じ本を読んで見ることは、自分で精神的身長の増大を知るゆえんである。」p.29
・「今日日本語の本ばかりを読んでも、読むべきものはずいぶん豊富である。しかしいやしくも読書の楽しみを味わうには、せめて一つだけはぜひ外国語をものにしておきたいものである。」p.30
・「語学力をつける一の方法としてすすめたいのは翻訳である。一冊の本または一篇の作品(論文でも小説でも)を日本語に翻訳して、書き上げるということは、一の事業として異常な楽しみにも励みにもなるものである。」p.42
・「?外は批評に対して常に敏感で、一々これに答えずにはいられない性分の作家であったが、殊にその少壮時代は鋭鋒当るべからざる勢いがあり、しばしば段違いの腕力で相手をねじ伏せるような議論をした。」p.48
・「次に、読んだ本は記憶して自分のものにしたいものである。(中略)どうすればよいか。 読者として他人から受動的に受け入れたものを、今度は逆に自分のものとして外に出してみるが第一であるとおもう。」p.50
・「次に私は、書籍に囚われるなということを言いたい。(中略)読書は大切であるが、それと共に自分の目で見、自分の頭で考える観察思考の力を養うことが更に大切であるというのである。」p.66
・「本書の始めから、私は何を読むべきかということを様々に論じて来たが、ここに至って、何を読むべきかと共に、或いはそれよりも一層、如何に読むべきかの問題が大切であることを思わざるを得ない。そうしてそれは、読書と共に如何に観察し思考するかということに帰するであろう。」p.77
・「明治以来、日本学者の業績として他に誇るべきものは、多くは西洋学者の業績を継ぎ、彼らの方法によっての研究に成功したものであるのが常であって、漱石のように、納得できない西洋学者の学説に対して根本的の異議を挟み、自分で問題を出して自分の方法でその解法を企てたというごとき敢為の例は、ただ極めて稀れに見るところである。」p.91
・「本書では、今まで福沢、?外、漱石という三人の作物を、最も頻繁に引用して来たが、近代日本の文章を論ずるとすれば、やはり先ず話題に上すべきはこの三者であろう。」p.93
・「漱石は漱石でいう。「写実的のものではスヰフトのガリバーズ・トラベルスが一番好きである。多くの人はこれを名文とは思はないが、これは名文の域を通り越してゐるから、普通人には分らぬのである。実に達意で、自由自在で、気取つてゐない。ケレンがない。ちつとも飾つた所がない……実に名文以上の名文であると自分は思ふ」と。」p.94
・「ドイツの学術書というものは、英米仏のそれに比して読み憎い。」p.106
・「推敲とは唐の一詩人が僧敲(ハク)月下門としようか僧推(ハス)月下門としようかと迷って苦心したというところに由来するという、」p.110
・「言うまでもなく不満の第一は、蔵書の貧弱にたいするものであった。しかしそれよりも強く感じたのは、どうしてこんなに詰まらない本を沢山買って持っているかということであった。」p.122
・「人は意外に定評ある古典的名著をおいて、二次的三次的の俗書をよむことに労と時とを費やすものである。読む方はしばらくおき、買う方でも実につまらないものを買い込み易いのである。」p.123
・「大部な高価な書籍のみを選んで買うということが、購書上の一の賢こい方針だということができる。実際これを実行して成功している蔵書家も少なくない。 購書家の自戒すべきは、急場の間に合わせるためとかく手頃な便利な本を買うということである。」p.124
・「以上、選択して読むことが大切であると共に選択して買うことが大切であり、これがためにぜひとも書評の発達ということがあって欲しいという主旨を説いた。」p.129
・「私は十二、三の頃太平記を愛読し、また維新の志士の事蹟に興味を以って雑書を読んだ。」p.132
・「福沢の死後塾生の気風も次第に変化したから一様には云えないが、世間一般を見渡して、さて自分の学校を顧みると、慶応に学んだものには、相手の上下に差別をつけ、下の者に威張るという風が割合少ないのではないかと思う、もしこの所見通りであるなら、それは一の美風と称してよいと思う。」p.135
・「「福翁自伝」によれば、福沢諭吉も学問に対する興味を覚えたのが晩く、十四、五になって始めて本気で本を読み出したと語っている。」p.135
・「後年佐藤春夫が或る機会に、自然主義運動は文学を、飛ぶことも歌うこともしない鶏のようなものにしてしまった、といったのは至言である。そうしてまたその鶏に、飛ぶ翼と歌う声とを与えたものは永井荷風と谷崎潤一郎とであったといったのも人の首肯するところであろう。」p.147
・「私は全く偶然の機会から「吾輩は猫である」が「ホトトギス」に出たその第一回から読んだ。そうしてまた続けて「倫敦塔」「薤露行」「幻影の盾」を読んで驚いた。これらの後に挙げた作品を、今の私は必ずしも漱石の最高のものとは思わない。けれども、これらのものが発表せられた明治38、9年当時の文壇に於いて、漱石の出現、その学殖と詞藻と空想力とは驚嘆すべきことであった。」p.149
・「読書や学問の苦心などというものは、過ぎてしまえば存外記憶に残っていないものである。」p.155
・「「風と共に去りぬ」といえば、これはアメリカ人の書いたもので私が読んだ最初の大作であった。この作が出たのは1936年の春であったが、たまたまその秋、私は慶応義塾から派遣されて、アメリカ各地を旅行した。その時どこで本の話が出ても、どこでも聞くのはこの作の評判であった。早速一部買い求めて帰り、帰ってから読んで感心して、その梗概とそれに対する感想を故岩波茂雄に話すと、岩波はぜひ岩波書店でその翻訳を出したいから周旋しないかという。あんな大部のものを翻訳する根気のあるものも、通読するものもあるまいからと、私はいい、岩波は不承不承思い止まった。ところが後に他からその訳本が出てみると、あの通りの成功で、今日まで十幾年読まれ続けて、最近はまた盛んに売れている。これも私が岩波にした誤った忠告の一である。」p.162
・「音楽が好きだということを前に書いた。したがって本を読んでいる間に音楽のことが出てくると今でも目敏い。」p.167
?かんい【敢為】 物事を反対や障害に屈しないで、やり通すこと。押し切って行なうこと。敢行。決行。
?しゅくせい【夙成】 早くからでき上がること。早くおとなびること。子どもの時から学業などが他の人より進んで、でき上がっていること。早熟。早成。
?しそう【詞藻】 1 文章の修辞。美しいことば。ことばのあや。 2 詩歌または文章。
《チェック本》谷崎潤一郎『雪』
・明治生まれの著者による骨太な読書論。読書の方法について特に目新しい記述はありませんが、福沢諭吉、夏目漱石、森鴎外など、今となっては歴史上の人物についての身近な話題が多く、歴史の生き証人的な記述が所々に出てきます。章は『何を読むべきか』、『如何に読むべきか』、『読書と思索』、『書斎及び蔵書』と進みますが、最後は自らの半生を振り返る、回顧録のような雰囲気に。読書の技術的なことよりも、著者自身の留学体験を含む読書遍歴や、当時の世相を感じられる点で、興味深い内容です。
・このテーマでなら、私でも何がしかの文章が書けそうな気がしてきます。 『読書論 ~ぴかりんの場合』 近日公開!?
・「即ち大別すれば、共産主義者無政府主義者が三人(マルクス、エンゲルス、バクーニン)、社会主義劇作家が一人(ショー)、経済学者が二人(スミス、ウェッブ)、政治家が二人(グレイ、チャーチル)、教育家が一人(福沢)、文芸作家が三人(漱石、?外、露伴)ということになる。もちろん私の愛読作家がこれで尽きるというわけではないけれども、およそ私がどんなものを好んで読むかはこの小さい縮図にも示されているといえるであろう。」p.2
・「書籍を離れて読書を論じている閑に、先ず書籍に向かって突進せよということが差し当たり親切な忠告である。「ファウスト」の一句「始めに業(実行)ありき」がここでも大切であると思う。美術や音楽の鑑賞も同様であろう。」p.3
・「一般方針として私は心がけて古典的名著を読むことを勧めたい。」p.5
・「すぐ役に立つ人間はすぐ役に立たなくなるとは至言である。同様の意味において、すぐに役に立つ本はすぐ役に立たなくなる本であるといえる。」p.12
・「たしかに大著を読むことによって、人は別人となる。極言すれば、その顔も変ると言えるかも知れない。」p.18
・「一芸一能の士、或いは何かの事業を成し遂げた人の容貌には、何か凡庸でない気品と風格がおのずからにして備わるものであることは、多数の例証の吾々に示すところである。読書もまた然り。本を読んで物を考えた人と、全く読書しないものとは、明かに顔がちがう。」p.18
・「私の特に言いたいと思うのは、大抵の本はくり返して読めば解るもの、また意外によく解るものだと謂うにある。」p.24
・「少年が柱に印して身長を測り、自分で自分の成長を知るように、時を隔てて同じ本を読んで見ることは、自分で精神的身長の増大を知るゆえんである。」p.29
・「今日日本語の本ばかりを読んでも、読むべきものはずいぶん豊富である。しかしいやしくも読書の楽しみを味わうには、せめて一つだけはぜひ外国語をものにしておきたいものである。」p.30
・「語学力をつける一の方法としてすすめたいのは翻訳である。一冊の本または一篇の作品(論文でも小説でも)を日本語に翻訳して、書き上げるということは、一の事業として異常な楽しみにも励みにもなるものである。」p.42
・「?外は批評に対して常に敏感で、一々これに答えずにはいられない性分の作家であったが、殊にその少壮時代は鋭鋒当るべからざる勢いがあり、しばしば段違いの腕力で相手をねじ伏せるような議論をした。」p.48
・「次に、読んだ本は記憶して自分のものにしたいものである。(中略)どうすればよいか。 読者として他人から受動的に受け入れたものを、今度は逆に自分のものとして外に出してみるが第一であるとおもう。」p.50
・「次に私は、書籍に囚われるなということを言いたい。(中略)読書は大切であるが、それと共に自分の目で見、自分の頭で考える観察思考の力を養うことが更に大切であるというのである。」p.66
・「本書の始めから、私は何を読むべきかということを様々に論じて来たが、ここに至って、何を読むべきかと共に、或いはそれよりも一層、如何に読むべきかの問題が大切であることを思わざるを得ない。そうしてそれは、読書と共に如何に観察し思考するかということに帰するであろう。」p.77
・「明治以来、日本学者の業績として他に誇るべきものは、多くは西洋学者の業績を継ぎ、彼らの方法によっての研究に成功したものであるのが常であって、漱石のように、納得できない西洋学者の学説に対して根本的の異議を挟み、自分で問題を出して自分の方法でその解法を企てたというごとき敢為の例は、ただ極めて稀れに見るところである。」p.91
・「本書では、今まで福沢、?外、漱石という三人の作物を、最も頻繁に引用して来たが、近代日本の文章を論ずるとすれば、やはり先ず話題に上すべきはこの三者であろう。」p.93
・「漱石は漱石でいう。「写実的のものではスヰフトのガリバーズ・トラベルスが一番好きである。多くの人はこれを名文とは思はないが、これは名文の域を通り越してゐるから、普通人には分らぬのである。実に達意で、自由自在で、気取つてゐない。ケレンがない。ちつとも飾つた所がない……実に名文以上の名文であると自分は思ふ」と。」p.94
・「ドイツの学術書というものは、英米仏のそれに比して読み憎い。」p.106
・「推敲とは唐の一詩人が僧敲(ハク)月下門としようか僧推(ハス)月下門としようかと迷って苦心したというところに由来するという、」p.110
・「言うまでもなく不満の第一は、蔵書の貧弱にたいするものであった。しかしそれよりも強く感じたのは、どうしてこんなに詰まらない本を沢山買って持っているかということであった。」p.122
・「人は意外に定評ある古典的名著をおいて、二次的三次的の俗書をよむことに労と時とを費やすものである。読む方はしばらくおき、買う方でも実につまらないものを買い込み易いのである。」p.123
・「大部な高価な書籍のみを選んで買うということが、購書上の一の賢こい方針だということができる。実際これを実行して成功している蔵書家も少なくない。 購書家の自戒すべきは、急場の間に合わせるためとかく手頃な便利な本を買うということである。」p.124
・「以上、選択して読むことが大切であると共に選択して買うことが大切であり、これがためにぜひとも書評の発達ということがあって欲しいという主旨を説いた。」p.129
・「私は十二、三の頃太平記を愛読し、また維新の志士の事蹟に興味を以って雑書を読んだ。」p.132
・「福沢の死後塾生の気風も次第に変化したから一様には云えないが、世間一般を見渡して、さて自分の学校を顧みると、慶応に学んだものには、相手の上下に差別をつけ、下の者に威張るという風が割合少ないのではないかと思う、もしこの所見通りであるなら、それは一の美風と称してよいと思う。」p.135
・「「福翁自伝」によれば、福沢諭吉も学問に対する興味を覚えたのが晩く、十四、五になって始めて本気で本を読み出したと語っている。」p.135
・「後年佐藤春夫が或る機会に、自然主義運動は文学を、飛ぶことも歌うこともしない鶏のようなものにしてしまった、といったのは至言である。そうしてまたその鶏に、飛ぶ翼と歌う声とを与えたものは永井荷風と谷崎潤一郎とであったといったのも人の首肯するところであろう。」p.147
・「私は全く偶然の機会から「吾輩は猫である」が「ホトトギス」に出たその第一回から読んだ。そうしてまた続けて「倫敦塔」「薤露行」「幻影の盾」を読んで驚いた。これらの後に挙げた作品を、今の私は必ずしも漱石の最高のものとは思わない。けれども、これらのものが発表せられた明治38、9年当時の文壇に於いて、漱石の出現、その学殖と詞藻と空想力とは驚嘆すべきことであった。」p.149
・「読書や学問の苦心などというものは、過ぎてしまえば存外記憶に残っていないものである。」p.155
・「「風と共に去りぬ」といえば、これはアメリカ人の書いたもので私が読んだ最初の大作であった。この作が出たのは1936年の春であったが、たまたまその秋、私は慶応義塾から派遣されて、アメリカ各地を旅行した。その時どこで本の話が出ても、どこでも聞くのはこの作の評判であった。早速一部買い求めて帰り、帰ってから読んで感心して、その梗概とそれに対する感想を故岩波茂雄に話すと、岩波はぜひ岩波書店でその翻訳を出したいから周旋しないかという。あんな大部のものを翻訳する根気のあるものも、通読するものもあるまいからと、私はいい、岩波は不承不承思い止まった。ところが後に他からその訳本が出てみると、あの通りの成功で、今日まで十幾年読まれ続けて、最近はまた盛んに売れている。これも私が岩波にした誤った忠告の一である。」p.162
・「音楽が好きだということを前に書いた。したがって本を読んでいる間に音楽のことが出てくると今でも目敏い。」p.167
?かんい【敢為】 物事を反対や障害に屈しないで、やり通すこと。押し切って行なうこと。敢行。決行。
?しゅくせい【夙成】 早くからでき上がること。早くおとなびること。子どもの時から学業などが他の人より進んで、でき上がっていること。早熟。早成。
?しそう【詞藻】 1 文章の修辞。美しいことば。ことばのあや。 2 詩歌または文章。
《チェック本》谷崎潤一郎『雪』