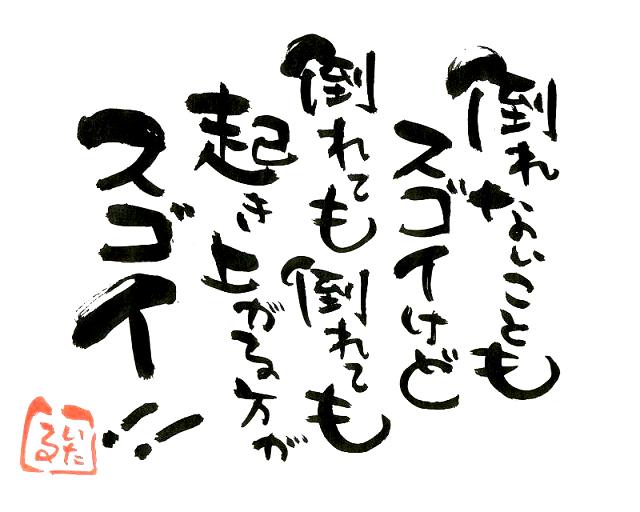
土佐のくじらです。
土佐のくじらの歴史シリーズも、段々と近世に近づいて参りました。(笑)
今回からは、(鎌倉)源氏にスポットを当てて参ります。
源頼朝は、父が平治の乱で平氏に破れ、伊豆に島流しに合いました。
平氏の監視の中で成長し、成人して挙兵にいたりますが、もちろん最初は、極々小さな勢力でありました。
そして最後には、武士による始めての、天下統一事業を成し遂げるのですね。
源頼朝には、織田信長の権勢拡張、徳川家康の天下統一、明治維新・・・これらの大事業に共通することがあります。
それは、これらの事業は極々小さな規模から始まっていたり、戦の当初においては少数派であって、世間からは「負けるだろう。」と思われていたことです。
信長は、尾張一国の主でしかありませんでした。
家康は、関が原の戦いでは、当初は石田光成勢が絶対的に優勢でした。
明治維新の中心勢力は、薩摩や長州という、一介の【藩】でしかありませんでした。
つまり大事業を成した彼らは、通常は勝てるはずのない戦いに勝利しているのです。
それらを実現可能にしたもの・・・それは、的確でわかりやすい 【ワンフレーズ】 を使って、戦いに勝利しているのですね。
信長は、【天下布武】
家康は、【反光成・はんみつなり】
薩長は、【倒幕】 です。
天下布武は、天下を武力で統一し、戦国時代を終わらせるの意味です。
実は、この時代の有力戦国大名は、誰も天下統一を望んでいなかった節があります。
詳細はまた、後ほど記述しようと思いますが、
永遠の戦国時代の中で、「自分たちのテリトリーをいかに増やすか。」ということだけで、戦国大名は戦っていたように私には思えます。
そのような中、信長だけが唯一、「戦国を終わらせる。」と宣言したのです。
家康の有名な戦い、関が原の戦いは、実は豊臣政権内の内部抗争なのですね。
あくまで、建前上ですが、家康にとっては、石田光成に反感を持っている武将たちの手助けをした戦・・・という位置づけなのです。
その証拠に家康は、関が原の戦いの処分を、大阪城内で執り行っております。
そして、言わずと知れた薩長の【倒幕】ですね。
では、源頼朝の使ったワンフレーズは何か?
打倒平家?
源氏の再興?
武士の世の中をつくる?
違います。
以外ですけれども、どれも違うのですね。
頼朝が挙兵した時に加わった、御家人と言われる武将は、北条氏を始め、実は皆、平家の一門なのですね。
ですから、打倒平家・・・の掛け声で、集まれるはずがないのです。
ですから頼朝挙兵時の彼らは、将来平家を倒す立場に立つとは、その時にはまだ、思ってもいなかっただろうと思います。
実は、この時の頼朝のキャッチフレーズは、 【 関東の独立 】 だったのです。
もちろん、天皇制などの国体を無視した独立ではありません。
税制面、納税の待遇に関する意味でのキャッチフレーズなのです。
当時の武士は、実は農家です。
ですから武士は当時、朝廷に年貢を納めていたのですね。
東国は都から遠いので、年貢を納めに行くのが大変だったのです。
寒冷化で、だんだんと収穫量は減ってきています。
ですから、
「関東は独立して、年貢を京の都にまで、届けに行かなくて良いようにする。」
これが、頼朝挙兵時のキャッチフレーズ・・・。言わば、立候補時の公約です。
この、「関東の独立」の実現のために、頼朝の周囲に武将たち一所懸命で、頼朝のために戦ったのですね。
今、役人たちが、自分たちの生活レベルを落とさないために、必死で好景気にブレーキをかけるべく、消費増税をあの手この手で仕掛けております。
景気が良くなると、ほぼ固定給である公務員は、相対的な貧者となるからです。
昨今の、マスコミや有識者を抱き込んでの「消費増税やむなし論」の流布には、「二度とバブル景気を起こさない。」という財務官僚側の、とても強い意志を感じざるを得ません。
彼らはバブル景気で、相当の屈辱感を味わったと思われます。
頼朝の成した、武士による国つくりは、実は税金問題から端を発しました。
日本はまた、新たな国つくりの時代の、必然性の中にいるのかも知れません。
(続く)













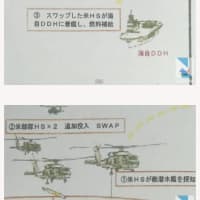






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます