
土佐のくじらです。
歴史部門の記事が、最近遅れております(笑)。
前回から家康にスポットを当てて来ておりますが、この頃になると、さすがに史実が多くなって来ますし、研究者も多いので、歴史ミステリーが余りありません。
つじつま合わせの歴史ヲタクとしては、余り出しゃばる部分が少のうございます。(笑)
さて、日本で最も有名な武将である、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の戦国三傑には、共通の施政方針があったというのが、当ブログの特徴です。
それは共に、天下布武=脱戦国だと私は思います。
これには、当時の世界史の動きである、大航海時代と白人植民地主義の台頭が、深く絡んでいると私は考えます。
織田信長の脱戦国施策が、原理主義的天下布武です。
豊臣秀吉の脱戦国は、現実主義的天下布武。
そして徳川家康の脱戦国が、統治型天下布武です。
簡単に言うと、
信長が、「戦国時代を終わらせる宣言」をし、秀吉は、実際に戦国を終わらせて見せ、家康が、それを維持させて見せたと言えます。
それぞれには特徴があり、長所と短所がございます。
信長流、原理主義的天下布武の特徴は、当時の日本で初めてそして唯一、「戦国時代を終わらせる。」と宣言し、それを実際に行動論として示したことです。
当時は、有能で人間性の豊かな武将は数多くいましたが、誰一人として、戦国時代が終わるとは考えてはいなかったはずです。
それを、「やる!」と宣言し、実際に行動して見せて、社会に「やれるかも知れない。」と思わせたのが、信長の偉業であります。
しかし信長流は、自分たちの勢力以外が全て敵になる・・・という、重大な欠点がありました。
それを克服したのが、秀吉流脱戦国である、現実主義的天下布武です。
秀吉は、多数派形成と戦力の集中と、朝廷工作や政治的権謀によって、それまで敵として戦っていた勢力と、服従による和解による天下統一を成し遂げました。
しかし秀吉流で出来た豊臣政権は、言わば「天下統一=天下布武」というスローガンに共鳴した勢力との、一大連立政権でした。
ですから政権内部に、徳川家康や毛利輝元などの、巨大勢力を抱えておりました。
それらは、豊臣秀吉という、歴史的カリスマがいればこその連立体制であり、カリスマ亡き後、内部の巨大勢力の内部抗争によって、再び戦国化する可能性を秘めていたのです。
それはとりもなおさず、徳川家康が頭角したことで、誰の眼にも明らかになってしまいました。
家康は、この豊臣政権が本質的に持つ、現実主義的天下布武の弱点を突いたのが家康だったのです。
これら先人の特徴をつぶさに研究し、弱点を克服した・・・否、しようとしたのが家康でした。
つまり家康は、二度と戦国時代に戻さないためには、為政者は圧倒的なスーパーパワーを持つ必要がある・・・ということに気付いたはずです。
家康が仕掛けたであろう関が原の戦いにも、それを裏付けるものがあります。
まず、五大老を分裂させました。
前田家は徳川方、宇喜多家・上杉家・毛利家は豊臣方になりました。
また加藤清正など、豊臣恩顧の家臣を豊臣家と戦わせております。
家康は関が原の戦いは、もう少し長期化すると思っていただろうと思います。
ゆえに、豊臣家の中心をまず戦わせて、大部分の勢力を削いだ後、徳川軍本体である秀忠が決着を付ける・・・という腹積もりだったと考えます。
しかし秀忠軍の到着が大幅に遅れ、豊臣恩顧の大名だけで、半日で戦が終わってしまったために、豊臣勢力が戦後も相当残ってしまいました。
徳川家は関が原の戦いでは、日本最大勢力のままで、圧倒的スーパーパワーにはなれなかったのです。
それでは再び、日本は戦国化し、分裂の危機を迎えます。
そこで家康が考えた統治型天下布武が、『 徹底的に、天下取りを諦めさせる 』 という方法論であったと思うのです。
大きなテーマは脱戦国・・・つまり、二度と戦国時代に戻さない・・・とい理念で、方法論が、諦めさせる・・・というものです。
これが、その後250年以上続いた江戸幕府の大きな政治理念であり、それが今でも日本人の心に染み付いていると、私は考えているのです。
(続く)













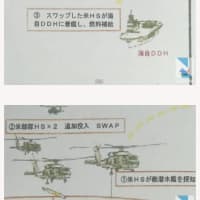






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます