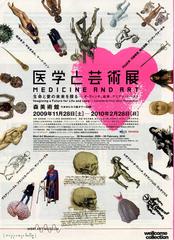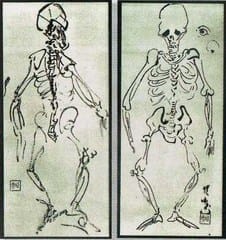12月27日(日)
当日の行程:【高瀬川一之船入】 → 【島津創業記念資料館】 → 【大文字山】 → 【琵琶湖疎水記念館】 → 【豊国廟】

琵琶湖疏水記念館に行く。
気にはなっていたのだけれど、関西在住中に行けなかった場所のうちのひとつ。

記念館の入り口に置かれた自販機には、「京の水道 疏水物語」というお水が並んでいる。
1本100円。

東京遷都後の衰退した京都の復興させようと、琵琶湖疏水の建設が始まったらしい。
開国後の日本は盲目的と言えるほどまでに焦っていたが、遷都後の京都も焦っていた、と思う。
平安神宮建立での町おこしや、内国勧業博覧会のことなどを考える。
京都は、焦らずに、そのままでいいのに……と粗野な関東人は思う。
だが、人口は激減し、産業は衰退し……京都の人だって生活しているのだ。
焦るのも仕方ない。
疏水記念館の話に戻ろう。
館内には、琵琶湖疏水の計画と建設に関する資料や、復元模型が展示されている。
琵琶湖疏水の水は、水道用水の確保や船での交通のためだけでなく、水力発電にも利用されているらしい。
水力発電の仕組みをうまく説明できない私。
帰宅後調べたら、自転車の電灯にたとえたうまい説明があった。
自転車のペダルにあたるのが水車、ペダルを踏むのは人の足にあたるのが高い位置にある水。
足でペダルを踏むとチェーンとタイヤが回って電灯が点くけれど、水力発電の場合は、水を落として水車が回ると発電機が回り出すという仕組み。

インクライン

台車
インクラインは、高低差が大きな場所で、貨車を使って船を引き上げるための線路。
船は、「船受枠」という台車にのせられて移動していたそうだ。
琵琶湖疏水のインクラインが運用されていたのは明治24年(1891)から昭和23年(1948)まで(その後、昭和26年に、砂を積んだ30石船が通るのに使われたが)。
陸運の発展が原因で、衰退していったらしい。
移動にはどのくらいの時間がかかったのか、興味深い。
大津~蹴上間の上りには約2時間20分、下りには約1時間20分を要したとのこと。
さて現在は?
ルートにもよるけれど、20~30分前後で移動できるようになった。
役割を終えたインクラインだが、春には桜を楽しむ人で賑わうようだ。
当日の行程:【高瀬川一之船入】 → 【島津創業記念資料館】 → 【大文字山】 → 【琵琶湖疎水記念館】 → 【豊国廟】

琵琶湖疏水記念館に行く。
気にはなっていたのだけれど、関西在住中に行けなかった場所のうちのひとつ。

記念館の入り口に置かれた自販機には、「京の水道 疏水物語」というお水が並んでいる。
1本100円。

東京遷都後の衰退した京都の復興させようと、琵琶湖疏水の建設が始まったらしい。
開国後の日本は盲目的と言えるほどまでに焦っていたが、遷都後の京都も焦っていた、と思う。
平安神宮建立での町おこしや、内国勧業博覧会のことなどを考える。
京都は、焦らずに、そのままでいいのに……と粗野な関東人は思う。
だが、人口は激減し、産業は衰退し……京都の人だって生活しているのだ。
焦るのも仕方ない。
疏水記念館の話に戻ろう。
館内には、琵琶湖疏水の計画と建設に関する資料や、復元模型が展示されている。
琵琶湖疏水の水は、水道用水の確保や船での交通のためだけでなく、水力発電にも利用されているらしい。
水力発電の仕組みをうまく説明できない私。
帰宅後調べたら、自転車の電灯にたとえたうまい説明があった。
自転車のペダルにあたるのが水車、ペダルを踏むのは人の足にあたるのが高い位置にある水。
足でペダルを踏むとチェーンとタイヤが回って電灯が点くけれど、水力発電の場合は、水を落として水車が回ると発電機が回り出すという仕組み。

インクライン

台車
インクラインは、高低差が大きな場所で、貨車を使って船を引き上げるための線路。
船は、「船受枠」という台車にのせられて移動していたそうだ。
琵琶湖疏水のインクラインが運用されていたのは明治24年(1891)から昭和23年(1948)まで(その後、昭和26年に、砂を積んだ30石船が通るのに使われたが)。
陸運の発展が原因で、衰退していったらしい。
移動にはどのくらいの時間がかかったのか、興味深い。
大津~蹴上間の上りには約2時間20分、下りには約1時間20分を要したとのこと。
さて現在は?
ルートにもよるけれど、20~30分前後で移動できるようになった。
役割を終えたインクラインだが、春には桜を楽しむ人で賑わうようだ。