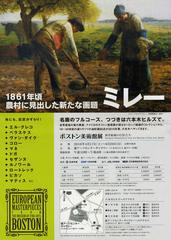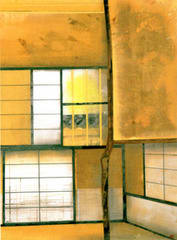5月4日(火)

カキツバタを観に行く。

尾形光琳『燕子花図屏風』(国宝)・右隻

左隻
使われている色は濃紺と緑。
背景は金箔。
描かれているのは、燕子花だけ。
ただそれだけなのだけれど、絶妙なバランス。

「伊年」印『四季草花図屏風』・左隻

『桜下蹴鞠図屏風』(重要美術品)・右隻

鈴木其一『夏秋渓流図屏風』・右隻

左隻

庭のカキツバタも満開。


カキツバタだけでなく、藤も見ごろを迎えていた。

カキツバタを観に行く。

尾形光琳『燕子花図屏風』(国宝)・右隻

左隻
使われている色は濃紺と緑。
背景は金箔。
描かれているのは、燕子花だけ。
ただそれだけなのだけれど、絶妙なバランス。

「伊年」印『四季草花図屏風』・左隻

『桜下蹴鞠図屏風』(重要美術品)・右隻

鈴木其一『夏秋渓流図屏風』・右隻

左隻

庭のカキツバタも満開。


カキツバタだけでなく、藤も見ごろを迎えていた。