特定秘密保護法 刑事司法は濫用を抑制する機能を果たせるのか
投稿日 2013年12月5日 投稿者: nobuogohara
特定秘密保護法案が、少数の野党の反発やマスコミなどの強い反対を押し切って、今日、参議院で採決され、成立する見通しだと報じられている。
私も、このような行政への一層の権限集中を招く立法が行われることには反対である。しかし、それは、法案自体に問題があるということではない。むしろ、官僚組織である検察に権限が集中し、しかも、マスコミも、それに対して批判機能を果たせない日本の刑事司法の現状の下では、その法律に基づく権限の濫用を抑制することが困難だという、刑事司法の実情の方に問題がある。検察出身の法律実務家の立場から、その点を中心に、私の見解を述べてみることにしたい。
まず、特定秘密保護法案をめぐる議論の現状を、私なりに整理してみる。
外交、防衛に関して、国家が厳重に管理しなければならない秘密があることは確かであり、そのような秘密を保護するために、秘密を取扱う公務員に特別に厳格な義務を課すことも、合理的と言えるであろう。そして、公務員がその義務に反しないようにするためには、公務員に秘密を漏えいさせようとする行為も一定の範囲で処罰の対象とせざるを得ない。そして、そのような行為は、現在の国家公務員法でも罰則の対象とされているのであり、特定秘密保護法によって初めて処罰の対象とされるわけではない。
このように考えると、特定秘密保護法案の内容には問題はないとして、法案に反対するマスコミを批判する池田信夫氏、高橋洋一氏らの見解は、一応筋が通っていると言えよう。
また、元法制局長官の阪田雅裕氏が、「公務員が職務上知り得た秘密全般について、漏らす行為やその煽り、そそのかしが、現行の国家公務員法で処罰の対象とされており、何が秘密なのかについては曖昧で、その指定の手続も定められていない。特定秘密保護法は、その中で特に厳格に管理すべき秘密について、指定の手続と、それを保護するための措置を定めているものであり、国公法で秘密とされていないものが秘密にされるわけではない。」と述べているのも、特定秘密保護法案に対する法律家としての常識的な見方だと言えよう(【特定秘密保護法案法律としては構造的な問題はない】 )。
安倍内閣が、現行憲法の解釈変更によって集団的自衛権の行使を認めようとしたことに対して、憲法改正によらなければ不可能であると異を唱えた阪田氏ですら、このように述べているのであり、少なくとも、純粋に法律家の立場から考えると、この法案に根本的な問題があるとはいえない。
しかし、同法案に対しては、当初から強い反対意見がある。特に、衆議院で強行採決された後は、法案を短期間で成立させようとする政府与党のやり方に対する批判も加わり、反対意見が高まっている。
法案に反対する立場・意見は、次のように整理できる。
第1に、「国家として、外交、防衛などに関して、厳重に管理しなければならない秘密事項があるのは当然である。」という法案の前提に関して、その背景にある外交政策に反発する立場がある。
今回、この時期に、急いで法案を成立させようとしている背景に、アメリカの意向が働いていることは否定できないであろう。現在の、日本の外交政策の下で、外交・防衛に関する秘密管理を厳格化することは、「対米追従」を一層進め、アメリカとの軍事同盟を強化することにつながる。それ自体に反対する立場からは、法案に強く反対するのは、ある意味では当然と言えよう。
しかし、自公両党及びそれと外交政策的には大きな違いはない野党が、衆参両院で圧倒的多数を占める現状では、そのような「対米追従」を批判する「反米イデオロギー」は、国民の支持するところではない。外交政策的な観点からの反対は潜在化し、法案自体の内容に関する批判に振り向けられることになる。
第2に、秘密の指定権・判断権が、基本的に当該行政機関に委ねられていることに対する反発がある。「特定秘密に当たるか否かの判断は、第一次的には、行政行為を遂行する行政機関に委ねざるを得ないのであり、その濫用に対するチェックも、国家として『厳重に管理すべき秘密』であることから、第三者に関与させることには限界があり、基本的には政府内部によるチェックに委ねざるを得ない。」というのが、政府与党側の論理である。
行政機関の権限の源泉は、行政の遂行に関して、情報を独占することにある。その情報の独占状態は、2001年に「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」が制定され、情報公開制度が拡充されることによって、大幅に緩和されてきた。そして、2006年に公益通報者保護法が施行され、企業の世界においては、内部告発が積極的に行われるようになり、それを奨励することが社会的風潮になってきたが、行政機関の職員も、この法律による保護を受けて内部告発を積極的に行うことになると、行政機関による情報の独占は一層崩れていくことになる。
特定秘密保護法が、行政機関側に秘密を厳格に管理する権限を与え、それを重い罰則で担保することは、このような情報公開制度等による、行政の権限を制約する流れに逆行することになる。情報を入手して報道することを仕事としているマスコミとしては、それに反発するのは、ある意味では当然の反応と言えよう。そこでは、マスコミの「報道の自由」、国民の「知る権利」が侵害されるという点が強く主張される。
第3に、これらの反対や懸念を背景に、現在、法案の最大の問題点とされているのが、 防衛に関する事項、外交に関する事項、外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項、テロ活動防止に関する事項とされている特定秘密の範囲の問題である。
特に、自民党の石破幹事長の「単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質において変わらない」というブログでの発言も相まって、特定秘密の範囲に関する「テロリズム」の定義が大きな問題となっている。
この点に関しては、法案における「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう」という定義が、「強要」、「殺傷」、「破壊」を同列に並べているように読めることも問題とされている(「与える目的で」と「人を殺傷」の間に読点「、」が入っていれば、このような誤解を受けることはなかったと思われ、細かい点ではあるが法案の文言上の欠陥と言えよう)。
この点に関連して、「公安捜査」の実情から、法定刑も重く、処罰範囲が広範な罰則の導入に対して、捜査権限濫用に対する危惧感を表明するのが、元検事の落合洋司弁護士である。同弁護士は、「公安事件では、『犯罪があるから捜査する。』だけでなく、『捜査すべき組織や人がいるから捜査する。」『捜査することに意味、意義がある。』『捜査により組織や人に打撃を与える。』という観点から捜査が行われる」として、「秘密」に関わる行為を広範囲に処罰対象にしている今回の法案が、公安事件捜査で濫用される恐れがあることを指摘している(ブログ【弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日】 )。
私も、1980年代末から90年代にかけて、東京地検公安部に約2年半在籍した。落合弁護士が在籍した90年代と異なり、中核派、革マル派などの過激派の事件を含む公安事件が多発していた時代であった。そのような時期に公安事件の捜査を経験した者として、特にこの点に言及する必要があるだろう。
公安事件捜査は、一般の刑事事件捜査のように、発生した犯罪について捜査し、犯人を特定して逮捕する、という経過をたどるのではない。政治的目的で活動する特定の団体という対象が予め設定され、その活動を制圧・排除するという目的に沿った捜査活動が行われる。そして、そこでは、あらゆる罰則、あらゆる権限が使われる。
その実態については、拙著【検察の正義】 (ちくま新書:2009年)25頁以下で触れている。
≪当時は、極左暴力集団と言われる中核派、革マル派などの非公然活動家によるテロなどの破壊活動や内ゲバ殺人事件が多発しており、警視庁公安部は、その対策のために、非公然活動家の検挙を目的とする取締りを行っていた。非公然活動家が警視庁公安部に逮捕され送致されてくると、東京地検公安部では、主任検事とは別に取調べ担当検察官を指名して共同捜査体制で臨む場合が多かった。
非公然活動家というのは、テロなどの「軍事行動」を実行する革命軍に所属する者と、そのための偵察、情報収集活動などの後方支援活動を行う者に分かれる。いずれも、家族、親族、知人など、すべての個人的つながりを絶って、その存在と活動が、まったく把握されないよう地下に潜って活動を行っている。その行方を追い続けているのが公安警察だった。過去の内ゲバ殺人事件やテロ事件などの重大事件で指名手配されている革命軍所属の「兵士」が、その所在を突き止められて逮捕状によって逮捕される、というケースもあったが、多くは、後方支援部隊の非公然活動家が、警察官から職務質問を受けた際に警察官に暴行を加えたという公務執行妨害の現行犯や、運転免許証の更新手続の際に、住居不定で非公然活動をしているのに、実家などを住所として申告して免許証を取得したという免状等不実記載罪など、いわゆる「微罪」で逮捕されてくるケースだった。
非公然活動家が公務執行妨害で逮捕される場合の多くは「転び公妨」などと呼ばれる事案だった。指名手配をされているわけでもない非公然活動家であれば、警察官から職務質問を受けても、おとなしくしていれば何も問題はないはずなのに、なぜ、警察官を突き飛ばしたりするのか、疑問に思える。しかし、警察の送致書類の上では、被疑者が職務質問を受けた途端に抵抗を始め、警察官に暴行を働いた状況を複数の警察官が詳細に報告している。
このような事案でも、公務執行妨害の嫌疑を裏付ける警察官の供述があり、非公然活動家である以上「住居不定」などで、当然に、勾留の要件は充たされる。そこで、その身柄拘束の期間内、完全黙秘の被疑者と取調べ担当検察官とが対峙することになる。≫
ここで言っている「免状不実記載」「転び公妨」で逮捕されても、ほとんど起訴されることはない。要は、20日間余りの身柄拘束のネタに使われるというのが実態だった。
犯人の処罰に向けての刑事事件の手続という面から考えると、そのような事実で身柄拘束をする必要性は、実際にはない。そのことは、検察官も裁判官もわかっているはずだ。しかし、公安事件で、「非公然活動家」が逮捕され、送致されてきた事件で、検察官が勾留請求をしないということはほとんどなかったし、裁判官が勾留請求を却下した例も少なかった。
このようなことは、「刑事司法に対する一般的な認識」としては考え難いことであろう。しかし、それも、テロなどの軍事活動を標榜する過激派の取締りという目的の下では、刑事司法の現場で実際に起こり得るのである。
特定秘密保護法の罰則が、そのような目的で使われる恐れがあるのかどうかは、何とも言えない。しかし、刑事司法が、常に適切に、法の目的に沿って運用されているという前提で考えることは危険である。
捜査機関が法の本来の趣旨に反する権限行使を行おうとした時、刑事訴訟法上、それを抑制する多くの手段が定められている。検察官が勾留請求するかどうかという判断、裁判所が勾留請求を認めるかどうかの判断、最終的な判決における事実認定などを通して、適切な判断が行われるというのが、刑事訴訟法の建前だが、ひとたび国家が一定の方向に動き始めたときは、それらの手段によって抑制できるとは限らないのである。
前出の阪田元法制局長官が、「特定秘密保護法案には法律として構造的な問題はない」とする理由として、「もし、不当に特定秘密に指定された事項に関して、刑事事件が立件され起訴された場合には、裁判所が適切に判断するはずだ」と述べている。それは、「刑事司法に対する一般的な認識」に基づく見解としては正しいであろう。しかし、実際に、公安事件も含め、刑事司法の現場が、すべて、そのような認識通りに運用されているかといえば、必ずしもそうではないのである。
日本の刑事司法は、事実を否認する被疑者を長期的に身柄拘束する「人質司法」、検察官による証拠の独占など、検察官にあらゆる権限が集中している。そして、検察は、第一次捜査機関の警察とは極めて近い関係にある。
このような刑事司法の実情を考えた時、私は、「刑事司法への信頼」を前提に、特定秘密保護法に問題がないとする意見には、賛成できない。
特定秘密保護法案に関して問題なのは、法案の中身自体というより、むしろ、現行の刑事司法の運用の下で、このような法律が成立し、誤った方向に濫用された場合に、司法の力でそれを抑制することが期待できないということである。
そのような刑事司法に対して、マスコミは、これまで十分に批判的機能を果たしてきたであろうか。過去に、過激派等に対する公安捜査の実情に関する問題を指摘した報道がどれだけあったであろうか。「人質司法」など、刑事司法の問題点について、どれだけ指摘してきたであろうか。直近では、検察の一部が、虚偽の捜査報告書で検察審査会を騙して政治的目的を遂げようとした陸山会事件での「特捜部の暴走」に対して、民主主義を危うくするものとして徹底した批判が行われたであろうか。
検察や警察との「もたれ合い」的な関係によって、刑事司法の歪みを温存してきたという点からは、責任の一端はマスコミにもあるのではなかろうか。そういうマスコミが、「知る権利」「報道の自由」を振りかざして、法案に反対していることに対して、若干の違和感を覚えざるを得ない。
しかも、日本の官僚、行政組織と親密な関係を維持してきた自民党が、昨年12月の衆議院選挙で圧勝して政権に復帰し、今年7月の参議院選挙でも圧勝して、衆参両院において安定的な勢力を維持する政治状況になったことから、行政権限の肥大化、官僚組織による情報の独占に向けて立法が行われることも、ある意味では当然の趨勢と言うべきであろう。
このような政治状況を招いてしまった最大の原因は、昨年12月まで政権の座にあった民主党が事実上崩壊してしまったことにある。それは、第一次的には、民主党の自業自得だ。しかし、政権交代直後から、民主党が「政治とカネ」の問題をめぐる党内抗争に明け暮れる状況になったことには、マスコミも深く関わっている。
その結果できあがった、「単一の価値観に支配される政治状況」の下で、今、行政組織の権限の更なる強化に向けての特定秘密保護法が成立しようとしているのである。
いかに少数野党が抵抗しようと、マスコミがこぞって批判しようと、多くの知識人、文化人が反対しようと、特定秘密保護法が今国会で成立することを阻止することは避けられないであろう。
そういう政治の現実を、重く受け止めるべきではなかろうか。
元法制局長官の阪田氏も言うように、法律家の常識から法案自体の内容を客観的に見れば、特に問題があるとは言えない。であれば、重要なのは法案が成立した後である。法の趣旨を逸脱する、法律家の常識に反する法の運用が行われた場合に、適切な抑制機能を果たし得る刑事司法の実現に向けて、マスコミを含め世の中全体が問題意識を持ち、議論を深めていくべきではなかろうか。
投稿日 2013年12月5日 投稿者: nobuogohara
特定秘密保護法案が、少数の野党の反発やマスコミなどの強い反対を押し切って、今日、参議院で採決され、成立する見通しだと報じられている。
私も、このような行政への一層の権限集中を招く立法が行われることには反対である。しかし、それは、法案自体に問題があるということではない。むしろ、官僚組織である検察に権限が集中し、しかも、マスコミも、それに対して批判機能を果たせない日本の刑事司法の現状の下では、その法律に基づく権限の濫用を抑制することが困難だという、刑事司法の実情の方に問題がある。検察出身の法律実務家の立場から、その点を中心に、私の見解を述べてみることにしたい。
まず、特定秘密保護法案をめぐる議論の現状を、私なりに整理してみる。
外交、防衛に関して、国家が厳重に管理しなければならない秘密があることは確かであり、そのような秘密を保護するために、秘密を取扱う公務員に特別に厳格な義務を課すことも、合理的と言えるであろう。そして、公務員がその義務に反しないようにするためには、公務員に秘密を漏えいさせようとする行為も一定の範囲で処罰の対象とせざるを得ない。そして、そのような行為は、現在の国家公務員法でも罰則の対象とされているのであり、特定秘密保護法によって初めて処罰の対象とされるわけではない。
このように考えると、特定秘密保護法案の内容には問題はないとして、法案に反対するマスコミを批判する池田信夫氏、高橋洋一氏らの見解は、一応筋が通っていると言えよう。
また、元法制局長官の阪田雅裕氏が、「公務員が職務上知り得た秘密全般について、漏らす行為やその煽り、そそのかしが、現行の国家公務員法で処罰の対象とされており、何が秘密なのかについては曖昧で、その指定の手続も定められていない。特定秘密保護法は、その中で特に厳格に管理すべき秘密について、指定の手続と、それを保護するための措置を定めているものであり、国公法で秘密とされていないものが秘密にされるわけではない。」と述べているのも、特定秘密保護法案に対する法律家としての常識的な見方だと言えよう(【特定秘密保護法案法律としては構造的な問題はない】 )。
安倍内閣が、現行憲法の解釈変更によって集団的自衛権の行使を認めようとしたことに対して、憲法改正によらなければ不可能であると異を唱えた阪田氏ですら、このように述べているのであり、少なくとも、純粋に法律家の立場から考えると、この法案に根本的な問題があるとはいえない。
しかし、同法案に対しては、当初から強い反対意見がある。特に、衆議院で強行採決された後は、法案を短期間で成立させようとする政府与党のやり方に対する批判も加わり、反対意見が高まっている。
法案に反対する立場・意見は、次のように整理できる。
第1に、「国家として、外交、防衛などに関して、厳重に管理しなければならない秘密事項があるのは当然である。」という法案の前提に関して、その背景にある外交政策に反発する立場がある。
今回、この時期に、急いで法案を成立させようとしている背景に、アメリカの意向が働いていることは否定できないであろう。現在の、日本の外交政策の下で、外交・防衛に関する秘密管理を厳格化することは、「対米追従」を一層進め、アメリカとの軍事同盟を強化することにつながる。それ自体に反対する立場からは、法案に強く反対するのは、ある意味では当然と言えよう。
しかし、自公両党及びそれと外交政策的には大きな違いはない野党が、衆参両院で圧倒的多数を占める現状では、そのような「対米追従」を批判する「反米イデオロギー」は、国民の支持するところではない。外交政策的な観点からの反対は潜在化し、法案自体の内容に関する批判に振り向けられることになる。
第2に、秘密の指定権・判断権が、基本的に当該行政機関に委ねられていることに対する反発がある。「特定秘密に当たるか否かの判断は、第一次的には、行政行為を遂行する行政機関に委ねざるを得ないのであり、その濫用に対するチェックも、国家として『厳重に管理すべき秘密』であることから、第三者に関与させることには限界があり、基本的には政府内部によるチェックに委ねざるを得ない。」というのが、政府与党側の論理である。
行政機関の権限の源泉は、行政の遂行に関して、情報を独占することにある。その情報の独占状態は、2001年に「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」が制定され、情報公開制度が拡充されることによって、大幅に緩和されてきた。そして、2006年に公益通報者保護法が施行され、企業の世界においては、内部告発が積極的に行われるようになり、それを奨励することが社会的風潮になってきたが、行政機関の職員も、この法律による保護を受けて内部告発を積極的に行うことになると、行政機関による情報の独占は一層崩れていくことになる。
特定秘密保護法が、行政機関側に秘密を厳格に管理する権限を与え、それを重い罰則で担保することは、このような情報公開制度等による、行政の権限を制約する流れに逆行することになる。情報を入手して報道することを仕事としているマスコミとしては、それに反発するのは、ある意味では当然の反応と言えよう。そこでは、マスコミの「報道の自由」、国民の「知る権利」が侵害されるという点が強く主張される。
第3に、これらの反対や懸念を背景に、現在、法案の最大の問題点とされているのが、 防衛に関する事項、外交に関する事項、外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項、テロ活動防止に関する事項とされている特定秘密の範囲の問題である。
特に、自民党の石破幹事長の「単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質において変わらない」というブログでの発言も相まって、特定秘密の範囲に関する「テロリズム」の定義が大きな問題となっている。
この点に関しては、法案における「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう」という定義が、「強要」、「殺傷」、「破壊」を同列に並べているように読めることも問題とされている(「与える目的で」と「人を殺傷」の間に読点「、」が入っていれば、このような誤解を受けることはなかったと思われ、細かい点ではあるが法案の文言上の欠陥と言えよう)。
この点に関連して、「公安捜査」の実情から、法定刑も重く、処罰範囲が広範な罰則の導入に対して、捜査権限濫用に対する危惧感を表明するのが、元検事の落合洋司弁護士である。同弁護士は、「公安事件では、『犯罪があるから捜査する。』だけでなく、『捜査すべき組織や人がいるから捜査する。」『捜査することに意味、意義がある。』『捜査により組織や人に打撃を与える。』という観点から捜査が行われる」として、「秘密」に関わる行為を広範囲に処罰対象にしている今回の法案が、公安事件捜査で濫用される恐れがあることを指摘している(ブログ【弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日】 )。
私も、1980年代末から90年代にかけて、東京地検公安部に約2年半在籍した。落合弁護士が在籍した90年代と異なり、中核派、革マル派などの過激派の事件を含む公安事件が多発していた時代であった。そのような時期に公安事件の捜査を経験した者として、特にこの点に言及する必要があるだろう。
公安事件捜査は、一般の刑事事件捜査のように、発生した犯罪について捜査し、犯人を特定して逮捕する、という経過をたどるのではない。政治的目的で活動する特定の団体という対象が予め設定され、その活動を制圧・排除するという目的に沿った捜査活動が行われる。そして、そこでは、あらゆる罰則、あらゆる権限が使われる。
その実態については、拙著【検察の正義】 (ちくま新書:2009年)25頁以下で触れている。
≪当時は、極左暴力集団と言われる中核派、革マル派などの非公然活動家によるテロなどの破壊活動や内ゲバ殺人事件が多発しており、警視庁公安部は、その対策のために、非公然活動家の検挙を目的とする取締りを行っていた。非公然活動家が警視庁公安部に逮捕され送致されてくると、東京地検公安部では、主任検事とは別に取調べ担当検察官を指名して共同捜査体制で臨む場合が多かった。
非公然活動家というのは、テロなどの「軍事行動」を実行する革命軍に所属する者と、そのための偵察、情報収集活動などの後方支援活動を行う者に分かれる。いずれも、家族、親族、知人など、すべての個人的つながりを絶って、その存在と活動が、まったく把握されないよう地下に潜って活動を行っている。その行方を追い続けているのが公安警察だった。過去の内ゲバ殺人事件やテロ事件などの重大事件で指名手配されている革命軍所属の「兵士」が、その所在を突き止められて逮捕状によって逮捕される、というケースもあったが、多くは、後方支援部隊の非公然活動家が、警察官から職務質問を受けた際に警察官に暴行を加えたという公務執行妨害の現行犯や、運転免許証の更新手続の際に、住居不定で非公然活動をしているのに、実家などを住所として申告して免許証を取得したという免状等不実記載罪など、いわゆる「微罪」で逮捕されてくるケースだった。
非公然活動家が公務執行妨害で逮捕される場合の多くは「転び公妨」などと呼ばれる事案だった。指名手配をされているわけでもない非公然活動家であれば、警察官から職務質問を受けても、おとなしくしていれば何も問題はないはずなのに、なぜ、警察官を突き飛ばしたりするのか、疑問に思える。しかし、警察の送致書類の上では、被疑者が職務質問を受けた途端に抵抗を始め、警察官に暴行を働いた状況を複数の警察官が詳細に報告している。
このような事案でも、公務執行妨害の嫌疑を裏付ける警察官の供述があり、非公然活動家である以上「住居不定」などで、当然に、勾留の要件は充たされる。そこで、その身柄拘束の期間内、完全黙秘の被疑者と取調べ担当検察官とが対峙することになる。≫
ここで言っている「免状不実記載」「転び公妨」で逮捕されても、ほとんど起訴されることはない。要は、20日間余りの身柄拘束のネタに使われるというのが実態だった。
犯人の処罰に向けての刑事事件の手続という面から考えると、そのような事実で身柄拘束をする必要性は、実際にはない。そのことは、検察官も裁判官もわかっているはずだ。しかし、公安事件で、「非公然活動家」が逮捕され、送致されてきた事件で、検察官が勾留請求をしないということはほとんどなかったし、裁判官が勾留請求を却下した例も少なかった。
このようなことは、「刑事司法に対する一般的な認識」としては考え難いことであろう。しかし、それも、テロなどの軍事活動を標榜する過激派の取締りという目的の下では、刑事司法の現場で実際に起こり得るのである。
特定秘密保護法の罰則が、そのような目的で使われる恐れがあるのかどうかは、何とも言えない。しかし、刑事司法が、常に適切に、法の目的に沿って運用されているという前提で考えることは危険である。
捜査機関が法の本来の趣旨に反する権限行使を行おうとした時、刑事訴訟法上、それを抑制する多くの手段が定められている。検察官が勾留請求するかどうかという判断、裁判所が勾留請求を認めるかどうかの判断、最終的な判決における事実認定などを通して、適切な判断が行われるというのが、刑事訴訟法の建前だが、ひとたび国家が一定の方向に動き始めたときは、それらの手段によって抑制できるとは限らないのである。
前出の阪田元法制局長官が、「特定秘密保護法案には法律として構造的な問題はない」とする理由として、「もし、不当に特定秘密に指定された事項に関して、刑事事件が立件され起訴された場合には、裁判所が適切に判断するはずだ」と述べている。それは、「刑事司法に対する一般的な認識」に基づく見解としては正しいであろう。しかし、実際に、公安事件も含め、刑事司法の現場が、すべて、そのような認識通りに運用されているかといえば、必ずしもそうではないのである。
日本の刑事司法は、事実を否認する被疑者を長期的に身柄拘束する「人質司法」、検察官による証拠の独占など、検察官にあらゆる権限が集中している。そして、検察は、第一次捜査機関の警察とは極めて近い関係にある。
このような刑事司法の実情を考えた時、私は、「刑事司法への信頼」を前提に、特定秘密保護法に問題がないとする意見には、賛成できない。
特定秘密保護法案に関して問題なのは、法案の中身自体というより、むしろ、現行の刑事司法の運用の下で、このような法律が成立し、誤った方向に濫用された場合に、司法の力でそれを抑制することが期待できないということである。
そのような刑事司法に対して、マスコミは、これまで十分に批判的機能を果たしてきたであろうか。過去に、過激派等に対する公安捜査の実情に関する問題を指摘した報道がどれだけあったであろうか。「人質司法」など、刑事司法の問題点について、どれだけ指摘してきたであろうか。直近では、検察の一部が、虚偽の捜査報告書で検察審査会を騙して政治的目的を遂げようとした陸山会事件での「特捜部の暴走」に対して、民主主義を危うくするものとして徹底した批判が行われたであろうか。
検察や警察との「もたれ合い」的な関係によって、刑事司法の歪みを温存してきたという点からは、責任の一端はマスコミにもあるのではなかろうか。そういうマスコミが、「知る権利」「報道の自由」を振りかざして、法案に反対していることに対して、若干の違和感を覚えざるを得ない。
しかも、日本の官僚、行政組織と親密な関係を維持してきた自民党が、昨年12月の衆議院選挙で圧勝して政権に復帰し、今年7月の参議院選挙でも圧勝して、衆参両院において安定的な勢力を維持する政治状況になったことから、行政権限の肥大化、官僚組織による情報の独占に向けて立法が行われることも、ある意味では当然の趨勢と言うべきであろう。
このような政治状況を招いてしまった最大の原因は、昨年12月まで政権の座にあった民主党が事実上崩壊してしまったことにある。それは、第一次的には、民主党の自業自得だ。しかし、政権交代直後から、民主党が「政治とカネ」の問題をめぐる党内抗争に明け暮れる状況になったことには、マスコミも深く関わっている。
その結果できあがった、「単一の価値観に支配される政治状況」の下で、今、行政組織の権限の更なる強化に向けての特定秘密保護法が成立しようとしているのである。
いかに少数野党が抵抗しようと、マスコミがこぞって批判しようと、多くの知識人、文化人が反対しようと、特定秘密保護法が今国会で成立することを阻止することは避けられないであろう。
そういう政治の現実を、重く受け止めるべきではなかろうか。
元法制局長官の阪田氏も言うように、法律家の常識から法案自体の内容を客観的に見れば、特に問題があるとは言えない。であれば、重要なのは法案が成立した後である。法の趣旨を逸脱する、法律家の常識に反する法の運用が行われた場合に、適切な抑制機能を果たし得る刑事司法の実現に向けて、マスコミを含め世の中全体が問題意識を持ち、議論を深めていくべきではなかろうか。










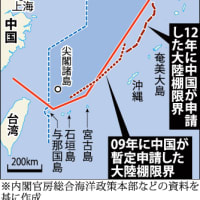





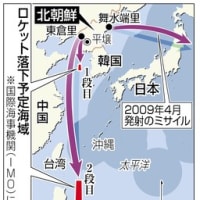
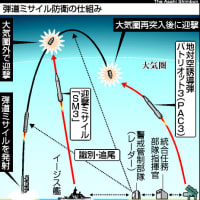







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます