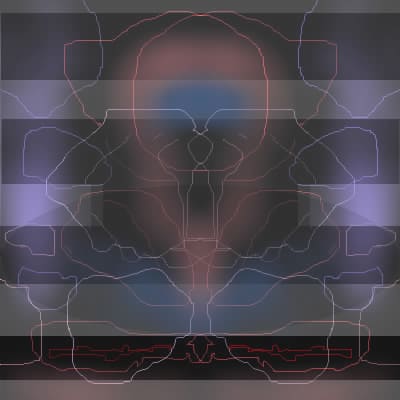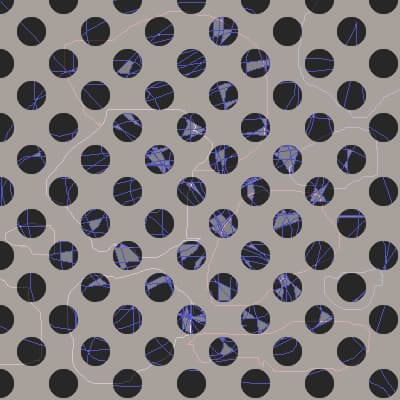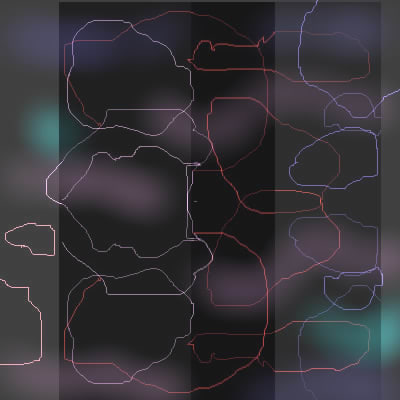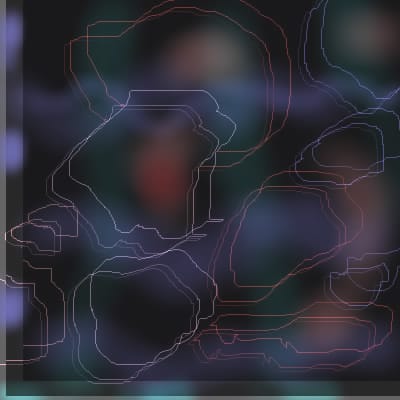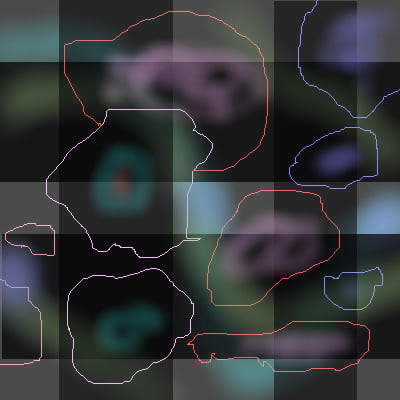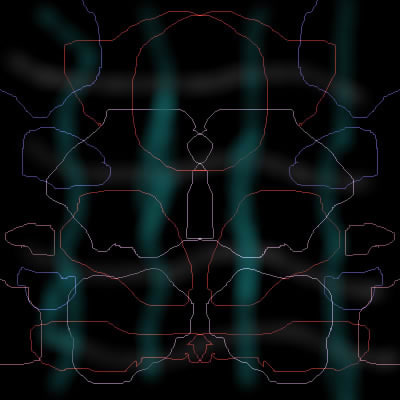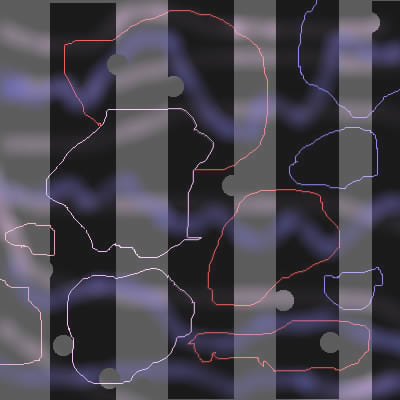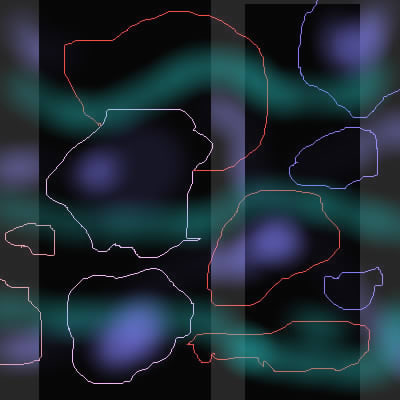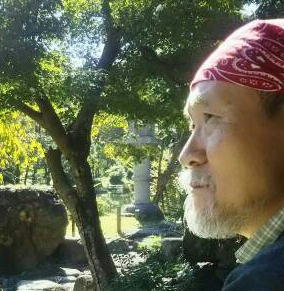私の横で里依子は静かに絵を見ていた。絵に対する里依子の心のリズムはとても快いものだった。私は彼女を眼を細めて眺めやった。「濱風のなでしこ」伊藤整が根見子を表現した言葉が私の頭をよぎって消えた。濱風に揺れるなでしこのような人、私にとってそれは里依子に他ならなかった。
館内は静かでまばらな鑑賞者が思い思いに絵の前に立っている。そんな雰囲気が心ゆくまで好きな絵を見せてくれた。そしてその傍らにいつ . . . 本文を読む
有島武郎の『生まれいずる悩み』は、中学生の頃に読み、高校で再読し、成人を超えて絵を描き始めてから、行き詰った心に救いを求めて三読した。
何よりこの主人公の、自然を有りのままに愛する姿に惹かれたのだ。そして少し成長してからは、生活に押し流されながらも、自分の内心の喜びをごまかすことの出来ない主人公に共感した。
厳冬の雷電峠の雪原に踏み込み、雪に覆われた山に向い、食も忘れて激情のままにその山を . . . 本文を読む
館内は人が少なかったために私達は随分ゆったりと絵を楽しむことができた。一枚の絵を胆のうするまで眺めると、私たちは自然に歩調を合わせて次の絵に向かって歩いた。その先に木田金次郎の絵があった。
「この人は有島武郎の『生まれいずる悩み』の主人公のモデルになった人です。」
絵の前に立つと、里依子はそう説明して私を見た。
木田金次郎の絵は3枚掛けられている。その中で馬の絵が私の気を惹いた。高い山の裾野 . . . 本文を読む
森田沙伊の絵の前で里依子は、この絵は前に送った絵ハガキの画家だということを私に伝えた。私はそれをよく覚えていた。
里依子から送られてきた絵ハガキの中の1枚が、森田沙伊の絵で赤い服を着せられた人形を描いたものであった。
その絵ハガキを見た瞬間、内側からうごめくような生々しい生命力を感じたのであったが、今目にしている絵もまた、絵柄や色調は全く違っていたにもかかわらず同じ感覚を私に呼び起こさせた . . . 本文を読む
何人かで美術館に行くと、たいてい私は気に入った作品の前で動かなくなる。相手のことを忘れて絵に没頭してしまう悪い癖があった。気付くと私一人が取り残されていることが常だったのだが、この日も私は片岡球子の富士の前で自分を失っていたのだった。それがどれ程の時間だったのか分からなかったが、ふと我に帰ったとき、里依子は私の横に立って熱心に絵を眺めていたのだ。
それをどのように表現しても、その時の里依子 . . . 本文を読む
いつになったら私にこんな絵が描けるのだろうか。片岡球子の絵を前にして私はため息を漏らした。
私はこのような大胆な表現をいつも夢見ながら、それを実現しようとする前に崩れてしまう脆弱さを持っている。片岡球子の絵には私には越えることのできない精神の峻厳さを感じるのだ。その迫力を私はただ羨ましいと思うばかりだった。
私は富士から眼を放すことができず長い間立ち尽くしていた。本物の絵に出合うと、反発す . . . 本文を読む
美術館は合掌造りを模した近代的は建物で、まだ新しかった。それを里依子に言うと、この美術館が出来てまだ4.5年だと彼女は答えた。
館内は人がまばらで、ゆったりとしていた。大きすぎず小さすぎず、ちょうど心にぴったりくるスペースの1階フロアがあって、常設展示室が見えた。
自然に私たちは展示室に入って行った。するとすぐに激しい色彩が私の目に飛び込んできた。300号はありそうなキャンバスに描かれた富 . . . 本文を読む
西18丁目という駅から再び地上に出て、しばらく歩くとそこはもう道立近代美術館である。そしてこのあたりは、西の方に山並が近かった。
のんびりとして横に広がる山々は、広い広い平原の向こうに雪をかぶっていた。
「あれが大倉山です」里依子が山を指差して教えた。
その山は一番手前にあって丸くこんもりとしていて、中央から長い鼻のように白い直線が垂直に伸びていた。札幌冬季オリンピック会場としてテレビ . . . 本文を読む
「どうしたの?」私が突然笑ったので、里依子が不思議そうに私を見た。
私は昨夜の居酒屋の話をし、札幌の地下鉄の車輪のことを説明した。ここでは普通なんですけどねと、里依子が笑顔で還した。
そうすると、夏、この地下鉄には風鈴が付けられるのだという板前の信じられない話も、本当のことなのかも知れない。思いだして私は里依子にそのことを聞いてみた。すると彼女は頷き、車両の天井を指差した。そこには大きな通 . . . 本文を読む
無理をしている。そう思うと私は里依子が健気なもののように思えてならなかった。考えてみれば、千歳に発つ前日に突然電話をし、会いたいという私に田舎に帰る予定だった里依子がそれを取りやめて会ってくれたのだ。
しかも明日、大切な仕事を控えていてどうしても休むわけにはいかない体を、風邪気味であるにもかかわらずこうしてやって来てくれた。それは私にとって言い知れぬ喜びだった。
同時に私のためにこうまでし . . . 本文を読む