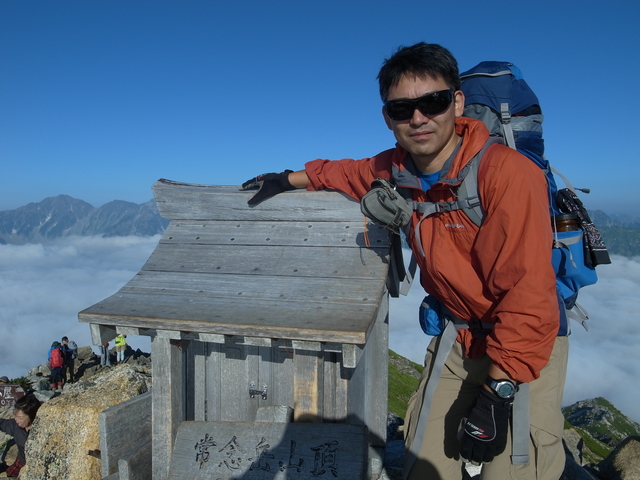「悩んだときは哲学者に聞け!」小川仁志著という本をまとめた記事があった。
なるほどというところがいくつかあったのでアップしてみる。
・人生に意味を求めなければ強い心で生きられる
・身体をいたわってあげることが、心をスッキリさせる方法になる
・消費による心の満足は悪いことではない
・主体的な決断をすれば、不安は解消され、必ず絶望は乗り越えられる
・恋愛がうまくいかないのは当たり前だと思うとラクになる
・説得ではなく合意を目指すことで他者とわかり合える
・幸せになろうと願って行動をおこせば、幸福がつくられる
・与えられた状況に積極的にかかわっていくことで、人生の目標が生まれる
・人間に与えられた時間には限りがあることを意識すると頑張れる
・欲望は新しい世界を切り開くための武器になる
・何でも経験してみることが、人生に深みをもたらす
・知識はものを考えるための道具。「役立たせよう」と思うことが大事
・成長したいと強く願うことが、成長へのエネルギーとなる
・あらゆるものはシステムとして考えることでシンプルになる
私もいくつか加えてみよう。
・心(意識、無意識)は身体の一部もしくは現象である。身体の動きや働きを観察することで心をよみとる。
・やる気の無い時は、目の前のちいさいことに集中してリズムを作る。
・人生に意味は無い。ただ、野垂れ死にがあるだけだ。それを意識したときから本当に生きはじめる。