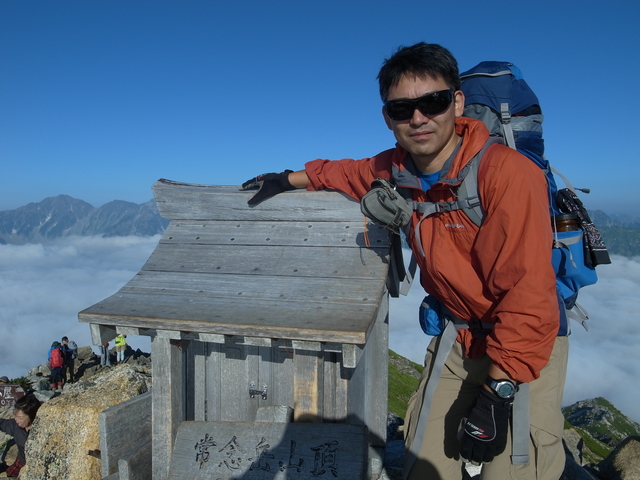「ZOO」を読了。
乙一という作家のことはよく知らない。今まで日本の作家はあまり読まなかった。最近、いろんな作家の作品を読んでいる。当たり前だが、いろんな人がいて、よく選ばないと時間がいくらあっても足りない。
ちょっと今まで読んだことのないタイプの短編小説。
構成が技巧的で唸ってしまう。しかし、ちゃんと感情の起伏が生まれる。只者ではないうまさ。
10編の短編小説が収録されている。当然、好きなもの、それほどでもないものがある。
個人的には、「カザリとヨーコ」 「陽だまりの詩」が好きである。
どれか1つあげるとすれば、「カザリとヨーコ」、児童虐待の話である。
もし、親が子供を虐待しているとすれば、その子の世界は想像を絶するほど厳しいものになるだろう。小さい時は親との関係がほとんどだからである。
しかし、その中で誰でもいいからその子供に温かさを示す人がいれば、その子の人生は大きく変る。人間は、ひどさも覚えているが(いつか弱まる)、温かさはもっと強烈に記憶するからである。人から受けた温かさの記憶があれば、人間はそれだけで力強く生きていける。経験的に。
そういうことがうまく表現されている短編である。
短いしどれもそれぞれに変わっているので飽きないと思う。それにしても才能のある小説家だ。