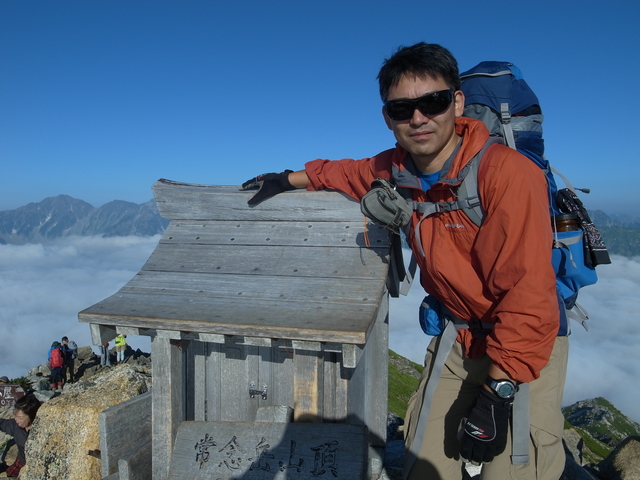アマゾンのKindle Unlimited、電子書籍の読み放題に加入している。
そこに「働くおっぱい」というエッセイ集があったので、ダウンロードして読んでみた。
著者は、男なら一回は見たであろうと思われる国民的AV女優の紗倉まなさんだ。
冒頭から笑ってしまった。
「AVの撮影現場は、肉棒という刀に狩られる戦場である…と、私は思っている」と。
でも読み進めていると、ちょっと印象の違ったエッセイだった。
AV女優という特殊な職業ではあるが、そこには書かれていたのは、働いている女性の苦労や悩みであり、一生懸命仕事に打ち込んでいる女性の姿だった。
たとえば、引っ越し屋さんが「重たいダンボール100個を五階まで階段で運んだんですよ。チョー腰いた」というのと「昨日、21Pしてフェラしまくって、うっかり顎が外れそうになったんですよ。腰も痛いっす」というのに、基本的な違いはない。仕事の内容が違うだけだ。
問題は、セックスが男女の愛情に深く関わっていることである。
回転のはやい世界で、七年間も人気女優なのだから、彼女が非常に魅力的な女性なのはいうまでもない。
男性から言い寄られることもあるし、恋愛もしているだろう。
しかし、その場合、セックスに関して、仕事と愛情の切り替えをうまくしなくてはならない。
しかし、そうは簡単にはいかない。
彼女たちは、世間の先入観と戦わざるをえないし、少しだけ心に傷を負う。
でも、その辺の心の動きが、コミカルに描かれていて、読んでいて気持ちのいい内容になっている。
彼女は、学生の時に空港の滑走路の整備点検のインターンをしたそうだ。二ヶ月間、伊藤英明似のお兄さんと一緒に。
その時の文章を、ちょっと紹介しよう。
「遠方のイベントがあって、その空港を利用するたびに、あのときのことが浮かんできて、時々、ひどく切ない気持ちに駆られる。記憶の中で、ロメンパッチや点検車が淡い青春として深く刻まれているのは、お兄さんに瞬間的なときめきを抱いたからではなく、あの夜の自分が、なりたくてももう二度となれない姿であり、今の自分にはなれない ”理想の社会人”という姿であったからだと思う。だからこそ、滑走路はずっと美しく輝き続けているのかもしれない」