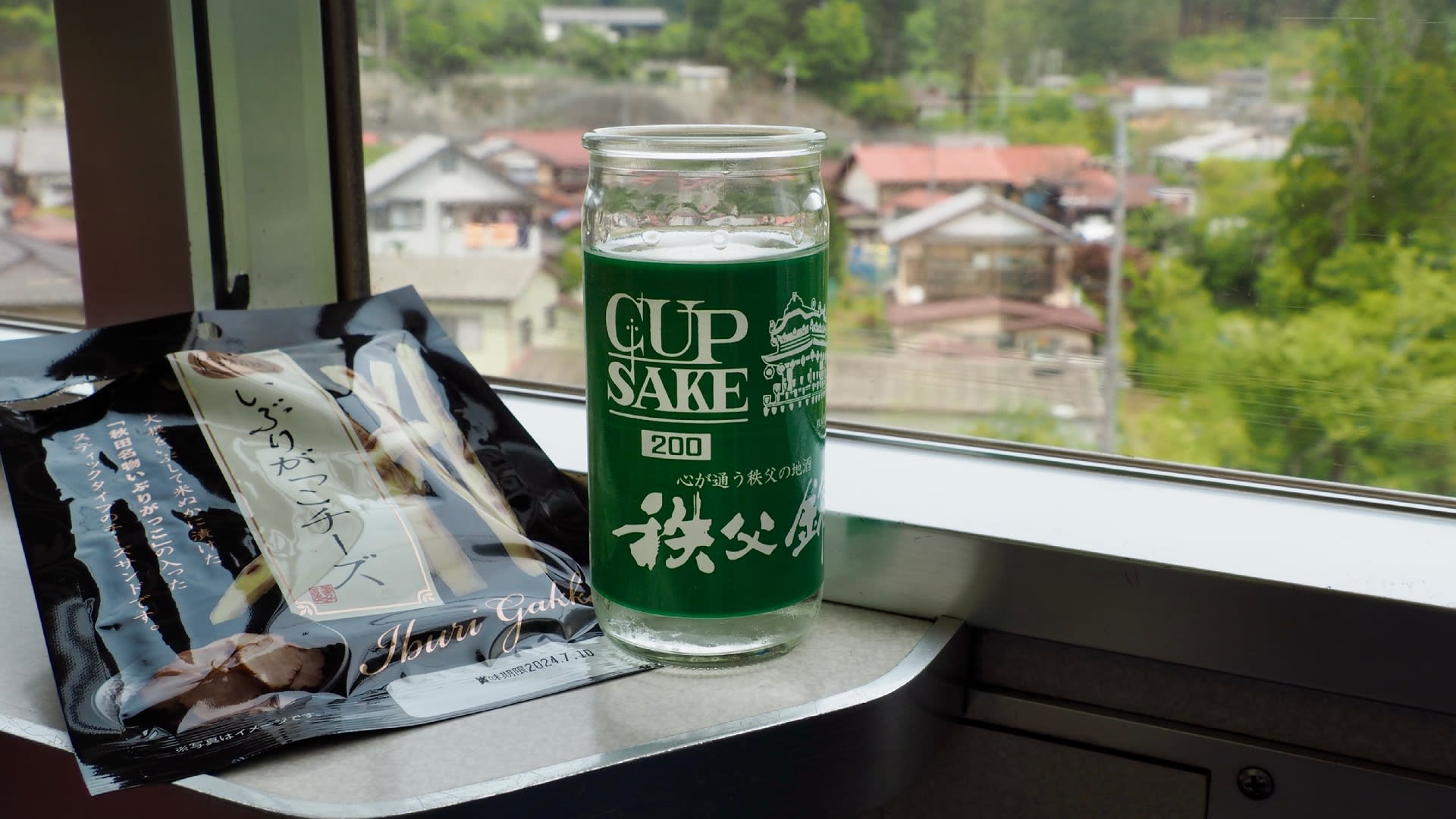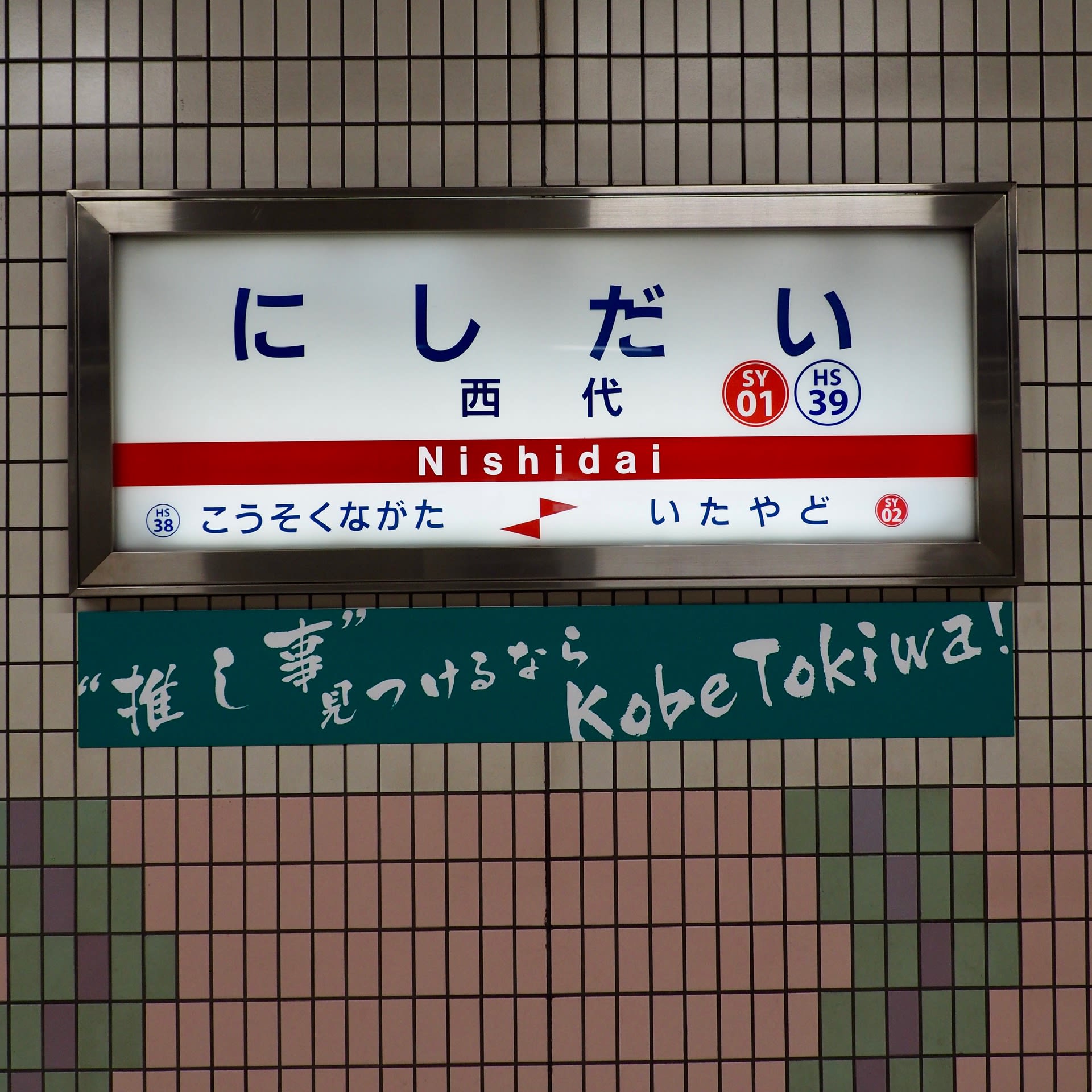地上ホームからローズバーミリオンのGSE70000形が滑り出して来た。
こんな優雅な車両で箱根まで旅行したいと思うけれど、呑み鉄の旅は有料特急には乗らないのがルールだ。

そしてボクはと云えば、各駅停車の本厚木行きでのんびりと小田急線の旅を始める。
2019年度に完成した複々線、内側の急行線を快速急行やら急行が後から後から各駅停車を追い越して行く。

最初の途中下車は祖師ヶ谷大蔵駅、ここにはかつて特撮の円谷プロダクションがあった。
駅前広場には巨大なウルトラマンのモニュメントが屹立する。正に僕らの世代のヒーローなのだ。

ウルトラマン商店街(祖師谷きた通り)を北上する。
ある意味名所となった木梨サイクルを行き過ぎると、赤い看板の「祖師酒家」が見えてくる。
開店時間に飛び込んで、先ずは町中華で軽く一杯といきたい。


ゴマだれをたっぷりかけて “蒸し鶏サラダ” が登場。ヘルシーな一皿でしょう。
よく冷えた一番搾りのジョッキを片手に、さっぱりと蒸し鶏が美味しい。


“焼き餃子” を一つ放り込むと、ジュワーっと肉汁が口に広がる。
爽やかな “レモンサワー” で流して、ちょっと一杯のつもりが、案外満腹感のある昼呑みなのだ。

多摩川を渡って来たのは最新鋭の5000形、なかなか精悍なマスクの男前だ。
河川敷の野球少年を眺めて、小田急線は登戸から神奈川に入る。ここで急行に乗り換えて先を急ぐ。

新百合ヶ丘駅では1番線に待避して、追いかけてくるフェルメール・ブルーに先を譲る。
特急はこね93号は北千住を出て、大手町、霞ヶ関、表参道に停まって、千代田線を潜ってくる変わり種だ。

二度目の途中下車は伊勢原駅、北口に抜けると大山阿夫利神社の大鳥居がある。
そして④乗り場から「かなちゅう」の黄色いバス、臨時便に乗車して大山ケーブル山麓駅へ。
477‰の最急勾配をケーブルカーで登って、終点の阿夫利神社駅は標高678m、
振り返ると鈍く光る相模湾の向こうに三浦半島が横たわっている。

大山阿夫利神社を詣でた後は徒歩で山を下る。途中の大山寺は関東にあって紅葉の名所だ。
大山寺へと続く見上げるような階段の両脇には、ずらりと三十六童子像が並んでいる。
その前掛けと、階段に覆いかかぶさるモミジの色付きが、鮮やかな赤を競って楽しい。

弱々しい午後の陽を背負って、緑の切り通しをEXE30000形が新宿へと戻って行く。
大山に登ったら、伊勢原のひとつ先、鶴巻温泉に降りてくると良い。

鶴巻温泉駅の近くには公営の日帰り入浴施設「弘法の里湯」があって山歩きの疲れを癒してくれる。
湯に浸からないまでも、足湯に浸せば、帰りの小田急線に乗る足取りも軽くなるだろう。

そしてボクはハイカーとは反対のホームから、西陽を追いかけて小田原までラストラン。
この先の小田急線といったら、大小のカーブをくねり、谷間を抜け、トンネルを潜り、地方の幹線を行く様だ。
15:25、各駅停車は小田原駅の7番ホームに終着する。鶴巻温泉からは約30分の乗車となる。

冬至が近いこの頃だから、日没までは30分を残すだけだ。西口の北条早雲公にすでに陽は当たらない。
馬上の北条早雲公が睨みを利かせる先には小田原城天守閣があるはずだ。

急足で八幡山古郭東曲輪跡に登ってみる。
曲輪は戦国時代の小田原城中心部で、東海道新幹線を隔てて小田原城を一望するスポットだ。
深い青の相模湾を背景に、夕陽を浴びた天守閣が美しい。

日が暮れて小田原駅に戻ってきた。今宵は駅前東通り商店街(おいしいもの横丁)で一杯。
老舗の練り物屋や豆腐屋の種を仕込んだご当地おでんを梅味噌で味わう「小田原おでん本陣」に伺う。
この店、神奈川県下13蔵の日本酒を楽しめるのがポイント高い。


先ずは神泡の “The Premium Malts” を呷る。
本日のお刺身は、“ハナダイ” に “シロウマ” それに “カツオ”、厚切りの旬が嬉しい。


刺身に合わせて日本酒へと急ぐ。丹沢の “松みどり” は穏やかな香りの純米酒。
ボクは断然に冷酒派だけれど、これは燗をつけても美味しいんじゃないかな。やや辛が刺身によく合うね。
おでんは季節限定の「秋冬おでん」から択んで “大根そぼろあんかけ”、三種の薬味から柚子こしょうが良いかな。


もう一品は “ゆず味噌田楽焼きとうふ”、ご当地の梅味噌を付けながら箸で崩して美味しい。
大井町の “曽我の誉” は、酸味が強くて苦味も感じる純米酒、昆布とカツオ節の出汁と相性がよい。
ほどよく酔いがくる頃には、人気店の外には席待ちの列が出来ている。
それではっと升に残った純米酒をグイと呑んで「おあいそ」しましょうか。
ほろ酔いで小田原駅、帰りくらいはロマンスカーに乗ろうか。缶ビールでも買って。いやまだ呑むんかい?
小田急電鉄 小田原線 新宿〜小田原 82.5km 完乗

<40年前に街で流れたJ-POP>
Chance! / 白井貴子 1984