 (ゴマブックス刊。)
(ゴマブックス刊。)七色の虹といい7つの海といいます。人間が一度に識別できるのは対象物が7個前後までです。
それ以上の数を認識しようとすると、7個くらいの対象物をひとまとまりにして、このまとまりを1チャンクと呼ぶことにすると、今度は人間は7チャンク前後まで識別できるようになります。ざっと49人ですね。
今度は7チャンクをひとまとまりにして・・というように段階的にまとめなければ、人間はたくさんの対象を認識できないのです。(このことを実験心理学的に証明したのが、「マジカルナンバー7プラスマイナス2」という超有名な論文です。この論文は 2013-10-21 の記事でもご紹介しました。)
狩猟採集時代には人類は30~40名の「バンド」という単位で行動しました。1家族7人で7家族という感じでチャンクが構成されていますね。石器時代にはその程度の人数を認識できればそれでよかったのです。
ところが、人間が何万何十万と集まって国家を作ろうとすると、まずおおまかに大集団を7つくらいの集団に分けないと認識できなくなります。そこで採用されたのが身分制度でしょう。
つまり、身分制度は組織(の成員)を認識する手段のひとつなのです。士農工商は4段階でインドのカーストも4段階ですよね。身分が7段階より多くなると今度は認識できないのです。身分制度というものは、人間が国家を成すときに必然的に要求されるチャンク分けの一方法だったというのが私の仮説です。
能力でチャンク分けすると、社会が不安定になります。(身分制度にくらべて、能力はテーマによって異なるから。)だから、企業では身分制度に代わって「年功序列」によってチャンク分けを行うことによって、企業集団を認識可能にし、組織の安定化を図ったのではないでしょうか?(社長、役員、部長、課長、係長、ヒラという分け方も7段階を超えていません。)
「年功序列」制度は、こうした人間の基本的な認識能力の限界にも基礎を置いていますから、軽々に壊せないのだと私は考えています。












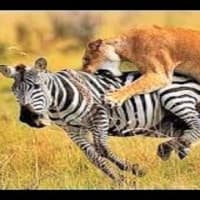






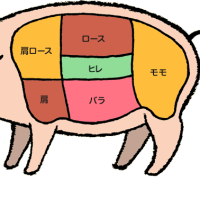
年功序列システムは日本文化によるもので、(7プラスマイナス2という)認識能力の限界とは関係がないというご意見と承りました。
そのとおりですね。そうでないと、世界中どこでも年功序列が採用されることになりますものね。
正確には年功序列システムは日本文化に根ざすが、その際の序列の数は7個程度以上にはなりえないと、はっきり分けて述べるべきでした。
今後とも鋭いコメントをお願いいたします。