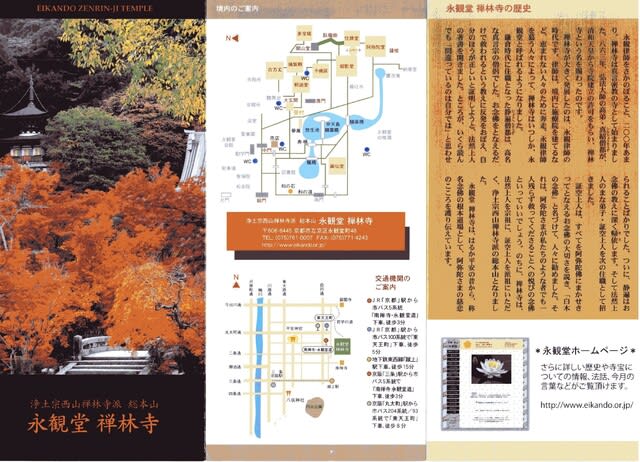午後からドライブ。
杉坂の道風神社を目指します。
以前に京見峠から行ったときは
行き違いに失敗してガードレールを擦ったので、
今日は162号線で高雄方面から回りました。
杉坂口からの道が狭い!
ようやく到着、1時間以上かかってしまいました。

入口に架かる橋。

由緒書き。
ふだんは無人のようです。

北山杉とカエデの対比がおもしろい。
茶色は枯れ葉。

この池の水で墨をすると字が上達するとか!?
ペットボトルを持っていけば良かったかも。
和香水の碑、お堂の左側。


読めない・・・となりに解釈表記板。

「お札希望の人は**さん宅へ」と案内があったのでいってきました。
しばしおしゃべり。
そこで教えてくれたのは、
「道風神社のカエデは主に黄色の紅葉。高雄などの赤い紅葉とは違っているでしょう?」
そういえばそうですね。品種が違うんでしょうか。
お札をいただいて、帰り道、平岡八幡宮へ。

実は往路、「花の天井特別公開中」の看板をチェックしていたんです。
ここは2回ばかり行っているけれど、
公開の時期と外れていたのでリベンジです。
宮司さんの解説と大福茶付き。
もともとは弘法大師が神護寺の守護神として創建した京都最古の八幡宮、
足利義満が再建して花の天井が作られたとのこと。
格天井に極彩色でさまざまな花の絵が描かれていて紅葉も山桜もジャスミンも・・・。
華やかな北山文化の一つですね。
廃仏毀釈の波の中寺域も狭くなり、神仏の分離も行われて別々になったそうです。
さて、境内さまざまな椿があって、先祖返りではないかという金魚の葉っぱ。

木に着いているのも観察。宮司さんの案内なしには気付かないよね、こんなの。
花の天井の建物内は撮影お断りでしたが、他の場所はOKでした。

芸能の神様の弁天さんが蟇股にあったので、拝んでおきましたよ。
弁天さんのしたには龍。
色は再現修復したものですって。
神社にはなかなかお金がないので、修復もままならないようですね。
早咲きの椿がちらほら咲いていました。

以前来たときは椿の終わりかけの時期だったし、
こんどは花真っ盛りの時期に来たいものです。
宮司さんの説明を聞いたから新しい視点で見ることができそう。
帰り、道を間違えました!
福王子から観光道路に入ってしまって仁和寺の前!
ほんとは天神川通に行くべしだったのに。
馬代通だとかふだんは選ばない道をくねくね。
予定より帰りが遅れてしまいました。