 | 秀吉と利休新潮社このアイテムの詳細を見る |
今年は小説は野上弥生子を中心に読もう、ということで、森に次いで読んだのがこの本です。新潮と中央公論社の二社が文庫にしているので、長編では一番手に入りやすいかもしれません。
正直、利休には興味がなかったのです。朝顔を全部切ってしまって一輪だけ部屋にかざってみせた話とかがどうも好きになれなくて。
しかし、読み始めてみると、そんないいかげんな好き嫌いなどけちらされてしまったようなかんじです。人物描写にのせられてぐんぐん読み進み、豪華絢爛な安土桃山文化の描写にわくわくし、茶の湯で代表されている芸術、芸術家とその庇護者の関係の問題提示に頭を抱え込み、最後に綿密にはりめぐらされた構成のすごさに唖然としてしまいました。
あらすじは次のとおりです。
天下一の茶頭であるだけでなく、政治顧問としても秀吉に尊重されていた利休が、久しぶりに聚楽第を退き、堺の自宅でゆったりとした一日を迎えるところから話ははじまります。
秀吉は自分の芸術を実現させてくれる大切な庇護者であることは認め緊密な提携を結んでいます。しかし、ほんの数年前までは、地位も自分よりも下であれば、茶の湯では、せいぜい「まあ、まあ」の腕前しかもっていない秀吉を今は関白様と呼び、その気まぐれにふりまわされるのに、疲れを感じています。秀吉は秀吉で、利休の才能を愛し、重んじていながらも、時に憎まずにはいられません。そして互いに互いの気持ちがわかっている、と、話の始めから、この二人は愛憎相反する関係にあります。
秀吉の弟である秀長は、利休の才能を認め、庇護しますが、秩序を好む能吏の石田三成にとって、秩序の範囲外にある利休は取り除かなければならない存在として映っていました。
二人の間に波風を立たせたのは、権力者秀吉の癇気でした。親友の古渓和尚は追放され、利休の一番弟子の山上宗二は無残に殺されてしまいます。利休は抵抗の気持ちを抱いていきます。そこに秀長が病死します。後ろ盾を失った利休が、不用意に「唐御陣が、明智討ちのようにいけばでしょうが」と口をすべらせたことが、三成に利休を咎める格好のきっかけを与えます。あくまで謝罪を拒む利休に癇癪をおこした秀吉は、利休の切腹を命じます。「憎く、腹の立つ、しかも掛け替えのない、そう思うことによっていっそうこころの惹かれる、それでなお憎く、腹の立つものと完全に絶縁するには、殺してしまうほかはない」と考えたからです。
ここに書かれている利休は、清濁を飲み込む一種の怪物です。至高の芸術家である一方、保身にまわりながらたくみに有利に物事を進める政治家としてえがかれてもいれば、商人らしく、茶道具の売り込みに力をいれる姿も描かれています。自分の美意識が耐えられないというのを理由にそして、才能にあふれているのに反抗的で扱いにくい末息子(これはフィクションの人物)に頭を悩ませる親でもあります。
芸術一つとっても、利休のふり幅は大きく、奥も深いです。
たとえば、利休の死の原因の一つというのであげられるのが、秀吉と利休の美意識の違い。侘び茶、数奇屋に代表される利休の美意識が、黄金の茶室に代表されるような豪華絢爛を好む秀吉の好みと対立していたと言われています。
しかし、この本の利休は、無に近づけた美の創造を楽しむ一方で、黄金の茶座敷が見せる過剰なで豊満な華麗さにも意欲を注いでいます。一つのスタイルを突き詰めると、他を排除したくなるものではないかと思うのですが、それどころではなく、極端にちがうものも許容し、のみこんでしまうというのは、一筋縄ではいかない大きさを感じます。
そんな利休がたてる茶は、茶が自然に茶碗に湧き出てくるように見える、というのですから、まるで人間の力をこえた仙人が、仙術を使っているようなものです。ところが、頭の中で芸術の構想をねっても、それを実現させ、世間に認めてもらおうとすると、バックアップが必要です。それで秀吉のような庇護者が必要なわけですが、秀長のように心から敬愛できる人物であればともかく、よさはよさと認めながらも、どこかうんざりし、軽蔑を感じずにはいられない権力者であれば、何かのきっかけで抵抗せずにはいられなくなるのかもしれません。














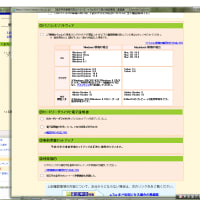





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます