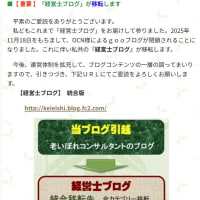■【若狹の生意気言ってすみません!】4 投資・スタートアップ・個人の資産運用の前に
■【若狹の生意気言ってすみません!】4 投資・スタートアップ・個人の資産運用の前に


■ 筆者挨拶
特定非営利活動法人「日本経営士協会」首都圏支部の経営士 若狹晃司です。
当ブログに、私の経営士として日常考えたこと、感じていることをラフなスタイルで掲載させて頂きます。「生意気なヤツ!」と言われるのを覚悟で出来る限り本音のお話をしていますので、よろしくお願いします。
■【若狹の生意気言ってすみません!】 No.4
~~~ 投資・スタートアップ・個人の資産運用の前に ~~~
若狹の「生意気言ってすみません」と言い訳しながら言いたい放題言うコーナーの第4回です。毎回皆様の御気分を悪くさせて本当にすみません。で、話に入ります。
先日、当協会でスタートアップ研究会というものが立ち上がりました。若い方々にスタートアップのプレゼンテーションの表彰制度やスポンサー企業を募集したりする事業です。巷でよくある手法ではありますが、当協会の齋藤先生が緒方先生を「崖の上から落とす」くらいの【勢い】で説得し立ち上がったようです。私には真似ができません。敬服致します。この日本にスタートアップ企業、ユニコーン企業が多数輩出されるようにしたいというのが本研究会の目的と心得ております。陰ながら応援です。
本事業ではプレゼンテーション表彰に向けて色々なイベントが開催されると思います。研究会の資料から政府が税制の他各種制度等で応援し官民挙げて動いているのがわかりました。事業が軌道に乗るまでのメンバーの奮闘、投資家ファンドの資金投入などごく「あたり前」のことかもしれませんが実に詳細に記載されていました。
ここで個人的な話です。3月の中旬に尼崎へ行く用事があり、新幹線に乗りました。自由席1号車(1・2両しか自由席は通常月はありません)の2席側の窓際に座ったところ、後から外国人の若者が相席されました。Can I have some conversation ?と声を掛けた所、「いいっすよ!」と日本語で返されました。二十歳のカナダからの国費留学生でした。京都までアメリカ大陸英語とイギリス英語の違いや彼の海外経験など、楽しく過ごさせて頂きました。「あなたは将来何をしたいですか?」と質問したところ、彼から「日本で起業したい!」との答えでした。彼は心理学を日本で学んでいますが、これをビジネスで活かして起業するということでした。「君はきっと成功するよ!」と伝え別れました(特に名前住所などはメモしておりません)。
何が言いたいかというと、このカナダの若者のチャレンジ精神、開拓精神、意気込み、生き様、そういうマインドが根底にあるべきで「これぞスタートアップ精神だ!」と私は言いたいです。彼が言うには「日本はチャレンジしがいのある機会が豊富な国だ」そうです。そうなのか!?!と多少ビックリしました。彼は高校時代に香港にも短期留学したり、外国に対する興味関心が強く、日本語を勉強した際に覚えた漢字でなんとか中国語でコミュニケーションを図る?という無謀なことをやったり、様々なチャレンジをしていました。(実際には中国語の四音というイントネーションが困難で結局英語で話したそうです。)
欧米のスタートアップの業界は熾烈な競争がある一方で日本はそこまでではなく、生活面でも安全で人々は真面目な国民性で、こんなスタートアップに恵まれた環境は無いということでした。なるほど本や新聞ではわからないことが多いなと感じました。また、彼は人を引き付ける何かあるな、と感じました。私も何か引き出す力があるのかも?と思いました(自惚れです)。
話が脱線しましたが、スタートアップがなぜ日本では育たないかという根本原因はこのマインドにあるのだろうというのがこの話の結論です。経済産業省等が進める手段・方法がどんなに多く施策されても、事業を起こす「ヒト」の心、心de経営、マインド、等々が
あまりに日本は出来ていないからこんな状況なのだと思いました。また、マインドのある日本の若者に必要なのは、先にスタートアップして成功したり、結果を残したりした先駆者との交流等を行って、マインドをさらに磨き、吸収し、突き進むという環境を提供することかもしれないと思いました。
しかし、それでも何か違う感じがします。与えるのではなく、自分から獲得するのが事業家(起業家・企業家)ではないでしょうか。国家公務員エリートが設定した方程式が成功方程式とは思えません。そもそも彼らは受験戦争エリートであって起業戦争エリートではありません(今や受験戦争は死語であり中国・韓国の学生用語)。政府の施策で成功した人が多数いるわけでもなく、政府の施策でGAFA、マグニフィセントセブンが生まれる訳でもありません。あくまでインフラです。成功する者は自らチャンスを獲得します。人脈すらそうです。孫正義はシャープの有名副社長兼技術者「ロケット佐々木」(佐々木正氏)を自ら尋ねて翻訳機を買っていただき、その後の起業資金(当時1億円)にしたということです。これが本当の「起業家」であり、スタートアップです。
企業家精神に溢れる人との交流や親交からマインドが触発されたり、同じマインドの人が集まって最初の企業の「核」となったりするのではと私は考えております。成功する手段や道筋ばかりを設定したところで、企業家精神そのものを育てなければ何も生じません。そこが国家公務員の方々はおわかりになっているのでしょうか。明治維新の官僚達がいかに優れていたかわかります。
また、スタートアップやベンチャーに関する株式やネットによる資金調達の話が出てきますが金融機関も大事な関係と私は考えております。新興企業の事業が軌道にのり始めると様々な人が集まり、それがさらに銀行の有名支店長への紹介に繋がり、様々に成功していった例もあります(個別の会社は守秘義務があり言いません)。実際に自分の元上司の話では、「この会社の社長に会ってくれ。」という話が法人新規班のみならず地方財界の有力者等からも舞い込んだりしたそうです。そのくらいメガバンクのネットワークは凄いものがあります。信用金庫様のとある方から「ウチも上場支援している会社がいっぱいありますよ。」(裏には「信金も結構やってる!舐めるなよ!」というニュアンス)と言われたことがあります。預金総額の規模に係わらず上場を目指す世界では、金融機関同士凄まじい競争が繰り広げられているのでしょう。メガ銀行が本気で支援するとなると不動産・証券・海外展開、様々な関与があり、全国展開・海外も含めた全世界展開となっていきます。マネーパワーの力です。
時価総額10億円超がユニコーンの定義らしいですが、時価総額の強調ばっかりのような印象がします。時価総額の金額のレベルというよりマネーワパーの本質がどうなっていうかが問われるべきだと思います。マネーパワーの本質は、ヒト・モノ・カネ・情報が多大に流入する効果のことで、だからこそ「時価総額が大きい!=凄い!」ということです。単純に株価を上げれば良いという問題では全くありません。上場を目指すことが社内で決定されると、「ヒト・モノ・カネ・情報」が流入し且つ各々が【良質化していくスパイラル】になり、企業が大きく成長していきます。上場をする会社の社員の方と何度か話をしたことがありますが、上場までの社内の雰囲気や動きなどほんの一部ですが成長の躍動を感じました。マネーに引き寄せられる様々な人が従来出来なかった部分をあっという間に補強していきます。大変な状況ですが、それに耐えないといけない。ここがポイントなのだろうと思います。これも起業家・社員のマインドの問題ではないでしょうか。
言いたい放題言いましたが、日本経営士協会の取り組みが明日のスタートアップのみならず将来の日本の産業を強化することに貢献できれば幸いです。そういう方程式は存在せず、あくまでマインドを作らないと何も起きません。「心de スタートアップ」なのかもしれません。アイデア・思想発想を収益に変えることがスタートアップ起業ですから、「心(マインド)」が一番大事だと思います。
スタートアップやユニコーンの件で、「銀行が当初から関与していると様々な点で金融機関が彼らの成長の芽を潰して台無しにする。金融機関ってとんでもない。」との話を聞いたことがあります。おっしゃる通り、よく「あるある」の話だと思いました。というのも金融機関はお金の出し手というだけで上から目線、資金管理目線が本能的にあります。それだけでなく、金融機関では毎日営業報告書をネット(以前は紙)で報告して、毎日何があったか、どういう成果(失敗も?私はしっかり報告しましたが)があったか、など報告と計数管理が凄かった記憶があります。そういう事に慣れていない方(含む公務員)から見れば、「アイツら銀行が成長の芽を潰してる!」となるでしょう。イチイチ細かいことまで報告を求め、いつまでに何をどうした・どうなった・どうする?と毎日聞かれます。こういう業界体質ですから金融機関がスタートアップ支援や企業支援をする際は相手に対する十分な配慮が必要と思います。実際失敗例や批判例が多々ある以上は。かといって金融機関は短期嗜好・目先思考ばかりでビジネスセンスはゼロだ!と徹底的に貶す人もビジネスマンとしてはいかがなものかと思います。
銀行員の中にもスタートアップを上場させた人もいます。私の別の元上司が何某スタートアップ(ベンチャー企業)に副社長として招聘され、本当に睡眠時間や体力を削り、過激な業務にも耐え上場に成功させました。私が銀行の中でも最も尊敬する方のお一人です。新店舗開設の際の支店長としての最初のお言葉は「(この街の)街作りに貢献しましょう!」がスローガンでした。預金を集め貸出をしてNo.1にしましょう!ではありません。地域・お客様に貢献することが我々の使命だ!とおっしゃっていました。そういう優れた銀行マンもかつてはいました。金融機関の者がすべからく糞でゴミだというのには反論したくなります。公務員とて別の意味で職場文化バイアスで問題はあるぞと言いたいです。上記の元上司は上場の数年後病気になりお亡くなりになりました。このくらい頑張らないとユニコーンだのスタートアップだのは夢で終わってしまうのだろうと思います。身近な話だからそう思っているとしたら私の見当違いですが。
いろんな話をしましたが、企業(起業・ビジネス)というのはマインドが極めて重要なファクターであることがお分かりいただけたかと思います。
次の話に移ります。
最近NISAだの、グロカン(グローバルカントリー)だの、(金融の)資産運用について政府自ら宣伝しており金融界・証券界は恩恵に預かっていると思います。小学生から金融リテラシーを学べというイベントも散見されます。金融界出身の自分としては、半分OK!でもう半分は「?」という気持ちです。
ネットで伝説の投資家ウォーレンバッフェット氏のYouTube番組をたまたま発見し、視聴しました。とても参考になりました。一例として「投資は習慣である。投資の習慣が無い者はお金持ちになっても投資をしない。感情によるキャッシュコントロールが出来ない者はいくら収入を上げてもその分金を浪費してキャッシュは残らない。無駄を省き少額からでも始めない限り投資で成功は無い。」などなどです。よく世のFPは人生のライフ・サイクルを念頭に資産・資金の運用をしましょうと言っております。しかし、そのライフサイクル(人生の金融設計)の前の段階で、日々の生活における「感情によるキャッシュコントロール」ができるようになっていなければいけないのだと、あたり前のことが話されていました。
また、投資は少額でも始めないといつまで経っても自分の投資スタイルが確立できません。これも大事なことです。一度やり始めると株価―為替―金利の三面バランス、日々の出来事などさまざまな事に注意や関心が生まれます。私自身は少額であれ自らの考えで積極的に投資をしようとしたことがなく(本当に少額しか運用経験は無し)、「先を読む習性・習慣」は身についていません。確かに貯金至上主義から抜け切れていない私には投資を語る資格もないでしょう。私の別の別の上司など資金運用専用PC2台を机に並べて運用で儲け、車を数台買い替え、家も1棟買い替える程です。私のFP1級の国家資格は何の意味があったのでしょうか。名刺に掲示するのがお恥ずかしいです。
それでも言いたいことがあります。投資は貯金とのバランスが1丁目1番地だということです。住宅ローンの担当をしていた頃の話です。「住宅ローン借入のある家はそもそも貯金など無理ですね。」と私がローン課長に話をしたところ、「住宅ローンを返済しているからといって貯金を全くしない人はいないよ。返済額と同額とまでは言わないが必ず将来必要資金について貯金をしているのが大半だよ。見当違いだよ。」と諭されました。なるほどその通りです。ということは、投資というものも同じく、人それぞれの金融嗜好により違いはあるものの、返済(借入や家賃)・投資・貯金のバランスを調整しながら長期に亘って行うべきだということです。投資をするなら同額を貯金するという意味ではなく、生活プランに合わせて一定額を必ず投資だけでなく貯金もやって初めて生活が長期にわたり安定するということだと思います。「貯金が貯まったら運用するなんていつになったら投資できるの?運用に良好な時期を外してしまうよ!」と言われてしまいます。とはいえ、やはり、資産運用はあくまでバランスだと思います。家計も企業会計と同様に、PLとBS、CF計算書を念頭に入れ、キャッシュコントロールしながらBSも成長させるということだと思います。PLの最後に捻出される「利益(当期利益)」を全て有価証券等の投資に回す企業は存在しません。個人の家計も同じことではないかと思います。
若い頃(地主新規工作班だった頃)、お客様から言われた言葉に「四・六(シブロク)」というのがあります。金融資産4割、土地建物6割の比率で保有・運用するのが鉄則だという意味の言葉です。経済環境の変動や現在及び将来の税金の発生を考慮して考えた配分割合だそうです。これが全ての人に合致するとは言えませんが、資産運用の堅い考え方として素晴らしいと思います。預貯金は安全資産に対する投資と考えるべきでポートフォリオの構成としても外せるはずがないです。政府がNISAで運用!運用!とばかり喧伝して国民に対して金融資産運用の一大キャンペーンを張るというのは役所としてどうなのだろうかと思います。預貯金も投資の一部として、毎月(年間)残るお金の半分なり3分の1なり(又は一定割合)を毎月(毎年)積み立てることをお勧めしたいです。―――割合はライフプランの上で毎年見直し、むしろ預貯金の積立てが金融資産運用の中心にすべきと考えています。ウォーレンバッフェット氏は私のようなことは言っておりません。上記はあくまで、私個人が主張するFP風運用指針です。お粗末で大変失礼致しました。
いつもこのコーナーのネタをどうしたらいいか、ああしようか、こうしようかと直前まで悩んでおります。一旦PCを打ち始めてやっとネタを思い浮かべる有様です。できる限り、面白い話題や日常の出来事を絡めて皆様にお伝えしたいと考えております。次回も頑張りますので、今後共どうぞご贔屓下さいませ。
以上で第4回を終了致します。