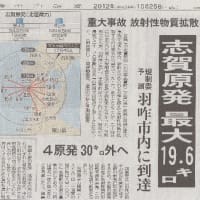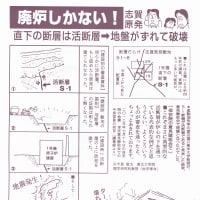駅武蔵地区で隔週金曜日定例実施しているホームレス自立支援夜回りから戻ると、丁度、NHKテレビが、厚労省が生活支援戦略を策定したことを報じていた。中間的就労、即ち一般就労に到るまでの段階的な体験型就労を就労支援員(ジョブコーチ等)のサポートを受けながら積み重ねていく就労支援事業を本格化させるという。この戦略を今後、事業計画に具現化していくとしている。
厚生労働省は、増え続ける生活保護受給者に対する自立と社会復帰を支援するために、4年ほど前から「社会的居場所づくり事業」を国の全額補助事業として展開してきた。金沢市が今年度から始めている「子どもの学習支援事業」も貧困の連鎖を断ちきることを目的にした一連の事業だ。上記の戦略の特色は、それを一歩進め、中間的就労支援の実施に、行政、NPO、民間事業者がネットワークを組み、就労相談から個別の就労支援をワンストップサービスで行っていくことだ。ワンストップサービスの考え方は、リーマンショック後の大量失業、年越し派遣村への対策から生まれたことは記憶に新しい。200万人を突破し、生活保護事務に増員が追いつかない地方自治体の窮状にも対応しようと意図している。
私は、個々人にとって労働は生きる基本であり、社会で自己実現を図る基本的人権であると考えている。しかし、その権利保障が絵に描いた餅になっているのが現状だ。憲法第25条「文化的生存権保障」にもとづく生活保護制度であるが、その捕捉率(制度受給者の割合)が2割程度とOECD諸国中最低レベルであるにも拘わらず、不正受給や貧困ビジネスを針小棒大に採り上げて、制度の縮小、水準の切り下げを世論誘導する政治の流れが強まっている。この中間的就労支援事業が、労働の権利保障の考え方に立って実施されていくのか、生活保護縮小の企図をもって、その手段として実施されていくのか、分岐点に立っていることを見極めていく必要がある。
ホームレス状態から生活保護受給に移行する多くの人々に立ち会ってきた私たち金沢夜回りの会には、労働を通じて人間の尊厳をとりもどすことへの想像以上の困難さが、これでもかこれでもかと実感せられる5年間だった。本人個々が様々な問題を抱えていることは否定しない。しかし、就労の問題の背景には、営利企業が競争力の名の下に、人件費を削減し、就労機会をどんどん縮小させてきた社会的な構造問題があることを申し立てておく必要がある。資本金10億円以上に限っても、250兆もの内部留保、増え続ける億万長者、増え続けて1000万人を越えた年収200万円以下層。この社会の分裂の中から、ホームレスと生活保護にまつわる諸問題が生み出されていること、そしてそれは明日は我が身であることを忘れてはいけない。
明日は、市民の政策研究会「くるま座」の定期総会だ。この問題についても、総会議論になる。
厚生労働省は、増え続ける生活保護受給者に対する自立と社会復帰を支援するために、4年ほど前から「社会的居場所づくり事業」を国の全額補助事業として展開してきた。金沢市が今年度から始めている「子どもの学習支援事業」も貧困の連鎖を断ちきることを目的にした一連の事業だ。上記の戦略の特色は、それを一歩進め、中間的就労支援の実施に、行政、NPO、民間事業者がネットワークを組み、就労相談から個別の就労支援をワンストップサービスで行っていくことだ。ワンストップサービスの考え方は、リーマンショック後の大量失業、年越し派遣村への対策から生まれたことは記憶に新しい。200万人を突破し、生活保護事務に増員が追いつかない地方自治体の窮状にも対応しようと意図している。
私は、個々人にとって労働は生きる基本であり、社会で自己実現を図る基本的人権であると考えている。しかし、その権利保障が絵に描いた餅になっているのが現状だ。憲法第25条「文化的生存権保障」にもとづく生活保護制度であるが、その捕捉率(制度受給者の割合)が2割程度とOECD諸国中最低レベルであるにも拘わらず、不正受給や貧困ビジネスを針小棒大に採り上げて、制度の縮小、水準の切り下げを世論誘導する政治の流れが強まっている。この中間的就労支援事業が、労働の権利保障の考え方に立って実施されていくのか、生活保護縮小の企図をもって、その手段として実施されていくのか、分岐点に立っていることを見極めていく必要がある。
ホームレス状態から生活保護受給に移行する多くの人々に立ち会ってきた私たち金沢夜回りの会には、労働を通じて人間の尊厳をとりもどすことへの想像以上の困難さが、これでもかこれでもかと実感せられる5年間だった。本人個々が様々な問題を抱えていることは否定しない。しかし、就労の問題の背景には、営利企業が競争力の名の下に、人件費を削減し、就労機会をどんどん縮小させてきた社会的な構造問題があることを申し立てておく必要がある。資本金10億円以上に限っても、250兆もの内部留保、増え続ける億万長者、増え続けて1000万人を越えた年収200万円以下層。この社会の分裂の中から、ホームレスと生活保護にまつわる諸問題が生み出されていること、そしてそれは明日は我が身であることを忘れてはいけない。
明日は、市民の政策研究会「くるま座」の定期総会だ。この問題についても、総会議論になる。