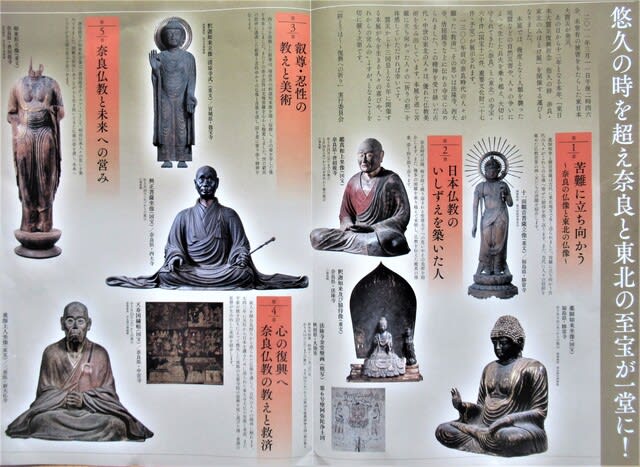1泊で山形県に来ています。刈り払い作業が一段落したところで息抜きです。
隣県なので大概日帰りが可能です。1泊となると少々遠い最上や庄内。
東北自動車道を北上、通常あまり通らない大崎市から加美町を抜ける国道347号線を西へ山脈越え。
銀山温泉はしばらくぶりです。
夜はガス灯に火がともり、郷愁漂う雰囲気が味わえますが、今回は泊まりはなし。
銀山川の両岸を散策。

木造の旅館が立ち並ぶ温泉街は昼間でもレトロな雰囲気が十分楽しめます。

銀山温泉はかのドラマ「おしん」で一躍有名になりました。

風光明媚な自然も楽しめます。
洗心峡。

銀山温泉からスイカが特産の尾花沢へ。
道の駅「尾花沢」。

寄るのは初めて。期待度が高かっただけに少々残念な気持ち。

当地に来ればお昼はやはり蕎麦。
近くでは知名度の高い次年子蕎麦がありますが、今回は新庄の手打ち蕎麦屋「さぶん」さんで。
美味しくいただきました。
近くの「新庄ふるさと歴史センター」。

新庄祭りの大きな山車が展示されています。

古い民具や農具がおびただしい数展示されています。

これほど多いのは見たことがありません。

今回は敢えて新庄から最上川を下らず、金山町の町並みを眺めながら真室川町へ。
良かったのが正源寺。

立派な山門です。
参道を歩くと山門の手前に何と線路と踏切があります。

この山門は湯殿山大日坊の総門であったものを昭和36年に移築したものだそうで、なるほどと納得。
本堂も大きい。

西に向かって酒田は何度か来ているので今回はパスし、湯野浜温泉へ。
海水浴場。

30年ほど前泳いだ記憶があります。
こちらのホテルで宿泊。部屋から夕日の沈むのが見えました。