除夜詣に行ったときのこと。除夜の鐘につられて遠くの方で犬が遠吠えをしておりました。そこで詠んだ句
除夜の鐘遠くで吠ゆる犬の声
で、参考までに「除夜の鐘」という季語の句を探したところ、以下の句にめぐり合いました。
おろかなる犬吠えてをり除夜の鐘 山口青邨
とても有名な句だそうで、類想句というのもおこがましい、恥じ入るばかりの対比ではありますが、青邨のこの句については「おろかなる」というところにひっかかりを感じました。除夜の鐘につられて遠吠えをしてしまうのは、犬の本能の所作であり、人間様が「おろか」というのは人間の勝手では、と思ったのです。
ただ、繰り返し読み、その意味を考えるにつれ、印象は変ってきました。
まずは当該句を見つけた清水哲男さんの『新・増殖する俳句歳時記』から清水氏の解題を引用します。
犬は人間世界の事情を解していないだけのことなのであって、彼にとっては吠えるほうが、むしろ自然の行為なのだ。そんなことは百も承知で、あえて作者が「おろか」と言っているのは、むしろ犬の「おろか」を羨む気持ちがあるからである。「おろかなる犬」なのだから、人間のように百八つの煩悩などはありえない。ありえないから、「除夜の鐘」などはどうでもいいのだし、はじめから理解の外で生きていられる。だから、素朴に驚いて吠えているだけだ。
除夜の鐘につられて吠えるのは、人間的な知からすれば「おろか」であるが、そもそも除夜の鐘は人間のおろかな煩悩を洗い流すもの、犬にはまったく関係ない慣習であり、おろかさ加減でいけばどっちもどっちでしょう。むしろ無垢なだけ犬の方がしあわせである。作者は除夜の鐘と重なる犬の声を聞きながら、「おろかなる犬」にすらなれない人間存在に対する諦念を感じているかのようです。
ただ、下五できったその先に、ちょうど鐘の音が虚空に吸い込まれる時のような余韻を感じます。「この除夜の鐘が終われば、年が改まる。人間は、煩悩を抱えて四苦八苦しているが、それでもまた新しい年が訪れ、リスタートができる。まあ、そういうことだ」といった煩悩に対する受容も伺えます。
道すがら簡単に作った拙句を顧み、このくらい、つきつめて表現してはじめて詩と呼べるんだな、としみじみ思いました。
最新の画像[もっと見る]
-
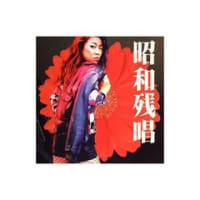 大西ユカリと新世界
18年前
大西ユカリと新世界
18年前
-
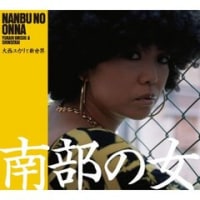 大西ユカリと新世界
18年前
大西ユカリと新世界
18年前
-
 鎌倉のちょっといい古本屋
18年前
鎌倉のちょっといい古本屋
18年前
-
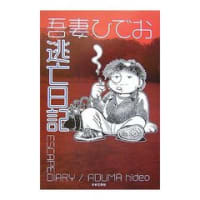 吾妻ひでお「逃亡日記」
18年前
吾妻ひでお「逃亡日記」
18年前
-
 月刊漫画ガロINDEX 1967年11月号(通巻39)
18年前
月刊漫画ガロINDEX 1967年11月号(通巻39)
18年前
-
 月刊漫画ガロINDEX 1967年11月号(通巻39)
18年前
月刊漫画ガロINDEX 1967年11月号(通巻39)
18年前
-
 Bluesの学習 Robert Johnson
18年前
Bluesの学習 Robert Johnson
18年前
-
 Bluesの学習 Charlie Patton
18年前
Bluesの学習 Charlie Patton
18年前
-
 月刊漫画ガロINDEX 1967年10月号(通巻38)
18年前
月刊漫画ガロINDEX 1967年10月号(通巻38)
18年前
-
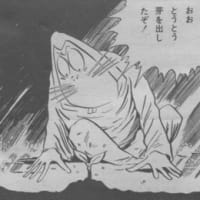 月刊漫画ガロINDEX 1967年9月号(通巻37)
18年前
月刊漫画ガロINDEX 1967年9月号(通巻37)
18年前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます