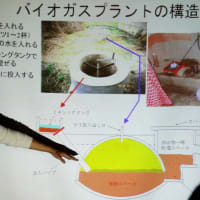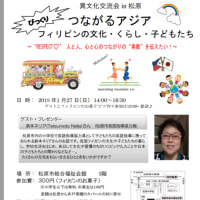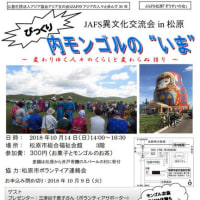30周年を迎えたJAFSアジア協会アジア友の会が、新しい基金を新しいコンセプトで始めます。
★★★以下、JAFS関東グループのブログから抜粋です★★★
「援助される人が『貧しいから援助してもらうのは当たり前』という考えから抜け出し、他者を助けることを通じ、自分たちの自立を確認できるようにしていく仕組みが“Asian Frendship Fund~アジアフレンドシップ・夢基金”です。アジアの人達みんなが少しずつ出し合ったお金をアジア18ヶ国の現地提携団体と共同管理し、必要なことに使っていきます。
12月にバンコクで基金創設が決定され、提携団体の代表スタッフと議論が進んでいます。

この基金の使途として、貧しくてシンジケートに売られた子ども達、ストリートチルドレンの子ども達を集めて、日曜学校(チャイルドアカデミー)を行うことを計画しています。 チャイルドアカデミーでは、将来への希望を持てるよう、立志伝的な多くの人の伝記を話し、貧しくても一生懸命やれば世の中に役立つことを教えます。指導は地域の年配者にしてもらい、栄養確保のため、給食にはバナナ・パン・ゆで卵などを用意します。
インドなどでは、多くの子ども達がHIV/AIDSに感染しており、6歳で学校に行く頃には自分が限られた命であると知り、将来の希望を失ってしまいます。 子ども達の望みは『雨の時にぼろ布の下に敷くビニールがほしい』『夜働きに出るお母さんが夜も家にいるようにしてほしい』など、とても切実で胸を打つものです。
この子ども達が一日でも“生まれてきて良かった!”と思えるようにするために、基金を使ったいろいろな方法を考えていく必要があります。」
現地の人たちが自ら立ち上がるのを支援するこの仕組み。多くの人たちの賛同を得てこの仕組みが広がって行くことを、願わずには居られませんでした。
★★★以下は、昨年10月に紹介された新聞記事です。★★★
アジア助け合い基金を創設…30周年のNGO「友の会」 支援先18か国の団体と
ワークキャンプで、井戸の建設作業を行うボランティアら(2007年12月、カンボジアで)=アジア協会アジア友の会提供
関西のNGOの草分けで、開発途上国の生活支援に取り組む「アジア協会アジア友の会」(大阪市西区)が、貧しい地域の福祉向上に役立てるため、インドやタイなどアジア18か国の民間団体と共同で今月、「アジアフレンドシップ『夢』基金」を創設した。 10日が設立30周年になるのを機に、ネットワークを築いてきた各国の提携団体に呼びかけた。20~23日、タイ・バンコクで、初の理事会を開く。
友の会は1979年10月、アジア各国に安全な生活用水を贈るために設立され、井戸・パイプラインを13か国で約1400基、学校を9か国に約100校建設し、10か国で約213万本の植林を行い、約200万人の生活向上に努めてきた。
基金は、助け合いの輪を広げ、飢えに直面する子どもたちへの食事の提供や、識字教育を行う「チャイルドアカデミー」(仮称)設立などに役立てる。
募金には、30年前から同会が支援してきたインド・マハラシュトラ州の2地域の住民らも、1日分の生活費にあたる約1ドルを出し合うなど、参加している。友の会の村上公彦・事務局長は「30年の活動の中で、支援を受ける側だった人々に、〈今度は自分が人々のために〉という機運が生まれてきた。多くの人に、アジアの仲間と一緒に基金に参加してほしい」と話している。
募金は1口1000円。郵便振替00960・6・10835、加入者名は「アジア協会アジア友の会」、通信欄に「夢基金」と記入。問い合わせは同会(06・6444・0587)。(2009年10月09日 読売新聞)