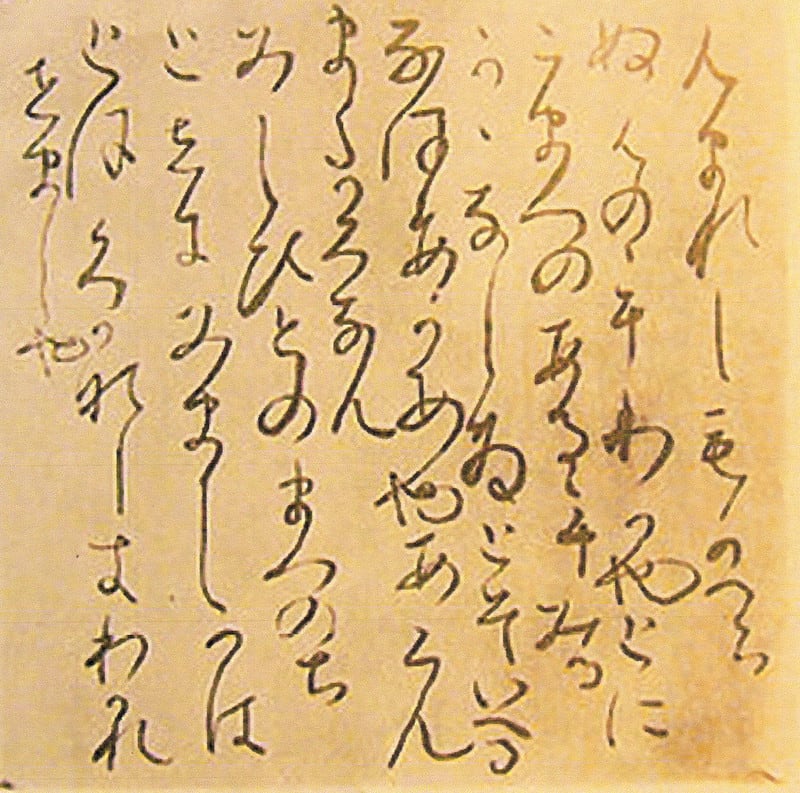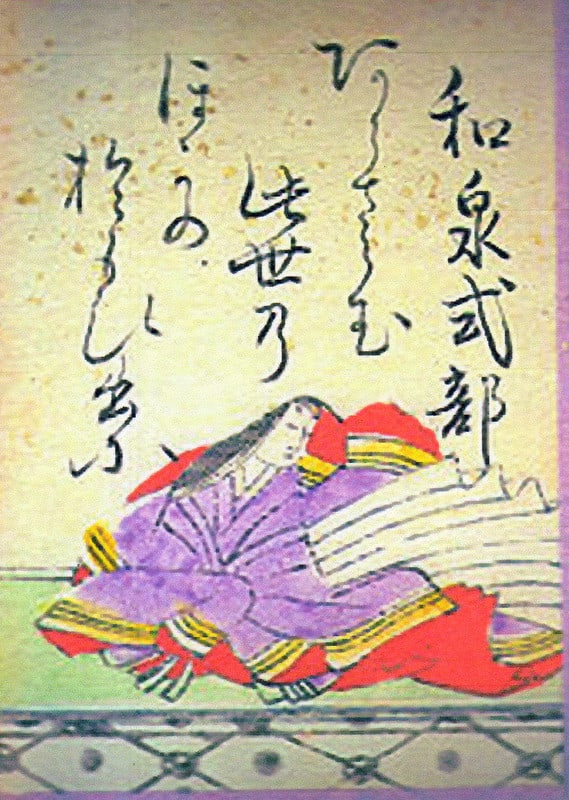十一世紀の半ば過ぎに即位した、第71代「後三条天皇」は、「藤原氏」と血縁関係が薄かったこともあり、「藤原氏」との政治をはなれ、自ら政治を行い、「摂関家」の力を抑えようとしました。
祭71代「後三条天皇」
「後三条天皇」のあと、「白河天皇」も摂関家を抑えて「天皇親政」を行い、位を譲り「上皇」となってからも政治を行いました。
第72代「白河天皇」
「上皇」の御所を「院」と言った為、この政治は「院政」と呼ばれました。
「上皇」は源氏と平氏の武士に身辺の警護をさせ、「荘園」の寄進を受けた貴族や武士に、「不輸」(ふゆ)、「不入」(ふにゅう)の権与を与え保護しました。
その0結果荘園は「上皇」のもとに集まり、「上皇」の力は独裁的なものとなりました。また、、「上皇」があつく信仰した寺社にも荘園が寄進されたため、寺社の勢力も増大しました。