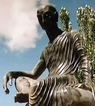少し前の NHKニュースに、文楽の後継者育成のため、昭和47年から2年毎 行ってきた研修生募集(研修期間が2年のため)ですが、初めて 応募 (令和5年度生) がないことから、締め切りを延長する旨の アナウンスがありました。
足遣い10年 左遣い15年、それでやっと黒子衣装から抜け出せ 顔と右手を操る主遣い (おもづかい) という 長い行程(ぎょうてい)が、あたかもブラック企業を連想され、敬遠させてるのかもしれません。ならば、
「決してそうではないですよ」「こんな夢と希望と楽しいことがありますよ」といった広報が求められてると思いますが、文楽は日本を日本たらしめている文化の 大切な大切なアイテムです。如何に守り発展させてゆくか、今こそ更なる知恵が必要かと存じます。
さてと、オイラは『歌舞伎』には 足が向かわないですが、『文楽』は好きでありまして、


(上はそれぞれ 館内の宙吊りパネルを撮影させていただいたものです)
ことに『国立文楽劇場』4月公演は、『妹背山婦女庭訓』と『曽根崎心中』という 2大人気演目が組まれましたので、「待ってました !!! 」とばかり、泊り掛けで行ってきてます。



「こんなん、つらすぎる~~」、やるせないほどに切ない幕切れの『妹背山婦女庭訓』ですが、その舞台というものは、この世のものかと思わんばかり?の、特に 吉野川の流れる様子 および 両岸の 妹山・背山の満開の桜の見事な表現には、目を見張りましたし

これは、撮影OKの『資料室』掲示のパネルを撮らせていただいたものですが、実際は、もっともっと華やかで動きもあって綺麗でした。なお、物語の舞台であります現実の 妹山と背山 は、『ぐるりん関西』さんのホームページ掲示写真を拝借させていただきますと、

こんな具合であります。
一方『曽根崎心中』は、何たって 心中場面である『天神森の段』。”死” をこんなに美化していいのだろうかと心配になるほどの 美しさ。もう、うっとりさ 募るばかりであります。

(本公演パンフレット P22 を撮影させていただきました)
特に 桐竹勘十郎さんの お初の、心中直前の ひらひらひらと舞いまわる動きは、はかなさ満開。まっこと見事でございました。写真の無いのが、大層 辛く感じられます。
以下は『資料室』の展示品をいくつか撮ってきていますので、アルバム代わりに掲載です。
 .
.
 .
.

↑ 三味線の譜

↑ 太夫さんの 床本 ほか 小道具

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 .
.
当日購入の 吉田玉男さん『文楽藝話』はまだ読んでませんが、ブックオフで求めた 人間国宝を務められた竹本住大夫さん『人間、やっぱり情でんなぁ』は、たいへん面白く読了してまして、以下 オイラが付箋を付けた部分の要約をメモ書きするとします。
P49 住大夫さんの師匠の代から、名前を表すときは点ナシの ”大夫”、仕事や職分を表すときは点アリの ”太夫”と区別するようになった
P50 ”文楽” と呼ばれるようになった由来は、江戸寛政年間、淡路島出身の植村文楽軒さんが、人形浄瑠璃の芝居小屋を今の国立文楽劇場近くに建て、評判を取り、いつしかそれを文楽と呼ぶようになった
P70 太夫は体のいろんなところから声を出すんやけど、眉間から声をだせたら楽でんねん
P120 人形は動かすより、じっとしているほうが数倍しんどいでっせ。あれは重労働です
P150 大勢の女性を知ったからと言うて、芸に色気が出るということはありまへんな
P181 浄瑠璃には『ことば』:役者でいうセリフ
『地(地合い』:情景描写や説明
『色』:上の二つの中間 という 3つの部分がある
P208,9 どうして浄瑠璃と呼ぶようになったか
源平時代のこと。子宝に恵まれなかった矢作の長者夫婦は、鳳来寺の薬師瑠璃光如来に祈願。そうして授かった娘は、その仏様にあやかり 浄瑠璃姫と名付けられ、大切に育てられ、然る後、平泉へ下向途中 その長者宅に宿を取った牛若丸は、 美しく成長した浄瑠璃姫および姫の奏でる筝に たちまち魅了され、自身の笛の音を重ねるとともに契りを結ぶのであるが、その名笛『薄墨』を形見に再会を約し旅立ったそうな。されど再び逢うは叶わぬ夢と絶望した姫は、川に身を投じてしまったと。で この悲恋物語が、琵琶法師の『平家物語』が流行った後の世に語られ始めると、たいへんな人気を博すこととなり、いつしかその独特の抑揚をつけて語られる物語は ”浄瑠璃” と呼ばれるようになったと
P212 近松門左衛門の演目は好きでない。本で読んでる分にはいいが、芝居にするのは難しい。七五調なら語りよいが、字余り字足らずが多い。人形も遣いづらいし、近松はんに会うたら言いたいことは仰山ある
P228 舞台で間が抜けるのは、あきまへん。大夫はあれだけたくさんの言葉を口から出していながら、何もゆうてない。息を詰めてる時間、すなわち『間』でいちばん多く語ってまんねんで
足遣い10年 左遣い15年、それでやっと黒子衣装から抜け出せ 顔と右手を操る主遣い (おもづかい) という 長い行程(ぎょうてい)が、あたかもブラック企業を連想され、敬遠させてるのかもしれません。ならば、
「決してそうではないですよ」「こんな夢と希望と楽しいことがありますよ」といった広報が求められてると思いますが、文楽は日本を日本たらしめている文化の 大切な大切なアイテムです。如何に守り発展させてゆくか、今こそ更なる知恵が必要かと存じます。
さてと、オイラは『歌舞伎』には 足が向かわないですが、『文楽』は好きでありまして、


(上はそれぞれ 館内の宙吊りパネルを撮影させていただいたものです)
ことに『国立文楽劇場』4月公演は、『妹背山婦女庭訓』と『曽根崎心中』という 2大人気演目が組まれましたので、「待ってました !!! 」とばかり、泊り掛けで行ってきてます。



「こんなん、つらすぎる~~」、やるせないほどに切ない幕切れの『妹背山婦女庭訓』ですが、その舞台というものは、この世のものかと思わんばかり?の、特に 吉野川の流れる様子 および 両岸の 妹山・背山の満開の桜の見事な表現には、目を見張りましたし

これは、撮影OKの『資料室』掲示のパネルを撮らせていただいたものですが、実際は、もっともっと華やかで動きもあって綺麗でした。なお、物語の舞台であります現実の 妹山と背山 は、『ぐるりん関西』さんのホームページ掲示写真を拝借させていただきますと、

こんな具合であります。
一方『曽根崎心中』は、何たって 心中場面である『天神森の段』。”死” をこんなに美化していいのだろうかと心配になるほどの 美しさ。もう、うっとりさ 募るばかりであります。

(本公演パンフレット P22 を撮影させていただきました)
特に 桐竹勘十郎さんの お初の、心中直前の ひらひらひらと舞いまわる動きは、はかなさ満開。まっこと見事でございました。写真の無いのが、大層 辛く感じられます。
以下は『資料室』の展示品をいくつか撮ってきていますので、アルバム代わりに掲載です。
 .
.
 .
.

↑ 三味線の譜

↑ 太夫さんの 床本 ほか 小道具

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 .
.
当日購入の 吉田玉男さん『文楽藝話』はまだ読んでませんが、ブックオフで求めた 人間国宝を務められた竹本住大夫さん『人間、やっぱり情でんなぁ』は、たいへん面白く読了してまして、以下 オイラが付箋を付けた部分の要約をメモ書きするとします。
P49 住大夫さんの師匠の代から、名前を表すときは点ナシの ”大夫”、仕事や職分を表すときは点アリの ”太夫”と区別するようになった
P50 ”文楽” と呼ばれるようになった由来は、江戸寛政年間、淡路島出身の植村文楽軒さんが、人形浄瑠璃の芝居小屋を今の国立文楽劇場近くに建て、評判を取り、いつしかそれを文楽と呼ぶようになった
P70 太夫は体のいろんなところから声を出すんやけど、眉間から声をだせたら楽でんねん
P120 人形は動かすより、じっとしているほうが数倍しんどいでっせ。あれは重労働です
P150 大勢の女性を知ったからと言うて、芸に色気が出るということはありまへんな
P181 浄瑠璃には『ことば』:役者でいうセリフ
『地(地合い』:情景描写や説明
『色』:上の二つの中間 という 3つの部分がある
P208,9 どうして浄瑠璃と呼ぶようになったか
源平時代のこと。子宝に恵まれなかった矢作の長者夫婦は、鳳来寺の薬師瑠璃光如来に祈願。そうして授かった娘は、その仏様にあやかり 浄瑠璃姫と名付けられ、大切に育てられ、然る後、平泉へ下向途中 その長者宅に宿を取った牛若丸は、 美しく成長した浄瑠璃姫および姫の奏でる筝に たちまち魅了され、自身の笛の音を重ねるとともに契りを結ぶのであるが、その名笛『薄墨』を形見に再会を約し旅立ったそうな。されど再び逢うは叶わぬ夢と絶望した姫は、川に身を投じてしまったと。で この悲恋物語が、琵琶法師の『平家物語』が流行った後の世に語られ始めると、たいへんな人気を博すこととなり、いつしかその独特の抑揚をつけて語られる物語は ”浄瑠璃” と呼ばれるようになったと
P212 近松門左衛門の演目は好きでない。本で読んでる分にはいいが、芝居にするのは難しい。七五調なら語りよいが、字余り字足らずが多い。人形も遣いづらいし、近松はんに会うたら言いたいことは仰山ある
P228 舞台で間が抜けるのは、あきまへん。大夫はあれだけたくさんの言葉を口から出していながら、何もゆうてない。息を詰めてる時間、すなわち『間』でいちばん多く語ってまんねんで