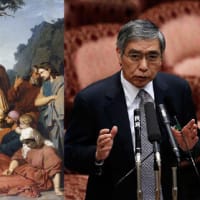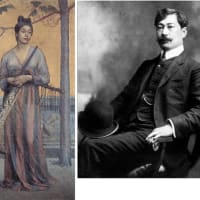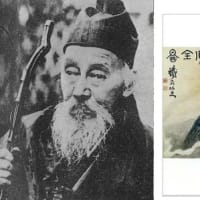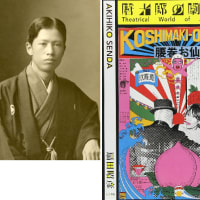A.なんでもありの“現代美術”
「現代美術」といえばもうキャンバスに絵具で何かを描くなどというのは古臭く、人体彫刻も時代遅れで、床になにか大きなオブジェを置いたり、吊り下げたり、暗い部屋に映像や光線を投影したり、コンピューターで音や画像を散らす中に鑑賞者が歩いたり、もう何をやってもアートだ、という感じになっているが、じつはそういう現代アートも始まりは70年も昔のアメリカで登場した抽象表現主義から始まっているのだという。さらにM・デュシャンが便器《泉》を美術展に出して拒否された1917年から数えればもう100年を越えるわけだから、「現代美術」といっても20世紀の「過去の美術」なのかもしれない。
『ポストモダンを超えて』のもとになった研究会の第1回は、戦後美術をリードした1950年代アメリカの抽象表現主義をテーマに、新進美術史家河本真理さんの報告である。中心はジャクソン・ポロックになるが、抽象表現主義にはじつはいろいろな側面があるのと、理論的にその後に大きな影響をもたらしのはアラン・カプローであるというあたりの説明。
「河本真理 次にアラン・カプローの登場です。彼は「アッサンブラージュの芸術」を踏まえて、1966年に『アッサンブラージュ、環境芸術、ハプニング』という大著を刊行します。
高階 当時、学生たちがバイブルみたいに持っていた本ですね。
河本 カプローはハプニングの芸術家として知られていますが、アメリカの大学で教鞭も執っていて、体系的、教育的な観点から理論を展開しました。カプローによれば、アッサンブラージュも環境芸術もハプニングも、すべて「拡張」の原理に従っています。アッサンブラージュと環境芸術の違いは大きさだけで、アッサンブラージュは手に取ることができるか、ないしはその周りを歩くことができる(たとえばラウシェンバーグの《モノグラム》)のに対して、環境芸術はそのなかに入らなければなりません。
では、環境芸術とハプニングは何が違うのでしょうか。環境芸術は、視覚性、触覚性や素材の扱いに重点が置かれているのに対し、ハプニングは、時間、音、人間の身体的存在といった、運動や時間の経験を前面に出します。環境芸術は空間を、ハプニングは時間を対象としているわけです。それゆえ、カプローは、ハプニングのことを「イヴェントのコラージュ」と呼んでいます。芸術と生、芸術家と観客との間の境界線を意識的に曖昧にすることがカプローの戦略で、受動的な環境芸術と能動的なハプニングは、じつは表裏一体ということになります。
カプローは、イーゼル絵画の存在を支えてきた、画廊や美術館や住宅の箱型空間という既存の「枠組み」を断固として拒否します。こうした抽象的な箱型空間――ホワイト・キューブ――は、サイズの異なる、日常生活の多種多様な素材やオブジェを持ちるアッサンブラージュや環境芸術には、もはや適していないと主張したのです。しかしながら、こうした芸術創造に対応するはずの新しい「有機的」な建築は遅々として登場しません。業を煮やしたカプローは、芸術家が街の通りに出て、廃工場や野外で制作するよう勧めました。
ここで興味深いのは、カプローが「ジャクソン・ポロックの遺産」という論考を1958年に書いていることです。カプローによれば、オールオーヴァーの構図の遠心力に従ってタブローの「なかで」描くという行為と、その作品のモニュメンタルなスケールゆえに、絵画という場を超える可能性を最初に示したのはジャクソン・ポロックでした。カプローは、「われわれの議論にとって主要な点は、[ポロックの描いた]壁画のスケールを持つ絵画が、絵画であることをやめて「環境になったということだ」と述べています。我田引水のように思われますが、こうしてカプローは、アメリカ美術の正統と認められているポロックの遺産の継承者であることを主張するのです。
ポロック自身は、絵画という場の限界を超えたことはなく、「四方を囲まれた闘技場」のなかにとどまっていたにもかかわらず、ポロックが絵画の伝統を「ほぼ破壊」(カプローの言葉)したことによって、その後の世代が「絵画の実践を完全に放棄する」ことを可能にした、と言うのです。その根拠を示すために、『アッサンブラージュ、環境芸術、ハプニング』のなかで、自信の環境芸術《置場》を、上から見下ろしたように撮影した写真と、ドリッピングをしているポロックの写真を、見開きペーに左右隣り合わせで掲載しました。片やカプローが置場に投げ捨て、積み上げたタイヤの山のうねうねとした円形のつらなりと、片やポロックがカンヴァス上に撒き散らした絵具の跡が曲がりくねって絡み合う様との間に、形態と同時に身振りのレベルにおいても関連性があることを示唆しようとしたのです。
芳賀 こういうふうにタイヤを置いたのはカプロー?
河本 はい。このなかにいるのが本人です。
芳賀 写真が彼の作品ではなくて、このタイヤの置き方が彼の作品なの?
河本 ええ。ポロックは、ある意味でこのようにも受け継がれていたことになります。
三浦 カプローの意識としてはね。ぼくはぜんぜんそう思わないけど。(笑)
河本 ポロックはこの時代は英雄になっていますから、カプローとしてはそれを制度化したいということもあったかもしれません。ここで着目したいのは、カプローが大学で教鞭を執っていたように、アメリカの現代美術にとって大学の果たした役割が重要になってくる点です。美術館や大学といった文化機関が、美術史の言説に次第に決定的な影響力を及ぼすようになっていきます。文化機関の絶対的な影響力と芸術動向へのかかわりが、アヴァンギャルドの概念の終焉をもたらすことになるのです。ダダが美術館や大学にプロモートしてもらうなどということはヨーロッパでは考えられなかったのに対し、ネオ・ダダやアッサンブラージュは、早い時期からニューヨーク近代美術館で展覧会が開催され、大学なども一体となってそれを打ち出していきました――これはアメリカに顕著な特徴です。
芳賀 アカデミズムに入れちゃった。
河本 アヴァンギャルドの制度化と言えるでしょう。
三浦 文学も同じで、詩人も小説家もみんな大学の先生になっていく。
芳賀 最後はみんな大学に隠棲するわけだ。
高階 大学の権威主義に弱いんですよ、向こうの連中は。日本ではそれほど権威がないんだけど。
三浦 権威なんでしょうか、むしろ生活費のほう?
高階 生活費だけど、画家にとっては大学のお墨付きが欲しいわけですよ。ジャーナリストより大学の先生のお墨付きが。
三浦 ああ、そういうことですね。じゃあ、日本もそうなりつつあるのかな?
高階 なると思います。
芳賀 美術館の学芸員でも権威があるんじゃない?
河本 フランスの学芸員は大学の教授より地位が高いのです。
高階 ぼくは西洋美術館から大学に移ったんだけど、ルーブルの館長が、「おまえ、なんでそんな身を落すんだ」って。(笑)
山崎 アメリカでもMoMAだけが例外なのではないかと私は見ています。すべてのキュレーターが偉いわけではなくて。あそこでキャプテンをやると、それ自体が環境芸術なんだ。(笑)
河本 最後に、「エニシング・ゴーズ(何でもあり)の時代?」についてお話します。批評家リチャード・コステラネッツに「若い娘が花を摘み、それをスーパーマーケットに持って来る」というもともとの現実の状況と、それとまったく同じ行為がハプニング(《セルフ・サービス》1966年)で行なわれる場合とでどう違うのかと問われたカプローは、文脈(コンテクスト)の違いに着目するようにと答えます。カプローによれば、「場面を選択し、そこに焦点を合わせるプロセスが行なわれるという事実が、ハプニングの行為に別の意味を与える」のです。カプローは結局、「ハプニングは現実の生のようではあるが、現実の生自体に置き換わるものではない」と述べています。こうしてみますと、カプローの理論にも亀裂が生じており、もしハプニングが現実の生に行くら近づこうと、結局のところ現実の生ではないとすれば、画廊と美術館の「枠組み」の外に出るために、現実の生と芸術の境界を曖昧にしようとしてきたカプローの努力自体が水泡に帰しかねません。なぜなら、カプローが自身の考えに反して、現実の生自体ではない芸術的なコンテクストを前提とし、維持していることになるからです。
三浦 すると河本さんの意見はカプローとは違うことになる。
河本 私は今お話した1960年代のカプローの理論には矛盾があると考えています。ただ、カプローも晩年には考えが変わっていくので、私の意見は、晩年のカプローに近いのです。それについては後で説明しますが、ここでは1960年代のハプニングについてもう少し補足説明させてください。ハプニングと現実の生の見分けがつかなくなればなるほど、ハプニングは逆説的に、現実の生との区別を強調する言説に従属するようになります。デュシャンのレディ=メイドの問題が執拗に回帰してくるわけですが、ハプニングの場合この問題は一層激化することになります。
高階 これはあなたがそう言っているわけね。
河本 はい。なぜなら、ハプニングにおいては、携帯を変貌させることにも、意味を逸脱させることにも関心が払われなくなり、残るのは日常生活のオブジェを画廊や美術館、美術史の言説といった、芸術を聖化するコンテクストである「聖域」に移すことだけになってしまうからです。ハプニングのいくつかが、物理的に美術館の箱型空間の外に出たとしても、やはり文化制度の言説的な枠組みから逃れたわけではありません。人間の生活がそのまま混沌とした要素の並置として提示され、「芸術」と命名されるのなら、芸術の概念は、現実の生と重複した余剰となるのではないでしょうか。
カプローは当初、楽観的だったように思われます。1966年の段階では、芸術を放棄するという行為さえ芸術と見なされるという意味において、「非芸術は不可能である」と考えていました。しかしながら、芸術の分野が限りなく拡がることの意味する危険性を意識するようになったカプローは、2001年にはこう書いています。「もし何でも芸術であったのならば、何も芸術ではなかったことになる」。
山崎 同じ1966年に私は『芸術現代論』という本を出したんです。当時の若い、建築家なら黒川紀章さんとか、いきのいい芸術家たちにインタビューをして、それに基づいて私が議論を書いたものです。なかで非常に印象的なのが音楽家の一柳慧さん。私とほとんど同年配の彼が、過激だったときのカプローと同じことを言いました。たとえば、歩道橋の上から石を投げる。誰かの頭に当たってギャーという。これは俺の作品だと。やがて、彼女か誰かが倒れる。そこへ救急車がピーポーピーポーといってやって来る。これも俺の作品だ。やがて彼女は入院する。死んで、葬儀が始まる。お経が読まれる。これも俺の作品だ。要するに、世界が作品になるわけだね。
三浦 勢いがあったんですよ、時代に。
山崎 勢いがあったというよりは、まったく無智蒙昧で。
三浦 そうかも分からないけど、無智蒙昧をやるだけの勢いがあったんですよ。
山崎 私は保守反動ですから、その本では手ひどく批判している。だけど、彼は追いつめられてそこまで言ってしまったわけだ。「そうなるだろう」と聞いたら「そうだ」と。
三浦 問いつめると理論的にはそうならざるをえない。赤瀬川原平にしても中西夏之にしても同じ問題を抱えていたと思うけれども、ある意味ではそこから引き返してきちゃったんですね。一柳さんはいまやきわめて古風なアーティストになっているとぼくは思う。
山崎 そう、一柳さんも戻ってきたし、いちばん古風に戻ったのは黒川紀章さんですよ。彼はそのとき「建築の永遠性を否定する」と言っていた。だから、はじめから壊す装置を建築の中に入れてある。ボーンだかガシャだか知りませんけど、とにかくつねに建築は流動している。
三浦 そうですよ、メタボリズムですよ。」三浦雅士編『ポストモダンを超えて 21世紀の芸術と社会を考える』平凡社、2016.pp.81―90.
美術大学に行って画家とかデザイナーとかになろうとする若者は、高校の美術部で紙やキャンバスに絵を描いて、石膏デッサンや平面構成で受験勉強をしたのに、大学で現代美術を教わるともうそんな作品は過去のもので、イーゼル絵画なんかやめて表に出てインスタレーションを作り、パフォーマンスで人を驚かすのが新しい美術だ、といわれて考え込む。それも実はすでに、半世紀も前に理論的にはいくところまでいっていた、と知れば、あとは何をやればいいのか、結局自分でなにか誰もやっていない変わったことをやるしかないことになる。それは袋小路になるから、先端的なアーティストは結局、古典に戻っていくというわけか。

B.学校“部活”のない社会
日本では、小中学校からどこの学校にもたいてい“部活”があって、なにかスポーツか、音楽か、美術を体験する機会がある。それを指導できる力のある教員がいるとは限らないし、いたとしても“部活”指導に熱心になると過重労働で負担が増す状況ではあるが、とにかく子どもたちは、学校で運動やアート活動に触れることで自分の関心や能力を刺激され、さらに上達を目指したいと思えば、主体的に動くだろう。学校とは別に楽器や踊りや技芸の「お稽古」の個人教授に通う場合ももちろんあるけれど、スポーツにせよアートにせよ、“部活”という幅広い基盤がなければ子どもたちの能力や個性は芽生えないだろう。しかし、これは日本に特有な文化かもしれない。世界各国がどうなっているのか知らないが、ドイツにいた時見たのは、学校部活というものは一般的ではなく、学校が終わると子どもたちはコミュニティーが用意する各種のスポーツクラブやサークルに参加して、自分の好きなことができる機会を利用しているようだった。欧州はこのクラブ文化が定着しているとすれば、学校単位の“部活”という考え方はとっていないことになる。また、就学率の低い発展途上国などは別の理由で、子どもたちに余暇を活用する教育を学校が与えるのが難しいのかもしれない。
日本の“部活”には過剰な集団主義や競争主義という負の面もありそうだが、広くスポーツやアートに触れるチャンスがあることは文化の土壌を培うプラスの側面があると思う。イギリスでの文化格差が子どもに及ぶという欧州からの報告があった。
「長い目で文化格差解消を 大変革時代の教育:欧州季評 ブレイデイみかこ
「小泉劇場」「小池劇場」という言葉が日本では使われてきたが、英国にも「ジョンソン劇場」の時代がやってきた。合意なきEU(欧州連合)離脱だと言っているかと思えば、議会を閉会すると言い、解散総選挙をほのめかす。目まぐるしく舞台が変わる劇場が、メディアに派手な見出しを提供し続けている。
Ipsos・MORI社の7月の世論調査では、ジョンソン政権の国の運営に満足していないと答えた有権者は75%。満足していると答えたのはわずか18%で、過去40年間で最悪の数字だという。遅かれ早かれ総選挙は避けられないだろうが、保守党は既にその準備を始めており、8月には教育改革に関する書類がリークされた。教員の賃金引上げ、小中学校への投資などを含むこの改革案は、有権者の人気取りだとも言われている。言い方を変えれば、英国の有権者はそれほど現在の教育に不満を抱いているということだ。
長年の緊縮財政は学校現場を疲弊させ、貧困層の子どもを増やした。広がっているのは経済格差だけではない。サッカーの母国として知られ、音楽や演劇、ダンスの分野でも世界中の人々から「本場」と呼ばれてきた国の子どもたちの間で、「文化格差」が広がっている。
政府の社会流動性委員会(SMC)の調査によれば、学校の外で楽器を習ったり、合唱やオーケストラの一員になったりする機会に恵まれる10歳から15歳の児童の数は、低所得層では裕福な層の約3分の1になるという。また、パキスタン系英国人の児童の4%が音楽のレッスンを受けているのに対し、インド系の児童では28%、白人の児童では20%になる。イングランドの北東部では9%の児童が音楽のレッスンを受けているが、ロンドンを含む裕福な南東部では22%だ。
裕福でない家庭の児童がスポーツや演劇、ダンス、芸術などの課外活動に参加する機会を失っているため、SMCは奨学金や学校への資金援助、サポートの必要性を指摘している。
課外活動にはお金がかかる。だが、音楽やスポーツ、芸術などを通して、児童たちは思わぬ自分の才能に気づいたり、自信を身につけたり、チームスピリットを学んだりする。資金不足のためアフタースクール・クラブ(学童保育)の運営をやめたり、夏休みなどの休暇中に課外活動をできなくなったりしている学校が増え、児童たちがこうした活動に参加する場が失われている。
文化活動やスポーツに参加する機会がなければ、子どもたちは「溶け込めないという不安」を抱くようになるそうだ。つまり、例えば楽器を習うことや歌うこと、クリケットをプレーすることに敷居の高さを感じ、自分は音楽や演劇、芸術、スポーツには「値しない」人間だと感じるようになる。
こんなに早い時期から児童たちが好奇心や芸術性や遊びの精神を培う機会から引き離されていると思うと、ビートルズやシェークスピアの国はいったいどうなってしまったのかと思う。自己表現ができるのは裕福な子どもたちだけで、貧しい子どもたちは文化の外側に押しやられている。これではエリート主義の構造を強化させ、支配層と庶民の意識の乖離を増長するばかりだ。
EU離脱で揺れ続ける英国は、1945年に労働党のアトリー政権が誕生したとき、そして80年代のサッチャー革命以来の、大きな変化の時期に直面していると言われる。アトリ-政権は「ゆりかごから墓場まで」と呼ばれた福祉社会の礎を築いた政権だった。だが、それもやがて行き詰まり、80年代のサッチャー革命は、「もはや社会は存在しない」をスローガンに個人主義と新自由主義を推進した。
この二つの大改革の間には60年代があった。ブリティッシュ・インベイジョンと呼ばれた英国文化の黄金時代だ。ビートルズやローリング・ストーンズなどのロックバンドや英国発のファッション、映画、演劇、芸術が世界中を熱狂させた。その背景には階級の流動性があった。アトリ―政権が福祉国家の建設に着手し、その結果として「ワーキングクラス・ヒーロー(労働者階級の英雄)」の時代が到来した。それまでは大学に行ける裕福な層の人々に独占されていた音楽やメディアの世界に、労働者階級の子どもたちが進出し、それまでとは違うセンスや考え方を注入して英国文化を活性化させた。あの時代の進取の精神に富んだ文化は、偶然生まれたのではなく、格差を縮める政治の産物だったのである。
45年や80年代に続く大変革の時代といわれるいま、「次は何か」とメデイアは騒ぐ。だが、何か新しいものは、数十年単位の長期的視野に立った政策の結果として出てくるのであり、いきなり才人がぞろぞろ空から降ってきて世の中を変えるわけではない。
劇場の派手な舞台は2,3時間で終わるが、社会を変えるには長い時間がかかる。45年の改革の果実が花開いたのは60年代だったように。いま読み取るべきブリティッシュ・インベイジョンの教訓はそれなのだ。」朝日新聞2019年9月12日朝刊、17面オピニオン欄。
ブリテイッシュ・インベイジョンが、労働党アトリ―政権の福祉政策から生まれた、というのはちょっと単純化しすぎた話だと思うが、労働者階級出身のビートルズ世代が60年代後半から、創造的な活動を展開したのはイギリスのみならず、世界の各地で起こった動きだったと思う。第二次世界大戦の終った戦後世界が一種の深い反省に立って、生まれてきた子どもたちにチャンスを与えようと努め、また少年たちが戦争をやった上の世代とは違う文化を作って自信をもったという状況は確かだと思う。いま進行している事態は、それとは逆の方向だということに不安と危惧を感じる。