A.ぼくらの世代にとっての「恋愛」
ぼくは1949年生まれの団塊世代の最後で、やたら子どもの多かった戦後の物が足りない復興期と、その後に来たどんどん物質的に豊かになる高度経済成長の日本を記憶している、いまや老いぼれ高齢者になってしまった人間である。ぼくらの世代にとって「恋愛」とはどんなものとして感知されていたのか。とりあえずぼくが20歳前の若者だったのは1960年代後半、経済成長の恩恵が一般大衆の生活にも及んで、もう貧しさが見ればわかる服装や言葉や住宅などから消えていく時代だった。しかし、まだ家庭の経済力がなくて高校にも進学できない同級生がいたし、大学生になれるのは同世代の3割ちょっとだけだった。東京など大都市の消費的な生活と地方のつつましい生活の格差はむしろ際立っていた。ぼくは東京の繁華街に近いところで暮らしていて、家は裕福とはいえなかったが小遣いを貯めれば、面白そうな映画を見たり好みのレコードを買ったりする文化的なアクセスも可能だった。普通科の都立高校生は、頑張って勉強すれば名の知れた大学に入ってそれなりに明るい未来を期待できた。甘く幸福な青春を生きていたともいえる。
そういう環境のなかで、戦争中に子供だった上の世代は、豪華な洋画が描く甘美な「恋愛」など観念の中の幻影に過ぎなかったが、男女共学の高校生活を送ったぼくたちには、クラスの憧れの彼女と「恋愛」できるかもしれないという可能性は、観念ではなく手の届きそうな現実だった。でも、今にして思うと平和な高校に通っていた男の子も女の子も、「恋愛」というものを自分勝手にただ夢のように憧れていたのかもしれない。それは清らかな恋心を抱きながら高校を出て、大学に行ったり就職したりして、いずれ20代なかばには彼と彼女は恋の成就としての結婚に到達し、みんなに祝福されるはずだと思い込んでいた。しかし、そのために男と女はどのような努力をしなければならないかなど、全然考えていなかったのである。
「恋愛」を実践するには見習うべきモデルが要る。しかし、あの時代の日本にはアメリカ映画の恋人たちはあまりに放埓でぶっ飛んでいたし、フランス映画の恋人たちは気まぐれで洗練され過ぎてちょっとひいてしまった。だから、日本でなにかピンとくる「恋愛」のモデルがあれば飛びついたはずだが、そこは古臭い旧世代の純愛物語か男本位の権力思想しかないので、ぼくたちは愚かにもしぶしぶサブカル・マンガの中に拠るべき拠点を求めてしまった。梶原一騎の「愛と誠」は、正直ぼくには当時ばかばかしいとしか思えなかった。だって、この社会への違和感にむらむらと反抗するだけが生きる意味である虐げられた若い男が、あらゆる意味でポジティヴな高貴な美女・お嬢様となぜか恋に落ちて、ひたすら愛の嵐に見舞われるというのだから。
■ 山根成之監督「愛と誠」1974・「続・愛と誠」(1975)「 愛と誠・完結編」(南部英夫監督1976)の3部作
今は昔1970年代なかば、はじめは少年誌の連載マンガでヒットし、これを受けて映画になりヒットしたのが、この「愛と誠」。この頃、原作者の梶原一騎は、「巨人の星」「あしたのジョー」など大ヒットを連発し、格闘技で鍛えた大きな身体とヤクザみたいな服装と態度でマスコミでも注目の的だった。「愛と誠」も喧嘩に明け暮れるアウトロー的高校生が主人公なのだが、これに絵に描いたようなお嬢様(実際絵に描いているのだが・・)が、惚れまくるというラブストーリー仕立てなのが違うといえば違う。いまさら「愛と誠」なんか、引っ張り出して見ちゃったのは、まったくの偶然に始まるのだが、それはちょっと後で書く。
なぜか映画の冒頭に、元インド首相ジャワハルラール・ネルーが娘(後の首相インディラ・ガンディー)へ宛てた手紙(『父が子に語る世界歴史』より)の一説が引用されており、それに含まれる「愛」と「誠(誠実)」という言葉がタイトルの由来にもなっている。少年誌に連載された純愛物の先駆けとなり一世を風靡。ヒロイン・早乙女愛が幼き日の太賀誠を回想して語った「白馬の騎士」や、その早乙女愛への報われない愛を貫く優等生・岩清水弘のセリフ「きみのためなら死ねる」などが流行語になった。女優の早乙女愛は、この漫画が実写映画化された際の一般公募でデビューし、芸名もヒロインの名前から取られた。
信州の蓼科高原で早乙女愛(早乙女愛)が偶然出会った不良青年・太賀誠(西城秀樹)。彼は幼い頃、愛の命を救った時、額に大きな傷を負ったばかりでなく両親や自らの人生さえも壊れていた。愛はその償いとして誠を東京の名門高校へ転入させ、更生させようとするが、誠の怒りは強く、逆に暴力で学園を支配しようと企む。しかし愛の献身的な行為でこれを阻止される(これが第1作)と、誠は関東一の不良高校・花園実業へと転校する。愛、そして彼女を愛し陰から支える男・岩清水弘(仲雅美)も花園へ移り物語は新たな展開を示す。学園を支配する影の大番長・高原由紀(多岐川裕美)、座王権太(千田孝之)との対決(これが第2作)、そして第3勢力の砂土谷峻(柴俊夫)の登場。学園を舞台に誠と砂土谷の最後の対決(これが第3作)が始まる。自分を捨てた母との悲しい再会ゆえに命を捨てて挑む誠の気迫に砂土谷は敗れる。という学園暴力純愛?ドラマである。第1作の誠は去年亡くなった西城秀樹が演じていた。
70年代の日本では同世代の子どもの80%が高校に行く時代になっていた。しかし、学校は階級社会の縮図で、中卒社会人として働く道を捨て、底辺高校に行った勉強のきらいな青少年は、学校の中でやさぐれてマンガでも読んでケンカするしかなかったのである。そういう子たちに「愛と誠」が発するアピールは、根性入れて優等生や教師をぶん殴れば、可愛いあの子が夢中で惚れてくる、という幻想である。この裏側に体制への叛逆を叫んだ全共闘的心情が響いていた。ネルーの言葉やロシア文学を持ち出す梶原一騎の妙な教養主義は、彼自身の学歴インテリへのコンプレックスの裏返しだったと思う。素手の腕力で解決することなどほとんどないのに、彼は極真空手に精を出して暴力こそ弱者の武器だとばかりに、徒手空拳で戦う男の物語を書いた。「巨人の星」は模範的スポ根成功物語。「あしたのジョー」はアウトローの精神玉砕物語。そして愛と誠は、宮本武蔵と大山倍達と力道山を合成した怪物に、彼が憧れたハイ・ソサエティの超絶美女・お姫様が、卑しい身分の自分に愛してるわ!と飛び込んでくるファンタジーを捏造したのだ。
そういえば、思い出したが、梶原一騎は実生活でも太賀誠をやろうとしたのかもしれない。あの頃、ベストセラー小説「氷点」のヒロイン陽子でデビューした清楚な美人女優で、70年代に海外にも国際派女優として知られた島田陽子という女優がいた。いわばとびきりお嬢様の大女優である。梶原一騎は雑誌の対談か何かで島田陽子と知り合い、もの凄いアタックでスキャンダルになったあげく、ついに島田陽子を手に入れた(らしい)。彼には、腕力で欲しいものを獲得する人生が夢であり、彼が憧れたこの世の権力財力、そして高尚なエリートの文化を象徴するものが絶世の美女島田陽子であり、それを手に入れたと思いたかったのだろう。誠の悲哀。
つまり、梶原一騎が生きていた1970年代の日本の心情の布置状況は、この社会の底辺に繋がる大衆の隠微な権力への復讐は、男と女の恋愛という次元でのみ果たされる夢だった。誰もが崇拝し憧れる妖精のような美女を、卑しく蔑まれてきた野蛮な男が手に入れ凌辱する、という性愛の革命。そういう無垢な幻想を、映画によってからくも表現したのが1970年代の奇妙な出来事だった。でもこれは相当に歪んでいる。そのことに映画として、きわめてシニカルかつテクニカルに反応した快作が2012年の三池崇史の「愛と誠」である。70年代にぼくたちが「恋愛」をどのようにイメージしたか?ほんとはもっと格調の高い映画作品があったらよかったのだが、どうもこういう滑稽でひねった作品しか思い浮かばない。
■ 三池崇史監督「愛と誠」2012
大昔の「愛と誠」なんか見てしまったのは、たまたま家に帰ってTVをつけたら、うるさいだけのお笑いバラエティばかりだったので、気まぐれに有線TVに切り替えたら、なんだか変な映画をやっていたのである。それがこの2012年版「愛と誠」だった。妻夫木聡主演映画特集の一つで、ぼくはこんな映画があるのを全然知らなかった。見るともなく見ていたら、なんか凄く変なのである。昔の「愛と誠」というマンガは知っていたから、今時あの70年代的熱血青春ドラマなんかリメイクしてどうすんだろ?と思ったが、これはどうやら手の込んだパロディなのだ。しかも、大マジメにやると冗談みたいなクサい科白を、ミュージカルにして歌と踊りにしてしまい、その歌はみんなかつての昭和のヒット曲を使っているのだ。これはそうとう曲者の映画だと驚いた。
それでパロディの真価を味わうためには、オリジナルがどうだったかを確認したくなって、結局昔の「愛と誠」も見てしまったわけだ。三池崇史監督は確かに鬼才である。今の若者は70年代は知らないわけで、たぶんこの面白さは理解不可能かもしれない。歌と踊りで数々のファイト・シーンがたたみかける。こんな笑えるアクション映画はない。
富豪のひとり娘で天使のように純真無垢なお嬢様・早乙女愛(武井咲)は、復讐を誓い単身上京した、額に一文字の傷がある不良の誠(妻夫木聡)の鋭い眼差しを一目見たときから恋に落ちる。身の上も性格も何もかも違う二人。境遇の違いをまざまざと感じさせるような出来事や命を賭して彼女を愛するという同級生岩清水弘(斎藤工)の存在もあるが、愛は決して一途な心を曲げない。己の拳以外誰も信じない頑なな誠に、全身全霊をかけて愛する愛の心は通じるのか。
暴力学園花園高校のスケバン・ガムコ(安藤サクラ)、影の裏番長・高原由紀(大野いと)、その兄蔵王権太(伊原剛)、愛の父早乙女将吾(市村正親)と母早乙女美也子(一青窈)、そして実の母太賀トヨ(余貴美子)、みんなマンガになりきって歌い暴れている。とくに、老けた高校生蔵王権太が歌う「狼少年ケン」が盛り上がる。ババンババンバン、バンババンババン、ババンバナンバン、バンババ~ン!うお~かみしょ~ねん…ケン!昔聞いた唄だが懐かしい。
でも、昔の「愛と誠」とこれを比べて見て、40年も昔の大衆エンタメの時代背景というか気分というか、文化のなかに表現されるアウトローとエリートの構図について、直接には梶原一騎的なものについて、いくつか考えが沸いてきた。
たんなる学園青春ドラマに、梶原一騎が持ち込んだのは、まず階級社会の熱い壁とそれに腕力と気力だけで立ち向かうアウトローの不良青年の敵意である。金持ちの優等生が通う名門高校に異物としてやってきた太賀誠は、学校にも世間にも叛逆反抗して暴れまくる。それだけなら退学になって終りだが、金持ちお嬢さまで容姿端麗、成績抜群のうえ運動神経も人並み以上という愛が、昔のいきさつもあり誠を熱愛するという、ありえない設定がミソ。それでも退学になった誠は、今度は非行少年の巣のような荒れた学校に転校すると、彼を追って愛と岩清水までついてくる。そして影の番長とその兄は、実は政界の黒幕の子で、社会でも裏の闇権力を握っている。これもありえない話だが、どうせはじめからあり得ない物語なのだから、もう何が起きても不思議でないのである。
ぼくたちは明治時代に捏造された「恋愛」という言葉と、西洋の映画で洗脳されたロマンチック・ラヴ・イデオロギーに愚かにもなにかを期待してしまった。梶原一騎の「愛と誠」が大真面目で形象化していたものと、その爆発した逆転パロディの面白さだけを追求した21世紀三池版「愛と誠」を、あえて日本が作った「恋愛映画」の稀有な成果として記憶してもいいと思う。なぜかといえば、この日本には、「恋愛映画」と言えるようなものは、映画100年の歴史で皆無だったかもしれないからだ。だから伝統日本文壇の閉鎖的世界ではなく、文字を書く女の価値を表に出すことはとても大事だと思うのだ。でも、問題はもっと先にあって、ヤンキー文化がたんにパロディーに引用されるだけなら変革は先送りされる。高校生だったぼくは、できることなら想う彼女と「恋愛」がしたかったが、結局ノウハウも決め手も知らずに失恋していた。
「恋愛」はたんに子孫繁栄の生殖の相手をものにする性行為でもなければ、イエという社会制度の内部で処理される血縁関係の再確認でもなく、かといってフランス革命期の『危険な関係』は近代文学の古典だとしても、不倫や背徳のお遊びできるほど日本の若者は余裕などなかった。

B.70年代の女性作家たち
日本近代文学をきわめて総括的に要領よく解説してくれる新書として、中村光夫の『日本の近代小説』(1954)と『日本の現代小説』(1968)があることは、ある世代までにはよく知られていた。ぼくも学生の頃読んだ覚えがある。だが、これは明治の仮名垣魯文からはじまって昭和初期の芥川から私小説、新感覚派、戦後は1960年代の石原慎太郎、開高健、大江健三郎あたりで終わっていて、その後の文学が当然まったく登場しない。そこで1960年代末から平成が終わる現在までの、日本文学史(主として小説だが)を一気に一冊でまとめて語ってしまうという試みが、岩波新書新刊で最近出た。著者は斎藤美奈子である。
その2章「1970年代 記録文学の時代」から。
「この時期にデビューした女性作家に共通して感じられるのは、既存の「小説らしさ」を否定するところから出発していることです。
最近はすっかり廃れましたが、「エクリチュール・フェミニン」という言葉があります。フランスのフェミニスト(ジュリア・クリステヴァ、リュス・イリガライ、エレーヌ・シクスーら)が七〇年代に流行らせた概念で、「権力化した男性が支配する言葉」に対抗する「権力を撹乱する女性の言葉」くらいのニュアンスです。かなり抽象的ですが、七〇年代以降の女性作家の作品には、たしかに「撹乱」の傾向が見えます。
三十代半ばで詩人から小説家に転身した富岡多恵子は、その方面の先駆的な作家でした。
小説デビュー作『丘に向ってひとは並ぶ』(1971)は〈ヤマトの国からきたといっても、ヤマトの国というのはどこなのかだれも知らない〉という、日本そのものを相対化する一文ではじまる寓話ないし神話風の作品です。物語は男の代表と思われる「ツネやん」と、女の代表というべき「おタネ」の夫婦、およびその子どもたちの生涯を語っていますが、これが、悪意に満ちた日本の近代家族のカリカチュアになっている。八〇年代には、この種の「偽史」が連発されますが、センスは富岡多恵子が上かもしれない。
田村俊子賞を受賞した富岡の初の長編『植物祭』(1973)は、三十代半ばの「わたし」ことツシマさんと、二四歳の「ぼく」ことナツキが進行役を務める小説。二人はドライブやデートを楽しむ友達以上恋人未満の関係にありますが、ナツキの出生の秘密(姉のミサコが、じつは一八歳で自分を生んだ母だった)が明らかになるに至り、「魔女としての母」がグロテスクに描かれて、恋人や母に対する男たちの幻想をみごとに打ち砕きます。
同人誌から頭角をあらわし、七〇年代に地歩を固めた戦後生まれの津島佑子も当初はとんがりまくった作家でした。出世作の『謝肉祭』(1971)は遊園地やサーカスを舞台にした連作ですが、その中の一作『メリー・ゴーラウンド』における遊園地で迷子になった少年と同じで、奇想天外なことが起こりすぎ、読者もどうかすると迷子になりそう。
その後の津島佑子は、シングルマザーを主役にした小説で認められました。第一回野間文芸新人賞を受賞した『光の領分』(1979)もそう。語り手の「わたし」は夫との同棲をへて結婚、娘が生まれましたが、生活力のない夫は別れて暮らしたいといいだした。「わたし」は三歳の娘を預け、ライブラリーに勤務しながら、雑居ビルの最上階に住まいを見つけ、ひとりで娘を育てる道を選びます。が、そこで語られるのは別居や離婚にまつわる苦悩ではなく、他の男との一夜の契りなども含む日常です。母子家庭の小説は後にひとつのジャンルをなすほど増えますが、その先駆的作品でした。
戦後生まれで、同世代の作家より一足早くデビューしたのは金井美恵子です。彼女がどれほど早熟だったかは、デビュー作『愛の生活』(1967)を読めばわかります。〈一日のはじまりがはじまる〉と書きだされた小説は「わたし」の一日をたどるのですが、どうやら「愛の生活」とは「結婚生活」のことらしい。十九歳の女性作家が、二五歳の主婦のアンニュイな生活を一人称で書く。この悪意と批評性と背伸びっぷりは鮮烈です。
文學界新人賞を受賞した松浦理恵子一九歳のデビュー作『葬儀の日』(1978)も前衛的な作品でした。テキストは葬儀で泣くのが仕事の「泣き屋」である「わたし」と、その片割れともいうべき「笑い屋」の「彼女」の関係を描いています。後の「ナチュラル・ウーマン」(1987)などを参照することで、その意図はおぼろげに見えてきます。近すぎるゆえに結ばれない一心同体の二人。それはレズビアニズムと近似した感覚です。
内容面だけ見ても、これらの作品は、従来の男女関係とは異なる関係をモチーフにしています。あえて共通点を探せば、「反ロマンチック・ラブ・イデオロギー」の感覚です。ロマンチック・ラブ・イデオロギーとは「愛と結婚とセックス」を三位一体とする思想のこと。別にいえば、「愛する二人が結ばれる」という恋愛結婚イデオロギーです。七〇年代の初頭にウーマンリブ運動が出現し、男女の規範をめぐるそれまでの価値観が大きく揺らいだという話は最初にしましたが、リブ的なゆらぎはこの時代の小説にも共通していた。
ただ、プロの批評家には高く評価されたものの、一般の読者の間で話題になったのは、こうした前衛的な作品ではありませんでした。女性作家の作品として七〇年代にベストセラーになったのは、見延典子二三歳のデビュー作『もう頬づえはつかない』(1978)と、中沢けい一九歳のデビュー作『海を感じる時』(1978)です。
『もう頬づえはつかない』の語り手「わたし」は東京の私大に通う女子大生。半同棲の関係にある橋本くんと、風来坊みたいな三十男の元カレの恒雄との間でゆれています。やがて「わたし」は妊娠しますが、どちらの男の子どもかわからない。不誠実な男たちに嫌気がさした「わたし」はひとりで妊娠中絶の手術を受け、強烈な言葉とともに二人の男をふるのです。〈ごみをすてるついでに、あなたと、あなたの子供をすてちゃったわ〉
一方、『海を感じる時』は女子高生の性体験を描いています。語り手の「わたし」は母ひとり娘ひとりの母子家庭で育った高校三年生。東京で働きながら大学で学ぶ先輩と付き合っていますが、二人の間に肉体関係があることを知った母は「けがらわしい」と激怒します。しかし、母への屈託を抱える「わたし」は投げやりな態度の恋人に懇願します。〈あたし、もてあそばれてもいいんです。あなたのそばにいたいんです〉
この二冊がベストセラーになったのは、読者のスケベ根性を刺激したからでしょう。女子大生や女子高生が性体験を描いているというだけで色めき立つほど、当時の日本は保守的だった。女子大生や女子高生が小説の主役として文学シーンに躍り出るのはもう少し後になりますが、これらの小説に価値があるとしたら、同時代の男子青春小説を相対化した点でしょう。女子から見れば、男子高生のセックス観など、まったく「いい気なもの」なのです。」斎藤美奈子『日本の同時代小説』岩波新書、2018.pp.81-85.
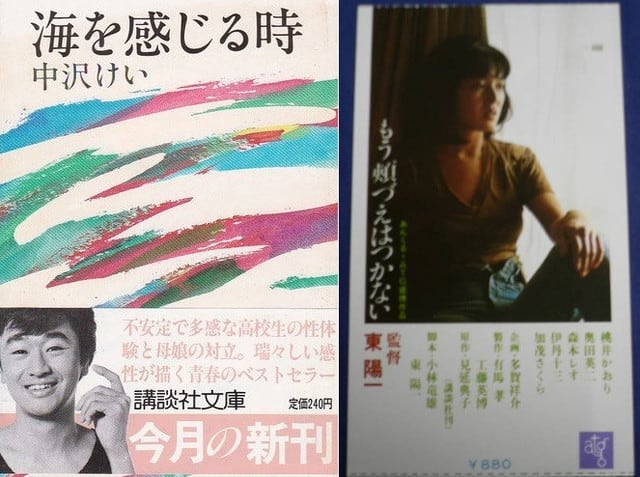
そう、ぼくはその頃、20代の終わりを迎えていたはずだが、気分はまだ「男子青春小説」とたいして違わない「いい気なもの」でしかなかったかもな、と思う。つまり同世代の女が何を考えていたか、想像してもちっとも具体性がなかったのだ。捨てられる彼女すらいなかったし…。
ぼくは1949年生まれの団塊世代の最後で、やたら子どもの多かった戦後の物が足りない復興期と、その後に来たどんどん物質的に豊かになる高度経済成長の日本を記憶している、いまや老いぼれ高齢者になってしまった人間である。ぼくらの世代にとって「恋愛」とはどんなものとして感知されていたのか。とりあえずぼくが20歳前の若者だったのは1960年代後半、経済成長の恩恵が一般大衆の生活にも及んで、もう貧しさが見ればわかる服装や言葉や住宅などから消えていく時代だった。しかし、まだ家庭の経済力がなくて高校にも進学できない同級生がいたし、大学生になれるのは同世代の3割ちょっとだけだった。東京など大都市の消費的な生活と地方のつつましい生活の格差はむしろ際立っていた。ぼくは東京の繁華街に近いところで暮らしていて、家は裕福とはいえなかったが小遣いを貯めれば、面白そうな映画を見たり好みのレコードを買ったりする文化的なアクセスも可能だった。普通科の都立高校生は、頑張って勉強すれば名の知れた大学に入ってそれなりに明るい未来を期待できた。甘く幸福な青春を生きていたともいえる。
そういう環境のなかで、戦争中に子供だった上の世代は、豪華な洋画が描く甘美な「恋愛」など観念の中の幻影に過ぎなかったが、男女共学の高校生活を送ったぼくたちには、クラスの憧れの彼女と「恋愛」できるかもしれないという可能性は、観念ではなく手の届きそうな現実だった。でも、今にして思うと平和な高校に通っていた男の子も女の子も、「恋愛」というものを自分勝手にただ夢のように憧れていたのかもしれない。それは清らかな恋心を抱きながら高校を出て、大学に行ったり就職したりして、いずれ20代なかばには彼と彼女は恋の成就としての結婚に到達し、みんなに祝福されるはずだと思い込んでいた。しかし、そのために男と女はどのような努力をしなければならないかなど、全然考えていなかったのである。
「恋愛」を実践するには見習うべきモデルが要る。しかし、あの時代の日本にはアメリカ映画の恋人たちはあまりに放埓でぶっ飛んでいたし、フランス映画の恋人たちは気まぐれで洗練され過ぎてちょっとひいてしまった。だから、日本でなにかピンとくる「恋愛」のモデルがあれば飛びついたはずだが、そこは古臭い旧世代の純愛物語か男本位の権力思想しかないので、ぼくたちは愚かにもしぶしぶサブカル・マンガの中に拠るべき拠点を求めてしまった。梶原一騎の「愛と誠」は、正直ぼくには当時ばかばかしいとしか思えなかった。だって、この社会への違和感にむらむらと反抗するだけが生きる意味である虐げられた若い男が、あらゆる意味でポジティヴな高貴な美女・お嬢様となぜか恋に落ちて、ひたすら愛の嵐に見舞われるというのだから。
■ 山根成之監督「愛と誠」1974・「続・愛と誠」(1975)「 愛と誠・完結編」(南部英夫監督1976)の3部作
今は昔1970年代なかば、はじめは少年誌の連載マンガでヒットし、これを受けて映画になりヒットしたのが、この「愛と誠」。この頃、原作者の梶原一騎は、「巨人の星」「あしたのジョー」など大ヒットを連発し、格闘技で鍛えた大きな身体とヤクザみたいな服装と態度でマスコミでも注目の的だった。「愛と誠」も喧嘩に明け暮れるアウトロー的高校生が主人公なのだが、これに絵に描いたようなお嬢様(実際絵に描いているのだが・・)が、惚れまくるというラブストーリー仕立てなのが違うといえば違う。いまさら「愛と誠」なんか、引っ張り出して見ちゃったのは、まったくの偶然に始まるのだが、それはちょっと後で書く。
なぜか映画の冒頭に、元インド首相ジャワハルラール・ネルーが娘(後の首相インディラ・ガンディー)へ宛てた手紙(『父が子に語る世界歴史』より)の一説が引用されており、それに含まれる「愛」と「誠(誠実)」という言葉がタイトルの由来にもなっている。少年誌に連載された純愛物の先駆けとなり一世を風靡。ヒロイン・早乙女愛が幼き日の太賀誠を回想して語った「白馬の騎士」や、その早乙女愛への報われない愛を貫く優等生・岩清水弘のセリフ「きみのためなら死ねる」などが流行語になった。女優の早乙女愛は、この漫画が実写映画化された際の一般公募でデビューし、芸名もヒロインの名前から取られた。
信州の蓼科高原で早乙女愛(早乙女愛)が偶然出会った不良青年・太賀誠(西城秀樹)。彼は幼い頃、愛の命を救った時、額に大きな傷を負ったばかりでなく両親や自らの人生さえも壊れていた。愛はその償いとして誠を東京の名門高校へ転入させ、更生させようとするが、誠の怒りは強く、逆に暴力で学園を支配しようと企む。しかし愛の献身的な行為でこれを阻止される(これが第1作)と、誠は関東一の不良高校・花園実業へと転校する。愛、そして彼女を愛し陰から支える男・岩清水弘(仲雅美)も花園へ移り物語は新たな展開を示す。学園を支配する影の大番長・高原由紀(多岐川裕美)、座王権太(千田孝之)との対決(これが第2作)、そして第3勢力の砂土谷峻(柴俊夫)の登場。学園を舞台に誠と砂土谷の最後の対決(これが第3作)が始まる。自分を捨てた母との悲しい再会ゆえに命を捨てて挑む誠の気迫に砂土谷は敗れる。という学園暴力純愛?ドラマである。第1作の誠は去年亡くなった西城秀樹が演じていた。
70年代の日本では同世代の子どもの80%が高校に行く時代になっていた。しかし、学校は階級社会の縮図で、中卒社会人として働く道を捨て、底辺高校に行った勉強のきらいな青少年は、学校の中でやさぐれてマンガでも読んでケンカするしかなかったのである。そういう子たちに「愛と誠」が発するアピールは、根性入れて優等生や教師をぶん殴れば、可愛いあの子が夢中で惚れてくる、という幻想である。この裏側に体制への叛逆を叫んだ全共闘的心情が響いていた。ネルーの言葉やロシア文学を持ち出す梶原一騎の妙な教養主義は、彼自身の学歴インテリへのコンプレックスの裏返しだったと思う。素手の腕力で解決することなどほとんどないのに、彼は極真空手に精を出して暴力こそ弱者の武器だとばかりに、徒手空拳で戦う男の物語を書いた。「巨人の星」は模範的スポ根成功物語。「あしたのジョー」はアウトローの精神玉砕物語。そして愛と誠は、宮本武蔵と大山倍達と力道山を合成した怪物に、彼が憧れたハイ・ソサエティの超絶美女・お姫様が、卑しい身分の自分に愛してるわ!と飛び込んでくるファンタジーを捏造したのだ。
そういえば、思い出したが、梶原一騎は実生活でも太賀誠をやろうとしたのかもしれない。あの頃、ベストセラー小説「氷点」のヒロイン陽子でデビューした清楚な美人女優で、70年代に海外にも国際派女優として知られた島田陽子という女優がいた。いわばとびきりお嬢様の大女優である。梶原一騎は雑誌の対談か何かで島田陽子と知り合い、もの凄いアタックでスキャンダルになったあげく、ついに島田陽子を手に入れた(らしい)。彼には、腕力で欲しいものを獲得する人生が夢であり、彼が憧れたこの世の権力財力、そして高尚なエリートの文化を象徴するものが絶世の美女島田陽子であり、それを手に入れたと思いたかったのだろう。誠の悲哀。
つまり、梶原一騎が生きていた1970年代の日本の心情の布置状況は、この社会の底辺に繋がる大衆の隠微な権力への復讐は、男と女の恋愛という次元でのみ果たされる夢だった。誰もが崇拝し憧れる妖精のような美女を、卑しく蔑まれてきた野蛮な男が手に入れ凌辱する、という性愛の革命。そういう無垢な幻想を、映画によってからくも表現したのが1970年代の奇妙な出来事だった。でもこれは相当に歪んでいる。そのことに映画として、きわめてシニカルかつテクニカルに反応した快作が2012年の三池崇史の「愛と誠」である。70年代にぼくたちが「恋愛」をどのようにイメージしたか?ほんとはもっと格調の高い映画作品があったらよかったのだが、どうもこういう滑稽でひねった作品しか思い浮かばない。
■ 三池崇史監督「愛と誠」2012
大昔の「愛と誠」なんか見てしまったのは、たまたま家に帰ってTVをつけたら、うるさいだけのお笑いバラエティばかりだったので、気まぐれに有線TVに切り替えたら、なんだか変な映画をやっていたのである。それがこの2012年版「愛と誠」だった。妻夫木聡主演映画特集の一つで、ぼくはこんな映画があるのを全然知らなかった。見るともなく見ていたら、なんか凄く変なのである。昔の「愛と誠」というマンガは知っていたから、今時あの70年代的熱血青春ドラマなんかリメイクしてどうすんだろ?と思ったが、これはどうやら手の込んだパロディなのだ。しかも、大マジメにやると冗談みたいなクサい科白を、ミュージカルにして歌と踊りにしてしまい、その歌はみんなかつての昭和のヒット曲を使っているのだ。これはそうとう曲者の映画だと驚いた。
それでパロディの真価を味わうためには、オリジナルがどうだったかを確認したくなって、結局昔の「愛と誠」も見てしまったわけだ。三池崇史監督は確かに鬼才である。今の若者は70年代は知らないわけで、たぶんこの面白さは理解不可能かもしれない。歌と踊りで数々のファイト・シーンがたたみかける。こんな笑えるアクション映画はない。
富豪のひとり娘で天使のように純真無垢なお嬢様・早乙女愛(武井咲)は、復讐を誓い単身上京した、額に一文字の傷がある不良の誠(妻夫木聡)の鋭い眼差しを一目見たときから恋に落ちる。身の上も性格も何もかも違う二人。境遇の違いをまざまざと感じさせるような出来事や命を賭して彼女を愛するという同級生岩清水弘(斎藤工)の存在もあるが、愛は決して一途な心を曲げない。己の拳以外誰も信じない頑なな誠に、全身全霊をかけて愛する愛の心は通じるのか。
暴力学園花園高校のスケバン・ガムコ(安藤サクラ)、影の裏番長・高原由紀(大野いと)、その兄蔵王権太(伊原剛)、愛の父早乙女将吾(市村正親)と母早乙女美也子(一青窈)、そして実の母太賀トヨ(余貴美子)、みんなマンガになりきって歌い暴れている。とくに、老けた高校生蔵王権太が歌う「狼少年ケン」が盛り上がる。ババンババンバン、バンババンババン、ババンバナンバン、バンババ~ン!うお~かみしょ~ねん…ケン!昔聞いた唄だが懐かしい。
でも、昔の「愛と誠」とこれを比べて見て、40年も昔の大衆エンタメの時代背景というか気分というか、文化のなかに表現されるアウトローとエリートの構図について、直接には梶原一騎的なものについて、いくつか考えが沸いてきた。
たんなる学園青春ドラマに、梶原一騎が持ち込んだのは、まず階級社会の熱い壁とそれに腕力と気力だけで立ち向かうアウトローの不良青年の敵意である。金持ちの優等生が通う名門高校に異物としてやってきた太賀誠は、学校にも世間にも叛逆反抗して暴れまくる。それだけなら退学になって終りだが、金持ちお嬢さまで容姿端麗、成績抜群のうえ運動神経も人並み以上という愛が、昔のいきさつもあり誠を熱愛するという、ありえない設定がミソ。それでも退学になった誠は、今度は非行少年の巣のような荒れた学校に転校すると、彼を追って愛と岩清水までついてくる。そして影の番長とその兄は、実は政界の黒幕の子で、社会でも裏の闇権力を握っている。これもありえない話だが、どうせはじめからあり得ない物語なのだから、もう何が起きても不思議でないのである。
ぼくたちは明治時代に捏造された「恋愛」という言葉と、西洋の映画で洗脳されたロマンチック・ラヴ・イデオロギーに愚かにもなにかを期待してしまった。梶原一騎の「愛と誠」が大真面目で形象化していたものと、その爆発した逆転パロディの面白さだけを追求した21世紀三池版「愛と誠」を、あえて日本が作った「恋愛映画」の稀有な成果として記憶してもいいと思う。なぜかといえば、この日本には、「恋愛映画」と言えるようなものは、映画100年の歴史で皆無だったかもしれないからだ。だから伝統日本文壇の閉鎖的世界ではなく、文字を書く女の価値を表に出すことはとても大事だと思うのだ。でも、問題はもっと先にあって、ヤンキー文化がたんにパロディーに引用されるだけなら変革は先送りされる。高校生だったぼくは、できることなら想う彼女と「恋愛」がしたかったが、結局ノウハウも決め手も知らずに失恋していた。
「恋愛」はたんに子孫繁栄の生殖の相手をものにする性行為でもなければ、イエという社会制度の内部で処理される血縁関係の再確認でもなく、かといってフランス革命期の『危険な関係』は近代文学の古典だとしても、不倫や背徳のお遊びできるほど日本の若者は余裕などなかった。

B.70年代の女性作家たち
日本近代文学をきわめて総括的に要領よく解説してくれる新書として、中村光夫の『日本の近代小説』(1954)と『日本の現代小説』(1968)があることは、ある世代までにはよく知られていた。ぼくも学生の頃読んだ覚えがある。だが、これは明治の仮名垣魯文からはじまって昭和初期の芥川から私小説、新感覚派、戦後は1960年代の石原慎太郎、開高健、大江健三郎あたりで終わっていて、その後の文学が当然まったく登場しない。そこで1960年代末から平成が終わる現在までの、日本文学史(主として小説だが)を一気に一冊でまとめて語ってしまうという試みが、岩波新書新刊で最近出た。著者は斎藤美奈子である。
その2章「1970年代 記録文学の時代」から。
「この時期にデビューした女性作家に共通して感じられるのは、既存の「小説らしさ」を否定するところから出発していることです。
最近はすっかり廃れましたが、「エクリチュール・フェミニン」という言葉があります。フランスのフェミニスト(ジュリア・クリステヴァ、リュス・イリガライ、エレーヌ・シクスーら)が七〇年代に流行らせた概念で、「権力化した男性が支配する言葉」に対抗する「権力を撹乱する女性の言葉」くらいのニュアンスです。かなり抽象的ですが、七〇年代以降の女性作家の作品には、たしかに「撹乱」の傾向が見えます。
三十代半ばで詩人から小説家に転身した富岡多恵子は、その方面の先駆的な作家でした。
小説デビュー作『丘に向ってひとは並ぶ』(1971)は〈ヤマトの国からきたといっても、ヤマトの国というのはどこなのかだれも知らない〉という、日本そのものを相対化する一文ではじまる寓話ないし神話風の作品です。物語は男の代表と思われる「ツネやん」と、女の代表というべき「おタネ」の夫婦、およびその子どもたちの生涯を語っていますが、これが、悪意に満ちた日本の近代家族のカリカチュアになっている。八〇年代には、この種の「偽史」が連発されますが、センスは富岡多恵子が上かもしれない。
田村俊子賞を受賞した富岡の初の長編『植物祭』(1973)は、三十代半ばの「わたし」ことツシマさんと、二四歳の「ぼく」ことナツキが進行役を務める小説。二人はドライブやデートを楽しむ友達以上恋人未満の関係にありますが、ナツキの出生の秘密(姉のミサコが、じつは一八歳で自分を生んだ母だった)が明らかになるに至り、「魔女としての母」がグロテスクに描かれて、恋人や母に対する男たちの幻想をみごとに打ち砕きます。
同人誌から頭角をあらわし、七〇年代に地歩を固めた戦後生まれの津島佑子も当初はとんがりまくった作家でした。出世作の『謝肉祭』(1971)は遊園地やサーカスを舞台にした連作ですが、その中の一作『メリー・ゴーラウンド』における遊園地で迷子になった少年と同じで、奇想天外なことが起こりすぎ、読者もどうかすると迷子になりそう。
その後の津島佑子は、シングルマザーを主役にした小説で認められました。第一回野間文芸新人賞を受賞した『光の領分』(1979)もそう。語り手の「わたし」は夫との同棲をへて結婚、娘が生まれましたが、生活力のない夫は別れて暮らしたいといいだした。「わたし」は三歳の娘を預け、ライブラリーに勤務しながら、雑居ビルの最上階に住まいを見つけ、ひとりで娘を育てる道を選びます。が、そこで語られるのは別居や離婚にまつわる苦悩ではなく、他の男との一夜の契りなども含む日常です。母子家庭の小説は後にひとつのジャンルをなすほど増えますが、その先駆的作品でした。
戦後生まれで、同世代の作家より一足早くデビューしたのは金井美恵子です。彼女がどれほど早熟だったかは、デビュー作『愛の生活』(1967)を読めばわかります。〈一日のはじまりがはじまる〉と書きだされた小説は「わたし」の一日をたどるのですが、どうやら「愛の生活」とは「結婚生活」のことらしい。十九歳の女性作家が、二五歳の主婦のアンニュイな生活を一人称で書く。この悪意と批評性と背伸びっぷりは鮮烈です。
文學界新人賞を受賞した松浦理恵子一九歳のデビュー作『葬儀の日』(1978)も前衛的な作品でした。テキストは葬儀で泣くのが仕事の「泣き屋」である「わたし」と、その片割れともいうべき「笑い屋」の「彼女」の関係を描いています。後の「ナチュラル・ウーマン」(1987)などを参照することで、その意図はおぼろげに見えてきます。近すぎるゆえに結ばれない一心同体の二人。それはレズビアニズムと近似した感覚です。
内容面だけ見ても、これらの作品は、従来の男女関係とは異なる関係をモチーフにしています。あえて共通点を探せば、「反ロマンチック・ラブ・イデオロギー」の感覚です。ロマンチック・ラブ・イデオロギーとは「愛と結婚とセックス」を三位一体とする思想のこと。別にいえば、「愛する二人が結ばれる」という恋愛結婚イデオロギーです。七〇年代の初頭にウーマンリブ運動が出現し、男女の規範をめぐるそれまでの価値観が大きく揺らいだという話は最初にしましたが、リブ的なゆらぎはこの時代の小説にも共通していた。
ただ、プロの批評家には高く評価されたものの、一般の読者の間で話題になったのは、こうした前衛的な作品ではありませんでした。女性作家の作品として七〇年代にベストセラーになったのは、見延典子二三歳のデビュー作『もう頬づえはつかない』(1978)と、中沢けい一九歳のデビュー作『海を感じる時』(1978)です。
『もう頬づえはつかない』の語り手「わたし」は東京の私大に通う女子大生。半同棲の関係にある橋本くんと、風来坊みたいな三十男の元カレの恒雄との間でゆれています。やがて「わたし」は妊娠しますが、どちらの男の子どもかわからない。不誠実な男たちに嫌気がさした「わたし」はひとりで妊娠中絶の手術を受け、強烈な言葉とともに二人の男をふるのです。〈ごみをすてるついでに、あなたと、あなたの子供をすてちゃったわ〉
一方、『海を感じる時』は女子高生の性体験を描いています。語り手の「わたし」は母ひとり娘ひとりの母子家庭で育った高校三年生。東京で働きながら大学で学ぶ先輩と付き合っていますが、二人の間に肉体関係があることを知った母は「けがらわしい」と激怒します。しかし、母への屈託を抱える「わたし」は投げやりな態度の恋人に懇願します。〈あたし、もてあそばれてもいいんです。あなたのそばにいたいんです〉
この二冊がベストセラーになったのは、読者のスケベ根性を刺激したからでしょう。女子大生や女子高生が性体験を描いているというだけで色めき立つほど、当時の日本は保守的だった。女子大生や女子高生が小説の主役として文学シーンに躍り出るのはもう少し後になりますが、これらの小説に価値があるとしたら、同時代の男子青春小説を相対化した点でしょう。女子から見れば、男子高生のセックス観など、まったく「いい気なもの」なのです。」斎藤美奈子『日本の同時代小説』岩波新書、2018.pp.81-85.
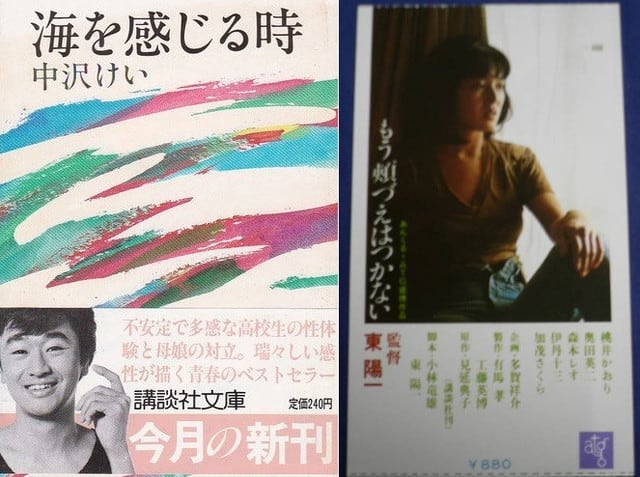
そう、ぼくはその頃、20代の終わりを迎えていたはずだが、気分はまだ「男子青春小説」とたいして違わない「いい気なもの」でしかなかったかもな、と思う。つまり同世代の女が何を考えていたか、想像してもちっとも具体性がなかったのだ。捨てられる彼女すらいなかったし…。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます