
貞亨義民記念館
長野県安曇野市三郷明盛3209 Visit :2006-08-11 12:50
◆貞亨義民記念館(じょうきょう ぎみん きねんかん)
当館は、全国的に見ても珍しい「百姓一揆」をテーマにした展示館であり、貞亨年間に信州松本藩で起こった騒動の「義民を顕彰した」記念館である。
この義民(ぎみん)という意味は、 義のため、一身を投げ出して尽くす人を云うが、特に江戸時代、百姓一揆の指導者として処罰され、民衆に敬慕された人をいう。
当ブログでは、松本水野藩に関連しこの騒動を紹介したい。
◆貞亨騒動の概要
寛永十九年(1642)七月二十八日、初代水野隼人正忠が三河国吉田から松本藩に移封されてくる四十余年前の元和年代(1615--1624)の頃、当領地であった高遠領(西五千石)や、諏訪領(東五千石)が松本藩から分割された。その後、年貢については分割された両領郷は当時のまま、籾一俵は“米二斗五升挽”(*1)であったのに対し、松本藩では水野家入封前に“三斗挽”に引き上げられ、水野家もそれを受け継いだことから農民は仕方なく三斗挽に耐えていた。
貞亨三年(1686)、松本藩主三代水野忠直の時、近年不作が続いて困窮を極めていた中、藩はこの年の収納に当たっては、“芒(のぎ)踏磨き(*2)”と“三斗四・五升挽”を厳命してきた。これに対し、安曇郡長尾組中萱村の庄屋である多田加助を首領とする各組の同志達は、このような過酷な年貢に多くの農民が苦しむのを見るに忍びず、身を挺して農民を救おうと十月十日の夜、中萱の権現の森(熊野神社)に集まり密議し、旧両領の五千石並の“二斗五升挽”の要求など五ヶ条の訴状をしたため十四日、郡奉行へ訴え出た。この企てが村々に伝わると、農民達はこれに加勢しようと簑笠に身を固め鋤鍬を手に松本城に押し寄せた。
藩主は参勤交代による江戸詰で国許に不在であったことから、この突然の大騒動に狼狽した家老達はこれを鎮圧するために色々な策を講じたが、農民達は聞き入れず、日増にその数は増加し万余に及んだと云われている。この騒動が幕府に聞こえると藩のお取潰にも繋がると困惑した重臣達は、十六日夜、郡奉行の名で籾納は従来通り“三斗挽”でよく、のぎ踏磨きは無用、など農民の願いを聞き届ける旨の覚書を組手代(*3)に届けた。これを知らされた農民の大半は村々に引き上げた。しかし加助等同志と百数十人の農民は、あくまで“二斗五升挽”の要求と家老の証文を求めて留まった。家老等は騒動が長引くことと、江戸表への直訴を恐れて十八日に“二斗五升挽”をも聞き届ける旨の「家老連判覚書」を出したので、加助ら農民達は一応安堵して村々へ引き上げ騒動は鎮まった。
ところがその後、藩は村々へ先に渡した覚書を返上させ、家老や奉行は江戸の藩主に、年貢の引き上げや芒(のぎ)取りを命じたことを正しく伝えようとはせず、昨年と同じように年貢を命じたのに百姓が一揆を起こしたと真相を秘して注進したことで、その報告を聞いた藩主忠直は厳しい罰を許可した。藩主の裁許を得た家老達は首謀者とその子弟を一斉に捕縛して上土(*4)の牢舎へ投獄した。数日後の十一月二十二日、安曇野の者は松本城北西の勢高(*5)で、筑摩の者は同南の出川(*6)の刑場で処刑された。その刑は磔(*7)八人、獄門(*8)二十人という極刑で、百姓一揆史上稀にみる多人数であった。加助等は磔柱の上から城を睨み“二斗五升挽”を絶叫しつつ息絶えたと伝えられている。
一方、江戸に詰めていた藩士鈴木伊織は、国許からの報告を聞き、厳罰を持って臨むことはよくないと考えた。彼は百姓の苦しい生活を思いやって、民の暮らしの立つような政治を願っていた一人であった。加助らの死罪が許可されて、松本への使者が江戸を起った後、伊織は藩主忠直公を諫めて、厳しい処罰の中止の許しを得、自ら馬を駆って松本へ向かったが、折悪しく松本へ入ったところで馬が倒れ、また伊織自身も疲れのため気を失ってしまい、残念なことに処刑の中止には間に合わなかった。伊織の墓は、松本市中央四丁目、中町を東に行ったところにあり、今でも花を手向ける人が絶えないという。
この貞亨騒動は、信濃国松本藩に起こった百姓一揆であり、首謀者が庄屋の多田加助であったことから加助騒動とも云われている。
♦処刑された人々
【勢刑場】
◇長尾組中萱村(長野県安曇野市三郷明盛中萱)
多田加助――――磔
子 伝八――――獄門
子 三蔵――――獄門
弟 彦之丞―――獄門
◇長尾組楡村(長野県安曇野市三郷温楡)
小穴善兵衛―――磔
子 しゅん―――獄門
子 惣助――――獄門
弟 松右衛門――獄門
その子 長之助―獄門
弟 治兵衛―――獄門
◇上野村大妻村(長野県松本市梓川倭)
小松作兵衛―――磔
子 兼松――――獄門
◇上野組氷室村(長野県松本市梓川倭)
川上半之助―――磔
子 彦―――――獄門
子 権之助―――獄門
弟 左五兵衛――獄門
◇出川組笹部村(長野県松本市笹部)
赤羽金兵衛―――獄門
(川上半之助の弟)
【出川刑場】
◇島立組堀米村(長野県松本市島立堀米)
丸山吉兵衛―――磔
子 権太郎―――獄門
子 与作――――獄門
◇島立村堀米村(長野県松本市島立堀米)
堀米弥三郎―――獄門
◇出川組梶海渡村(長野県松本市神林梶海渡)
塩原惣左衛門――磔
子 三之丞―――獄門
◇岡田組浅間村(長野県松本市浅間温泉)
三浦善七――――磔
◇岡田組岡田町村(長野県松本市岡田町)
橋爪善七――――磔
弟 勘太郎―――獄門
◇会田組執田光村(長野県松本市会田)
望月与兵衛―――獄門
子 藤兵衛―――獄門
◆貞亨騒動の後
当館長のお話によると、水野家が騒動後も長らく領民と不和であったという訳ではなく、第三代水野忠直の孫で第五代水野忠幹の代には、父の第四代忠周が領民から借金しており、その返済を気に掛けていたものの財政が困窮していたことから、返済を待ってもらえるよう饗応して詫びるなど交流もあり、騒動後は領民を大切にしたことが、水野家の古文書に書かれていると聞かれた。また、加助等を処刑した水野家では凶事が相次いだことで、これは加助の霊のたたりであると前非を悔い、その像を刻み邸内に弔っていた。明治三十一年(1898)、貞亨義民社殿の造営に際し、水野家から同像が贈られ、現在もご神体として祀られている。レプリカが貞亨義民記念館に展示されている。
[註]
*1=一俵に入った籾米を、藩の検査用磨臼(すりうす)で挽いて、籾殻を取り除き玄米二斗五升が採れるだけの籾米が入っていること。三斗挽なら年貢は約20%増、三斗四・五升挽なら更に15%の増加。
*2=芒(のぎ)とは、稲・麦などイネ科植物の実の外殻にある針のような毛(のげ)のことで、従来のように俵に籾米を単に詰めて年貢として納めるのではなく、更に一手間掛けて芒を磨り落としてから納めること。
*3=くみてだい。江戸時代、郡代・代官・奉行の下で雑務を担当した役人で、複数の村を束ねる「組」を管理していた。
*4=長野県松本市大手四丁目付近。
*5=せいたか。長野県松本市宮渕。
*6=いでがわ。長野県松本市出川。
*7=はりつけ。「張り付け」と同源。昔の刑罰の一。罪人を柱にしばりつけ、槍で突き殺したもの。古くは体を地面や板に張りひろげ、釘を打って処刑した。はっつけ。磔刑(たくけい)。
*8=ごくもん。(1)牢獄の門。(2)斬罪になった囚人の首を牢獄の門にさらしたことから刑罰の名称となった。江戸時代の刑罰の一で、斬首のうえ、その首を一定の場所または悪事をした場所にさらすこと。獄門台にのせ、そばに罪状を記した立て札を立てた。梟首(きょうしゅ)。晒首(さらしくび)。
貞亨義民記念館のホームページ http://www.anc-tv.ne.jp/~gimin/
小河水野系譜 http://blog.goo.ne.jp/heron_goo/e/694986f5283c9212e7114538de019f95












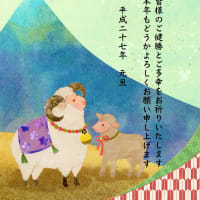
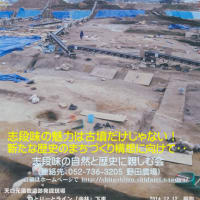
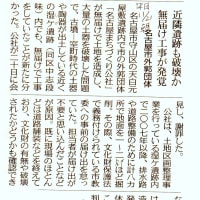

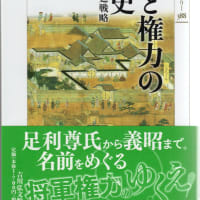
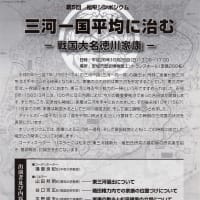
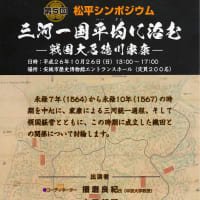
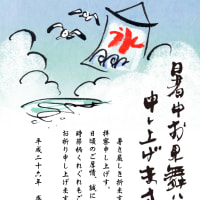
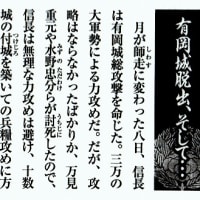
相変わらずご熱心ですね。
私は浅学寡聞にして「年貢問題」には詳しくありません。ただ信濃地方では、諏訪高島藩が異常に年貢騒動が少なかった藩だと記憶しているぐらいです。
それと、松本・水野氏は「加助騒動」のあと名君が出て善政を布いていますが、数代後の忠恒が暗君で、確か城内で毛利藩主に刃傷沙汰を起し改易されていた筈ですね。
早速のコメント誠にありがとうございます。
大分涼しくなってきましたから、先生も古城探訪の本格復活のようですね。(^^)
今回の取材で、年貢米一俵と単純に云っても“二斗五升挽”などと細かく取り決めがあったことを新たに知りました。
またご指摘のように、六代忠恒の乱心による改易は、加助の祟りともいわれています。